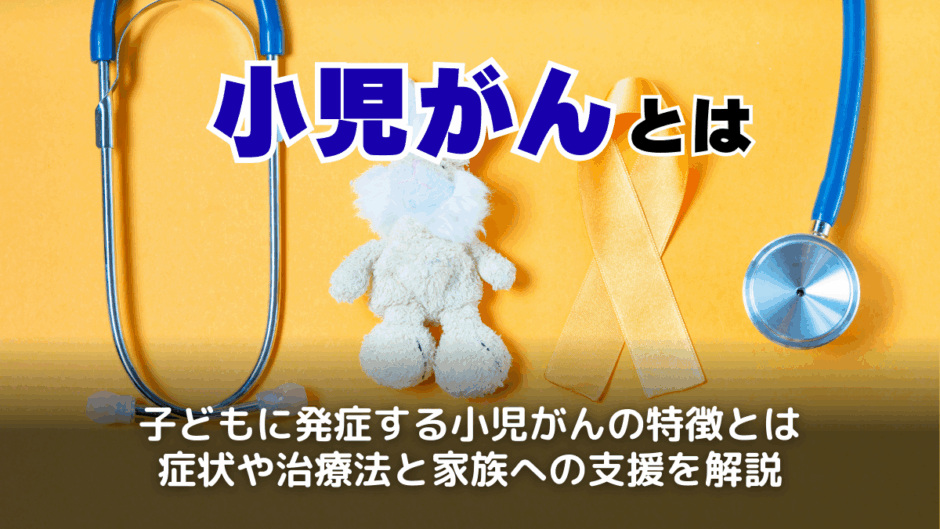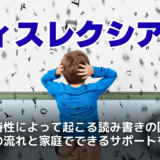小児がんは、15歳未満の子どもに発症するがんの総称で、全体のがんの中では約1%と患者数は少ないものの、小児の死亡原因の上位を占めています。発症には年齢や種類ごとの特徴があり、白血病や脳腫瘍など成人のがんには見られない特定のがんが多く見られます。
治療の進歩により生存率は向上してはいるものの、治療後の晩期合併症や家族の精神的・経済的負担など多くの課題が残されているのが現状です。本記事では小児がんの定義や主な疾患の種類・症状や治療法・発症率や生存率の現状・原因やリスク要因・さらに公的支援や相談窓口など、知っておくと役立つ情報を分かりやすくまとめています。
小児がんとは?

小児がんとは、15歳未満の子どもに発症するがんの総称です。小児期に見られるがんの多くは、白血病やリンパ腫を除くと成人が発症するがんにはほとんど見られない種類であり、発症の背景や進行の仕方も成人のがんとは大きく異なります。小児がんには白血病・脳腫瘍・神経芽腫・胚細胞腫瘍など多様な種類が存在し、それぞれ治療法や経過も大きな違いが見られます。
従って小児がんの治療を成功に導くためには経験豊富な医療チームによる診断と、治療が必要不可欠です。特に症例数の多い小児専門病院や大学病院での治療が推奨され、専門医や看護師・薬剤師・心理学士など多職種のスタッフがチームを組み、子どもと家族を支えながら治療を進めます。
治療は入院による集中的なケアや、外来での通院治療として継続されることが多く、医療面だけではなく、小児患者に対しての学習や生活支援など包括的なサポートが重視されています。
小児がんの主な種類
小児のみが発症する小児がんにはさまざまな種類がありますが、ここでは特に代表的な小児がん5つをピックアップしました。解説する小児がんは以下の5つです。
- 白血病
- 脳腫瘍
- リンパ腫
- 神経芽腫
- 胚細胞腫瘍
各小児がんの主な症状や特徴などを詳しく解説します。
白血病
白血病は、小児がんの中で最も多い血液のがんです。血液中の白血球が異常に増えて正常な血球が作られにくくなるため、さまざまな症状が見られます。代表的な症状は以下の通りです。
- 発熱が続く
- 顔色が悪くなるほどの貧血
- 少しの刺激でもあざができたり鼻血が出やすくなる出血傾向
- リンパ節や肝臓・脾臓が腫れる
また、骨や関節の痛みを訴える子どもも少なくありません。治療は抗がん剤による化学療法が中心となり、必要に応じて放射線治療や造血幹細胞治療が行われます。近年は新しい分子標的薬や免疫療法の導入により、治療成績は大きく向上しており、適切な治療を受けることで長期生存する子どもも増加傾向にあります。
脳腫瘍
脳腫瘍は、小児がんの中で白血病についで多く見られる病気です。脳や脊髄にできる腫瘍のため、腫瘍の部位や大きさによってさまざまな症状が表れます。主な症状を以下に提示します。
- 頭痛が長期間続くまたは朝方に強くなる
- 吐き気・嘔吐が繰り返し起こる
- 視覚障害(二重に見える・視力低下など)
- 歩行時のふらつきやバランスの悪化
- 乳幼児では頭囲の拡大や大泉門(頭の柔らかい部分)の膨らみ
治療は腫瘍の種類や位置によって異なり、外科手術での摘出が行われることが多いです。さらに放射線治療や化学療法を組み合わせることで再発を防ぎます。小児の場合は脳の発達への影響も考慮する必要があり、治療後は学習支援やリハビリを含めた長期的なケアが重要とされています。
リンパ腫
リンパ腫は、リンパ球という免疫を担う細胞ががん化して増えることで起こる小児がんです。首やわきの下、足の付け根などにあるリンパ節が腫れることが多く、しこりのように触れることがあります。リンパ腫では以下のような症状が見られます。
- リンパ節の腫れ(痛みは伴わないことが多い)
- 原因不明の発熱
- 体重が急に減少する
- 就寝中に大量の汗をかく
診断には血液検査や画像検査に加えて、生検による腫瘍の組織診断が重要です。治療は抗がん剤による化学療法が中心ですが、場合によっては放射線治療を併用します。治療法の進歩によって予後は改善しており、早期に適切な医療を受けることが大切とされています。
神経芽腫
神経芽腫は、交感神経という自律神経の一部に由来する細胞ががん化して発生する小児がんで、特に乳幼児に多く見られる疾患です。副腎や腹部の神経組織に発生することが多く、症状は腫瘍の大きさや場所によって異なります。神経芽腫の主な症状は以下の通りです。
- お腹にしこりが触れる・または腹部の膨らみ
- 腹痛が続く
- 食欲不振や体重減少
- 眼の周囲にあざができる(転移によるもの)
- 骨転移による痛みや歩行障害
神経芽腫は進行の早いがんで、診断時にはすでに転移していることもあります。一方で年齢が低い場合や特定のタイプでは自然に縮小・消失する例もあり、病気の経過は多種多様です。治療は手術・化学療法・放射線治療を組み合わせて行われ、再発リスクが高い場合には造血幹細胞移植や免疫療法が検討されます。
治療後は長期的な経過観察と、成長や発達を考慮したサポートが必要です。
胚細胞腫瘍
胚細胞腫瘍は性腺(精巣や卵巣)や脳などに発生する小児がんの一種で、胚の発生段階に由来する細胞からできる腫瘍です。腫瘍の部位によって症状は異なりますが、性腺に発生した場合はしこりとしてさわれたり、思春期前後のホルモン異常が現れることがあります。脳に発生した場合は、頭痛や吐き気・視覚障害などの神経症状が見られることもあります。
胚細胞腫瘍では以下のような症状が見られます。
- 性腺のしこり・腫れ
- 思春期前後の早期または遅延性のホルモン異常
- 脳腫瘍に伴う頭痛・吐き気・視覚異常
- 腹痛や腹部の膨らみ(腹部に腫瘍がある場合)
血液検査で腫瘍マーカーを測定するほか、画像検査や生検が主な診断方法です。治療は化学療法や外科的切除・放射線治療を組み合わせて行われることが多いですが、腫瘍の種類や進行度によって実際に治療方法が決められます。早期発見と専門医による適切な治療により、予後は改善していますが、成長やホルモンバランスへの影響を考慮した長期フォローも重要です。
参考:小児がん | 国立成育医療研究センター
参考:小児がんについて:[国立がん研究センター がん情報サービス 一般の方へ]
小児がんの症状と治療方法
ここでは小児がん全体で多く見られる症状や、現在行われている主要な治療法について分かりやすく解説しています。小児がんは早期発見・早期治療が非常に重要な疾患なので、あらかじめ症状や治療の特徴を把握しておくことで適切に対応できるようになります。
小児がんの症状
小児がんは初期症状が風邪と似ていることも多く、気づきにくい場合があります。代表的な症状として長引く発熱や顔色の悪化による貧血・皮膚にあざができやすくなること・骨や間接の痛み、首やわきの下や腹部などに触れるしこりが挙げられます。腫瘍の種類や部位によっては、嘔吐や視覚障害・体重減少などが現れることがあります。
小児がんの症状は軽度の場合も多いため、家庭ではしばらくすれば症状は改善するだろうと見過ごされてしまいがちですが、持続したり複数の症状が重なる場合は注意が必要です。早期発見と適切な治療が治療の成否に大きく影響するため、気になる症状が続く場合は迷わず小児科または小児がんを扱う専門医のいる医療機関を受診しましょう。
小児がんの治療
小児がんの治療は、抗がん剤(化学療法)が中心となっており、主要の種類や進行度に応じて手術や放射線治療が組み合わせられます。白血病などの血液のがんでは化学療法が主体となり、固形腫瘍では手術での切除が基本ですが、再発リスクや主要の位置によって放射線治療が行われているのが実情です。
近年は治療法の進歩により成績が向上しており、適切な治療を受けた子どもの多くは長期生存できています。実際に、急性リンパ性白血病では5年生存率が80%を超える例も報告されており、医療の発展によって以前よりも安心して治療に臨める状況が整えられつつあります。治療中は副作用への対応や生活支援も重要で、医療チームが継続的にサポートしています。
参考:小児がんの原因は?疑うべき10の症状~ 白血病/脳腫瘍/リンパ腫/網膜芽細胞腫
参考:小児がんの原因とは? 5年生存率や早期発見するためのポイントについて解説 | がん免疫療法コラム | 一般社団法人同仁会 同仁クリニック
発症・生存率のデータから見る小児がんの現状
本章では、小児がんへの発症率や生存率、死亡率の推移をデータで示し、さらに世界と日本の比較について解説します。小児がんの現状を数値で把握することでより理解が深まることでしょう。
日本の小児がん発症率・生存率の推移
小児がんは子どもの病死原因の第1位であり、日本では年間約2,000~2,500人が新たに発症しています。人口に換算すると、10,000人あたり1~1.5人の割合で発症する計算です。
| 調査施設数(カ所) | 調査対象数(人) | 実測生存率(%) | 相対生存率(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 白血病 | 102 | 946 | 87.9 | 88.0 |
| リンパ腫 | 86 | 203 | 90.6 | 90.7 |
| 脳腫瘍 | 156 | 698 | 74.5 | 74.6 |
| 神経芽腫 | 68 | 163 | 78.5 | 78.6 |
| 網膜芽腫 | 27 | 105 | 95.2 | 95.4 |
| 腎腫瘍 | 32 | 50 | 93.8 | 93.8 |
| 肝腫瘍 | 43 | 69 | 87.0 | 87.1 |
| 骨腫瘍 | 58 | 136 | 70.4 | 70.5 |
| 軟部腫瘍 | 78 | 151 | 79.2 | 79.3 |
| 胚細胞腫瘍 | 98 | 199 | 96.5 | 96.6 |
小児がんは成長途上にある細胞が原因であるため細胞分裂が活発なことから成人のがんに比べて進行が早いのが特徴ですが、その一方で治療効果も比較的高く、長期的な治療と継続的なフォローアップが求められます。治療法の進歩により、主要な小児がんの5年生存率は80%前後まで向上しており、急性リンパ性白血病ではさらに高い割合を示す例もあります。
しかし、治療後には晩期合併症のリスクが残るため、小児がん自体の治療がひと通り完了したとしても、長期にわたる健康管理や成長・発達のサポートが重要です。小児がんに関するデータは、治療方針や支援体制を考えるうえで欠かせない情報となるでしょう。
世界と日本の比較
日本では小児がんの5年生存率が約80~85%と高い水準を示していますが、途上国では20~30%にとどまることが多く、国によって生存率に大きな差があるのが現状です。
国によって生存率に大きな差が生じる主な要因としては医療インフラの整備が十分ではないこと、専門医や必要な薬剤・治療へのアクセスの制限・診断の遅れ・経済的格差の存在・医療費助成制度の有無などが挙げられます。途上国では設備や薬剤の不足により標準的な治療が受けられないことが多く、治療開始が遅れるケースも少なくありません。
また、家庭の経済的負担が重く、治療を受けたくても治療費が支払えず断念せざるを得ない場合もあります。国家間の生存率の格差に関する課題に対しては、国際的な支援や国内の医療体制の充実が必要で、早期診断と適切な治療をすべての子どもに届けることが求められています。
参考:低所得国の小児がん医療の現状
参考:国際小児がんデー « がんの子どもを守る会
小児がんの原因
小児がんの原因はひとつに特定できるものではなく、さまざまな要因が複雑に関与していると考えられています。成人のがんでは生活習慣や環境因子が大きく影響しますが、小児がんの場合は主に遺伝的な要因や発育途中の細胞で起こる突然変異によって発症することが多いです。
したがって成人のがんのように、喫煙や食生活・肥満といった生活習慣が直接の原因となることはほとんどありません。最近の研究では、一部の遺伝子異常や染色体の変化が特定の小児がんと関連していることが分かってきましたが、多くの場合は偶発的に発生するケースがほとんどです。また、成長過程にある子どもの細胞は分裂が活発であり、突然変異が起きやすいことも発症の背景にあると考えられています。以上の理由から、小児がんの予防は生活習慣だけでは不十分であり、早期発見や専門医による適切な診断が重要です。
小児がんになりやすい子の特徴はある?
小児がんは生活習慣や親の行動が原因で発症しやすくなるというケースはほとんどなく、特定の「なりやすい」定義というものが存在しないのが実情です。ただし、ごく一部では遺伝的な要因やダウン症など特定の疾患を持つ子どもで発症率が高い傾向にあります。その他の多くのケースでは、偶発的に発生するものであるため、予防することは非常に難しいです。
小児がんが発症するメカニズムを考慮すると、発症は親の責任ではなく、本人や家族が自分を責める必要はありません。医療従事者も小児がんの発症が偶発的であることは十分理解しており、子どもと家族を全面的に支えるサポート体制が整えられています。大切なのは、日常生活で健康管理に努めつつ、気になる症状があれば早めに医療機関を受診することです。
参考:小児がん(子どものがん) (しょうにがん)とは | 済生会
小児がんの現場で抱える課題・問題点
小児がんに対しての医療体制を整えるための活動は積極的に行われてはいるものの、地方や遠隔地では適切な治療を実施できなかったり、医療従事者が全国的に不足していたりと現場ではさまざまな課題に直面しているのが現状です。
治療中の子どもと家族の悩み
小児がんの治療では、長期入院や頻繁な通院が必要となることが多く、子どもは学校生活や友だちとの関係に悩むことがありますし、学業の遅れや社会性の変化が心配される場面も少なくありません。また、保護者は子どもの病状や治療の進行に対する不安やストレスを抱え、兄弟姉妹にも気を配る必要があります。
家族全体が精神的負担を感じることも多く、日常生活の維持や家庭内の役割分担に悩むケースも出ているのが現状です。家庭間の悩みを解決させるには、医療従事者や学校、支援団体が家族全体を見守り、気軽に相談できる環境を整えることが重要となります。適切なサポートがあれば、子どもも家族も安心して治療に専念できます。
地方・遠隔地での治療の現実
小児がん治療では、住んでいる地域によって受けられる医療やサポートに大きな差が生じることがあります。小児がん専門医や高度な医療設備は都市部に集中しており、地方では十分な治療を受けにくいといったケースが出ているのが現状です。
したがって、地方から都市部の拠点病院まで数時間かけて通院する家族も少なくありません。入院期間中は親が付き添うことも多く、通院や生活の負担が大きくなるケースもあります。また、専門的な支援を受けられる施設が限られているため、地方に居住していると医療情報や心理的サポートの入手にも困難を感じることもあります。
小児がんの治療に関する地域格差は、子どもや家族の生活に大きな影響を与える重要な課題であり、地方における医療体制の充実や、遠隔医療の導入が求められています。
医療従事者不足の課題
小児がん医療の現場においては、小児がん専門医や専門看護師が慢性的に不足していて、1人の医師が多数の患者を担当することも少なくありません。医師の負担が増加していることにより、治療内容の説明や心理的ケアに対して十分な時間を割くことが難しい場合があります。また、急性期の治療や入院管理に追われることにより、家族の不安や子どもの心のケアに十分対応できないケースが生じているのが現状です。
医療従事者の全体的な不足は、治療の質や患者・家族の安心感に直結する重要な課題であり、医師や看護師の増員や専門職の育成・働きやすい環境づくりが求められています。地方では専門医の不足が都市部以上に深刻で、遠隔地からの通院や医療支援の格差が生まれる大きな原因となっています。医療従事者不足を改善するためには、全国的な医療体制の強化や地域間連携の推進が必要不可欠です。
参考:はじめに |小児がん|九州大学病院のがん診療|九州大学病院 がんセンター
参考:がん患者さんと支える家族、周りの人とのインタビュー【対談】小児がんの親子と小児がんの子どもの支援を行った学校関係者に聞く|小野薬品 がん情報 一般向け | 小野薬品 がん情報 一般向け
参考:未来へ向かう私たちの相談窓口 参考書
参考:小児がん患者の親を支える
参考:小児科医師確保計画を踏まえた小児医療の確保についての政策研究
参考:小児科医確保に関する提言─より良き小児医療実現のために─|公益社団法人 日本小児科学会 JAPAN PEDIATRIC SOCIETY
参考:東京都の小児医療の今後の課題について
小児がんの地域・NPOなどの対策・アプローチ方法
小児がん治療においては医療費助成・交通費補助をはじめとする公的支援だけではなく、NPO法人や患者会など民間的支援も多数あり、課題解決に向けて多彩なアプローチが存在します。各支援の特徴を理解し、有効活用すれば安心して治療を受けられるようになるでしょう。
公的支援・医療費助成・交通費補助
小児がんの治療に伴って発生する医療費を軽減するための制度として、小児慢性特定疾病医療費助成制度があります。同制度は、小児がんをはじめとする小児慢性特定疾病の子どもが医療機関で治療を受ける際の医療費を助成する制度です。
申請はかかりつけ医や居住地の自治体の窓口を通じて行い、状況によっては通院や入院の際にかかる交通費や宿泊費の補助も受けられます。交通費や宿泊費の支援により、地方に住んでいて遠方から都市部にある拠点病院への通院が必要な家族でも、経済的負担を軽減しながら治療の継続が可能です。
制度の内容や申請方法は地域により異なるので、事前に確認しておくと良いでしょう。
拠点病院・遠隔医療
現在では全国に小児がん拠点病院が設置されており、地方に住む家族も以前と比べれば専門的な治療を受けやすくなりました。拠点病院では小児がんに特化した医師や看護師が治療にあたるため、都市部に行かずとも最新の治療やケアが提供されます。
また、遠隔診療や地域支援の仕組みも構築されつつあり、地方に住む子供や家族であっても地元に居ながら専門医のアドバイスを受けやすくなっています。遠方での診療や症例相談を通じて地方の医療機関でも高度な判断や治療方針の確認が出来るようになっていて、取り組みが進めば医療の地域格差を減らすことが可能です。拠点病院や遠方診療の体制が充実していくことにより、住んでいる場所に縛られることなく安全で質の高い医療を受けられるようになるでしょう。
NPO・患者会など民間支援の役割
ゴールドリボン・ネットワークやがんの子どもを守る会をはじめとしたNPOは、小児がんの子どもと家族を支援するさまざまな活動を実施中です。相談窓口を通じての精神的サポートや、学習支援、同じ経験を持つ家族とのピアサポート(同じような悩みを持つ人たちが互いに支え合うこと)など、民間ならではのきめ細やかな支援を提供しています。
治療中や退院後の生活で生じる不安や困難に対して、医療機関では補いきれない支援を受けられるのが最大の特徴です。また、イベントや情報提供を通じて、子どもや家族が安心して日常生活を送れる環境づくりにも取り組んでいます。民間団体の活動は、治療や生活の質向上のための大きな助けとなっています。
参考:厚生労働省 小児慢性特定疾病対策の概要
参考:医療費助成 – 小児慢性特定疾病情報センター
参考:小児がん拠点病院 | 国立成育医療研究センター
いま受けられる小児がんの子供・家族を支援やサポート
ここでは、小児がんの子どもを抱えるご家庭が安心して治療に集中できる環境を作っていくために現時点で利用可能な相談窓口・支援団体・学業・就労支援のサービスを紹介します。
相談窓口・支援団体のサポート
国立成育医療研究センターの小児がんセンターでは、小児がん医療相談ホットラインを設けており、患者やご家族からの治療内容・副作用・生活に関する不安など、小児がんの幅広い相談を専門スタッフが受け付けています。また、東京都では子どもの健康相談室を設け、小児がんを含む子どもの健康に関する悩みを電話や窓口で相談できる体制を整えています。
さらに全国のがん拠点病院にはがん相談支援センターを設置しているほか、民間の電話相談窓口もあり、専門的な情報提供や心理的なサポートを受けることが可能です。さまざまな相談窓口を活用することで、医療面だけではなく、精神的な負担を和らげ、安心して治療や生活に向き合えるようになります。
学習・就労支援
小児がん治療中の子どもに対しては、病院内に設置される院内学級で学習を続けられる仕組みが構築されています。学習支援ボランティアや公益財団法人ゴールドリボン・ネットワークによるオンライン学習支援など、病気療養児が学習の遅れを最小限に抑えるための取り組みも広がっています。
さらに親の就労支援としては、認定NPO法人ハートリンクワーキングプロジェクトが在宅勤務や短時間勤務の情報提供を行っており、活用することで仕事と看病の両立が可能です。利用にあたっては、病院や教育委員会、支援団体の窓口に相談し、必要に応じて申請手続きを経て支援を受ける流れが一般的です。紹介した制度やサービスを活用することで、子どもと家族が安心して学びや働く環境を整えることができます。
参考:小児がん医療相談ホットライン | 国立成育医療研究センター
参考:子供の健康相談室(小児救急相談)|相談窓口|東京都福祉局
参考:小児がんの相談・病院:[国立がん研究センター がん情報サービス 一般の方へ]
小児がんとSDGsの関係
小児がんの子どもたちや家族を支える活動は、「誰ひとり取り残さない」というSDGsの理念と直結しています。小児がんは長期入院や通院を伴うことが多く、子ども本人だけでなく家族の生活や仕事にも影響が出ます。そのため医療・教育・福祉が連携し、子どもと家庭を包括的に支える仕組みづくりが求められます。こうした取り組みは、SDGsがめざす持続可能な社会を達成することにもつながります。
SDGs3「すべての人に健康と福祉を」と小児がんの関係
SDGs3は、小児がんの治療やケアの質を高めるだけでなく、家族が経済的・精神的負担を抱えすぎないように支援を広げることも含まれています。また、小児がんの治療後のフォローアップや再発予防、そして生活の質(QOL)向上に対するサポートも重要です。
医療を充実させるだけでなく、地域や社会が小児がんを発症した子どもとその家族を支えることが、目標達成につながります。
SDGs4「質の高い教育をみんなに」と小児がんの関係
小児がんの治療中は治療や入院生活のために、学校を休んだり十分に勉強ができなくなるため、学習や友人関係に影響が出るケースもあります。SDGs4「質の高い教育をみんなに」の目標を達成するためには、小児がんを発症した子どもが安心して学べる環境づくりのために、病院内学級やオンライン学習、復学支援を充実させ、学びの機会を確保することも欠かせません
小児がんの子どもたちや家族を支える活動は、「誰ひとり取り残さない」というSDGsの理念と結びついています。小児がんは長期入院や通院を伴うことが多いため、子ども本人だけでなく家族の生活や仕事にも影響が出ます。
そのため医療・教育・福祉が連携し、子どもと家庭を包括的に支える仕組みづくりが求められます。こうした取り組みは、SDGsがめざす持続可能で公平な社会の土台となります。
小児がんのよくある質問
小児がんの治療に関して、患者やご家族は経験がないことばかりであり、さまざまな不安が襲ってくることでしょう。ここでは小児がん患者を抱える家族が抱く疑問のうち、特に多い5つをピックアップして回答例を紹介します。
Q1. 主治医や担当医が異動や退職した場合、どのように継続的なフォローアップを受ければよいですか?
小児がんの治療やフォローアップは病院単位で継続させる仕組みが整えられています。主治医が異動・退職しても次の医師に引き継ぎが行われて治療の継続性は保たれます。小児がん拠点病院や連携病院では、チーム医療体制が整っていて、複数の専門医や看護師が患者を支えるため、一人の医師に依存することはありません。
Q2. 治療中や治療後の妊娠・出産への影響が心配ですが、どこで相談できますか?
小児がん治療には抗がん剤や放射線療法が含まれることが多いです。そのため、将来の妊娠・出産に何らかの影響を及ぼす場合があるのは紛れもない事実です。治療前後には生殖機能温存の可能性を含めて相談できるよう、小児がん拠点病院や成育医療研究センターでは生殖医療や内分泌を専門とする医師が在籍しています。
また、市域のがん相談支援センターや患者会でも情報を得られます。妊娠・出産を考える時期になったら、必ず主治医・産婦人科医に相談し、医学的に安全な方法を検討するとよいでしょう。
Q3. 自分や家族が信頼できる医療情報をどうやって見分ければよいですか?
インターネットには多くの医療情報がありますが、中には信頼性が低いものも含まれているのが実情です。小児がんに関する正確な情報を得るには国立がん研究センターのがん情報サービスや日本小児がん研究グループなど、公的機関や専門団体が発信する情報を活用することが基本です。不安に感じる情報に出会った場合は、独断で判断せず、必ず主治医や相談窓口で確認しましょう。
Q4. 治療後の生活や学校復帰ではどのようなことを準備すればいいですか?
治療後の生活では、体力の回復や免疫の状態に個人差があります。したがって、学校復帰の際には主治医の意見書や復学支援シートを利用し、学校と病院が連携して支援を進めることが推奨されています。また、院内学級や教育委員会による学習支援制度を活用すると、学習の遅れを取り戻しやすいです。
友人関係や心理面のサポートも重要で、スクールのカウンセラーや支援員が関わることもあります。焦らず段階的に復帰し、子どものペースを大切にすることが基本です。
Q5. 新しい治療法や臨床試験について知りたい場合、どのように情報収集すればよいですか?
最新の治療法や臨床試験に関する情報は、国立がん研究センターのがん情報サービスや小児がん臨床試験グループの公式サイトで確認可能です。また、主治医に相談することで、臨床試験の対象となるかや適応可能な治療があるかを判断してもらえます。インターネットで個人の体験談や未承認治療を目にすることもありますが、信頼性が低い場合が多いため注意が必要です。
まずは専門医やがん相談支援センターを通じて、公的な情報に基づいた判断を心がけましょう。
まとめ
小児がんは遺伝的要因や突発性要因によって発症するケースが多く、予防が難しい病気です。しかし医療の進歩により多くの子どもが治療を乗り越えられるようになりました。一方で家族の心理的負担・地域格差・医療従事者不足など課題も残されています。しかし公的制度や拠点病院、遠隔診療、NPOの活動など、多様な支援の輪が広がることで少しずつではあるものの課題解決への道筋が見えつつあります。正しい情報を得て、相談窓口や支援制度を積極的に活用し、子供と家族が安心して未来を描ける環境を整えることが重要です。
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS