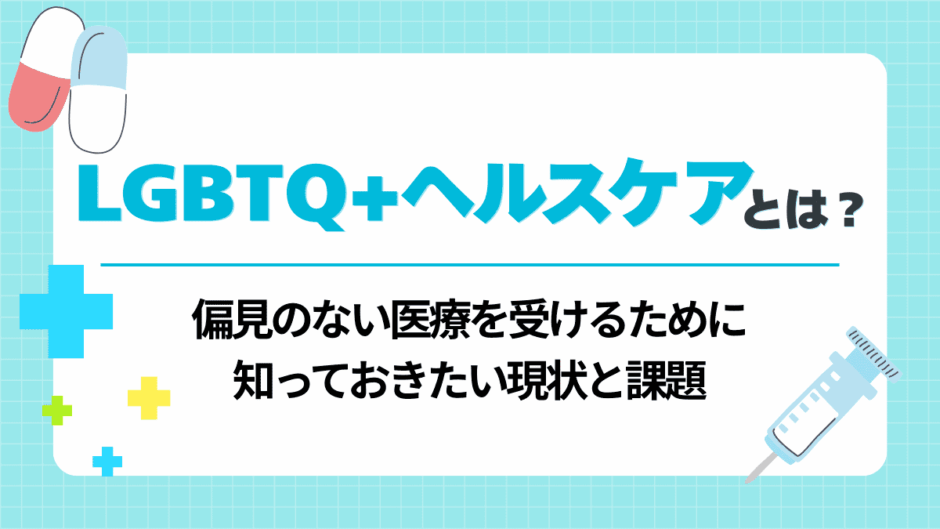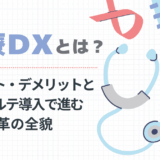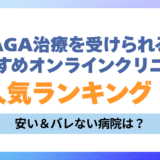LGBTQ+ヘルスケアは、性別や性的指向に関係なく、誰もが安心して医療を受けられる社会を目指す新しい医療の形です。近年、日本でも多様な性のあり方への理解が広がる一方で、医療現場ではまだ偏見や制度の壁が存在しています。たとえば、受診の際に性別欄で迷ったり、カミングアウトをためらったりする人も少なくありません。
本記事では、LGBTQ+ヘルスケアの基本的な考え方から、国内外の現状、支援体制、そして当事者が直面する課題までをわかりやすく解説します。
LGBTQ+ヘルスケアとは?

LGBTQ+ヘルスケアとは、多様な性のあり方を尊重し、すべての人が安心して医療を受けられる環境を整えることです。従来の医療は男性か女性がという考えが基本になっていたため、トランスジェンダーやノンバイナリーなど、多様な性の人々のニーズに応えられていませんでした。LGBTQ+ヘルスケアは、このような医療の差をなくし、誰もが気持ちよく健康に過ごせる社会を目指しています。
患者の性自認や呼び方への配慮、問診票やカルテの記入方法の見直しなど、小さな工夫が安心感につながります。LGBTQ+ヘルスケアは、特定の人々だけでなく、誰もが自分らしく健康に生きる権利を支える、社会全体の取り組みです。
LGBTQ+ヘルスケアがカバーする領域
LGBTQ+ヘルスケアがカバーする領域をご紹介します。
心理的なケアや社会的サポート
LGBTQ+ヘルスケアの考え方は、身体的な医療だけでなく、心理的なケアや社会的サポートも対象にしています。
医療の現場では、性別適合手術やホルモン療法などの性分化疾患や性同一性障害(GID)に関する治療が中心ですが、一般的な内科や婦人科、泌尿器科などの診療においても、性的指向や性自認を尊重した問診や診察が求められています。患者が安心して受診できることが、LGBTQ+ヘルスケアの基本です。
社会保障制度の活用支援
福祉の面では、法的性別変更に関する情報提供や支援、社会保障制度の活用支援が重要です。パートナーシップ制度に基づき、医療同意や緊急時の対応、戸籍上の性別に関わらず適切な医療を受けられるようになっています。
心理的なケアとしては、カウンセリングや心理療法、精神疾患の治療を通じ、性自認やカミングアウトに伴うストレスを軽減する支援も行われています。
日本と世界のLGBTQ+ヘルスケア事情
LGBTQ+ヘルスケアの取り組みは、国や地域によって大きく異なります。ここでは、日本と世界それぞれの現状を比較し、違いや課題、そして世界から学ぶべき点をまとめます。
日本のLGBTQ+ヘルスケアの現状
日本のLGBTQ+ヘルスケアの現状をご紹介します。
日本のLGBTQ+ヘルスケアはまだまだ発展途上
日本におけるLGBTQ+ヘルスケアは、まだ発展途上です。性的少数者への医療対応は十分とはいえず、専門医の数も限られています。
LGBTQ+の人たちのうち3人に1人が、医療サービスを利用する際に困難を感じたことがあるというデータもありました。中でも、T(トランスジェンダー)の人々は、自身の性別と体の性別に違和感があるため、約8割が医療サービスを受診する際の困難を感じたというデータもあります。
その結果約4割が病院の受診ができなくなるケースとなり、メンタルヘルスの悪化にも繋がってしまっているのが現状です。
他にも、問診票の性別欄が男性・女性のみであったり、異性愛を前提とした医師の偏見が受診を遠ざけてしまうといったこともあります。
性別適合手術やホルモン療法を行う医療機関が少ない
性別適合手術やホルモン療法を行う医療機関は少なく、都市部と地方で情報や受診環境に差があります。偏見や理解不足から、カミングアウトをためらい、必要な医療を受けられない人もいます。
医療機関によって対応の質にも大きなばらつきがあります。問診や診察で多様な性を尊重した対応が行われるかどうかは、医師やスタッフの理解度次第です。
LGBTQ+の人々が安心して通える病院を見つけるまでに時間がかかることも多く、医療機関を受診すること自体が難しいこともあります。
しかし前向きな変化も少しずつ見られます。LGBTQ+フレンドリーを掲げるクリニックが増え始め、一部の大学病院ではGID(性同一性障害)専門外来が開設されています。
世界のLGBTQ+ヘルスケアの現状
世界のLGBTQ+ヘルスケアの現状を見ていきましょう。
世界のLGBTQ+ヘルスケアの現状は日本よりも進んでいる
世界では、LGBTQ+ヘルスケアへの取り組みが日本よりも一歩進んでいる国々があります。特にイギリスでは、国民保健サービス(NHS)が中心となり、医療従事者に対するLGBT+ヘルスケア研修を制度化しています。
この研修では、性的指向や性自認に関する正しい用語の使用、差別禁止の徹底などが義務づけられ、現場での理解が深まっています。
カナダも先進国のひとつです。法律で性的指向や性自認に基づく差別を禁止しており、医療機関が差別的な対応をした場合、罰せられます。公的医療保険制度により、性別適合手術やホルモン療法の費用が抑えられるのも特徴です。
これらの国々では、制度だけでなく社会的な理解も進んでいます。LGBTQ+ヘルスケアが特別な支援ではなく、誰もが平等に受けるべき権利であるという考えが広がっています。
メンタルヘルスや性感染症(HIVなど)のリスクが高い
世界のLGBTQ+ヘルスケアの現状として、メンタルヘルスや性感染症(HIV)などのリスクが日本より高いのは、注目すべきポイントです。
特にうつ病などのメンタルヘルスはどうしてもLGBTQ+の人の中には多く、約4割がなんらかのメンタルヘルスを抱えているというデータもあります。この数字は、一般の人と比べると約12倍も多いのが現状です。
他にも性感染症になるリスクも日本に比べて高く、HIVなどが多い点も日本との大きな違いです。他の性病に罹患する可能性も日本より高く、レズビアン・バイセクシャルの身体的女性の場合は、乳がんのリスクが高まります。
トランスジェンダーの場合は、ホルモン関連療法を行うと心身ともにダメージを受けてしまう可能性が高まってしまいます。
日本の世界の取り組みとのギャップ
世界各国では、LGBTQ+の人々が平等に医療を受けられるよう、法制度や社会的支援の整備が進んでいます。たとえば欧米諸国では、法律によって多様な性的指向や性自認への差別を禁じています。性別承認(戸籍変更)の手続きも簡単におこなえます。さらに、多くの国で同性婚やパートナーシップが法的に認められ、医療の意思決定や面会が可能です。
一方で、日本はこうした国々と比べて遅れをとっています。性別適合手術やホルモン療法を受けるには、厳しい法的条件があり、戸籍変更にも複雑な手続きが求められます。同性カップルには法的保護がほとんどなく、医療同意や家族としての扱いが認められないことがおおいです。
海外では専門クリニックが増え、教育を受けた医療従事者も多いですが、日本では専門医が慢性的に不足しています。医療保険の適用外で治療費が高額になってしまうこともあります。そのため、LGBTQ+の人々が適切な医療ケアや精神的なサポートを受けにくい状況にあると言えます。これはLGBTQ+ヘルスケアの国際的な広がりと大きく乖離しているといえます。
LGBTQ+ヘルスケアの目的
なぜ医療へのアクセスや健康格差といった課題が生じてしまうのでしょうか。その背景には、制度や意識の壁が存在します。ここからは、LGBTQ+ヘルスケアの目的と意義を掘り下げていきます。
偏見や差別のない医療環境の実現
LGBTQ+ヘルスケアの大きな目的は、偏見や差別のない医療環境を作ることです。性的指向や性自認によって診察を拒否されたり、不適切な言葉をかけられたりする事例は、残念ながらまだ存在します。こうした状況を改善するには、医療現場における制度づくりが欠かせません。
差別禁止規定を明確化することで、患者と医療従事者は公平な関係を築けるようになります。また、全スタッフを対象とした研修を実施し、正しい知識と対応を身につけることが大切です。問診票やカルテの性別欄を見直すことも、改善策のひとつです。
これらの取り組みは、LGBTQ+当事者だけでなく、すべての人が安心して医療を受けられる社会につながります。偏見のない医療環境は、医療の公平性と質を高めることにもつながります。
LGBTQ+特有の健康ニーズへの対応
性的指向や性自認に応じた特有の健康ニーズに対応することも重要です。たとえば、トランスジェンダーの人にはホルモン療法や性別適合手術に関する継続的な医療管理が必要です。ホルモン投与による副作用や、検診の際の配慮など、一般的な医療とは異なる対応が求められます。
ゲイやバイセクシュアルの男性にとっては、HIVや性感染症(STI)の予防・検査体制の充実が重要です。レズビアンやトランスジェンダー女性が、婦人科検診や避妊指導を受けられないケースもあり、性別やパートナーシップに応じた情報提供が求められています。LGBTQ+ヘルスケアは、病気を治すだけでなく、一人ひとりの性のあり方を尊重し、健康で自分らしい生活を支えるものです。
メンタルヘルスの支援の向上
LGBTQ+ヘルスケアは、LGBTQ+の人々への心理的ケアも重要な目的のひとつです。性的指向や性自認に対する社会的偏見や差別、職場や家庭での理解不足は、当事者の心理的負担を大きくし、うつ病や不安障害、自尊感情の低下などを引き起こす要因です。精神的な問題を軽減するには、専門的な支援体制の整備が欠かせません。
LGBTQ+に理解のあるカウンセラーや臨床心理士による相談窓口の設置、医療機関とメンタルサポート機関の連携強化などが求められます。特に、カミングアウトやジェンダー移行の過程では心理的なサポートが重要です。
LGBTQ+ヘルスケアのリアル|当事者が直面する困難と課題
ここからは、制度や意識の課題を超えて、LGBTQ+当事者が実際に医療や福祉の現場でどのような困難に直面しているのか、その具体的な現状に目を向けていきます。
受診控えやカミングアウトの難しさ
LGBTQ+の人々が医療機関を受診する際に、「不適切な質問をされるのではないか」「プライバシーが守られないのではないか」といった不安を抱く人は少なくありません。こうした懸念から、医療従事者に性自認や性的指向を伝えることをためらうケースがあります。
こうした心理的抵抗は、「受診控え」につながってしまいます。体調の変化や病気の初期症状に気づいても、医療機関に行くことをためらい、自己判断で我慢してしまうこともあります。健康診断や婦人科・泌尿器科検診などの定期的な受診を避け、重症化してからようやく医療を受けるという悪循環が起こっているのです。
こうした負の連鎖を断ち切るためにも、誰もが安心して受診できる環境整備が欠かせません。医療従事者が理解を深めプライバシーに配慮した対応が広がることで、LGBTQ+の人々が早期受診できるようになり、健康を維持することができるのです。
医療従事者の知識不足・差別的対応
LGBTQ+ヘルスケアにおける深刻な課題の一つが、医療従事者の知識不足と無意識の差別的対応です。多くの医療従事者が性的指向や性自認に関する専門的教育を受けておらず、正しい対応方法や適切な用語を知らないまま診療にあたっています。そのため、患者がトランスジェンダーであることを打ち明けた際に、不適切な質問や誤った診察が行われることも少なくありません。
戸籍上の性別と見た目の違いから医療者が混乱し、必要以上に詮索したり、他の患者の前で呼び方を誤るなどの事例もあります。こうした行為は、当事者にとって精神的な苦痛を与え、医療機関への不信感につながります。
相談できる場や支援体制の不足
相談できる場の少なさや、支援体制の不十分さも課題です。LGBTQ医療福祉調査によると、行政・福祉関係者にセクシュアリティについて安心して話せないと答えた人は95.4%にのぼります。さらに、約半数がセクシュアリティを支援者に伝えなかったことで、必要な支援を受けられなかったと回答しています。
また、LGBTQの約7割が医療サービス利用時にセクシュアリティに関する困難を経験しており、特にトランスジェンダーの人々ではその割合が高くなっています。理由は「どの医療者に安心して相談できるかわからない」「医療者の知識不足」といったことが挙げられています。 結果として、体調が悪くても病院に行けなくなり、自殺念慮・未遂を経験した人もいます。命や健康を守るための医療・福祉サービスが、安全に利用できない現状は深刻です。LGBTQ+に配慮した相談窓口の設置や、医療従事者・行政職員への教育体制の強化が求められています。
変わる社会と進むLGBTQ+ヘルスケアへの取り組み
課題は依然として多いものの、社会は前へ進んでいます。医療現場や行政、企業、教育など、さまざまな分野でLGBTQ+ヘルスケアの取り組みが広がる今、その変化と未来への動きを見ていきましょう。
医療現場の改善策と実践例
日本の医療現場でもLGBTQ+ヘルスケアの理解促進と環境整備が進み始めています。一部の大学病院では、GID外来やジェンダークリニックが設置され、専門的な医療チームが形成されています。また、民間クリニックでもLGBTQフレンドリーを掲げ、問診票で性自認や呼称を尊重する設問を設け、配慮ある診療体制を導入する動きが広がっています。さらに、医療従事者への研修や教育も進んでいます。少しずつではありますが、このような取り組みが、誰もが安心して医療を受けられる社会の実現に近づいています。
国や自治体によるLGBTQ+ヘルスケアの支援の動き
国や自治体による支援 国や自治体でも、LGBTQ+ヘルスケアを推進するための支援が広がっています。性同一性障害特例法の運用改善が進められており、性別の取り扱いに関する柔軟な対応が検討されています。2023年には性自認に関する理解増進法が成立し、医療や福祉、教育などの現場で多様な性の理解を深める取り組みが求められるようになりました。地方自治体でも、独自の支援策が増えています。特にパートナーシップ宣誓制度は、同性カップルが病院での面会や医療同意の際にパートナーとして認められるケースを増やしています。
また、人権相談窓口の設置や、イベントの開催、医療機関へのガイドライン配布など、行政が果たす役割も大きくなっています。これらの取り組みは、LGBTQ+ヘルスケアについての理解を促し、偏見や差別のない医療環境の基盤となります。
LGBTQ+ヘルスケアに関する支援
LGBTQ+ヘルスケアを支えるためには、専門的な支援や相談体制が欠かせません。ここでは、安心して利用できる窓口や団体、制度などの支援情報を紹介します。
LGBTQ+ヘルスケア対応の相談窓口
現在、全国でLGBTQ+当事者や家族、医療従事者向けの支援窓口が整備されつつあります。たとえば、法務省の「みんなの人権110番」では性的指向や性自認に関する人権相談を受け付けています。また、厚生労働省の「よりそいホットライン」では、LGBTQ+に特化した専用回線が設けられ、匿名で専門の相談員に話すことができます。
認定NPO法人ReBitやプライドハウス東京などの団体も、医療や生活の困りごとに対応する無料相談を行っています。医療機関の紹介やカミングアウトのサポート、偏見に直面した際の対応方法など、具体的なアドバイスを受けることができます。
不安や悩みを抱えた際には、一人で抱え込まず安心して相談できる場を活用することが大切です。
LGBTQ+ヘルスケアの支援団体・コミュニティ
LGBTQ+ヘルスケアを支えるために、全国には多くの支援団体やコミュニティが存在します。代表的なものとして、プライドハウス東京があります。ここでは医療や福祉に関する相談、法的サポート、メンタルケアなどをワンストップで受けることができます。
NPO法人ReBitは、教育現場や企業、医療機関に向けて多様な性の理解を広める啓発活動を行い、社会づくりを推進しています。また、地域単位でもLGBTQ+ヘルスケアの情報共有や医療機関の紹介を行う団体が増えてきています。
このような支援団体やコミュニティが広がることで、LGBTQ+の人々が孤立せず、安心して医療を受けられる社会へと変化が生まれています。
LGBTQ+ヘルスケアに対する医療保険適用の拡大
LGBTQ+ヘルスケアにとって、性同一性障害(GID)に関する医療への健康保険適用の拡大は大きな前進といえます。特に2018年4月から、性別適合手術(性別変更のための手術)の一部が健康保険の対象となり、費用負担が大幅に軽減されました。これにより、手術費用のうち原則3割を自己負担すれば受けられるようになり、以前は数百万円も必要だった手術も、かなり負担が軽くなりました。
ただし、すべての関連手術が保険適用されるわけではありません。脱毛、豊胸、顔の女性化形成(FFS)など、美容的側面が強いと判断される医療行為は依然として保険の対象外です。また、保険を利用するには国の認可を受けた医療機関であることや、日本精神神経学会・GID学会の診断基準を満たすことなどの条件があります。
LGBTQ+ヘルスケアとSDGsの関係性
LGBTQ+ヘルスケアとSDGsの関係性をご紹介します。
目標3「すべての人に健康と福祉を」
LGBTQ+の人々は、差別や偏見などにさらされる機会が多く、一般人に比べても精神を病んでしまったりする確率が高いことがわかっています。医療従事者であっても、無理解の人も多いため受診をためらってしまったりする、LGBTQ+の当事者も数多くいます。
また肉体的にもLGBTQ+の人たちは危険に冒されやすく、HIVであったり乳がんといった病気が流行しやすくなっています。そのため、すべての人に健康と福祉をというSDGsの目標と深く関係しています。
目標5「ジェンダー平等を実現しよう」
目標5の「ジェンダー平等を実現しよう」についても、LGBTQ+と深く関わりがある目標です。
LGBTQ+の当事者たちが、自分自身の性自認であったり性的指向を自由に表現できる学校や職場、家庭などの環境を整備することは、ジェンダー平等の促進に寄与しています。
ジェンダー平等において日本が現在G7の中でも最下位と、多数の課題を残しているのが現状です。
LGBTQ+ヘルスケアのよくある質問
LGBTQ+ヘルスケアについて、疑問や不安を抱く方も多いのではないでしょうか。ここでは、受診や相談の際によく寄せられる質問をもとに、安心して医療を受けるためのヒントをまとめました。
Q1. LGBTQ+ヘルスケアに対応した医療機関はどうやって探せますか?
LGBTQ+ヘルスケアに対応した医療機関を探す際は、「Allyマップ(ノバルティス・ファーマ)」を活用するのがおすすめです。
Allyマップは、LGBTQ+の患者が安心して受診できる医師や医療機関を紹介するツールで、医療従事者向けの学習コンテンツとあわせて一般公開されています。また、医療機関の公式サイトで「SOGI(性的指向・性自認)への取り組み」や「LGBTQ+フレンドリー」などの記載を確認するのも有効です。
Q2. カミングアウトせずに受診できますか?
基本的にはカミングアウトせずに受診可能です。 多くの医療機関では、患者のプライバシーを尊重する取り組みが進められています。たとえば、問診票に「男性・女性」以外の性別選択肢を設けたり、希望する呼び方を自由に記入できる欄を用意しているケースがあります。
また、保険証に記載された性別と見た目が異なる場合でも、そのままの性別で診察室へ案内するなど、安心して受診できる環境を整える医療機関が増えています。心配な場合は「プライバシーに配慮してほしい」と伝えるといいでしょう。
Q3. パートナーと一緒に医療相談を受けたい場合、配慮してもらえますか?
多くの医療機関ではパートナーとの受診に対する配慮が進んでいます。 診察室への同席や病状説明を一緒に受けることを認める医療機関も増えています。
ただし、対応は医療機関によって異なるため、事前に電話などで「パートナーシップ関係にある者として同席が可能か」確認することが大切です。 また、自治体が発行するパートナーシップ証明書を提示すれば、家族に準じた扱いを受けやすくなる場合もあります。
Q4. 医療現場で差別的な対応を受けた場合、どこに相談できますか?
医療現場で差別的な対応を受けた場合は、まず医療機関内の「患者相談窓口」や「医療安全推進室」へ相談することをおすすめします。 患者の権利を守る立場から改善に向けた対応を取ってもらえることがあります。
それでも解決が難しい場合や、直接伝えにくい場合は、各都道府県の「医療安全支援センター」や「法務局の人権相談窓口」へ相談しましょう。さらに、LGBTQ+支援団体など外部の専門機関に相談することで、具体的な解決策や法的サポートを受けられる場合もあります。
Q5. 性自認と異なる性別の待合室や病室で過ごすことに抵抗がある場合、配慮してもらえますか?
性自認と異なる性別の待合室や病室で過ごすことに抵抗を感じる場合、個室の利用や中立的なスペースへの案内など、柔軟な対応を取るケースもあります。受診前に医療機関へ相談し、性別に関係なく安心して過ごせる環境を整えてもらえるか確認することが大切です。患者の希望を尊重する体制が徐々に広がっています。
まとめ
LGBTQ+ヘルスケアは、すべての人が自分らしく安心して医療を受けられる社会を目指すための大切な取り組みです。現状、日本では医療機関ごとの対応のばらつきや、医療従事者の知識不足、制度の未整備といった課題が依然として存在します。
しかし近年では、医療現場・行政・企業・教育機関・当事者コミュニティが連携し、理解促進や制度整備が着実に進んでいます。 LGBTQ+ヘルスケアを通じて偏見や差別のない医療環境を広げ、「誰もが自分らしく健康に生きる権利」を尊重される社会を目指しています。
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS