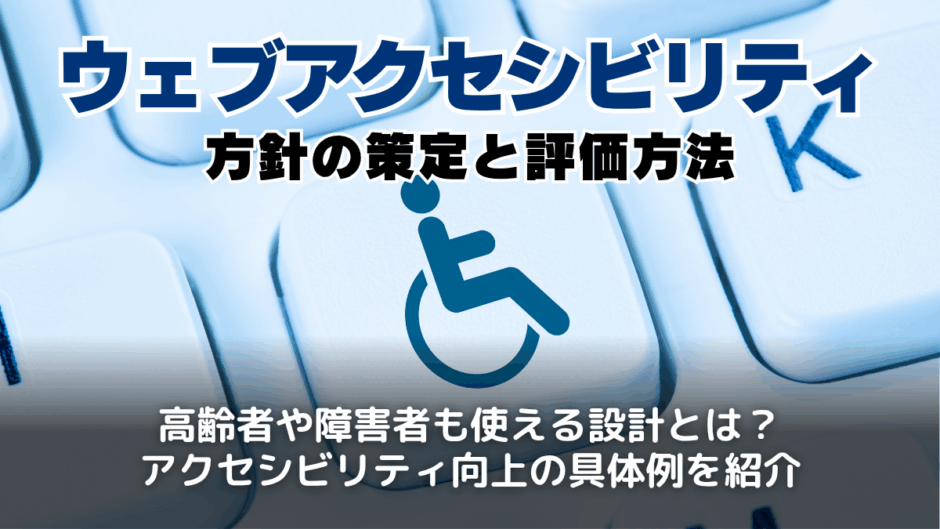ウェブアクセシビリティって何だろう?どうやって始めたらいいの?と思っている方も多いのではないでしょうか。ウェブアクセシビリティへの取り組みは、誰もが利用しやすいWebサイトを作るために欠かせません。法的義務としても位置づけられつつあり、企業の社会的責任として重要性が高まっています。
この記事では、ウェブアクセシビリティの基本概念から、JIS X 8341-3やWCAGとの関係、具体的な実装例まで詳しく解説します。ウェブアクセシビリティ方針の策定方法や、チェックツールを使った評価手法についても紹介。専門家でなくても、初心者でも取り組めるノウハウが満載です。ユーザー体験の向上やSEO対策にもつながるウェブアクセシビリティ。その導入方法と社内体制づくりのポイントを、事例を交えてお伝えします。
ウェブアクセシビリティとは?
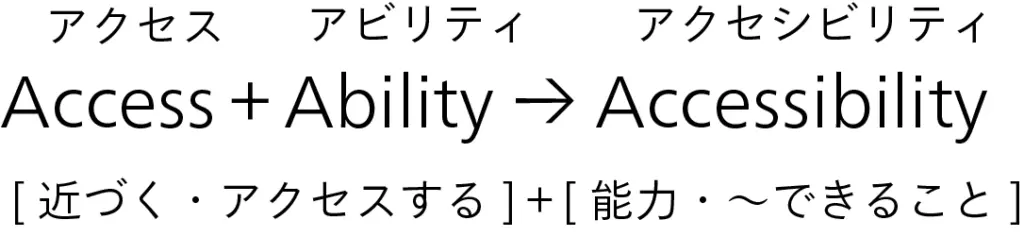
ウェブアクセシビリティとは、年齢や障害の有無に関わらず、使おうと思った人がWebサイトを利用できるようにすることを指す言葉です。目的は、すべての人に平等にWebの恩恵を提供することです。この章では、ウェブアクセシビリティの定義、対象となる利用者層、JIS X 8341-3とWCAGの違いや共通点、国際的・国内的な位置づけについて解説します。
ウェブアクセシビリティの対象と役割
ウェブアクセシビリティの対象となるのは、視覚障害者や聴覚障害者、肢体不自由者、認知障害者といった障害を持つ人々だけではなく、高齢者や一時的な障害を抱えている人、スマートフォンで閲覧している人なども含みます。
このような人々がWebサイトにアクセスしたり、情報を取得したりするときに、遮ってしまう要素を排除することがウェブアクセシビリティの重要な役割なのです。例えば、視覚障害者に対しては、画像に代替テキストを付与することで、スクリーンリーダーを使った情報取得を可能にします。聴覚障害者に対しては、動画に字幕を付けることで、音声情報を補完します。肢体不自由者に対しては、キーボードのみでの操作を可能にするなどの配慮が必要です。
多くの人々が障害なくWebサイトを利用できるように、適切な対応を行うことがウェブアクセシビリティの目的だといえます。
ウェブアクセシビリティの指標
JIS X 8341-3とWCAGは、ウェブアクセシビリティを確保するための指針として知られていますが、その内容には違いがあります。
JIS X 8341-3は、日本工業規格(通称:JIS)の一部で、高齢者、障害者等配慮設計指針の中のWebコンテンツのアクセシビリティに関する規格です。WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)は、W3C(World Wide Web Consortium)が策定した国際的なアクセシビリティガイドラインです。
以下の表は、JIS X 8341-3とWCAGの主な違いと共通点をまとめたものです。
| 比較項目 | JIS X 8341-3 | WCAG |
|---|---|---|
| 位置づけ | 日本の国内規格 | 国際的なガイドライン |
| 策定主体 | 日本規格協会(JSA) | W3C(World Wide Web Consortium) |
| 適合レベル | A、AA、AAA の3段階 | A、AA、AAA の3段階 |
| 内容 | WCAGをベースに日本の実情に合わせて作成 | Webアクセシビリティの国際的な指針 |
| 最新版 | 2016年発行(JIS X 8341-3:2016) | WCAG 2.1(2018年発行) |
| 法的拘束力 | 日本国内では一部の法令で準拠が求められる | 各国の法律により異なる |
ウェブアクセシビリティ達成のための具体例
ウェブアクセシビリティ達成のための具体例を見ていきましょう。
文字と背景の色味を適切なコントラスト比にする
文字と背景の色味を適切なコントラスト比にすることで、誰からも見えやすくなるようにすることもウェブアクセシビリティ達成の具体例です。
お店などで見るPOPや説明の資料など、文字と背景の色味が考えられていないと、色盲の人などで読めない人も見えやすいように工夫することが重要です。
動画に字幕を付ける
普段から動画を見ている人は、字幕があるかないかを気にしたことはあるでしょうか?
耳が聞こえない人にとって字幕が付いているかついていないかは、見る見ないの判断基準にもなります。これもウェブアクセシビリティの具体例です。
実際字幕がある動画も数多くありますが、ウェブアクセシビリティという点ではすべての動画で字幕が付くようになることが求められています。
ウェブアクセシビリティが必要とされている背景
ウェブアクセシビリティは、単なる法令遵守や社会的責任の問題だけではありません。アクセシビリティに配慮したサイトは、ユーザー体験の向上につながり、顧客満足度やロイヤルティの向上に寄与します。この章では、法的義務や社会的責任、ユーザー体験、SEOへの影響について紹介します。
障害者差別解消法の改正
2024年6月に施行される障害者差別解消法の改正により、合理的配慮の提供が義務化されます。サイトやアプリにおいては、動画字幕や音声解説を提供すること、キーボードの操作、十分な色のコントラストの確保などが要求されています。企業では、法律を遵守するだけでなく、全員が利用しやすいと思えるようなサービスを提供する責任を負っているのが事実です。特に公共性の高いサービスを提供する企業は、利用者の多様性を把握し、全員が平等にサービスを利用できる環境を整備しなければなりません。アクセシビリティへの取り組みを進め、平等な社会の実現に向けて、企業や自治体の果たす役割は大きいのです。
参考:2024年のウェブアクセシビリティについてわかりやすく解説 – ミニナレ [web制作会社シスコム]
満足度の高いユーザー体験
アクセシビリティに配慮したサイトは、障害者や健常者関係なくすべてのユーザーにとって利用しやすく、満足度の高いものになります。例を挙げると、検索エンジンはアクセシビリティの高いサイトを評価する傾向にあります。GoogleはWCAGへの影響が大きいことから、アクセシビリティ対応が適切なサイトは、検索結果で上位に表示される可能性が高くなります。ウェブアクセシビリティへの取り組みは、ビジネス成果に直結する重要なものであると捉えるべきでしょう。
参考:Home | Web Accessibility Initiative (WAI) | W3C
企業の社会的責任(CSR)
企業の社会的責任をご紹介します。
- 誰が見ても分かりやすいホームページを作成する
- 探しているコンテンツに素早くたどり着けるようにする
- 合理的配慮がなされているかを常に意識する
上記の3つが企業にとっての社会的責任です。誰が見ても分かりやすいホームページは、色の配色であったり求めているコンテンツにアクセスしやすくなっていたりと、わかりやすい工夫がなされています。
合理的配慮がなされているかは、特に重要で人によってはわかりにくいということがないよう、注意して作成する必要があるでしょう。
ウェブアクセシビリティの具体例と取り組み
ウェブアクセシビリティを進化させるべく、デザインでの工夫やマルチデバイスを用いた対応、音声支援技術の活用、適切な技術的実装など、様々な分野からの対策が必要です。
この章では、ウェブアクセシビリティの仕組みを改善させるための具体的な取り組みを、デザイン面、マルチデバイス対応と音声支援技術、技術的実装の3つの視点から解説します。
デザイン・UI面での工夫
ウェブアクセシビリティを改善させるためには、デザイン面、UI面での工夫が欠かせません。色のコントラストは、視覚障害者や色覚異常の方にとっても非常に重要な要素であり、具体例を用いると、背景色と文字色のコントラスト比を少なくとも4.5:1に保つことが推奨されているり、フォントサイズは最低でも16px以上がよいとされています。スマートフォンなどの画面が比較的小さなデバイスでも読みやすいよう、画面サイズに応じて見やすさを最適化することも重要です。
見出しの階層構造は、スクリーンリーダーを使用する視覚障害者にとって重要な意味を持ちます。H1からH6までの見出しタグを適切に使用し、論理的な構造を作ることが求められ、ボタンや、キーボードのみでも操作できるようにする必要があります。
マルチデバイス対応と音声支援技術
ウェブアクセシビリティの改善には、マルチデバイスへの対応、音声支援技術の活用が必要不可欠です。スマートフォンやタブレットなど、様々な電子機器で見ることを想定し、誰にとっても見やすく感じるようなデザインを採用することが重要です。電子機器の画面のサイズに応じてレイアウトを最適化し、どのデバイスでも快適に利用できるようにすることが目標です。
また、視覚障害者の多くは、音声ブラウザやスクリーンリーダーを使ってウェブサイトを閲覧します。これらの支援技術と相性の良いコーディングを心がける必要があります
技術的実装例
ウェブアクセシビリティを確保するためには、開発者による適切な技術的実装が不可欠です。まず、HTMLのセマンティックな使い方が重要です。適切な要素を使用し、見出しタグ(h1〜h6)で構造を明示することが求められます。また、ARIA(Accessible Rich Internet Applications)属性を活用することで、よりアクセシブルなウェブサイトを作ることができます。
画像には、必ず代替テキスト(altタグ)を付与しましょう。視覚障害者がスクリーンリーダーを使用する際、画像の内容を理解するために欠かせません。フォーム入力では、ラベルとフォーム・コントロールを関連付けるlabelタグの使用が重要です。プレースホルダーだけでは不十分で、明確なラベルを提供する必要があります。
また、CSSを使ってフォーカス時の表示を適切に設定することも大切です。キーボード操作でフォーカスが移動した際、現在位置がわかりやすいようにしましょう。JavaScriptを使う場合は、キーボード操作を妨げないよう注意が必要です。
ウェブアクセシビリティのチェックツールと評価方法
ウェブアクセシビリティのチェックツールと評価方法は、自動チェックツール、ユーザーテスト、第三者評価の3つに分類することができます。
この章では、サイトのアクセシビリティを定量的、定性的に評価する方法を解説します。
自動チェックツールの紹介
ウェブアクセシビリティを評価する際、自動チェックツールを活用することで効率的に問題点を発見できます。ここでは、よく知られている無料チェックツールを比較表にまとめて紹介します。
| チェックツール | 特徴 | 対応OS | 料金 |
|---|---|---|---|
| Lighthouse | Chromeブラウザに組み込まれたツール。ウェブサイトのパフォーマンス、アクセシビリティ、SEOなどを総合的に評価。 | Windows, macOS, Linux | 無料 |
| axe | Dequeが提供するブラウザ拡張機能。WCAGやSection 508などの国際的なガイドラインに基づいてチェック。 | Windows, macOS, Linux | 無料 |
| WAVE | WebAIMが提供するウェブベースのツール。視覚的なフィードバックによりアクセシビリティの問題を表示。 | Webブラウザから利用可能 | 無料 |
これらのツールは、いずれもウェブサイトのアクセシビリティを自動的にチェックし、問題点を指摘してくれる機能を持っています。ただし、自動チェックだけでは検出できない問題もあるのが現状です。そのため、手動での確認も必要となります。
Lighthouseは、Chromeブラウザに標準で組み込まれているため、手軽に利用できます。axeは、国際的なガイドラインの基準に沿ってチェックを行う点が特徴です。WAVEは、視覚的な指示の提示により、問題点を瞬時に把握できるというメリットを兼ね備えています。
この複数のツールを組み合わせてうまく利用することで、ウェブアクセシビリティの問題点を改善することにつなげることが期待できます。
ユーザーテストと第三者評価
自動チェックツールは、ウェブアクセシビリティの評価において効率的な手段ですが、実際のユーザー体験を理解するには不十分です。そこで、実利用者によるユーザーテストと、第三者機関によるアクセシビリティ診断サービスの活用が重要となります。
ユーザーテストでは、様々な障害や特性を持つ実利用者に、実際にウェブサイトを利用してもらいます。操作性、理解しやすさ、満足度などを評価してもらうことで、自動チェックでは見落とされがちな問題点を発見できます。また、実際のユーザーの意見を聞くことで、アクセシビリティ向上に必要な、具体的かつ現実的なアイデアを得ることができます。例を挙げると、視覚障害者の方にスクリーンリーダーを使ってウェブサイトを閲覧してもらい、理解しにくい、または改善した方がよいと思う点を指摘してもらうことで、より実用的なアクセシビリティの対応につなげることができます。
一方で、第三者機関によるアクセシビリティ診断サービスでは、専門知識を持つ者が、客観的な視点でウェブサイトのアクセシビリティを評価します。JIS X 8341-3やWCAGなどの基準に照らして、適合状況を詳細にチェックし、改善点を提示してくれます。第三者からの評価、つまり最も客観視できる方からの評価を受けることによって、自社のレベルを改めて認識し、信頼性が担保されたアクセシビリティ対応が実現可能です。また、第三者評価の結果を公表することで、企業の社会的責任を果たしていることを示すことができ、ブランドイメージの向上にもつながります。
ユーザーテストと第三者評価は、自動的なチェックツールでは捉えることが難しい点にも気づきをもたらしてくれるという利点があります。これらを組み合わせることで、より実効性の高いアクセシビリティ改善活動を展開することができるでしょう。
ウェブアクセシビリティの導入方法と社内体制の構築
ウェブアクセシビリティの導入は、アクセシビリティを推進していく上で欠かせない要素となっています。社内でアクセシビリティ対応を進めるための体制、教育、継続的改善のポイントを見ていきましょう。
ウェブアクセシビリティ方針の策定
アクセシビリティ方針を決めることは、全体でアクセシビリティ向上に取り組むための目安にもなります。方針を策定、公開することで、企業は社会的責任を果たし、全員が利用しやすいと感じるウェブサイトづくりに取り組んでいることを示すことが可能になります。また、従業員のアクセシビリティに対しての意識が変化し、一つひとつの業務の中でアクセシビリティを意識した行動が促進されます。さらに、方針を公開することで、企業の透明性が高まり、ステークホルダーからの信頼を獲得することができるでしょう。
アクセシビリティ方針には、企業がどれほど熱心に取り組んでいるのかという姿勢やそれぞれの目標、ガイドラインや対象となるウェブサイト、問い合わせ先などを明記することが理想とされています。これらの項目を盛り込み、企業のトップが承認したアクセシビリティ方針を公開することで、企業のアクセシビリティへの取り組みを内外に示すことができます。また、定期的に方針を見直し、PDCAサイクルを回していくことが重要です。
アクセシビリティ方針の策定と公開は、企業のアクセシビリティ推進における第一歩であり、方針に基づいた具体的な取り組みを進めることで、誰もが利用しやすいウェブサイトやアプリケーションの実現につなげていくことができるでしょう。
参考:アクセシビリティとは | ウェブアクセシビリティ基盤委員会(WAIC)
体制づくりと人材育成
まず、ウェブアクセシビリティの推進の先陣を切っていく「責任者」を任命し、自覚を持たせることが重要です。アクセシビリティ方針の決定や取り組みの指示役を担当してもらいます。推進責任者は、経営層とも連携しながら、組織全体のアクセシビリティ意識を高めていく役割を果たします。
次に、ウェブアクセシビリティの担当チームの設置です。ウェブサイトやアプリケーションのアクセシビリティ評価や改善案の提案を行うことなどを専門的に担当します。担当チームには、アクセシビリティに関する知識と経験を持つメンバーを配置し、継続的なスキルアップを図ることが大切です。
社内研修は、組織全体のアクセシビリティ意識を高め、具体的な対応方法を身につけるために欠かせません。研修では、アクセシビリティの基礎知識、JIS X 8341-3やWCAGなどの指針、制作工程における配慮事項などを扱います。対象者は、ウェブサイトやアプリケーションの企画、デザイン、開発、制作に関わる全ての社員とし、定期的な研修の実施が望ましいでしょう。
さらに、アクセシビリティ専門家の育成も重要です。IAAPの認定資格であるCPACC(Certified Professional in Accessibility Core Competencies)やWAS(Web Accessibility Specialist)などを取得することで、アクセシビリティに関する専門知識を証明できます。これらの資格取得者を中心に、社内のアクセシビリティ推進をリードしていくことが期待されます。
ウェブアクセシビリティの導入支援・ガイドブック・基盤委員会の活用
ウェブアクセシビリティの導入となると、支援が必ず必要になってきます。ここでは、導入支援やガイドブック、ウェブアクセシビリティ基盤委員会(WAIC)の活用方法について詳しく説明します。
デジタル庁ガイドブックの活用
デジタル庁が提供する「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」は、初学者にとって優れた資料となっています。このガイドブックは、アクセシビリティの基礎知識から応用的な知識まで、分かりやすくまとめられ、初心者でも学ぶことができるようになっています。
ガイドブックの特徴は、豊富な事例の紹介です。アクセシビリティを考慮したウェブサイトの設計や開発について、実際の事例を交えながら説明しているため、具体的なイメージを持ちながら学ぶことができます。事例は、様々な業種や組織から選ばれていることもあって、自分の求めている参考事例を見つけることができます。また、事例だけでなくチェックリストや評価方法なども提供されているため、より実践的な知識を身につけることができます。
さらに、ガイドブックには「ウェブアクセシビリティ導入ロードマップ」が含まれています。このロードマップは、ウェブアクセシビリティを導入するときの手順を初心者にも伝わりやすく示されたもので、ロードマップは、実装、評価、改善までの一連の流れを解説しており、各段階で実施すべき事や確認すべきポイントが記載されています。このロードマップに沿って進めることで、より効率的にアクセシビリティを促進することができます。
ガイドブックを活用する際は、まず全体を通して読み、アクセシビリティの基礎知識を身につけることをおすすめします。その上で、自組織の状況に合わせて、ロードマップを参考に導入計画を立てましょう。計画立案や実行の際には、ガイドブックに記載されている事例やチェックリストを参考にすることで、より実践的な取り組みを進めることができます。
ウェブアクセシビリティ基盤委員会(WAIC)の資料
ウェブアクセシビリティ基盤委員会(WAIC)は、ウェブアクセシビリティを普及させつつ、改善することを目的としている組織であり、多くの資料を世の中へ提供しています。WAICが提供する資料は、日本の規格や指針と連動しており、国内のウェブアクセシビリティ対応に役立つ情報がたくさんあります。
具体的な名前で紹介すると、「ウェブアクセシビリティ方針策定ガイドライン」「ウェブコンテンツのアクセシビリティ評価方法」「WCAG 2.1 解説書」などがあります。
WAICのウェブサイトでは、これらの資料を無料でダウンロードすることができます。また、ウェブサイト上には、アクセシビリティに関する最新情報や、セミナーやイベントの案内なども載っています。アクセシビリティの取り組みを進める上で、WAICのウェブサイトを定期的にチェックすることをおすすめします。
参考:ウェブアクセシビリティ基盤委員会 | Web Accessibility Infrastructure Committee (WAIC)
SDGsとウェブアクセシビリティの関係|「誰ひとり取り残さない」を実現するために
この章では、アクセシビリティとSDGsの関係、その中でも特にSDGsの目標の一部である10と16とのつながりについて解説します。
SDGs目標10・目標16との関連
SDGsは、誰一人取り残さない、持続可能な社会の実現を目指すことを目標としています。この目標達成に向けて、ウェブアクセシビリティが重要な役割を果たしています。特に、目標10「人や国の不平等をなくそう」と目標16「平和と公正をすべての人に」は、ウェブアクセシビリティと密接に関連しています。
目標10は、障害者を含むすべての人々の社会的、経済的、政治的な包摂を促進することを目指しています。ウェブアクセシビリティは、障害者が情報にアクセスし、サービスを利用する機会を平等に提供するために不可欠です。アクセシビリティに配慮したウェブサイトやアプリケーションを提供することで、デジタル社会における不平等の解消に貢献できます。
目標16は、すべての人々に対して平等に提供し、全員が自由かつ参加型の意思決定ができるように促進することを目指しています。ウェブアクセシビリティは、情報へのアクセスを保障し、オンライン上での意思決定プロセスへの参加を可能にします。これにより、障害者を含むすべての人々が社会的・政治的な意思決定に参加する機会を得ることができます。
ウェブアクセシビリティの推進は、SDGsの達成に向けた重要な取り組みの一つです。企業や団体は、アクセシビリティに配慮したウェブサイトやアプリケーションを提供することで、誰もが平等にデジタル社会に参加できる環境づくりに貢献することができます。また、政府や自治体は、アクセシビリティ規格の整備や普及啓発活動を通じて、デジタルインクルージョンを推進することが求められます。
参考:Issues and Barriers of Cross-border Flow of Data|Digital Agency
自治体・企業が果たすべき責任
自治体は、住民への情報提供や行政サービスのデジタル化を進める上で、アクセシビリティに配慮したウェブサイトやアプリケーションの設計が求められます。高齢者や障害者を含む多様な住民が、平等に情報にアクセスし、サービスを利用できる環境を整備することが重要です。
また、自治体は情報発信の際に、わかりやすい言葉や表現を用い、音声読み上げや文字の拡大などの機能を提供することで、より多くの人々の参加を促すことができます。これにより、住民の意見を広く収集し、包摂的な意思決定プロセスを実現することにつながります。
一方、企業は自社のウェブサイトやアプリケーションのアクセシビリティ対応を進めることで、多様な顧客層へのアプローチが可能になります。アクセシビリティに配慮したウェブ設計は、ユーザー体験の向上につながり、顧客満足度の向上や新たな顧客の獲得にもつながります。
私たちができるウェブアクセシビリティ支援
ウェブアクセシビリティの向上は、行政や事業者だけでなく、私たち一人ひとりの心がけでも実現できます。SNS投稿に代替テキストを添える、動画に字幕を付ける、リンク先が分かる言葉を選ぶなど、小さな工夫が大きな支援につながります。
個人・企業・社会がそれぞれの立場で取り組むことで、誰もが安心して情報にアクセスできる社会を築いていけるのです。
日常的にできるちょっとした工夫
ウェブアクセシビリティは、専門知識がなくても身近な工夫から取り入れられます。SNSやブログに画像を投稿するときに代替テキスト(altテキスト)を設定したり、リンクを貼る際に「こちら」ではなく内容を示す言葉を使うことは、誰でも簡単に実践できます。
また、文字色と背景色のコントラストを高めるなどの工夫も有効です。小さな取り組みの積み重ねが、より多くの人の利用しやすさにつながります。
さらに、音声読み上げに配慮して絵文字の多用を避けるなど、日常的に意識できる工夫は数多くあります。
企業や団体で取り組める支援
企業や団体にとって、ウェブアクセシビリティの確保は社会的責任であると同時に、利用者の信頼獲得にも直結します。ウェブサイトをJIS X 8341-3:2016という多くの人に見やすい規格に準拠させる、動画に字幕を付ける、フォーム入力の際に色だけでなく文字情報で必須項目を示すなどが重要です。
規格準拠などの取り組みは法令遵守だけでなく、顧客満足度やブランドイメージ向上にも貢献し、長期的にはビジネスの持続的成長にもつながります。
さらに、社内研修を通じて従業員にアクセシビリティの理解を広めることも効果的で、組織全体としての取り組みが社会に大きな影響を与えます。
社会全体で支えるために
アクセシビリティは特定の人のためだけではなく、社会全体の利便性向上につながります。
加齢により視力や聴力が衰えるのは誰にでも起こり得ることですから、アクセシビリティの確保は将来の自分自身を助ける取り組みにもなります。個人が日常で工夫し、企業が制度的に整備し、行政が環境を後押しすることで、誰もが安心して情報に触れられる社会を実現できます。それは多様性を尊重し、共生社会を築く大きな一歩となります。
さらに、教育現場でアクセシビリティの重要性を伝えることにより、次世代にも意識が広がり、持続的な社会基盤が築かれていきます。
日本の公的機関・自治体・企業のウェブアクセシビリティの取り組み具体例
日本の公的機関・自治体・企業のウェブアクセシビリティの取り組み具体例をご紹介します。
ソニー
ソニーは「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす。」という存在意義を掲げています。
自社製品の使用方法もアクセシビリティにもこだわって使いやすくしていますが、ウェブアクセシビリティにも取り組んでいます。
特に動画については副音声での解説にも随時対応していて、動画もウェブサイトに掲載される際には、ウェブアクセシビリティの対象となるため、注力しています。
ソニーは、障がいのある方や高齢者の方を含むすべての人にとってアクセシブルなウェブサイトを提供できるよう今後も努力を続けてまいります。
上記のように取り組みをはっきりと公式サイトにも記載がなされています。
参考文献:SONY
KDDIグループ
KDDIグループでは、「誰もが使いやすいサービス・商品の実現」を目指しています。特にKDDIグループは、auなどスマートフォンを販売している企業でもあるため、よりウェブアクセシビリティを意識している企業といえます。
ウェブサイトはもちろんのことながら、アプリといったデジタルサービスについても障害者や高齢者でも、簡単に利用できるよう取り組みを進めています。
制定したウェブアクセシビリティの方針を推進するのはもちろん、ウェブアクセシビリティについての研修も行っていくことが公式サイトに明記されています。
参考文献:KDDIグループ
姫路市
姫路市は、配慮の対象となる利用者を明確にしていて全盲や色覚障害、耳が聞こえにくい、手が不自由な人などを対象としています。他にも古いスマホやパソコンで閲覧する人のことも考えて、制作されています。
具体例としては、適切なページタイトルをつけたり複数の探索手段を用意するといったウェブアクセシビリティがなされています。他にもリンク先は別ページで開かないように設定したりという点も重要です。
リンク箇所は、識別と選択のしやすさに配慮するといった工夫も、公式サイトで行われています。
参考文献:姫路市
総務省
総務省では、公的機関向けウェブアクセシビリティ対応講習会などを開催して、ウェブアクセシビリティについての認識を広めています。総務省は他の企業や自治体に向けて、セミナーを行っている点が大きなポイントです。
他の企業や自治体では、まだまだ理解が進んでいないウェブアクセシビリティについて、しっかり伝えています。他にも「みんなのアクセシビリティ評価ツール」を提供しています。
「みんなのアクセシビリティ評価ツール」によって、問題がある箇所が判明したり、問題があるかどうかを人が判断すべき箇所かをチェックしたりできます。
参考文献:総務省
参考文献:情報アクセシビリティポータルサイト
NECグループ
NECグループでは、障害があったり高齢者の方であっても利用できるよう、ウェブアクセシビリティの確保や維持をしています。
NECは、安全・安心・公平・効率という社会価値を創造し、誰もが人間性を十分に発揮できる持続可能な社会の実現を目指します。
上記の目標をかかげているNECグループは、ウェブアクセシビリティの試験も受験しており、達成したレベルはAAと高い水準を保っています。またNECグループは、パソコンも制作しているため、製品もウェブアクセシビリティに適しています。
参考文献:NECグループ
ウェブアクセシビリティに関するよくある質問
以下に、ウェブアクセシビリティに関する質問を5つピックアップしました。読者の方の疑問が少しでも解決しましたら幸いです。
Q1. ウェブアクセシビリティとは何ですか?
ウェブアクセシビリティとは、障害者や高齢者を含む全ての人々が、ウェブサイトやアプリケーションを利用できるようにすることです。視覚障害者が画面読み上げソフトを使って閲覧できたり、肢体不自由者がキーボードのみで操作できたりするように配慮することを指します。また、聴覚障害者向けに動画に字幕を付けたり、認知障害者向けにわかりやすい言葉や構成を使ったりすることも含まれます。
ウェブアクセシビリティは、単に障害者への配慮だけでなく、全てのユーザーにとって使いやすいウェブサイトやアプリケーションを作ることにつながります。音声読み上げ機能は運転中や家事をしながらの閲覧に便利ですし、十分なコントラストの確保は明るい環境下でのスマートフォン使用時の見やすさを向上させます。ウェブアクセシビリティは、誰もが情報にアクセスし、サービスを利用できる社会の実現に寄与するものなのです。
Q2. ウェブアクセシビリティは法的に義務化されているのですか?
日本では、2016年に施行された障害者差別解消法により、事業者に障害者への合理的配慮の提供が求められています。ウェブアクセシビリティは合理的配慮の一部として位置づけられ、企業や団体は自主的な取り組みが期待されています。2024年の改正では、一部の事業者に合理的配慮の提供が義務化される予定です。
義務化の対象は不特定多数の者を対象とする一定規模以上の事業者で、義務化される合理的配慮の内容は今後具体的に定められますが、ウェブアクセシビリティ対応も含まれると考えられます。法的義務化の動向を注視しつつ、自主的な取り組みを進めることが重要です。
国際的にも、米国の「Section 508」や「ADA」、EUの指令などにより、ウェブアクセシビリティの法制化が進んでいます。日本国内だけでなく、グローバルな視点でウェブアクセシビリティ対応の重要性が高まっていると言えるでしょう。
Q3. ウェブアクセシビリティに対応するためには、どのような基準があるのですか?
日本では「JIS X 8341-3」、国際的には「WCAG」が主なウェブアクセシビリティの基準として知られています。JIS X 8341-3は、WCAGをベースに日本の実情に合わせて策定された基準で、適合レベルはA、AA、AAAの3段階です。WCAGは現在2.1版まで発行されており、同様の適合レベルがあります。
これらの基準は、ウェブコンテンツの提供者が守るべき指針を具体的に示しており、画像への代替テキストの提供、十分なコントラストの確保、キーボードのみでの操作への対応などが含まれます。
ウェブアクセシビリティ対応を進める際は、まずこれらの基準を理解し、自社のウェブサイトやアプリケーションの現状を評価することが重要です。その上で、適合レベルの目標を設定し、段階的に対応を進めていくことが求められます。JIS X 8341-3やWCAGは技術的な詳細も含まれているため、専門家の協力を得ながら進めることをおすすめします。
Q4. ウェブアクセシビリティ対応には、どのようなメリットがあるのですか?
ウェブアクセシビリティ対応には、障害者や高齢者を含む全ての人々が情報やサービスを利用できるようになるという社会的意義があります。企業にとっては、顧客層の拡大、社会的責任の遂行、ブランドイメージの向上、SEO効果、人材獲得や従業員満足度の向上などのメリットがあります。また、アクセシビリティ対応はウェブサイトのユーザビリティ向上にもつながります。長期的な視点で捉え、積極的に取り組むことが重要です。
Q5. ウェブアクセシビリティ対応を進めるためには、どのような取り組みが必要ですか?
ウェブアクセシビリティ対応には、組織的な取り組みが必要です。アクセシビリティ方針の策定、各段階でのアクセシビリティ配慮、教育・啓発活動、定期的な監査やユーザー評価による改善が求められます。
また、経営を行う上での戦略と関連付けること、継続的な改善などが重要視されます。着実に取り組みを進めることで、誰もが利用しやすいウェブサイトやアプリケーションの実現につながります。
まとめ
ウェブアクセシビリティとは、誰もがウェブを利用できるようにするための取り組みです。本記事では、その基本概念からJIS X 8341-3やWCAGとの関係、法的義務や社会的責任、ユーザー体験やSEOへの影響など、多角的な視点からウェブアクセシビリティの重要性を解説しました。
具体的な取り組みとして、デザインやUI面での工夫、マルチデバイス対応、音声支援技術、技術的実装例を紹介し、チェックツールや評価方法についても言及しました。ウェブアクセシビリティの導入方法や社内体制の構築、各種ガイドブックや支援リソースの活用方法も説明し、
さらにSDGsとの関連性や自治体、企業が果たすべき責任についても触れ、ウェブアクセシビリティが「誰ひとり取り残さない」社会の実現に不可欠であることを強調しました。本記事が、ウェブアクセシビリティへの理解を深め、取り組みを推進する一助となれば幸いです。
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS