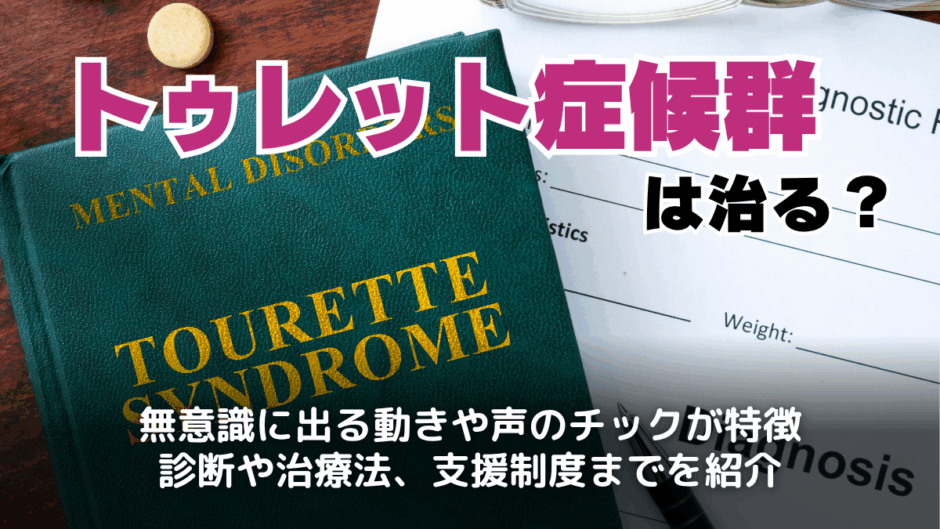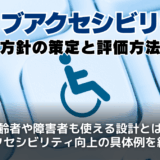トゥレット症候群は、運動や声のチックが特徴の神経発達症で、子どもから大人まで影響します。症状は人によって異なり、軽度の場合は日常生活にほとんど支障がない一方で、周囲から誤解を受けやすく、学校や職場で困難を抱えることがあります。
また、女の子は症状が目立ちにくく見逃されやすい特徴があります。正しい診断と支援により、薬物療法や行動療法で症状を和らげることができ、学習や仕事での能力を発揮しやすくなるメリットがあります。
一方で、治療に時間や努力が必要で、精神的負担が伴う場合もあり、家族や社会の理解が重要です。この記事では、トゥレット症候群の症状や診断、治療法、支援制度まで幅広く解説し、日常生活での工夫や社会参加への影響も紹介します。
トゥレット症候群とは?

トゥレット症候群とは、運動や声のチックが特徴の神経発達症です。
トゥレット症候群の症状の特徴は「チック」と呼ばれる動きや声です。チックは自分の意思で止められるものではなく、突然あらわれます。たとえば、まばたきを繰り返す、首を振る、声を発するなど、一見すると癖のように見える行動です。しかし実際には本人にとって強い衝動があり、我慢するほど苦しくなるため、意図的に行っているわけではありません。
発症の多くは子ども時代で、小学生ごろから症状が現れます。男の子に比較的多いとされますが、女の子や大人にも見られることがあります。大人になるにつれて症状が軽くなる人もいますが、逆に続く場合もあるため、生活のしづらさにつながることも少なくありません。
歴史的にみると、トゥレット症候群の人は「変わった癖がある」「落ち着きがない」と誤解され、からかわれたり叱られたりすることがありました。近年は医学的な研究が進み、脳の働きや神経の発達に関係する病気であることがわかってきています。正しい理解が広がれば、本人や家族が安心して過ごせる社会に近づくでしょう。
トゥレット症候群は発達障害?
ここで気になるのが「トゥレット症候群は発達障害なのか」という点です。日本の法律である「発達障害者支援法」では、トゥレット症候群は神経発達症に含まれています。発達障害とは、生まれつき脳の働きに特性がある状態を指し、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)が代表例です。
トゥレット症候群の人は、こうした発達障害を併せ持つことが少なくありません。特にADHDは不注意や衝動性といった特徴があり、トゥレット症と一緒にみられるケースが多いと報告されています。また、強迫性障害(同じ行動を繰り返してしまう症状)や不安障害と重なる人もいます。
ただし「トゥレット症候群=発達障害」ではありません。チックだけを持つ人もいれば、複数の特性が重なって生活に影響する人もいます。このあたりをきちんと区別して理解することがとても大切です。誤解が減れば、本人も家族も「自分だけが特別なわけではない」と安心でき、必要な支援につながりやすくなります。
トゥレット症候群は「珍しい病気」と思われがちですが、子どものおよそ100人に1人はチック症状を経験するといわれています。その多くは一時的に軽くなる場合もありますが、長く続く人もいます。正しく理解することが、偏見をなくし、支援の第一歩になります。
参考:難治性不随意運動症状を伴うトゥレット症候群に対する脳深部刺激の有用性に関する多施設共同研究
トゥレット症候群の症状
トゥレット症候群にみられるチックの症状は、運動チックと音声チックの2種類に分けられます。この章では、運動チックと音声チックの特徴について説明していきます。
運動チック
運動チックは、体の動きとして現れるチック症状で、まばたき、顔をしかめる、肩をすくめる、手足を急に動かすなどの症状が代表的です。軽い動きから始まり、時には体全体をねじるような大きな動きになることもあります。
これらの動作は本人の意思とは関係なく出てしまうため、意図的にやっているわけではありません。集中しているときやリラックスしているときには症状が軽くなる一方、緊張・疲労・ストレスなどが強いと悪化しやすくなります。また、しばらくの間は抑え込めても、その反動で後から症状が強く出ることもあります。周囲が「やめなさい」と叱ったり注意してしまうとと、かえって症状が強まることがあるため、本人の意思だけではなく周囲の理解が大切です。
音声チック
音声チックは、声や音として現れるチック症状です。
具体的には、咳払い、鼻をすする音、叫び声などの単純な音から、特定の言葉やフレーズを繰り返すケースまでさまざまな症状があります。
まれに、汚言を発してしまうこともありますが、これは本人の意思とは無関係に起こる症状です。そのため、誤解や偏見を受けやすく、本人や家族にとって精神的な負担が大きいことがあります。
音声チックも、緊張やストレスが高まると悪化しやすく、安心できる環境では軽減する傾向があります。周囲が症状を理解し、怒ったり注意するのではなく受容的な対応をとることが、症状の軽減につながります。
トゥレット症候群の原因と診断方法
トゥレット症候群の原因は、現在の医学でも完全には解明されていません。けれども近年の研究によって、脳の中で神経細胞同士が情報を伝える際に働く「神経伝達物質」の異常が関係しているのではないかと考えられています。神経伝達物質とは、ドーパミンやセロトニンといった脳内の化学物質のことです。これらのバランスが崩れると、衝動的な動きや声がコントロールしにくくなると説明されています。
また、遺伝的な要因も無視できません。親や兄弟にチック症状を持つ人がいる場合、発症のリスクがやや高いことが知られています。ただし「遺伝だけで決まるわけではない」点が重要です。家庭環境やストレス、妊娠・出産時の影響など、さまざまな環境因子が重なって発症につながると考えられています。
このようにトゥレット症候群は一つの原因で説明できるものではなく、複数の要素が複雑に関わっているとされています。そのため診断や治療には、症状の出方だけでなく生活環境や成長の過程も含めて丁寧に見ていくことが大切です。
トゥレット症候群は何科で診てもらえる?受診の流れ
「トゥレット症候群かもしれない」と感じたとき、多くの方がまず迷うのが「何科を受診すればいいのか」という点です。症状が子どもに現れることが多いため、最初は小児科に相談するケースが一般的です。そこからより専門的な診療科へ紹介されることがあります。
具体的には、子どもの場合は 小児神経科が適しています。小児神経科では、脳や神経の発達に関する病気を専門的に扱っているため、チックや発達に関わる症状を詳しく診てもらうことができます。
一方で、大人になってからも症状が続く場合や精神的な不安が強い場合には、精神科や心療内科での診察が検討されます。特にADHDや強迫性障害など他の症状を併発しているときは、精神科でのサポートが有効です。
受診の流れとしては、まず日常の症状をできるだけ記録しておくことが推奨されます。動画やメモで「どんな動きや声が、どのくらいの頻度で出ているか」を整理しておくと、診断の助けになります。診察では、問診と観察をもとに総合的に判断が行われます。
トゥレット症候群の診断基準と除外すべき他の疾患
トゥレット症候群の診断は、国際的に広く使われている DSM-5(精神疾患の診断と統計マニュアル第5版) の基準に基づいて行われます。DSM-5では、次のような条件を満たす場合に診断されます。
- 複数の運動チックと少なくとも1つの音声チックが存在すること
- チックは1年以上続いていること(連続していなくてもよい)
- 発症が18歳より前であること
- 他の病気や薬の影響では説明できないこと
ここで重要なのは「除外診断」です。つまり、似たような症状を示す他の病気を区別する必要があります。たとえば、てんかんの発作や自閉スペクトラム症に伴う常同行動、薬の副作用による不随意運動などが該当します。こうした疾患は一見チックに見える場合があるため、専門医による判断が欠かせません。
また、診断には心理検査や行動観察も組み合わせることがあります。本人や家族からの聞き取りを丁寧に行い、日常生活への影響を含めて評価していくことが求められます。
トゥレット症候群は原因が一つに特定できない複雑な病気です。そのため、早期に適切な診療科を受診し、他の病気との違いを慎重に見極めることが大切です。診断はゴールではなく、むしろその後の支援や治療につながるスタートラインといえるでしょう。
子ども・女の子・大人のトゥレット症候群の特徴
トゥレット症候群は子どもから大人まで幅広く見られる症状ですが、年齢や性別によって現れ方に違いがあります。さらに、社会の中でどう受け止められるかによって生活への影響も変わってきます。特に女の子や大人の症例は、周囲に理解されにくく、気づかれずに過ごしてしまうことが少なくありません。
ここでは、性別やライフステージごとの特徴と支援のあり方を考えていきましょう。
女の子に多いチックの見逃しと社会的な偏見
トゥレット症候群は男の子に多いとされていますが、女の子にも発症します。ただし女の子の場合、症状が軽めであることや、自分で抑え込もうとする傾向が強いことが知られています。たとえば、授業中にまばたきを繰り返したり、指先を小さく動かしたりするだけで、周囲からは「癖」としか見えない場合があります。
そのため、学校や家庭でも「気のせい」や「緊張のせい」と誤解されやすく、適切な支援につながらないことがあります。さらに、女の子は「おとなしくしているべき」という社会的な期待を受けやすいため、症状を隠そうと努力しすぎて心身に負担を抱えることも少なくありません。見た目に分かりにくい分、偏見やからかいの対象になりにくい一方で、理解の機会が失われてしまうのです。
大人のトゥレット症候群の特徴と誤解
大人になってもトゥレット症候群の症状が続く人は一定数います。子どものころよりは軽くなる場合もありますが、職場や家庭での人間関係に大きく影響することがあります。会議中に咳払いが止まらない、緊張の場で首を振ってしまうなど、本人にとっては制御できない動作が「不真面目」「落ち着きがない」と誤解されることが少なくありません。
こうした状況に対しては、職場での理解と配慮が必要です。たとえば、静かな作業環境ではなく、多少の音が気にならない場所を選ぶことや、定期的に休憩を取りやすい雰囲気づくりが役立ちます。日本では就労支援制度や障害者雇用制度を活用できる場合があり、精神障害者保健福祉手帳を取得することで勤務形態の調整や就労支援機関からのサポートを受けられることもあります。
大人の症状は「子どもの病気なのにまだ残っている」と誤解されることも多いため、社会全体が「大人にも続くことがある」という事実を知ることが重要です。
トゥレット症候群は治る?治療と予後
「トゥレット症候群は治るのか」という疑問は、多くの患者さんやご家族が抱える大きな関心事です。実際には「完全に治す薬」があるわけではありませんが、症状を軽くしたり生活への影響を減らしたりする方法は複数あります。さらに、成長とともに自然に症状が落ち着くケースも少なくありません。
続いて、薬を使った治療と行動療法、そして予後について整理してみましょう。
薬物療法と副作用のリスク
トゥレット症候群の症状が強く、学校や仕事に大きな支障をきたす場合には薬が使われます。代表的なのはハロペリドール や リスペリドンといった抗精神病薬で、神経伝達物質の働きを調整することでチックを和らげます。最近では副作用の少ない新しい薬が選ばれることも増えてきました。
ただし、薬物療法には注意が必要です。眠気、体重増加、筋肉のこわばりといった副作用が出る可能性があり、長期的に服用する場合は定期的な診察と調整が欠かせません。医師は「症状の強さ」と「薬の負担」のバランスを見ながら処方を決めていきます。そのため、薬を使うかどうかは本人と家族、医療チームが一緒に話し合いながら決めるのが基本です。
また、チック症状だけでなく、強迫症状や不安障害などの併存症がある場合には、抗うつ薬など別の薬が補助的に使われることもあります。
行動療法と心理社会的支援
行動療法と心理社会的支援を見ていきましょう。
ハビットリバーサル療法(HRT)
薬に頼らない治療方法として注目されているのが行動療法です。なかでも代表的なのがハビットリバーサル療法(HRT) という訓練法です。チックだけでなく、抜毛症といった習慣化してしまっている問題行動を改善するための方法です。
これは、チックが出そうになる前の「予兆」を察知し、どういった状況に起こりやすいのかを確認します。チックが出そうになる環境がわかれば、それとは別の行動に置き換えるという練習を重ねるものです。
薬物療法のように即効性は期待できないものの、長期的な目線で見ると効果が期待できるのでおすすめです。
包括的行動介入(CBIT: Comprehensive Behavioral Intervention for Tics)
さらに近年は、HRTを発展させた 包括的行動介入(CBIT: Comprehensive Behavioral Intervention for Tics) が広く使われるようになりました。
CBITではチックの置き換え練習に加えて、リラクゼーションなどのストレス管理や生活環境の工夫を取り入れるため、薬を使わずに症状を軽減できる可能性があります。
CBITの目的はチックを消すということではなく、チックが起きる頻度を下げることを目的としています。ただやみくもにやっても効果が期待できるわけではないため、専門医とかかわりを持ちながら進めていきましょう。
心理社会的支援
トゥレット症候群の治療には心理社会的な支援も欠かせません。学校での理解、職場での配慮、そして家族が安心して過ごせる環境づくりが治療の一部となります。
本人が「症状を隠さなくてよい」と感じられるだけで、ストレスが減りチックの頻度が下がることもあるのです。そのため不安を感じることのない環境で一定危機感過ごしてみることも、試してみることをおすすめします。
自然寛解
トゥレット症候群は一生続く病気というイメージを持たれがちですが、必ずしもそうではありません。多くの子どもは思春期を過ぎるころから症状が弱まり、大人になる頃にはほとんど目立たなくなることも珍しくありません。これを「自然寛解」と呼びます。
ただし、すべての人が自然に治るわけではなく、大人になっても症状が残る場合もあります。そのため「治るか治らないか」だけにとらわれるのではなく、「生活にどのくらい影響があるか」を基準に治療や支援を考えていくことが大切です。
トゥレット症候群には即効性のある治療薬は存在しませんが、薬物療法や行動療法を組み合わせることで症状を抑えることは可能です。また、成長にともなって自然に落ち着くケースもあり、希望を持つことができます。大切なのは、症状と上手につきあいながら、自分らしい生活を築けるようサポートを受けることです。
参考:小児と青年におけるトゥレット症候群とその他のチック症 – 23. 小児の健康上の問題 – MSDマニュアル家庭版
子どもへの支援と親の向き合い方
子どもにトゥレット症候群の症状がある場合、家庭や学校での支援が大切になります。具体的には、チックを無理に止めさせようとしないことが第一です。「やめなさい」と叱るのではなく、「出ても大丈夫だよ」と伝えるだけで子どもの安心感は大きく変わります。
学校では、授業中にチックが出ても周囲が過剰に反応しないように配慮することや、集中できない場合は一時的に教室を離れる選択肢を与えることが有効です。小さな工夫でも、子どもが自信を失わずに学びを続ける助けになります。
また、親自身のメンタルケアも欠かせません。子どもの症状を心配するあまり、親が孤独感や罪悪感を抱えるケースもあります。地域の相談機関や親の会に参加することで、同じ経験を持つ人とつながり、気持ちを共有できる環境を持つことが望ましいです。
トゥレット症候群は、年齢や性別によって症状の現れ方が異なり、その理解のされ方も変わります。女の子や大人のケースは特に気づかれにくいため、周囲の正しい知識と支えが必要です。家庭、学校、職場の小さな理解が積み重なれば、本人が安心して生活できる社会に近づいていきます。
トゥレット症候群と発達障害・精神疾患との違い
トゥレット症候群と発達障害・精神疾患との違いを見ていきましょう。
トゥレット症候群と発達障害の違い
トゥレット症候群と発達障害の違いは、症状です。トゥレット症候群は、目に見える症状がほとんどで主にチック症状が現れるのがメインの症状ですが、対して発達障害は見た目にはわからない場合がほとんどで、不注意が多かったり忘れ物が多かったり、空気が読めないといった症状がメインです。
他にも違いを挙げると、トゥレット症候群は神経疾患であるのに対して発達障害は脳機能の特性によって発生しています。
ただトゥレット症候群と発達障害の違いはあるものの、トゥレット症候群と発達障害の一つであるADHDなどは併発する場合があり、その確率は50%にも上ります。
またトゥレット症候群は、発達障害の症状の一つと診断される場合も多いです。
トゥレット症候群と精神疾患の違い
トゥレット症候群と精神疾患の違いは起こってしまう原因が異なります。トゥレット症候群の原因は、脳の神経回路機能の不全であるのに対して、精神疾患の原因は多種多様に渡ります。
症状も大きく異なり、トゥレット症候群の症状としては意図していない体の動きであったり、突然奇声を上げてしまったりといった身体的な症状がほとんどです。
対して精神疾患は心理的・精神的な部分が多く幻覚であったり、気分が落ち込むようなうつ症状、不安障害といった精神的な症状がほとんどです。見た目にはわかりづらい症状が多いでしょう。
トゥレット症候群は発達障害の一部と捉えられる場合がほとんどですが、重度になってしまった場合は精神障害者保健福祉手帳の対象になる場合もあるため、医師に確認してみましょう。
トゥレット症候群に対する障害者手帳・福祉サービスと社会的支援
トゥレット症候群を持つ人が、安心して暮らし、学び、働くには、周囲の理解だけでは足りません。制度的な支援や社会の仕組みを活用することが大切です。ここでは、障害者手帳の取得方法や福祉サービス、学校や職場での具体的な配慮について整理してみます。
精神障害者保健福祉手帳の取得とメリット
まずはトゥレット症候群で障害者手帳の取得を検討している方に向けて、取得の流行や手帳を持つことで得られる支援について解説していきます。
トゥレット症候群の場合、主に利用できるのは「精神障害者保健福祉手帳」です。これは市区町村の障害福祉課で申請します。必要なのは、医師の診断書や通院の証明書、そして申請書類。等級は1級から3級まであり、生活への影響の大きさによって決まります。
- 1級:日常生活のほとんどに介助が必要な状態
- 2級:サポートがあれば自立できるが困難が多い
- 3級:ある程度は自立しているが、社会生活に制約が出る
更新は2年ごとに行われ、症状が変化すれば等級も変わる可能性があります。
この手帳を取得すると、下記のような制度が使いやすくなります。
- 所得税や住民税の控除
- 電車やバスの割引
- 自立支援医療制度による医療費の軽減(上限額あり)
- 就労支援サービスの利用がスムーズになる
また、手帳を持っていることで障害年金の申請がしやすくなる場合もあります。ただし、手帳と年金は別制度なので、混同しないことが大切です。
教育・就労現場での配慮と合理的配慮
トゥレット症候群の誤解や偏見を解くために、教育現場や会社などで周囲の人ができる配慮について説明していきます。
学校での支援
子どもの場合、授業中にチックが出ても「ふざけている」と誤解されることがあります。そこで学校では、インクルーシブ教育の考え方をもとに、周囲が理解しやすい環境づくりが必要です。
具体例を挙げると、以下のようなものがあります。
- 授業中に症状が強まったら、一時的に教室を離れることを認める
- テストは別室で受けられるようにする
- 先生がクラス全体に病気の特徴を説明し、笑われない雰囲気を作る
さらに、特別支援学級や通級制度を利用することで、必要な部分だけ追加のサポートを受けることもできます。
職場での合理的配慮
大人の場合、職場での困難は少なくありません。電話応対中に音声チックが出る、静かな会議室で咳払いのような声が出てしまう、といったケースです。このとき役立つのが「合理的配慮」です。会社にとって大きな負担にならない範囲で、働き方を調整してもらえます。
例としては、このようなものがあります。
- 休憩をこまめに取れるようにする
- 集中しやすい作業環境を選ばせてもらう
- 同僚や上司に病気の特徴を伝えておく
制度的には、障害者雇用枠での採用や、ハローワークを通じた就労支援事業を活用できることがあります。障害者手帳を持っていると、これらの制度にアクセスしやすくなるのも事実です。
トゥレット症候群に向き合うには、本人や家族の努力だけでは限界があります。精神障害者保健福祉手帳の取得はその入口にすぎませんが、税制や医療、就労など生活全般での助けになります。さらに、学校や職場での「ちょっとした配慮」が加わることで、社会の中で無理なく自分らしく過ごせる可能性が広がります。
トゥレット症候群の患者に対して私たちにできること
トゥレット症候群は、本人の意思では抑えにくく、周囲の理解や支援が欠かせません。学校や職場、家庭での適切な対応や接し方を知ることで、患者の安心感や自信を高め、生活の質を向上させることができます。この章では、私たちにできる具体的な支援方法を整理します。
理解と正しい知識を持つ
トゥレット症候群について正しい知識を持つことは、支援の第一歩です。症状は本人の意思によるものではなく、意図的に抑えることが難しいことを理解しましょう。誤解や偏見はストレスや孤立を生む原因になります。学校や職場では、周囲が症状の特性を理解し、からかいや非難を避ける環境づくりが大切です。
患者が安心して過ごせる環境づくり
患者が安心して過ごせる環境を整えることも重要です。騒音や視線を避けられる場所の確保、プレッシャーをかけない対応、休憩やリラックスできる時間の確保など、日常生活での配慮が症状の悪化を防ぎます。学習や仕事の場面では、柔軟な課題設定や周囲の理解が、患者の能力発揮を助けます。
心理的サポート
トゥレット症候群の患者は、症状による自己否定感や不安を抱えやすい傾向があります。共感や肯定的な声かけ、安心して話せる環境を提供することが重要です。家族や教師、同僚が支えとなることで、患者の自尊感情や社会参加意欲が高まります。専門家によるカウンセリングも有効です。
医療・教育機関との連携
必要に応じて医療や教育の専門機関と連携することも、支援の質を高めます。学校での特別支援や職場での合理的配慮、医療機関でのチック症状の評価や治療情報の共有など、チームでのサポートが症状の管理や生活の安定につながります。情報の共有と協力が、長期的な安心を支えます。
SDGsとトゥレット症候群
トゥレット症候群は、医療や教育、そして社会生活のあらゆる場面で支援が必要となる疾患です。症状そのものだけでなく、周囲の理解不足や偏見が生活の質を下げる大きな要因となっています。近年注目されている国連のSDGs(持続可能な開発目標)では「誰一人取り残さない」という理念が掲げられており、トゥレット症候群を持つ人々の暮らしを考えることは、SDGsの達成にも直結します。
特に関連が深いのは、目標3「すべての人に健康と福祉を」、目標4「質の高い教育をみんなに」、目標10「人や国の不平等をなくそう」の3つです。これらの視点から、医療へのアクセス改善、教育現場での公平性、職場における合理的配慮を整えることが重要となります。
教育とジェンダーの交差点で見過ごされる子どもたち
教育の現場では、トゥレット症候群の子どもが十分な支援を受けられずに困難を抱えることがあります。特に女の子や軽度の症状を持つ子どもは「静かに我慢している」ことが多く、教師や保護者が気づかないまま学習の遅れや自己肯定感の低下につながるケースも少なくありません。
男の子に比べて目立たない症状は、周囲から「性格の問題」と誤解されやすい傾向があります。その結果、必要な支援が遅れ、教育格差が広がる危険性があります。SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」は、障害の有無や性別に関わらず、すべての子どもが学びの場で尊重されることを求めています。トゥレット症候群を正しく理解し、早期に支援につなげる体制を整えることが、教育の平等性を高める大切な取り組みです。
働きやすい職場環境と社会的包摂
大人になったトゥレット症候群の方が直面するのは、職場での誤解や不当な扱いです。症状をコントロールできないことから「集中力がない」「落ち着きがない」と見られることがあり、雇用の機会を狭めてしまうこともあります。こうした社会的障壁は、本人の能力とは関係なく不平等を生み出しているのです。
SDGs目標10「不平等をなくそう」は、まさにこの問題に通じます。合理的配慮と呼ばれる制度では、症状に合わせて勤務時間の調整や作業環境の工夫を行い、誰もが自分の力を発揮できるようにします。さらに、就労支援サービスや専門の相談機関を利用することで、雇用主と本人がより良い形で協力できる環境を築くことが可能です。
また、目標3「すべての人に健康と福祉を」に関連し、職場での心理的サポートや医療との連携も不可欠です。職業生活を支える体制が整えば、本人が安心して働けるだけでなく、組織全体にとっても多様性を尊重する風土が育まれます。
トゥレット症候群を持つ人々の生活を守ることは、SDGsの理念と強く結びついています。子どもが教育の機会を失わないようにすること、大人が安心して働ける社会を作ること、そして地域で安心して暮らせる仕組みを整えることが重要であり、このどれもが「誰一人取り残さない社会」を実現するために必要な取り組みです。
トゥレット症候群に関するよくある質問
トゥレット症候群については、症状や診断、日常生活への影響など、さまざまな疑問が寄せられます。ここでは、特に多く聞かれる質問を5つピックアップし、わかりやすく解説します。
Q1. トゥレット症候群は完治しますか?
トゥレット症候群は完全に治る場合もあれば、症状が長く続く場合もあります。多くは小学校高学年から思春期にかけて症状が最も強くなり、その後自然に軽くなることが知られています。薬物療法や行動療法を組み合わせることで、日常生活で困る場面を減らせます。たとえば、授業中にチックが出る場合でも、ハビットリバーサル法や作業環境の工夫で集中できる時間を増やすことが可能です。
症状の経過は人によって大きく異なるため、医師と相談しながら対応を決めることが大切です。
Q2. どの診療科で受診すればよいですか?
トゥレット症候群は、小児神経科や精神科で診断されることが一般的です。小児の場合は発達の観点から小児神経科が適しています。成人では、症状が持続する場合は精神科での診察が適しています。初診では、チックの種類や頻度、発症時期、家族歴の確認などが行われます。また、必要に応じて心理検査や血液検査が実施されることもあります。
初めて診察を受けるときは、症状を写真や動画で記録しておくと医師に伝わりやすくなります。
Q3. 女の子でも発症しますか?
トゥレット症候群は女の子でも発症します。ただし、女児の症状は比較的軽く、目立たないことが多いため、周囲に理解されにくいケースがあります。音声チックより運動チックが中心で、授業中や家庭で我慢していることもあります。見過ごされると、学習や自己肯定感に影響を及ぼす可能性があるため、早期に症状を理解し、必要なサポートを整えることが重要です。
教師や家族が、軽度のチックも「病気の一症状」として理解することが求められます。
Q4. 発達障害とどう違うのですか?
トゥレット症候群はチック症状が中心で、運動や声の反復的な動きが特徴です。一方、ADHD(注意欠如・多動症)は注意力の散漫や衝動性、ASD(自閉スペクトラム症)は社会的コミュニケーションの困難が主な症状です。トゥレット症候群はこれらの発達障害と併存することもありますが、症状の出方や強さを観察することで区別できます。
診断は専門医による慎重な評価が必要で、生活場面の具体例を共有することが、正確な判断につながります。
Q5. 障害者手帳や福祉サービスは利用できますか?
症状や日常生活への影響の程度に応じて、精神障害者保健福祉手帳を取得できます。手帳を持つと医療費助成や就労支援、教育現場での合理的配慮が受けやすくなります。申請には医師の診断書や通院の証明が必要で、生活への支障の度合いに応じて等級が決まります。また、就労支援機関や地域の福祉サービスを活用することで、仕事や日常生活を無理なく続ける環境を整えやすくなります。具体的には、勤務時間の調整や静かな作業場所の確保など、合理的配慮を受けることが可能です。
トゥレット症候群は、症状の出方や強さに個人差が大きい疾患です。正しい知識を持つことで、学校生活や職場での誤解を減らし、必要なサポートにつなげられます。医療・教育・福祉が連携することで、本人が安心して生活できる環境を整えることが可能です。家庭や周囲の理解も重要で、早期に支援を受けることが本人の自立と社会参加に大きく役立ちます。
まとめ
トゥレット症候群は運動や音声のチックが特徴ですが、症状は人によって大きく異なり、軽度の場合は周囲に気づかれにくく、特に女の子や軽症の子どもは見逃されやすいことがわかっています。また、ADHDやASDなどの発達障害、強迫性障害との併存も珍しくなく、正確な診断と理解が重要です。
治療法は薬物療法や行動療法を中心に、症状の軽減や生活の質向上を目指します。加えて、障害者手帳の取得や福祉サービスの活用、教育・就労現場での合理的配慮は、本人の自立や社会参加を支える大きな力となります。家族や学校、職場での支援体制を整えることで、本人が安心して生活できる環境を築けます。
トゥレット症候群を正しく理解し、多様性を尊重する社会の実現を目指すことが、本人だけでなく、社会全体にとっても豊かな未来につながります。
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS