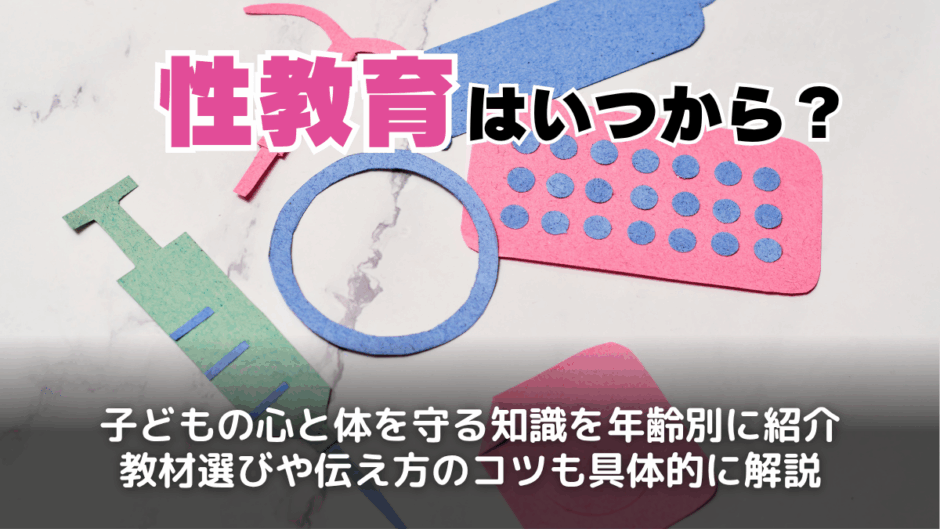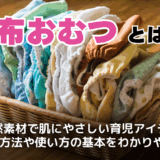性教育は、自分の体や心を守りながら、他者を尊重する力を育てる大切な学びです。正しい性教育を受けることで、性犯罪や性被害を防ぎ、健康な人間関係を築くことができます。一方で、性教育には「恥ずかしい」「まだ早い」と感じる人も多く、家庭や学校での話題にしづらいというデメリットもあります。しかし、適切な年齢に合わせて少しずつ学ぶことで、子どもは安心して成長できるほか、性に関する誤情報や偏見を減らせるメリットが大きいです。
この記事では、性教育の基本から年齢別の内容、教材選びのポイントまで幅広く解説します。
性教育とは?

性教育にはさまざまな考え方がありますが、世界保健機関(WHO)は「性に関する正しい知識を学び、自分や他者を尊重し、健康で安全に生きるための教育」と定義しています。また、国連教育科学文化機関(UNESCO)が提唱する「包括的性教育(CSE)」は、体の仕組みや妊娠の知識だけでなく、人間関係、感情、ジェンダー(社会的・文化的に作られる性の違い)や同意の大切さなども学ぶ幅広い内容を含みます。
この教育の大きな目的は、自分自身を大切にする力を育て、他人を思いやる態度を身につけることです。正しい知識を持つことで、インターネットや周囲の間違った情報に惑わされず、自分の気持ちを尊重した選択ができるようになります。また、自分の「イヤ」という気持ちをきちんと伝える力を育むことで、性被害やいじめを防ぐことにもつながります。
参考:Comprehensive sexuality education: For healthy, informed and empowered learners
性教育はいつから始める?年齢別の適切な内容
「性教育はいつから始めたらいいの?」「小さい子どもに性の話をして大丈夫?」と迷う方は少なくありません。性教育は大人になってからではなく、小さいころから段階的に始めることが大切です。ここでは、乳幼児期・小学生期・中高生期と年齢別に、どんな内容を伝えるのが良いかをわかりやすく説明します。
乳幼児期(0〜6歳)|体の名称、プライベートゾーンの理解
0〜6歳の乳幼児期は、「性教育」と聞いて多くの方が「まだ早いのでは」と思う時期です。しかし、この時期に伝えるのは難しい知識ではなく、自分の体を知ることや大切にする気持ちを育てることが中心です。
まず、自分の体の部位を正しい名前で教えることが大切です。「おちんちん」「おしり」などの言葉を恥ずかしがらず、自然に話すことで、子どもは体の部分を特別視せずに覚えます。そして、「プライベートゾーン」という言葉を使い、「ここは自分だけの大事な場所で、他の人に触らせなくていい」と伝えましょう。こうした学びは、将来の性被害を防ぐ力にもつながります。
また、子どもが「どうして男の子と女の子で体が違うの?」と聞いたときも、「体にはいろいろな違いがあって、それは自然なことなんだよ」と安心させてあげることが大切です。
小学生期|心と体の変化、他者への敬意と自分の尊重
小学生になると、体つきや心の面でも大きな変化が始まります。この時期には「第二次性徴(思春期の体の変化)」について話すことが大切です。たとえば「胸がふくらむ」「声変わりをする」など、男の子と女の子で起こる違いを具体的に伝えます。
さらに、自分だけでなく友達の体や心も変化することを知り、お互いをからかわない、尊重することの大切さも学びます。「からかうのは相手を傷つけることなんだよ」と教えることで、いじめやトラブルを防ぐ心を育てます。この時期には、絵本や図解で説明する本を使うと、子どもがイメージしやすくなります。また、親が恥ずかしがらずに自然に話すことで、子どもも安心して質問できるようになります。
中高生期|同意・避妊・性の多様性などを段階的
中学生・高校生になると、恋愛や性に対する関心が高まります。この時期には「同意(相手の気持ちを確認すること)」や「避妊」「性感染症の予防」など、より実践的な知識を伝えることが必要です。同意については、「相手がいやだと言ったらやめる」「自分がいやだと思ったら断ってもいい」という考え方を教えます。これは恋愛や人間関係だけでなく、日常生活の中でも役立つ大事な力です。
また、性の多様性(LGBTQ+など)についても触れ、「世の中にはいろいろな考え方や感じ方を持つ人がいるんだよ」と伝えることで、偏見を持たずに人と接する気持ちを育てます。
このように、性教育は「何歳から始めるべき」という決まりがあるわけではなく、子どもの発達や興味に合わせて少しずつ進めていくものです。そしてそれは、子どもが安心して自分を大切にし、他の人を思いやる力を育てる大切な学びなのです。
参考:命育
なぜ性教育が必要なのか?日本の現状と課題
日本では、性教育について「恥ずかしい」「まだ早い」という空気がいまだに強く残っています。その結果、性に関する正しい知識を学ぶ機会が限られ、SNS時代の今では特に深刻な問題が生まれています。たとえば、ネット上には誤った情報があふれており、性被害や差別、望まない妊娠などの社会課題が後を絶ちません。ここでは、日本の性教育の現状と課題について、わかりやすく解説します。
性情報へのアクセス格差と誤情報の拡散
現在、インターネットやSNSを通じて子どもでも簡単に性の情報を得ることができます。しかし、その多くは正しい知識とは言えないものです。たとえば、動画サイトやSNSで見かける情報の中には、「避妊をしなくても妊娠しない」「性行為は愛情の証だから断れない」といった危険な誤解も含まれています。
一方で、学校や家庭で性教育を十分に受けていない子どもは、どの情報が正しいのか判断するのが難しいのが現実です。この「性情報へのアクセス格差」が、間違った知識を信じる原因になっています。そして、その誤った知識がSNSでさらに広がり、次の世代にも影響を与えるという悪循環を生んでいます。
性犯罪・性被害を防ぐために必要な知識を教育現場で学べない
性教育が十分でないことは、性犯罪や性被害を増やす大きな要因でもあります。特にSNS時代では、見ず知らずの人から送られてくるメッセージや写真がきっかけで被害に遭うケースも増えています。
ここで大切なのは、「同意(相手に気持ちを確認すること)」の考え方です。「嫌なときはきちんと断る」「無理に求められたら逃げていい」という当たり前の感覚を持つことが、被害を防ぐ力になります。しかし残念ながら、日本ではこの「同意」の大切さを学校で学ぶ機会がほとんどありません。
また、「性的なことを誰かにされたらすぐ相談していい」という意識を持たない子どもも多いのが現状です。正しい性教育を通じて、被害にあったときに声を上げられる力を育むことが必要です。
親世代が性教育を受けていない
子どもに性教育を伝える役割は、学校だけでなく家庭にもあります。しかし、現在の親世代の多くは、自分自身も十分な性教育を受けてこなかった世代です。そのため、「何をどう伝えたらいいのかわからない」「恥ずかしいから話せない」と感じる人が多いのが現実です。
親が性の話を避けることで、子どもはますます聞きにくくなり、間違った情報を信じやすくなります。この課題を解決するためには、親自身も学び直し、正しい知識を身につけることが大切です。本や動画、講座など、親が学べる場をもっと広げることが必要です。
このように、日本の性教育はまだ課題が多く残っています。しかし、正しい知識を身につけることで、自分や周りの人を大切にできる社会に近づくことができます。そしてそれは、性被害や性差別のない未来をつくる大きな一歩なのです。
世界の性教育の現状
世界の性教育の現状も見ていきましょう。
包括的性教育が進められている
世界的にみると包括的な性教育が進められています。オランダやフィンランドといった先進国では、幼少期から包括的性教育が行われています。
包括的性教育とは、妊娠から出産までも含めて行われる性教育のことで、性感染症予防はもちろん人権やジェンダー問題に対しても適切な教育が行われます。
先進国では性感染症発症率が低かったり、妊娠率も低いなど効果もしっかりと表れています。
早期教育が行われている
性教育を行う年齢は先進国であればあるほど早いうちから始まります。早い国では5歳頃、言葉の意味をしっかりと理解できるようになった頃から性教育は始められます。
特にオランダは先進国の中でも進んでいて、幼少期の頃から性についてや愛の意味だけでなく、パートナーとのコミュニケーションスキルまで、しっかり学べるのでトラブルが少ない点も特徴です。
世界の性教育の実践事例と日本の違い
性教育は国によって内容や始める時期が異なります。海外では小さいころから自然に学べる仕組みを整えている国が多く、日本との差が大きな課題となっています。海外の先進事例と日本を比べることで、何が必要なのかが見えてきます。ここでは、「国別導入年齢・テーマ比較」の表も交えながら、わかりやすく説明します。
| 国・地域 | 性教育の開始年齢 | 主なテーマ | 特徴 |
|---|---|---|---|
| スウェーデン | 7歳(小学校1年生) | 体・心・同意・多様性など | 授業は必修。教員研修が充実 |
| オランダ | 4歳(幼児教育から) | 自己肯定感・関係性・同意 | 遊びや会話で自然に学ぶ |
| 日本 | 小学4年生〜(保健体育中心) | 思春期の体の変化が中心 | 教員研修や教材が不十分 |
北欧諸国(スウェーデン・オランダ)の成功例
スウェーデンでは小学校1年生から性教育が必修です。内容は体の仕組みだけでなく、「同意(相手の気持ちを確認すること)」や「性の多様性(LGBTQ+など)」も含まれます。教員がしっかり研修を受けており、安心して教えられる環境が整っています。
オランダではさらに早く、4歳から性教育が始まります。ただし難しい話をするのではなく、「自分の体を大事にする」「友達との関係を大切にする」といった生活の中のテーマから始まります。これが成長するにつれて、避妊や性病予防などの具体的な内容へと自然に広がります。
日本との比較|カリキュラム・教員研修・家庭の理解度
日本では小学校4年生頃から保健の授業で体の変化を学びますが、海外のように「同意」や「多様性」まで含む性教育はほとんどありません。教える先生も、専門研修を受ける機会が少ないのが現状です。
また、家庭での理解も課題です。「性の話は恥ずかしい」という空気が根強く、親も学校に任せきりになりがちです。北欧では家庭でも日常会話で性の話が出るのに対し、日本ではまだタブー視される傾向が強く残っています。
英語での性教育用語と教材例
世界では「Sexual Consent(性的同意)」「Gender Diversity(ジェンダーの多様性)」「Comprehensive Sexuality Education(包括的性教育)」などの言葉がよく使われます。英語で書かれた教材も豊富で、例えば『It’s Not the Stork!』や『It’s Perfectly Normal』は、絵とやさしい言葉で子どもにもわかりやすく説明しています。
海外と比べると、日本はまだ遅れていますが、改善のヒントは世界にたくさんあります。正しい知識を学ぶことは、子どもたちの安心と未来を守る第一歩になるのです。
性教育をするメリット
性教育をするメリットを見ていきましょう。
自己肯定感が高まる
日本では10代の死因一位が自殺と悲しい結果がありますが、その背景には自己肯定感の低さがあるといわれています。実は性教育を幼少期からしっかりと行うことで、自己肯定感が上がることがわかっています。
自己肯定感が高まる点は、性教育を行う上での大きなメリットとして挙げられます。
性教育の中には「妊娠から出産」についての内容も含まれているため、妊娠することも無事にこの世に生まれてこられたことも、実は奇跡ということを理解するだけでも、子どもの自己肯定感は育まれます。
性犯罪に巻き込まれない
性教育をしっかり受けていることにより、性犯罪に巻き込まれにくくなる点も性教育を受けるメリットとして挙げられます。
性の知識がないままある程度の年齢になってしまうと、性犯罪に巻き込まれても気づけない場合があり、後から気付いた時に大きな傷になってしまうこともあります。
また幼少期に性犯罪を犯してしまうことも、性教育を受けることで防げる点もポイントです。意外と多い幼少期の性加害も正しい性教育を受けていることで防げるようになります。
まだ子どもだから、子どものしたことだから、と見逃すのではなく、そうなる前に事前に性教育を施していくことが重要です。
性教育をしないことよるデメリット
性教育をしないことよるデメリットをご紹介します。
性的な内容を誤解して認識してしまう
性的な内容を誤解して認識してしまうと、恋人との関係がうまくいかなかったり、異性との間違ったコミュニケーションを正しいと感じてしまうがあり、これは大きなデメリットとして挙げられます。
性の知識を得るのが漫画やスマホからだった場合、正しい性知識が身につかないまま大人になってしまいます。その場合、気づかないうちに性加害をしてしまっていたり、間違った知識で異性を傷つけてしまったりといったことが起きてしまいます。
性の知識が乏しく望まぬ妊娠に繋がってしまう
10代のうち、性の知識が乏しい子どもは多数いて、にんしんSOSには10代からの問い合わせが多数届いているのは、性教育をしないことによる大きなデメリットです。
妊娠出産の仕組みを性教育で教えられていない場合に、仕組みがわからないから必要のない妊娠の心配をしたり、実際に間違った知識で妊娠してしまったりといったことも、十分に起こりえます。
具体的に何をしたら妊娠するのか、避妊具の正しい使い方は理解できているのか、そういったところにも幼いころから踏み込んだ性教育が必要なことが伺えます。
家庭で始める性教育の実践法
性教育は「学校で教えてくれるから大丈夫」と思いがちですが、実は家庭でも少しずつ伝えることがとても大切で、親ができる工夫はたくさんあります。ここでは、日常の中で自然にできる伝え方や、子どもから質問されたときの対応、恥ずかしさを和らげるコツについてご紹介します。
家庭でできる日常会話での伝え方
性教育というと特別な話をしないといけないと感じるかもしれませんが、実は普段の会話の中に少しずつ取り入れるのが効果的です。たとえば、お風呂で体を洗うときに「ここはとても大事な場所だから、自分でちゃんと守ろうね」と伝えるのも立派な性教育です。
また、テレビや絵本に登場する場面をきっかけに、「どう思う?」と子どもに聞いてみるのもおすすめです。これなら子どもも自然に考えるきっかけになりますし、親も話しやすくなります。
質問されたときの答え方のコツ
子どもから「赤ちゃんはどうやって生まれるの?」などと聞かれて、戸惑うこともあるかもしれません。そのときは無理に全部説明しようとせず、年齢に合った言葉で簡単に答えるのが大切です。
たとえば、小さい子どもには「お母さんのお腹の中で大事に育てられて生まれてくるんだよ」と伝えるだけでも十分です。もっと知りたそうなら「どうしてそう思ったの?」と聞き返し、興味の深さを確かめながら少しずつ話を広げましょう。
恥ずかしさやタブー感を取り除くには
性の話は「恥ずかしい」「話しにくい」と感じる親も多いと思います。しかし、親が恥ずかしそうにするほど、子どもも「聞いてはいけないことなのかな」と思ってしまいます。
そんなときは、本や絵本を使うのもひとつの方法です。本を一緒に読みながらなら、親も自然に説明できますし、子どもも安心して聞けます。また、「これってどう説明したらいいんだろう?」と正直に子どもに言ってみるのも大丈夫です。親も一緒に学んでいる姿を見せることは、子どもにとってとても大きな安心になります。
このように、性教育は特別な時間を作るよりも、毎日の生活の中で少しずつ話すことが大切です。学校に任せきりにせず、親だからこそできる声かけを続けることで、子どもは安心して体と心を大切にする力を育んでいきます。
参考:【第68号】「おうちで伝える『性』のおはなし その2 ~どうやって子どもに伝えよう?」NPO法人ピルコン理事長 染矢 明日香
性教育に使える絵本・本・イラスト教材
性教育を家庭や学校で始めたいと思っても、「どんな本や教材を使えばいいの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。信頼性のある絵本やイラスト教材を活用することで、子どもも大人も楽しく、そして安心して学ぶことができます。
ここでは年齢別におすすめの絵本や、本・動画教材などをわかりやすく紹介します。
年齢別おすすめ絵本(3歳〜小学生向け)
小さい子どもには、わかりやすい言葉とやさしい絵が使われている絵本が最適です。たとえば『からだのなまえ』という絵本は、体の部位を正しい名前で自然に教える内容で、プライベートゾーンの話も無理なく取り入れられます。
また、『みんなうまれてきたんだよ』は、赤ちゃんがどうやって生まれてくるのかを優しく伝える絵本です。小学生向けには、『からだの本』など、心と体の変化を絵と一緒に説明している本もおすすめです。こうした本は、読むだけでなく親子で話すきっかけにもなります。
イラスト・図解で伝える性教育(日本語・英語両方)
イラストや図解を使った本は、視覚的にわかりやすく、子どもが興味を持ちやすいのが特徴です。『せいとからだのえほん』などは、カラフルな絵で体の仕組みや思春期の変化を説明してくれるので、小学生から中学生まで幅広く使えます。
また、英語でも性教育の本があります。『It’s Not the Stork!』は幼児〜小学生向け、『It’s Perfectly Normal』は思春期向けに作られた本で、世界中で読まれているロングセラーです。英語と日本語の両方で学ぶことで、国際的な視点も広がります。
参考:命育
中高生におすすめの実用書・漫画・動画教材
中高生には、実際の悩みに近い内容を扱った本や漫画、動画教材が役立ちます。『14歳の世渡り術 性のこと、ちゃんと知ってる?』は、同意や避妊、性の多様性などをわかりやすく解説してくれる実用書です。
また、『あさきゆめみし』のように古典を題材にした漫画でも、恋愛や性のテーマを自然に学べます。動画教材では、YouTubeなどで専門家が監修した性教育チャンネルも増えており、親子で一緒に見るのもおすすめです。
このように、絵本やイラスト、本や動画などを使うことで、性教育はもっと身近で楽しいものになります。信頼できる教材を活用しながら、子どもたちが安心して学べる環境をつくっていきましょう。
性教育とSDGsとの関係
性教育は、SDGsの目標とも深い関わりがあります。特に関係が深いのは、目標3「すべての人に健康と福祉を」と目標5「ジェンダー平等を実現しよう」です。性教育を通じて身につく正しい知識は、自分の体や心の健康を守るだけでなく、無理な関係を断る勇気や性感染症の予防にも役立ちます。
また、目標5のジェンダー平等では、男の子も女の子も同じように大切にされるという価値観や、「同意」や「拒否する勇気」の重要性を学ぶことが含まれます。これらの学びは、性差別や暴力を減らし、互いを尊重し合える社会を築くための土台になります。
このように、性教育は単なる知識の伝達にとどまらず、一人ひとりが安心して暮らせる社会を目指すSDGsの理念とも深く結びついている大切な学びなのです。
性教育に関するよくある質問
性教育というと、「まだうちの子には早いのでは?」「どうやって話したらいいの?」と悩む親御さんや大人の方は少なくありません。性はとても大切なテーマだからこそ、誰でも迷うのは自然なことです。ここでは、特によく聞かれる5つの質問について、わかりやすく答えていきます。
Q1. 性教育は何歳から始めたらいいですか?
「性教育=思春期の子どもに教えるもの」と思われがちですが、本当はもっと早くから始めるのが望ましいとされています。たとえば、幼児期には「体の名前を正しく教える」「プライベートゾーンは大事だと伝える」といったシンプルなことから始められます。年齢が上がるにつれて、「体の変化」「心の成長」「相手を思いやる気持ち」などを少しずつ教えていくのが理想です。
このように段階を踏むことで、子どもも自然に理解を深めていきます。
Q2. 恥ずかしくてうまく説明できません。どうすればいいですか?
大人が恥ずかしいと感じるのは自然なことです。でも、「恥ずかしい」と思う気持ちは子どもにも伝わります。そのため、まずは親自身が少しずつ学び直すことから始めましょう。絵本やイラスト付きの本を一緒に読むと、説明しやすくなりますし、子どもも受け入れやすくなります。
また、すべてを一度に話そうとしなくても大丈夫です。子どもから質問されたときに、「とてもいい質問だね」とほめてから、少しずつ答える方法も効果的です。「親も一緒に学んでいるんだよ」という姿勢を見せることで、子どもも安心して話を聞けます。
Q3. 性教育で何を教えたらいいのでしょうか?
性教育というと「性行為」や「避妊」などを教えるイメージが強いかもしれません。しかし実際にはもっと広い内容があります。たとえば、「自分の体を大切にすること」「他人の体を尊重する気持ち」「同意(相手の気持ちを確認すること)の大切さ」「体や心の変化」「性の多様性(いろいろな感じ方や考え方があること)」なども含まれます。
学ぶ内容は年齢によって変わります。小さい子には体の名前やプライベートゾーン、中学生や高校生には避妊や性感染症の予防、恋愛や人間関係など、生活に近いテーマを段階的に伝えていくことが大切です。
Q4. 子どもがネットや友達から性の情報を仕入れているようで心配です
今はSNSや動画などで、簡単に性の情報を得られる時代です。その中には正しいものもあれば、間違った情報や偏った内容も多くあります。だからこそ、家庭での性教育がますます重要です。
「それはどこで知ったの?」と穏やかに聞き、「本当はこうなんだよ」と正しい知識を伝えることが大事です。頭ごなしに「そんな話しないで!」と言うと、子どもは余計に隠すようになります。話を聞いてくれる安心感を与えつつ、間違いを一緒に確認する姿勢が信頼関係を深めます。
Q5. 親自身が性教育を受けてこなかったので、どう教えていいかわかりません
親世代の多くは、性教育をきちんと受けてこなかった人も多いです。それでも大丈夫です。大切なのは「完璧に教えなければ」と思い込まないことです。今から一緒に学ぶ気持ちで本や動画を活用し、「知らなかったことを知るって楽しいね」と親子で話してみましょう。
また、市区町村や学校、保健センターなどで性教育講座を開催している場合もあります。専門家の話を聞いてみるのもおすすめです。親自身が知識を持つことで、子どもへの言葉も自然に出てくるようになります。
性教育は難しいテーマに見えますが、大切なのは「知っておいてほしい」という気持ちです。恥ずかしさを少しずつ減らしながら、一歩ずつ始めてみましょう。それが、子どもが自分の体と心を大切にし、他者を尊重する力を育てる第一歩となります。
まとめ
性教育は「体や心を守り、他者を尊重する力」を育む大切な学びです。年齢に合った内容を少しずつ伝えることで、子どもは安心して成長できます。また、SDGsの目標でもある「健康と福祉」「ジェンダー平等」にもつながる学びです。家庭でも学校でも特別なことではなく、日常の中で自然に話すことが大切です。恥ずかしさを少しずつ手放し、親子で一緒に考え学ぶことから始めてみましょう。
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS