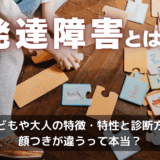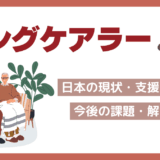SDGs(持続可能な開発目標)は、医療現場においても重要な役割を果たしています。特に「すべての人に健康と福祉を」という目標3は、医療機関が地域社会や環境へ配慮しながら質の高い医療を提供することを求めています。また、医療廃棄物の削減や省エネルギー対策など、環境負荷を抑える取り組みもSDGsの一環です。
本記事では、医療機関が進めるSDGsの取り組みについて、具体的な事例を交えながら詳しく解説します。医療現場が持続可能な社会にどのように貢献できるのか、一緒に考えてみましょう。
医療現場におけるSDGsの取り組み

SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)は、2015年に国連で採択された2030年までの国際目標です。17の目標と169のターゲットから構成されており、貧困の撲滅、環境保護、ジェンダー平等、持続可能なエネルギーの利用など、幅広い分野で持続可能な社会の実現を目指しています。
SDGsの基本概要
SDGsは、「誰一人取り残さない(Leave no one behind)」を基本理念とし、先進国も途上国も共に達成を目指す包括的な目標です。例えば、目標1「貧困をなくそう」や目標3「すべての人に健康と福祉を」は、医療の果たす役割が大きいです。特に、目標3は医療現場と直接的に結びつき、健康的な生活の提供や感染症の予防、母子保健の推進を目指しています。
例えば、日本国内では母子健康手帳の普及により、妊婦や新生児の健康管理が効率化されています。この取り組みはSDGs目標3の「すべての人に健康と福祉を」に貢献しており、母子の死亡率低下に大きく寄与しています。また、途上国においてはワクチンプログラムが展開され、感染症の予防が図られています。
SDGsと医療との関係
医療は人々の健康を守るだけでなく、地域社会の持続可能な発展にも大きな役割を果たします。例えば、地域医療の充実によって、都市部と地方の医療格差を是正することができ、遠隔診療の導入によってアクセスの悪い地域でも質の高い医療を提供することが可能です。また、持続可能なエネルギーの活用や廃棄物の削減など、環境保護への取り組みも重要な要素となります。
ソーラー発電を導入し、病院内のエネルギーを自給自足する試みを実施している病院もあります。これにより、CO2の排出削減し持続可能な病院の運営が可能です。また、ペーパーレス化の推進により、年間で数十万枚の紙資源が節約されています。
医療現場におけるSDGsの重要性
医療廃棄物の削減、エネルギー効率の改善、さらには地域社会との連携強化など、医療現場の日々の業務を通じて持続可能な社会づくりに貢献できます。特に、感染症の拡大防止や高齢化社会への対応は、地域の健康を守ると同時に、医療資源の有効活用を推進します。
例えば、リサイクル可能な資材への切り替えを進め、年間の廃棄物を大幅に削減した医療機関があります。地域住民を巻き込んだ健康教育プログラムを実施し、予防医療の推進も行われています。これにより、地域全体の健康水準が向上し、医療費の削減が可能です。
持続可能な医療提供を実現するためには、病院やクリニックが主体的にSDGsの考えを取り入れることが重要です。地域社会と連携しながら効率的なエネルギー管理、廃棄物のリサイクル、デジタル技術の活用など、具体的な取り組みを進める必要があります。これにより、医療現場は未来の持続可能な社会に向けて、大きな一歩を踏み出すことができるのです。
医療現場にSDGsの考えが必要だとされるのはなぜ?
医療現場にSDGsの考えが必要とされる理由は多岐にわたります。医療は人々の健康を守り、地域社会の発展に貢献するだけでなく、環境負荷の軽減にも大きな役割を果たします。ここでは、6つの観点からその重要性を詳しく解説します。
健康と福祉の向上(SDGs目標3)
SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」は、医療機関が最も深く関わる目標です。予防医療や感染症の管理、母子保健の推進を通じて、人々の健康を守り、福祉を向上させる取り組みが行われています。特に高齢化が進む日本では、在宅医療や訪問看護の拡充が求められ、地域全体の健康促進に貢献しています。さらに、遠隔診療の普及により、医療へのアクセスが限られた地域でも、質の高いケアを提供できる体制が整いつつあります。
遠隔診療システムを導入し、山間部や離島地域でも質の高い診療が受けられる体制を構築している地域もあります。また、地域の健康センターでは予防接種の普及と健康教育が進められており、感染症の発生率が大幅に低下しています。
貧困層への医療アクセスの改善
世界中には、経済的な理由で十分な医療を受けられない人々が数多く存在しています。日本国内でも、低所得世帯に対する医療費の負担軽減や、公的医療保険の整備が進められています。特に、地方自治体による無料健康診断の実施や、地域医療センターでの無料相談は、貧困層への医療アクセス改善に役立っています。
また、発展途上国ではNGOや国際機関による医療支援が行われ、診療所の設立や医薬品の提供が進んでいます。アフリカ地域では、モバイルクリニックの導入により、医療機関から離れた村落でも診療を受けられるようになりました。
持続可能な医療資源の活用
医療現場では多くの使い捨て製品やプラスチックが消費されています。これを削減するため、再利用可能な器具の導入や、廃棄物のリサイクルが進められています。再利用可能なステンレス製のトレーや器具の導入を進め、年間で数十トンのプラスチック廃棄物を削減した医療機関もあります。
また、エネルギー効率の向上も課題です。太陽光発電の設置やLED照明の導入により、医療施設のCO2排出削減が図られています。
持続可能な地域医療の確立
医療は地域社会と密接に結びついています。災害時の医療提供や高齢者の介護、予防接種の普及など、地域との協力が不可欠です。地域住民との信頼関係を構築し、健康教育を推進することで、持続可能な地域医療が実現します。
例えば、地域コミュニティと連携し、災害時の医療提供体制を強化する訓練を定期的に行う取り組みがあります。また、地域住民が参加する健康促進プログラムは、病気の早期発見・予防に役立ち、医療費の削減が可能です。
気候変動と医療インフラへの影響
気候変動による自然災害は、医療インフラに深刻な影響を与える可能性があります。台風や洪水で病院の機能が停止すれば、迅速な医療提供ができなくなります。持続可能なエネルギーの活用や防災対策を強化することで、医療現場のレジリエンスを高める取り組みが進んでいます。
例えば、九州地方の病院では、災害時の停電に備えて自家発電システムの導入が進められています。これにより、緊急時にも医療サービスの提供が確保され、地域住民も安心です。
医療現場でのグリーン調達と持続可能な資材利用
医療現場では、大量の医療資材や消耗品を日々使用しています。これらの資材の多くは使い捨てプラスチックや非再生可能な素材が中心ですが、近年、持続可能な資材利用への移行が進められています。これを促進する動きの一つが「グリーン調達」です。
グリーン調達とは、製品やサービスの調達において、環境負荷の少ない製品やエコ認証を受けた資材を優先的に選ぶ取り組みです。例えば、ヨーロッパの医療機関では、再生プラスチックや生分解性素材を使った手袋や医療器具が採用されています。また、日本国内でも、病院で使用する手術衣やシーツをリサイクル繊維に切り替える動きが見られます。
さらに、医療機器メーカーも環境に配慮した製品開発を加速しており、使い捨てから繰り返し利用できるデザインへシフトしています。例えば、再利用可能なステンレス製のトレーや、殺菌後に再利用できる医療器具の導入は、医療廃棄物の削減に大きく貢献しています。
このような取り組みは、SDGs目標12「つくる責任、つかう責任」に直結し、持続可能な社会の実現に向けて重要な役割を果たしています。医療現場がグリーン調達を意識することで、環境負荷を軽減しながらも質の高い医療提供が可能です。
医療現場にSDGsを取り入れるメリット
医療現場でSDGs(持続可能な開発目標)の考え方を取り入れることは、単に環境や社会貢献のためだけではありません。患者さんへの医療の質向上や公平性の確保、医療資源の有効活用、そして医療従事者の働きやすさ向上など、多くの具体的なメリットがあります。持続可能な社会を目指すだけでなく、日々の医療活動そのものをより効率的で安心できるものにするための取り組みとして、SDGsは医療現場にとって非常に有用です。
ここでは、その具体的なメリットを詳しく見ていきます。
医療の質と公平性の向上
SDGsの理念に沿って医療現場が取り組むことで、地域や所得による医療格差を減らせます。たとえば、情報共有やアクセス改善を進めることで、遠隔地や経済的に不利な環境にある人も必要な治療を受けやすくなります。
また、標準化された診療や研修制度の導入により、誰が対応しても一定水準の医療が提供できる体制を整えられます。これによって、患者の安心感や信頼性も向上し、持続可能な医療サービスにつながります。
持続可能な医療資源の活用
SDGsの観点を取り入れることで、医療資源の効率的な利用が進みます。医薬品や医療機器の廃棄を減らす取り組み、エネルギー効率の良い施設運営、そして紙や水の使用量削減などの環境への負荷を減らす工夫が可能です。限りある資源を無駄なく使うことでコスト削減にもつながり、患者の負担軽減や医療現場の持続性を高める効果があります。
長期的には、地球環境と医療現場双方の持続可能性を支えるメリットがあります。
患者中心の包括的ケアの推進
SDGsの視点を取り入れると、単に病気を治すだけでなく、患者の生活や社会的背景も考慮した包括的なケアが可能になります。地域の福祉サービスや教育機関、自治体と連携し、患者の心身の健康だけでなく生活全体を支える体制を作ることができます。
こういった体制により、再入院のリスクを減らし、生活の質を高めると同時に社会全体で健康を支える文化の醸成にも寄与します。
医療従事者の意識向上と働きやすい環境づくり
SDGsに沿った取り組みは、医療従事者の意識向上にもつながります。医療格差の是正や環境配慮など社会的使命を意識することで、仕事へのやりがいや目的意識が高まります。また、働き方改革や多様性の尊重、メンタルヘルス支援などと連動させることで、職場環境の改善にもつながり、離職防止やチーム力の向上に寄与します。
医療現場でSDGsを取り入れるためのポイント
持続可能な医療を実現するためには、具体的な取り組みが欠かせません。ここでは、医療現場でSDGsを効果的に取り入れるための6つのポイントについて解説します。
エネルギー効率の向上と省エネ対策
医療機関は24時間体制で稼働するため、エネルギー消費が非常に多くなります。太陽光発電の導入やLED照明の活用、空調システムの効率化など、持続可能なエネルギーの利用が進んでいます。
また、病院内のエネルギー消費を「見える化」することで、無駄な消費を抑え、環境負荷の軽減を図っています。エネルギー管理システムの導入により、ピーク時の消費抑制や効率的な電力運用が可能です。
医療廃棄物の削減とリサイクルの促進
医療現場では大量の使い捨てプラスチックや廃棄物が発生します。これに対し、再利用可能な医療器具の導入や、リサイクルシステムの確立が進められています。
また、医薬品の余剰廃棄を防ぐため、患者に適切な量の処方を行う取り組みも実施されています。さらに、使い捨て製品の代替として、シリコン製の再利用可能な器具の導入事例もあります。
デジタル技術の活用で医療サービスの効率化
電子カルテの導入やオンライン診療の普及により、ペーパーレス化が進んでいます。これにより、紙資源の削減だけでなく、患者情報の管理が効率化され、診療の質も向上しています。
さらに、AI(人工知能)を活用して診療予約の最適化や、遠隔地との医療連携も可能です。特に、過疎地域では専門医によるオンライン診療が実現し、医療格差の是正にもつながっています。
感染症対策と衛生管理の強化
医療現場では感染症のリスクが常に存在します。持続可能な消毒技術や衛生管理の強化により、院内感染の防止が重要です。抗菌素材の使用や、非接触型の診療システム、空気清浄システムの改善の導入が効果的な手段です。
多様性と包摂性のある医療の提供
国際化が進む社会では、多文化対応の医療提供が求められています。多言語対応やバリアフリー設計に加え、障がい者や高齢者にも優しい環境を整えることで、誰もが安心して医療を受けられる体制が築かれています。
多言語対応の医療ガイドを作成し、外国人患者へのサポートを強化する取り組みもあります。さらに、院内のバリアフリー化も進み、車椅子やベビーカーでもスムーズに移動できる環境が整備されています。
これらの取り組みは、持続可能な医療の実現に向けた重要なステップであり、地域社会全体の福祉向上にも貢献しています。
地域連携を強化するための取り組み
持続可能な医療提供には、地域社会との強固な連携が不可欠です。特に災害時の対応力や高齢者のケア、遠隔診療の充実は、地域と医療機関が協力し合うことで効果的に進められます。
具体例として、広島県では、地域コミュニティと医療機関が共同で災害対応訓練を実施しています。地域住民も参加することで、災害時の医療提供がスムーズに行える体制が整備されています。また、医療スタッフが地域の高齢者を定期的に訪問し、健康状態の確認や予防医療を提供する「地域医療パトロール」も実施されています。
さらに、デジタル技術を活用した地域連携も進んでいます。たとえば、遠隔診療システムを用いることで、山間部や離島でも医療アクセスが確保され、専門医の診察を受けることが可能です。これにより、地域間の医療格差が縮小され、住民の健康が守られています。
地域社会との協力による医療提供は、SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」だけでなく、目標11「住み続けられるまちづくりを」にも貢献しています。医療機関と地域が連携することで、持続可能な医療基盤が強化され、災害にも強い地域づくりが実現するのです。
医療現場にSDGsを普及させるための今後の課題・問題点
医療現場でSDGsの取り組みを広めることは、患者への医療の質向上や資源の有効活用に役立ちます。しかし、現場での理解不足や予算・人材の制約、制度との調整など、普及を妨げる課題も多く存在します。
これらを整理することで、より現実的で効果的な導入方法を検討することができます。主な課題を具体的に見ていきましょう。
医療従事者の理解と意識のばらつき
SDGsの理念や具体的な取り組みは、医療現場でまだ十分に浸透していないことがあります。医師・看護師・事務職など職種や経験年数によって理解度や関心の差が大きく、同じ施設内でも取り組みに温度差が生じやすい状況です。このため、研修や勉強会の実施、職種横断での情報共有などを進める必要があります。理解が深まらないままでは、制度の導入や日々の運用に支障をきたす可能性があります。
予算や人材の不足
SDGsに基づいた取り組みには、システム導入やデータ管理、環境改善、啓発活動などコストや人手がかかる場合があります。特に中小規模の医療機関や地方の病院では、予算や専任人材が不足しており、取り組みを後回しにせざるを得ないケースもあります。
持続可能な施策を行うためには、行政支援や補助金の活用、効率的な人材配置の工夫が重要です。
制度のルールとの整合性
医療現場は、医療法や個人情報保護法など多くの規制の下で運営されています。SDGsに基づくデータ共有やICT活用、地域連携などの取り組みが、既存の制度やルールとぶつかることがあります。規制を守りながら柔軟に運用する必要があり、制度改正やガイドラインの整備も課題です。現場レベルでの調整や行政との連携が不可欠となります。
成果の見えにくさとモチベーション維持
SDGsの取り組みは中長期的な効果が中心であり、短期的には成果が見えにくいことがあります。医療従事者や施設運営者にとって、効果が実感できないまま負担だけが増えると、モチベーション低下の原因にもなります。取り組みに関する目標の設定や経過報告・共有体制などを整えた上で、スタッフに取り組みの意義を明確化したり成果を可視化することが必要です。
病院・医療現場におけるSDGsの取り組み具体例
医療現場において、SDGsの達成に向けた具体的な取り組みは多岐にわたります。ここでは、日本国内の医療機関が進めている先進的な10の事例を紹介します。これらの取り組みは、地域社会や地球環境に貢献し、持続可能な医療提供を目指したものです。
事例1:東京北医療センター:SDGs部会の設立と環境対策

東京北医療センターでは、SDGs部会を設立し、プラスチックごみの削減やデジタル掲示による紙資源の削減、EV車の導入など、環境負荷の低減に努めています。また、病院内のエネルギー効率改善にも取り組み、太陽光発電の導入で年間20%の電力を自給しています。
また、東京北医療センターでは、国連が掲げるSDGsの実現に向けて、地域医療・福祉の充実や環境負荷の低減に積極的に取り組んでいます。24時間救急・小児医療の提供や健康啓発活動、障がい者雇用の推進、ジェンダー平等の実践、動画配信による啓発活動など、多様な視点から持続可能な社会づくりにも貢献しています。ソフトとハードの両面から取り組んでいるといえるでしょう。
- 関連SDGs:目標3(すべての人に健康と福祉を)、目標10(人や国の不平等をなくそう)、目標11(住み続けられるまちづくりを)
- 参考URL:東京北医療センター SDGsへの取り組み
事例2:済生会:無料低額診療と災害医療訓練の実施

生活困窮者への無料低額診療の提供や、災害時に備えた医療訓練の実施など、地域社会の安全と福祉の向上に貢献しています。特に、地域防災計画との連携を強化し、緊急時の医療支援体制を整備しています。
また、済生会では「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、医療・福祉・介護の枠を超えた支援を全国で展開しています。貧困層への無償診療をはじめ、就労支援や地域連携による見守り活動などを実践。ソーシャルインクルージョンの理念を軸に、SDGsの達成に貢献しています。
- 関連SDGs:目標1(貧困をなくそう)、目標7(エネルギーをみんなに そしてクリーンに)、目標13(気候変動に具体的な対策を)
- 参考URL:2030年までの国際目標 – SDGsと済生会
事例3:筑波学園病院:地域医療・働き方改革・環境配慮の三本柱
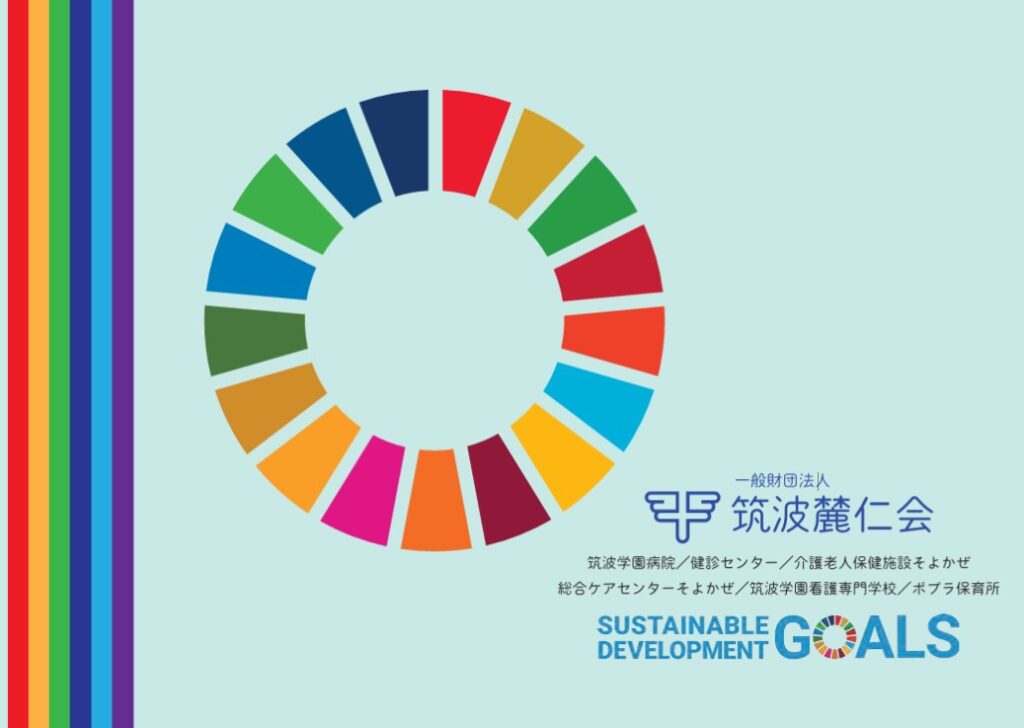
地域医療の強化、職員の働きやすい環境づくり、環境への配慮を進めることで、持続可能な医療提供を実現しています。また、電子カルテの導入や遠隔診療を推進し、患者の利便性向上にも寄与しています。
ほかにも筑波学園病院では、地域医療・働きがい・環境の3つの視点からSDGsに取り組んでいます。災害に強い病院づくりや再生可能エネルギーの活用、働きやすい職場環境の整備に加え、地域連携によるスマート医療実証にも参加。持続可能で誰もが安心できる医療体制の実現を目指しています。
- 関連SDGs:目標3、目標8(働きがいも経済成長も)、目標12(つくる責任 つかう責任)
- 参考URL:一般財団法人筑波麓仁会 筑波学園病院|「地域医療にイノベーションを」 – Spaceship Earth(スペースシップ・アース)
事例4:山下病院:サステナビリティ推進室の設置と医療機器開発

サステナビリティ推進室を設置し、労働環境の改善や企業との連携で医療機器の開発、地域でのSDGs教育も展開しています。これにより、地域住民の健康意識が高まり、持続可能な社会づくりが促進されています。
このように山下病院では、医療従事者の働き方改革や医療機器の開発、教育・啓発活動を通じてSDGsの達成に貢献しています。労働環境の改善や人間工学の活用により医療の質を高め、地域や企業と連携しながら持続可能な医療体制の構築を目指しているのです。
- 関連SDGs:目標3、目標9(産業と技術革新の基盤をつくろう)、目標17(パートナーシップで目標を達成しよう)
- 参考URL:サステナビリティ推進室 | 医療法人 山下病院|愛知県一宮市の消化器内科
事例5:横須賀市立うわまち病院:経済的支援による出産費用の補助

経済的理由で出産費用を負担できない方への補助を行い、安心して出産できる環境を提供しています。また、地域全体での子育て支援も進めており、若い世代の移住促進にもつながっています。
さらに横須賀市立総合医療センターでは、誰一人取り残さない医療の実現を目指し、17のSDGs目標に幅広く取り組んでいます。救急・周産期医療の提供、教育支援、外国人患者への多言語通訳、環境配慮型設備の導入などを通じて、地域と地球の持続可能性に貢献しているのです。
- 関連SDGs:目標1、目標3、目標10
- 参考URL:SDGsへの取り組み | 当院について | 横須賀市立総合医療センター
事例6:白十字会グループ:災害時拠点機能の整備とフードロス対策
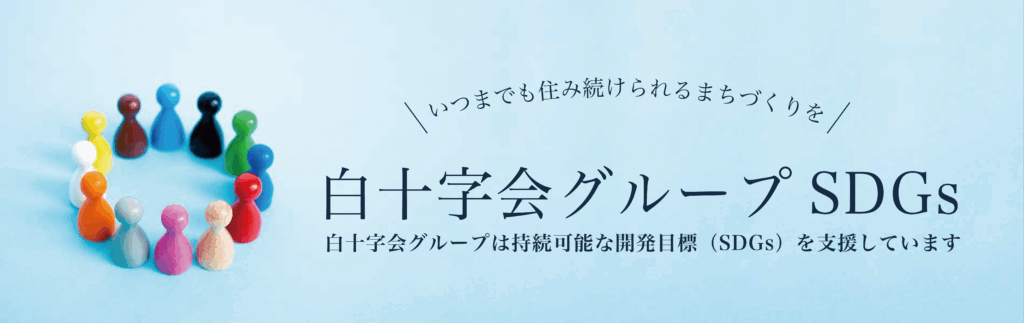
災害時の拠点機能の整備や、病院食のフードロス削減など、地域に根ざした持続可能な医療提供を行っています。また、地域農家との連携を強化し、地産地消の取り組みも推進しています。
ほかにも白十字会グループでは、「住み続けられるまちづくり」を目指し、災害時の医療継続体制や地域交流施設の整備、井戸水の活用など多面的なSDGsの取り組みを実施しています。リハビリや福祉用具の提案を通じて、障害があっても自宅で暮らし続けられる支援にも力を入れているのが特色です。
- 関連SDGs:目標11、目標12、目標13
- 参考URL:11 住み続けられるまちづくりを
事例7:ニューハート・ワタナベ国際病院:低侵襲治療と省エネルギー設備の導入

患者の負担を軽減する低侵襲治療や、ライフライン設備の高効率・省エネルギー化を推進しています。特に、手術室のLED化やエネルギー管理システムの導入により、消費電力の15%削減を達成しました。
また、ニューハート・ワタナベ国際病院では、すべての人に最先端かつ平等な医療を提供することを通じて、SDGsの達成に貢献しているのも注目です。低侵襲治療やロボット手術の普及、職員の働きやすい環境づくり、地球環境への配慮など、医療・教育・環境の各分野で幅広く取り組みを展開しています。
- 関連SDGs:目標3、目標7(エネルギーをみんなに そしてクリーンに)、目標9
- 参考URL:SDGsへの取り組み – 当院について – ニューハート・ワタナベ国際病院
事例8:真生会向日回生病院:地域密着型の医療と多様な雇用形態の導入

地域の基幹病院として、在宅医療や介護まで一貫したサービスを提供し、障害者や外国人技能実習生の雇用を積極的に行っています。また、多言語対応の医療提供を進め、地域の国際化にも対応しています。
さらに、患者本位の医療と介護を基本理念に、地域に根ざした医療・介護の提供を通じてSDGs達成に貢献しています。障害者や外国人の雇用、研修制度の充実だけでなく、災害対策、環境保全など、多方面から持続可能な社会づくりを推進。地域とともに成長する医療機関を目指しています。
- 関連SDGs:目標3、目標5(ジェンダー平等を実現しよう)、目標8
- 参考URL:真生会のSDGsへの取り組み
事例9:福岡記念病院:医療従事者の負担軽減と処遇改善

医師や看護職員の負担軽減を目的に、勤務体制の見直しや処遇の改善に取り組んでいます。特に、看護師の夜勤負担を減らすためのシフト管理システムの導入が効果を上げています。
このように福岡記念病院では、SDGsの理念に基づき、医療従事者の働き方改革を中心に行っていますが、他にも環境負荷軽減、職員の健康支援など多方面にわたる取り組みを行っています。エネルギー効率化やごみの適正処理、研修制度の充実を通じて、持続可能で安心できる医療環境の実現を目指しているのです。
- 関連SDGs:目標3、目標8
- 参考URL:病院の取り組み | 福岡記念病院
事例10:立川相互病院:24時間救急と地域医療支援の強化

24時間体制の救急医療を提供し、地域医療支援病院としての役割を果たしています。また、地域の防災訓練にも参加し、災害時の医療提供体制の強化に貢献しています。
- 関連SDGs:目標3、目標11
- 参考URL:SDGsの取り組み – 立川相互病院 24時間救急で地域のいのちを守る
これらの取り組みは、地域社会や環境への配慮だけでなく、患者や職員にとっても安心で持続可能な医療を提供する基盤となっています。各施設が独自のSDGs目標を掲げ、地域住民と連携しながら実現に向けた取り組みを推進しています。
さらに立川相互病院では、SDGsの17目標のうち13項目に対し、無差別・平等の医療の提供や地域福祉、教育支援など多岐にわたる取り組みを行っているのもポイントです。貧困対策やジェンダー平等、省エネ、防災、働き方改革にも注力し、誰もが安心して暮らせる持続可能な社会の実現を目指しています。
まとめ
医療機関がSDGsの目標に向けた取り組みを進めることは、地域社会の健康維持だけでなく、持続可能な社会の実現にも大きく貢献します。具体的には、エネルギー効率の改善や医療廃棄物の削減、インフラの強化が進められています。これにより、医療提供の質が向上し、地域医療の強化も実現しつつあります。また、遠隔診療やデジタル技術の導入は、都市部と地方の医療格差を縮小し、どの地域に住んでいても平等な医療サービスを受けられる環境を整えています。
さらに、地域社会との連携を強化することで、災害時の対応力も向上しています。災害発生時には迅速な医療提供とインフラの強化が求められ、これにより地域住民の安全と安心が確保されるのです。医療機関がSDGsの目標を意識した取り組みを進めることは、単なる医療の提供にとどまらず、社会全体の安全と安心を確保する重要な役割を担っています。
一方で、持続可能な医療の実現には多くの課題が残されています。医療廃棄物の適正処理やエネルギー消費の削減、地域間の医療格差の是正は依然として大きな問題です。また、高齢化の進展に伴う医療費の増加や、気候変動による災害リスクの増加も解決すべき課題です。こうした課題に対応するには、医療機関だけでなく、地域社会や行政、さらには個々の市民が一体となって取り組む必要があります。
医療機関の取り組みは、地域社会の健康を守り、未来へとつながる持続可能な社会の実現に向けた重要な役割を果たすのです。
<参考文献>
・「『Society 5.0』における医師会」
・すべての人に健康と福祉を | 国連広報センター
・【政策提言】環境と医療の融合で実現する持続可能な健康長寿社会~プラネタリーヘルスの視点を取り入れた第3期健康・医療戦略への提言~(2024年12月20日) | 日本医療政策機構
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS