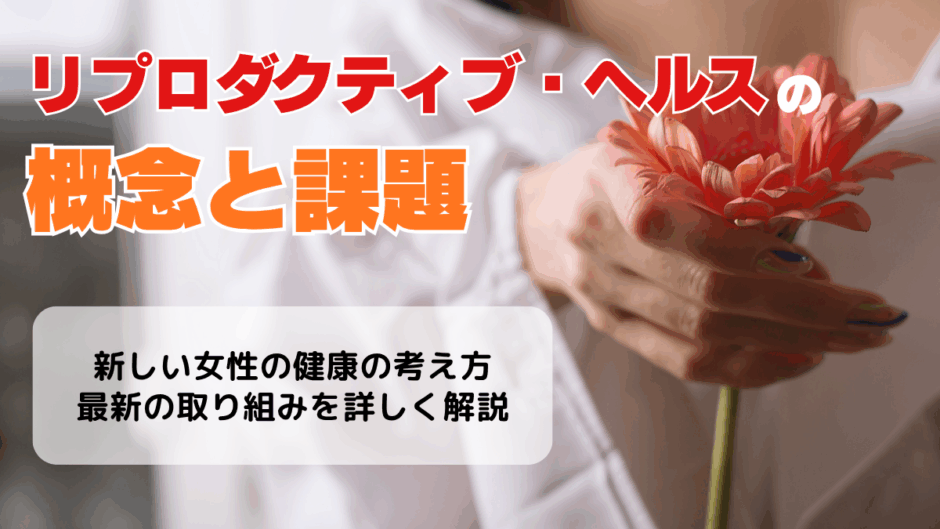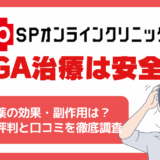リプロダクティブ・ヘルスは、心と身体、そして社会のバランスを保ちながら、自分の人生を自ら選択するための健康の在り方です。妊娠・出産だけでなく、避妊や不妊治療、性教育、さらにはジェンダー平等にも関わる重要なテーマとして注目されています。
この記事では、リプロダクティブ・ヘルスの基本概念や課題、世界と日本の現状、そして社会が変わり始めている最新の取り組みについて詳しく解説します。
リプロダクティブ・ヘルスについて、パートナーや周囲とオープンに話せる関係を築き、だれもが健康で自分らしい選択ができる社会を目指しましょう。
リプロダクティブ・ヘルスとは?

リプロダクティブ・ヘルスとは、WHO(世界保健機関)が提唱する「性と生殖に関する健康」の概念であり、「単に疾病がない状態だけでなく、性に関するあらゆる事柄において、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態であること」と定義されています。女性や男性が自らの身体を理解し、望むタイミングで妊娠・出産を選び、安全で満足のいく性生活を営むための権利と健康を含む考え方です。
この概念には、性感染症(STI)の予防、避妊の選択、不妊治療へのアクセス、妊娠中や出産時の安全確保といった医療的な側面だけでなく、セクシュアル・ハラスメントや性暴力からの自由を守る社会的・法的視点も含まれています。また、リプロダクティブ・ヘルスは「ライツ(権利)」の要素とも深く結びついており、誰もが性や生殖に関する決定を自ら行えることを目指します。
リプロダクティブ・ヘルスの概念
リプロダクティブ・ヘルスの概念は、1994年に開催された国際人口・開発会議(カイロ会議)で初めて国際的に認められ、その重要性が大きく転換しました。それまでの人口政策中心の視点から、「リプロダクティブ・ヘルス」は一人ひとりの健康や人権、特に女性のエンパワーメントを軸に据えた画期的な方向転換となりました。会議では、避妊や妊娠出産の自己決定権、不妊治療の権利、安全な出産環境の確保などが人権として強調されました。
国連が掲げるSDGs(持続可能な開発目標)でもリプロダクティブ・ヘルスは中核的なテーマとなっています。目標3「すべての人に健康と福祉を」、目標5「ジェンダー平等を実現しよう」にあるように、性や生殖に関する健康を守ることが、社会全体の幸福と平等の実現に欠かせません。
リプロダクティブ・ヘルスの対象
リプロダクティブ・ヘルスの対象は、単純に妊婦や出産に関係している女性だけではありません。男性女性問わずすべてのひとが対象となります。
男性も対象に含まれている理由としては、リプロダクティブ・ヘルスの中心の課題として、コンドームの使い方であったり安全で心配をしなくて良い性的な関係を持てることなども含まれているからです。
基本的には、女性が自分の意思で妊娠する時期や子どもの人数を決められることや、避妊方法の知識を身に着けるといったことも大切になります。
リプロダクティブ・ヘルスとライツの違い
リプロダクティブ・ヘルスは、「性と生殖に関する健康」そのものを指し、心身ともに良好で、望むときに安全に妊娠・出産・性生活を営める状態を意味します。一方で、リプロダクティブ・ライツは、その健康な状態を自らの意思で実現するための「権利」を示します。
リプロダクティブ・ライツの4つの要素
リプロダクティブ・ヘルスが『状態』であるのに対し、リプロダクティブ・ライツはその『実現手段』であり、自己決定権や選択の自由を保障するという考え方です。
リプロダクティブ・ライツの基本となる4つの要素は次の通りです。
- 女性が自らの妊孕性(妊娠する能力)をコントロールできること:
自分で避妊や妊活のタイミングを選び、妊娠の有無をコントロールする権利です。これは、キャリア形成や人生設計を主体的に行うための重要な要素です。 - すべての女性が安全な妊娠と出産を享受できること:
医療体制が整い、必要な支援を受けながら安全に出産できる環境を保障することを意味します。母体死亡率の低下や支援制度の充実が求められます。 - すべての新生児が健全な小児期を過ごせること:
出生後の医療・栄養・育児支援を受け、心身ともに健全に成長できる環境を整えることです。子どもの福祉と生涯の健康を守る基盤となります。 - 性感染症の危険なく、性的な関係を持てること:
感染予防や正しい性教育を通じて、安全で尊重し合える性的関係を築けることです。暴力や強制のない性の自由と同意が前提とされます。
リプロダクティブ・ヘルスとリプロダクティブ・ライツは、単なる健康や権利の枠を超え、人が自らの身体や人生を主体的に選択できる社会の基盤となります。そのため性や生殖に関する正しい知識と支援体制、そして尊厳が守られる環境づくりを通じて、すべての人が安心して生きられる社会の実現が求められています。
日本と世界のリプロダクティブ・ヘルスの現状
リプロダクティブ・ヘルスをめぐる状況は、国や地域によって大きく異なります。性教育の浸透度や医療制度、社会の意識にも差があります。日本と世界ではそれぞれどのような現状や課題があるのでしょうか。
世界におけるリプロダクティブ・ヘルスの実態
世界では、リプロダクティブ・ヘルスに関する格差が依然として深刻です。特に開発途上国では、妊産婦死亡率の高さが大きな課題となっています。医療施設へのアクセス不足や助産師の不足により、多くの女性が出産時に命を落としています。また、若年層の予期せぬ妊娠も社会問題であり、教育や避妊の知識が不十分なまま性的関係を持つことで、教育機会や将来の選択肢を奪われるケースが少なくありません。さらに、HIV/AIDSをはじめとする性感染症の蔓延も、適切な性教育や医療支援が届かない地域では深刻化しています。
一方で、先進国においても、性教育の水準や内容には国ごとの差があります。教育不足からなる避妊や性的同意に対する意識の低さは、健康リスクを高める要因となります。また、リプロダクティブ・ライツの実現に反して、性暴力被害やハラスメントの問題も根強く残っています。
日本におけるリプロダクティブ・ヘルスの実態
日本におけるリプロダクティブ・ヘルスの課題は、多方面にわたります。まず、避妊普及率の低さが顕著であり、特に経口避妊薬(ピル)の使用率は他の先進国と比べて極めて低水準です。その背景には、避妊に関する知識不足や社会的偏見、医療機関での入手のしにくさなどが影響しています。また、体系的な性教育の遅れも深刻で、若者が正しい知識を学ぶ機会が限られているため、望まない妊娠や中絶といった問題が依然として発生しています。
さらに、不妊治療へのアクセスや経済的負担も大きな課題です。近年は保険適用の拡大が進んでいるものの、治療の長期化や心理的ストレスなど、サポート体制はまだ十分とはいえません。また、性や生殖に関する話題がタブー視される傾向が強く、オープンに議論しにくい日本独特の文化的土壌も影響しているでしょう。ジェンダー規範に基づく固定観念も根強く、性教育の充実や医療情報へのアクセスを阻む一因となっています。
なぜリプロダクティブ・ヘルスが重要なのか
リプロダクティブ・ヘルスは単なる医療の問題ではなく、健康や自己決定権、ジェンダー平等など、すべての人の人生と権利に関わる重要なテーマです。ここからは、その重要性について、様々な視点から考えていきます。
すべての人の健康と自己決定権を守るため
リプロダクティブ・ヘルスは、すべての人が自分の身体や生き方を自ら選択できる「自己決定権」を支える健康の基盤です。避妊や妊娠、出産に関する選択を自ら決められることは、単に医療の問題ではなく、人権に関わる重要なテーマです。適切な避妊手段の利用や性感染症の予防、性教育を通じて、自分の身体を守り、健康な生活を送る力を養うことができます。
さらに、誰もが平等に医療へアクセスできる環境づくりも欠かせません。地域や経済状況、性別によって必要な医療を受けられない現状は、自己決定の自由を奪うことにつながります。リプロダクティブ・ヘルスの考え方は、性別や年齢を問わず、自分の身体と人生を尊重し、安心して生きられる社会を目指すものです。
安全で満足のいく性生活と家族計画を実現するため
リプロダクティブ・ヘルスが目指すのは、誰もが性や家族のことを安心して考え、自分らしい選択をできる社会です。避妊や中絶、妊娠・出産が安全に行えるということは、個人の健康を守るだけでなく、自分の人生を主体的に描くために欠かせません。
性教育の充実はリプロダクティブ・ヘルスを支える土台です。年齢や立場に応じた性教育を受けることで、身体や性の多様性を理解し、相手を尊重した関係を築くことができます。カップルが家族計画を自由に話し合い、社会的・経済的に支えられる環境を整えることは、幸福で持続可能な社会の実現にも直結します。
ジェンダー平等と女性のエンパワーメントを推進するため
リプロダクティブ・ヘルスは、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントを実現する大切な基盤です。性や生殖に関する健康と権利が保障されることで、女性は自らの身体や人生に関する選択を自由に行えるようになります。妊娠や出産を理由に教育やキャリアを諦める必要がなくなれば、女性の社会進出や自己実現の機会が大きく広がります。また、男女問わず、性別に関係なく健康や生き方を選べる社会は、相互理解やパートナーシップの向上にもつながります。
リプロダクティブ・ライツを保障することで、性暴力や差別、ハラスメントから個人を守るための社会的体制も整備されます。リプロダクティブ・ヘルスの普及は、単なる医療問題を超え、社会全体の意識改革と平等社会の実現を後押しする重要な柱と言えるのです。
リプロダクティブ・ヘルスの問題点と課題
リプロダクティブ・ヘルスを取り巻く課題の背景には、法制度の遅れや情報格差、そして根強いジェンダー意識の問題があります。こうした社会的要因が、個人の選択や健康にどのような影響を与えているのでしょうか。
法制度・政策の課題
日本のリプロダクティブ・ヘルスに関する法制度は、依然として多くの制約と課題を抱えています。特に、母体保護法では人工妊娠中絶を行う際に「配偶者の同意」が必要とされており、女性が自らの意思だけで中絶を選択することはできません。この規定は明治期から残る家父長的制度の名残といわれ、女性の自己決定権を制限しているとして国連の女性差別撤廃委員会(CEDAW)からも繰り返し是正を勧告されています。DV被害者や事実婚のケースでは運用上の例外が認められているものの、多くの現場では依然として配偶者同意が求められ、望まない妊娠の継続を強いられる女性もいます。さらに、中絶費用は全額自己負担であり、経済的にも大きな負担が伴います。
また、不妊治療に関しては2022年から一部治療が保険適用になりましたが、対象は限られており、体外受精や顕微授精では年齢制限(40歳未満で最大6回、43歳未満で最大3回)や回数制限が設けられています。治療を続けたい人や高齢出産を望む人にとっては依然として経済的・制度的な壁が存在します。こうした法制度や政策の不備は、女性の身体的自由や精神的健康に影響を与え、リプロダクティブ・ヘルスの実現を妨げる要因となっています。
医療アクセス・情報の格差
日本では、リプロダクティブ・ヘルスに関する医療や情報のアクセスに地域・経済格差が存在します。特に地方では医療機関の偏在が顕著で、産婦人科や不妊治療専門医が限られているため、必要な医療を受けるために長距離移動を強いられるケースもあります。また、経済的な理由から避妊具や不妊治療、中絶手術を受けられない人も少なくありません。
医療保険でカバーされる範囲が限られていることも、格差を広げている原因のひとつです。たとえば、保険で対象外となる治療が多いと、経済的に余裕のある人しか受けられない医療も出てきます。
さらに、正確な性に関する情報へのアクセスにも差が見られます。若年層や低所得者層の間では、十分な性教育が受けられていなかったり、性に関する誤情報がSNSやインターネット上で拡散している現状も大きな課題です。
社会的偏見やジェンダーギャップ
日本社会では、性に関する話題がいまだにタブー視される傾向が強く、自分の身体や性に関する悩みをオープンに相談しにくい空気があります。結果として相談先を見つけられずに孤立する人が少なくありません。また、性暴力の被害者が声を上げにくいのも社会的偏見が関係しています。「被害に遭った側にも非がある」といった誤った見方や、被害を申告すると職場・学校で不利になるという恐れから、沈黙を選ばざるを得ないケースが多いのが実情です。
また、男性がリプロダクティブ・ヘルスに関心を持ちにくい風潮もあります。「性や生殖の問題は女性の領域」という固定観念が根強く、男性自身の性機能障害や男性不妊といった健康問題が軽視されがちです。リプロダクティブ・ヘルスは本来、性別を問わず全員に関わるテーマであり、男性も健康面・心理面でサポートを受けられる社会づくりが今後の課題といえます。
リプロダクティブ・ヘルスの効果的な対策と最新の取り組み
リプロダクティブ・ヘルスの課題を解決するためには、教育・医療・制度の連携が欠かせません。近年は、国内外で新しい取り組みや政策提言も進んでいます。ここでは、その効果的な対策と最新の動きを見ていきましょう。
性教育や啓発活動の強化
リプロダクティブ・ヘルスを支えるためには、包括的な性教育(包括的セクシュアリティ教育)の導入が欠かせません。これは単に生殖機能を教える教育ではなく、性に関する正しい知識や人権意識を育てる教育として注目されています。国連や日本弁護士連合会も、性感染症や望まない妊娠の防止、性暴力の予防を目的に「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」に沿ったカリキュラムを導入するよう日本政府に勧告しています。
具体的な内容としては、避妊や性感染症の予防だけでなく、「同意(コンセント)」の理解、性暴力防止、多様な性のあり方の尊重、ボディイメージや自己肯定感の育成などを含みます。若者が早い段階から性と生き方に関する正しい情報を学ぶことで、自分や他者の尊厳を尊重する態度を身につけ、リスク回避能力を育むことができます。
法制度・医療体制の改善事例
近年、日本ではリプロダクティブ・ヘルスの推進に向けた医療体制・制度改善が進んでいます。2025年10月、厚生労働省は緊急避妊薬「ノルレボ」を薬局で販売できるスイッチOTC医薬品として正式に承認しました。これにより、医師の処方箋がなくても薬剤師の対面指導のもと購入可能となり、性的暴力や避妊失敗などによる望まない妊娠を防ぐ環境が整いつつあります。
同時に、低用量ピルの普及促進も進行中で、健康保険適用検討や医師会・企業によるオンライン処方体制の拡充など、女性の自己決定権を支援する動きが見られます。また、不妊治療への公的助成制度も拡充され、2025年度からは所得制限の緩和や保険外治療への補助が一部認められるなど、より包括的な支援体制が整備されています。
海外では、スウェーデンやオランダなどで包括的性教育の義務化や中絶の自由な選択権が保障されており、日本もこれらの国々のように「生殖に関する健康と権利(SRHR)」を統合的に支える政策設計が求められています。
テクノロジーや企業の新たなサポート
リプロダクティブ・ヘルス支援の分野では、テクノロジーの発展が医療や情報アクセスの不均衡を大きく改善しています。月経周期管理アプリは、生理日・排卵日の予測や体調変化の記録だけでなく、病院とのデータ連携やパートナーとの共有ができ、ヘルスリテラシーを高める手助けをしています。さらに、ウェアラブルデバイスは体温のリズムから排卵期やホルモンバランスを可視化し、オンライン診療やチャットで医師に相談できる新しい支援形態を提供しています。
企業においても、フェムテックや健康経営の一環として従業員のリプロダクティブ・ヘルスを支援する動きが広がっています。福利厚生サービス「ファミワン」では、専門家によるオンライン相談や性教育研修の提供を通じて、従業員の心身の健康維持とキャリア継続をサポートしています。また、多くの企業で生理休暇・不妊治療休暇の導入が進み、男性の育児休暇取得支援やパートナーシップ研修も拡充中です。こうした取り組みは、生産性の向上と多様な働き方の実現に直結し、企業の社会的責任(CSR)やダイバーシティ推進にも重要な役割を果たしています。
リプロダクティブ・ヘルスの支援策
リプロダクティブ・ヘルスを守るためには、行政や医療、地域団体が連携した支援体制が不可欠です。妊娠・出産・不妊治療など、人生のあらゆる段階で安心して相談・支援を受けられる仕組みが広がり始めています。
公的支援・助成制度
日本では、国や地方自治体がリプロダクティブ・ヘルスの向上に向けたさまざまな支援制度を整備しています。代表的なのが不妊治療や特定不妊治療(体外受精・顕微授精)への助成制度です。2022年の保険適用に続き、2025年現在では所得制限や回数制限が緩和され、治療を受ける夫婦や個人の経済的負担が軽減されています。また、地方自治体では独自に初診料や薬剤費の補助、カウンセリング支援を行うところも増えています。
性感染症検査やがん検診に対する公費助成も広がっています。多くの自治体では、HIV・梅毒などの性感染症検査を無料で受けられる体制を整え、子宮頸がん検診・乳がん検診についても一定年齢層を対象に無償または一部助成を実施しています。これにより、予防医療を早期に受けられる環境を支え、女性の健康維持に寄与しています。
民間団体・NGOの取り組み
日本各地では、民間団体やNGOもリプロダクティブ・ヘルスを支える重要な役割を果たしています。代表的な団体であるJOICFP(公益財団法人ジョイセフ)は、「性と生殖に関する健康と権利(SRHR)」をテーマに、国内外で包括的性教育や避妊・妊産婦支援活動を展開しています。特に、若年層への性教育教材の提供や、緊急避妊薬の普及を推進する啓発活動、妊娠・出産・中絶に関する相談支援をオンラインで受けられるサービスを行っています。
また、「国際家族計画連盟(IPPF)」や「SRHR Japan」なども、国際的なネットワークを通じてリプロダクティブ・ライツの実現を目指し、政策提言や調査活動を実施しています。一方で、国内ではNPO法人ピルコンなどが、性暴力防止教育の普及や、学生・社会人世代へのワークショップを通じて「性の安全」と「自己決定」を支援しています。
こうしたNGOや市民団体の活動は、公的制度ではカバーしきれない分野を補っており、誰もが安心して自身の健康や人生を選べる社会づくりに大きく貢献しています。
相談窓口・サポートサービス
国や自治体では、妊娠や不妊、避妊、中絶、性暴力被害などに関する専門相談窓口を全国的に整備しています。たとえば、「女性健康支援センター」や「いのちと暮らしの相談窓口」、「妊娠SOS」では、看護師・助産師・心理士などの専門家が匿名・無料で対応しています。また、若年層を対象とした「ユースクリニック」や「ユースヘルスケアアクション」なども拡大中で、性教育やメンタルケア、医療相談を一体的に提供しています。
NGOのジョイセフ(JOICFP)や「Youth Terrace」などのオンラインプラットフォームでは、チャットやメールで気軽に相談でき、性や生殖に関する正しい知識や医療機関の案内を行っています。地方自治体ごとに運営される「思春期・健康相談」もあり、性感染症や生理、不妊など幅広い分野に対応しています。
こうした窓口やサービスの拡充により、多くの人が性や健康の悩みを一人で抱え込まず、専門的な支援や正しい情報につながることができます。
日本の自治体や団体のリプロダクティブ・ヘルスの具体的な取り組み事例
日本の自治体や団体のリプロダクティブ・ヘルスの具体的な取り組み事例を見ていきましょう。
世田谷区
世田谷区では、思春期世代に向けたリプロダクティブ・ヘルスについての知識を深めてもらうための取り組みを、行っています。
主に中学生に対して自分の身体であったり、性的な悩みを抱えることなく性や生殖に関する正しい知識を持って、自分自身の生涯にわたって健康を意識できる環境を作れることを、目標としています。
具体的な取り組みとして、希望する中学校に対して「いのちと性の健康教育」を行っています。性感染症予防教育をメインとして、世田谷保健所から助産師会に委託して実施しています。
参考:世田谷区
彦根市
彦根市では、彦根市男女共同参画計画「ひこねかがやきプラン3」を掲げていて、これは以下の目標をさします。
基本目標3「尊重し認め合う男女共同参画」
基本施策3「男女の心と身体の健康に気づくための取組」
上記の中に、「リプロダクティブ・ヘルス/ライツの普及」も含まれています。誰もが健康でいきいき暮らすために、男女の身体的性差があることを理解して、お互いに思いやりを持って接することも非常に大切です。
リプロダクティブ・ヘルス/ライツの概念を周知して理解してもらい、「自分のからだは自分で守ること」から実践していくことを推奨しています。
参考:彦根市
江南市
江南市では、令和4年度から進めている「第3次こうなん男女共同参画プラン」の中にリプロダクティブ・ヘルスに関する取り組みが含まれています。
基本目標Ⅳ だれもが安心して心豊かに暮らせる家庭・社会づくり
視点2 男女共同参画推進のための社会的支援
上記を目標としています。妊娠期~子育て期の支援として保健センターで、妊婦さんが安心して過ごせるようサポートを行っています。
また希望があった中学校に対しても、具体的な取り組みとして思春期教室を開催しています。思春期の頃から正しい性に関する知識を身に着けてもらうことを目的としています。
参考:江南市
LALA+ Support for SRHR
LALA+ Support for SRHRは、助産師が中心となって他の多職種と連携をとりつつ、セクシュアル・リプロダクティブヘルスをサポートしている団体です。
女性のライフステージに応じた心身の健康やライフへの支援と、女性や女性の大切なパートナーやご家族の健康の維持・増進に努めることを目的としている
上記の目的のために、育児や健康の相談に乗ったり、様々な分野の専門家によるセミナーを開催したり、女性にとって必要な情報を発信したりしています。
NPO法人 にじの絲
NPO法人 にじの絲では、「性といのちのこと、もっと知ろう!話そう!」をテーマにリプロダクティブ・ヘルスが守られる社会を目指している団体です。
そのために性といのち、子どもや人権に関する講演や、展示などを行っています。情報交換ができる交流会であったり、意見交換ができる座談会といった場も設けています。
性を正しく学べない子どもを増やさないために、かるたや絵本など性について学べるツールの開発も行っています。
参考:NPO法人 にじの絲
リプロダクティブ・ヘルスのよくある質問
リプロダクティブ・ヘルスへの関心が高まるなか、実際にどんな行動をすればよいのか、悩む方も多いでしょう。ここでは、よくある質問に具体的に答えていきます。
Q1. パートナーとリプロダクティブ・ヘルスについて話し合うコツは?
パートナーと性や将来の健康について話すときは、「リプロダクティブ・ヘルス」という専門的な言葉を使うよりも、「将来の体のことを一緒に考えたい」「お互いの健康について共有したい」など、日常的な表現から切り出すのが自然です。大切なのは、相手に安心感を与え、話の主旨を押し付けるのではなく、対話として意見や気持ちを共有する姿勢です。
Q2. 男性がリプロダクティブ・ヘルスでできることは?
男性にとっても、性や生殖に関する健康を理解し、共に支え合う姿勢は欠かせません。パートナーの生理や月経痛、不妊治療、妊娠・出産に対する知識を持つことで、体調の変化や心理的負担を理解しやすくなり、協力し合える関係を築けます。特に不妊治療では、治療の主体が女性に偏りがちですが、男性自身の健康検査や生活習慣の見直しも重要です。
Q3. 職場や学校で配慮を求めるにはどうすればいい?
職場や学校で体調や治療に配慮してもらうためには、まず就業規則や校内規定を確認し、利用できる制度を把握することが大切です。多くの職場では生理休暇、不妊治療休暇、つわりや体調不良時の時差出勤制度が設けられており、学校でも養護教諭やスクールカウンセラーへの相談が可能です。体調がつらい時や通院が必要な場合、人事担当者や上司、学校の先生に早めに相談することで、勤務時間や出席扱いなど柔軟に調整できるケースもあります。
Q4. 海外と日本の制度や意識の違いは?
海外、特に欧米諸国では、性や生殖に関する話題がオープンに議論され、包括的性教育が幼少期から義務教育の一環として行われています。また、緊急避妊薬(アフターピル)のOTC化が進んでおり、薬局で誰でも購入できる国が多く、中絶も安全かつ合法的に行える環境が整っています。
一方、日本では性に関する教育や会話が依然として控えめで、社会的にも話題にしづらい雰囲気があります。緊急避妊薬の市販化がようやく始まり、不妊治療や中絶に関する制度面も海外に比べると保守的な傾向です。
Q5. 情報収集で信頼できるメディアや団体は?
国内では「厚生労働省」や「国立女性教育会館(NWEC)」、「日本産科婦人科学会」などが、妊娠・避妊・不妊治療・検診に関する正確なデータや最新方針を公開しています。また、国際的な視野で学ぶなら「世界保健機関(WHO)」や「国際家族計画連盟(IPPF)」の公式サイトも有益です。
SNSやネットの個人投稿は誤情報が混在しやすいため、専門家監修のサイトや実績ある団体の情報に基づいて判断することが安全です。
まとめ
リプロダクティブ・ヘルスは、すべての人が心身の健康を保ちながら「自分のからだと人生をどう生きるか」を自由に選ぶための基本的な権利です。しかし日本では、性教育の遅れや男女格差、避妊法の少なさなど、依然として多くの課題が残っています。
大切なのは、正しい知識を学び、信頼できる医療機関や支援団体へアクセスしやすい環境を活用すること、そしてパートナーや周囲とオープンに話せる関係を築くことです。リプロダクティブ・ヘルスを「自分ごと」として考えることが、より健康で自分らしい未来へつながる第一歩となります。
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS