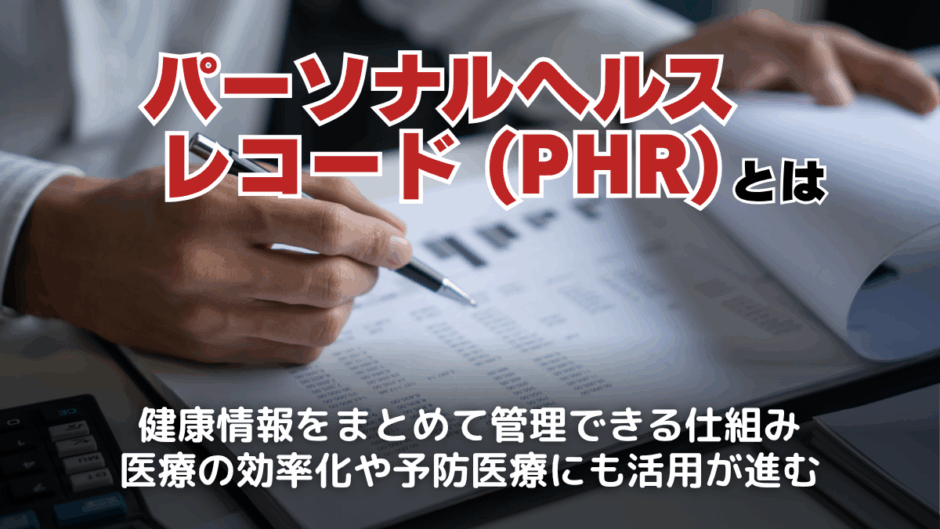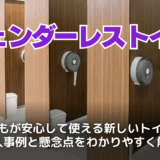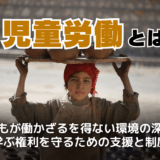パーソナルヘルスレコード(PHR)は、個人が自分の健康情報を一元管理できる新しい仕組みとして注目を集めています。病院ごとにバラバラだった診療記録や検査結果、日々の健康データをまとめて管理できることで、より精度の高い健康管理や医療の効率化が実現します。
さらに、マイナポータルなどとの連携により、医療機関や家族と情報共有することも可能です。本記事では、パーソナルヘルスレコードとは何か、その種類やメリット・デメリット、導入の目的や今後の展望まで、わかりやすく解説します。
パーソナルヘルスレコード(PHR)とは
パーソナルヘルスレコード(Personal Health Record)とは、本人が自分の健康・医療・介護・生活習慣などに関する情報を一つにまとめて管理し、いつでも確認・活用できる仕組みを指します。これは医療機関や行政が管理する「電子カルテ」や「電子健康記録(EHR)」とは異なり、情報の主体が“本人”である点が最大の特徴です。自分自身でデータを収集・保存・参照・開示することができ、医療機関や家族と共有する際にも本人の意思で操作できます。
近年では、健康診断の結果、服薬履歴、ワクチン接種歴、血圧・体重・歩数などのライフログをデジタルデータとして一元化できるようになっています。これにより、従来のように紙の健康手帳や母子手帳を探す手間が省け、スマートフォンやパソコンから簡単に閲覧・更新が可能です。また、マイナポータルや健康アプリとの連携により、病院・自治体・企業間のデータ共有もスムーズに行えるようになっています。
パーソナルヘルスレコードは、個人が自分の健康状態を正確に把握し、日常の生活習慣改善や予防医療に役立てるための基盤として注目されています。医療のデジタル化が進む中で、「自分の健康情報を自分で管理する」時代の中心的な仕組みといえるでしょう。
マイナポータルとパーソナルヘルスレコードの関係
マイナポータルは、政府が運営する公的オンラインサービスで、国民一人ひとりが自分の行政情報を安全に確認・利用できる仕組みです。マイナポータルを通じて健康診断結果、薬剤情報、電子処方箋の履歴、特定健診・予防接種の情報などを閲覧可能です。これらのデータは、医療機関や薬局での受診履歴と連携しており、本人が過去の診療内容や服薬状況を簡単に把握できるようになっています。
また、マイナポータルとパーソナルヘルスレコードが連携することで、行政機関が保有する医療情報と、個人が日常的に取得する健康データ(体重・血圧・歩数など)を一元的に管理することが可能になります。この連携によって、本人は自分の健康状態を総合的に確認でき、必要に応じて医療機関や薬局とデータを共有することも容易になります。
マイナポータルは主に公的な医療・行政情報の閲覧・取得を目的としていますが、民間のパーソナルヘルスレコードサービスは日常の健康管理や生活習慣の改善に焦点を当てている点が異なります。
パーソナルヘルスレコードのデータの種類
パーソナルヘルスレコードに登録される情報は、大きく「個人で収集するデータ」と「医療機関で管理するデータ」の2種類に分類されます。
| 項目 | 個人で収集するデータ | 医療機関で管理するデータ |
|---|---|---|
| 主な内容 | 体重、血圧、体温、歩数、睡眠時間、食事内容、ストレス指標、スマートウォッチ・アプリからのバイタルデータ | 診療情報(診察記録、病名)、検査結果、処方履歴、ワクチン接種記録、入院・手術歴、医療費情報 |
| 収集・管理主体 | 利用者本人、ウェアラブル端末、健康管理アプリ | 病院、クリニック、薬局など医療機関 |
| 利用目的・特徴 | 日常生活の健康状態把握、生活習慣改善、疾病予防、自己管理の指標 | 医療判断の補助、診療履歴の記録、複数医療機関での情報統合、必要時の共有・参照 |
これらを統合的に管理することで、個人が自分の健康状態をより正確に把握できるようになります。
個人で収集するデータ
まず、個人で収集するデータとは、日常生活の中で自分自身が取得・記録する情報を指します。
たとえば、体重・血圧・体温・歩数・睡眠時間・食事内容などの生活習慣データ、またはスマートウォッチや健康管理アプリから得られるバイタル情報などです。これらのデータは、生活習慣の改善や疾病予防のための重要な指標となり、パーソナルヘルスレコードに自動連携させることで、継続的な健康モニタリングが可能になります。
医療機関で管理するデータ
一方、医療機関で管理するデータには、診療情報、検査結果、処方履歴、ワクチン接種記録、入院・手術歴などが含まれます。
従来は各病院やクリニックが独自に保管していたため、複数の医療機関にかかっている場合、情報が分断される問題がありました。パーソナルヘルスレコードを活用することで、これらの医療情報を一元的に集約し、患者自身が必要なときに閲覧・共有できるようになります。
パーソナルヘルスレコード導入の目的
パーソナルヘルスレコード(PHR)の導入は、単なるデータ管理の効率化にとどまりません。ここでは、PHR導入によって期待される社会的・医療的な目的について解説します。
患者中心医療の推進
パーソナルヘルスレコード(PHR)の導入は、従来の「医療機関が主導する医療」から「患者中心の医療」への転換を促す大きな一歩です。患者自身が自分の医療情報をいつでも確認できるようになることで、治療内容や経過を正確に把握し、自分の健康状態を主体的に理解・管理できるようになります。
また、セカンドオピニオンを求める際や治療法を選択する場面では、PHRを活用することで、過去の検査結果や投薬履歴などを他の医師にスムーズに提示でき、より的確な診断や治療方針の検討が可能になります。さらに、医師との情報共有が円滑になることで、診察時の説明や相談の内容がより具体的かつ相互理解の深いものとなり、結果として治療の納得度・満足度の向上にもつながります。
自治体と企業による健康データ活用と医療連携
パーソナルヘルスレコード(PHR)は、個人の健康管理にとどまらず、自治体や企業が健康データを活用する仕組みとしても注目されています。企業では、従業員の健康診断結果や日々の健康情報をPHRで集約・分析し、健康経営の推進や職場の健康増進施策の立案に活かしています。これにより、従業員の生活習慣改善やメンタルヘルス対策を科学的根拠に基づいて実施でき、生産性の向上や医療費の削減にもつながります。
また、自治体では住民の健康データを活用し、予防接種履歴や健診情報を一元管理することで、地域全体の健康づくりを推進しています。こうした取り組みは、重症化予防や医療費の抑制にも寄与し、持続可能な地域医療体制の構築を後押ししています。
さらに、PHRを活用することで複数の医療機関や行政、福祉施設とのデータ連携が容易になり、地域包括ケアや災害時の情報共有にも大きな効果を発揮します。個人・企業・自治体が連携することで、社会全体で健康を支える新しい仕組みが形成されつつあります。
医療資源の最適化・効率化
パーソナルヘルスレコード(PHR)の導入は、医療資源の最適化と効率化を実現する大きな鍵となります。複数の医療機関で同じ検査や診療を繰り返すケースは少なくありませんが、PHRによって患者の検査結果や処方情報が一元管理されることで、重複検査や不要な投薬を防止し、医療費の無駄を削減できます。これは、増大し続ける日本の医療費問題に対して、持続可能な医療体制を築くための重要な施策といえます。
さらに、患者の健康情報が一元化されることで、症状や既往歴に応じて適切な医療機関や専門医に迅速に繋げることが可能になります。医療機関側も必要な情報を即座に共有できるため、治療までの時間短縮や医療スタッフの業務負担軽減にも寄与します。結果として、限られた医療資源を効果的に配分し、質の高い医療を安定的に提供できる環境が整うのです。
パーソナルヘルスレコード(PHR)のメリット
パーソナルヘルスレコードを理解するうえで、まずはその具体的なメリットを確認してみましょう。
健康情報の一元管理で自己管理が容易に
パーソナルヘルスレコードを活用することで、健康診断結果や通院履歴、服薬情報などの医療データを一括で管理できるようになります。これにより、自身の健康状態を時系列で把握しやすくなり、生活習慣の改善や病気の早期発見・予防といった自己管理を効率的に行える点が大きなメリットです。
従来のように、病院ごとにバラバラに保管されていた情報を探す必要がなく、スマートフォンやパソコンからいつでも閲覧・確認が可能です。かかりつけ医との情報共有がスムーズになることも利点の一つです。医師が患者の過去の経過や服薬状況を正確に把握できるため、よりパーソナルな健康指導や治療計画の立案が可能となります。
医療機関や家族との情報共有が迅速・正確に
パーソナルヘルスレコード(PHR)を導入することで、医療機関や家族との情報共有が格段にスムーズになります。たとえば転院時、従来は紹介状や検査結果のコピーを手渡しでやり取りする必要がありましたが、PHRを利用すればデジタル上で医療情報を安全かつ迅速に共有できます。転院先の医師は、患者の診療履歴や検査データを即座に確認できるため、重複検査の回避や治療の継続性の確保に大きく貢献します。
また、救急搬送時に本人が意識を失っている場合でも、救急隊や医療スタッフがPHRにアクセスすることで、既往歴・服薬中の薬・アレルギー情報などの重要データを瞬時に確認できます。これにより、誤投薬や遅延治療のリスクを減らし、迅速で適切な救命対応が可能となります。
さらに、家族共有機能を備えたPHRシステムも多く、離れて暮らす家族が利用者の健康状態をリアルタイムで把握できます。高齢の親の見守りや、慢性疾患を持つ家族の健康管理にも役立ち、家族全体で健康を支える仕組みとしても注目されています。
パーソナルヘルスレコードのデメリット
パーソナルヘルスレコードは多くの利点がある一方で、導入や運用においていくつかの課題も存在します。利用前に知っておきたいデメリットを詳しく見ていきましょう。
情報の誤入力・不正確さによる医療リスク
パーソナルヘルスレコード(PHR)は、個人が自分の健康情報を管理できる便利な仕組みですが、誤った情報入力や不正確なデータ登録は深刻な医療リスクを引き起こす可能性があります。特に複数の医療機関を受診している場合、情報の不整合が医療現場で混乱を招くケースも考えられます。
このようなリスクを避けるためには、利用者自身が定期的にパーソナルヘルスレコード(PHR)の内容を見直し、最新かつ正確な情報が反映されているかを確認することが欠かせません。また、診療の際には、PHRに記載された情報と実際の診断内容・処方内容が一致しているかを、医療スタッフと連携して確認することも大切です。
導入のための膨大なコスト負担
パーソナルヘルスレコード(PHR)の普及には、多くの利点がある一方で、導入や運用にかかるコスト負担が大きな課題となっています。医療機関側では、PHRシステムを導入するためのサーバー構築やセキュリティ強化、データ連携のためのシステム改修など、多額の初期投資と維持費が発生します。また、スタッフへの研修や運用ルールの整備など、人的コストも無視できません。
一方、利用者側にとっても、PHRを日常的に活用するためには、継続的な情報入力や記録管理が求められます。特にデジタルツールの扱いに不慣れな層にとっては、操作の複雑さや入力の手間が負担となり、モチベーションを維持することが難しい場合もあります。
さらに、PHRサービスによっては月額利用料やデータ保存料が発生するケースもあり、これらの費用負担が普及を妨げる要因となっています。コスト面でのハードルを下げ、誰もが使いやすい仕組みを整えることが、今後の普及促進に向けた重要な課題といえるでしょう。
パーソナルヘルスレコードの現状
パーソナルヘルスレコード(PHR)は、世界的に注目が高まる分野の一つです。PHRの世界と日本における現状をデータを交えて見ていきましょう。
世界のパーソナルヘルスレコードのソフトウェア市場規模
世界におけるパーソナルヘルスレコード(PHR)のソフトウェア市場は、2024年に1,015万米ドルと推定され、2029年までに1,614万米ドルへ拡大すると予測されています。市場の成長を支えているのは、医療データのデジタル化や、オンラインでの情報共有の普及に伴う合理化された医療情報管理の需要の高まりです。
さらに、各国で進む患者中心のパーソナルケアを推進する取り組みや、クラウド技術を活用したオンラインデータ統合の拡充も、市場拡大の大きな要因となっています。特に北米や欧州では、電子カルテや健康管理アプリとの連携が進み、個人が自身の健康データを積極的に活用する動きが広がっています。こうした流れは、PHRが単なる記録ツールではなく、世界的な医療DXの中核的プラットフォームとして位置づけられていることを示しています。
参考:PHR(Personal Health Record)ソフトウェア市場| 業界シェア 市場規模 成長性 2024 – 2029年
日本のパーソナルヘルスレコードのソフトウェア市場規模
日本のパーソナルヘルスレコード(PHR)市場は急速に成長しています。2023年の市場規模は3,577億円に達し、2030年には9,975億円へ拡大すると推定されています。これは、PHRを中心とした医療データ管理や健康支援サービス産業が今後さらに発展する可能性を示しています。
成長の背景には、スマートフォンやクラウドを活用したデジタル技術の進化と普及があります。さらに、政府が推進する医療DX(デジタルトランスフォーメーション)政策や、国民の健康意識の高まり・健康寿命延伸へのニーズも市場拡大を後押ししています。これにより、個人の健康情報を活かした新しい医療・ヘルスケアサービスが次々と誕生しており、日本におけるPHRの普及は今後ますます加速していくと考えられます。
日本でのパーソナルヘルスレコードの認知度
日本では、パーソナルヘルスレコード(PHR)の名称や仕組みがまだ十分に浸透していません。2023年の調査では、「PHRという言葉を全く知らない」と回答した人が66.7%にのぼり、さらに「PHRアプリを知らない」と答えた人も56.6%に達しています。この結果からも、PHR普及の最大の障壁は認知度の低さであることが明らかです。
一方で、社会全体では健康意識が高まり、医療や健康情報の管理・共有への関心やニーズが拡大しています。特にコロナ禍以降、オンライン診療や健康アプリの利用が進み、デジタルで健康を支える仕組みへの理解が徐々に広がりつつあります。今後は、国や企業による情報発信や教育を通じて、PHRの価値を社会全体に伝えていくことが重要といえるでしょう。
参考:民間PHRサービス利用者へのアンケート調査結果等 資料3
パーソナルヘルスレコード普及への課題
続いて、パーソナルヘルスレコードを普及させるために現時点で課題となっているいくつかの問題点について説明していきます。
標準化・データ連携への壁
パーソナルヘルスレコード(PHR)の普及を妨げる大きな要因の一つが、データの標準化とシステム間連携の難しさです。現在、日本の医療機関ごとに使用している電子カルテの仕様やデータ形式が異なり、同一の患者であっても病院やクリニックをまたぐと情報の統一管理が困難です。そのため、PHRへの自動的な情報取り込みが進まず、手動入力が必要になるケースも多く見られます。
さらに、複数のPHRサービス間での連携が十分に確立されていないことも課題です。異なるサービスを併用すると、同じ情報を何度も登録する手間が生じ、利用者の負担が増加しています。こうした技術的・運用的な壁を乗り越えるためには、共通フォーマットの策定や、医療・行政・企業間でのデータ共有基盤の整備が求められます。
医療機関や利用者間の格差
パーソナルヘルスレコード(PHR)の普及においては、医療機関や利用者間の格差が大きな課題となっています。大病院では電子カルテやオンライン診療などのデジタル化が進んでおり、PHRとの連携体制も整いつつありますが、一方で中小クリニックや地方の医療機関では導入や運用が遅れているのが現状です。これにより、地域や施設ごとに情報共有のスムーズさに差が生じています。
また、若年層と高齢者の間にも利用格差が見られます。デジタル機器に慣れた世代はPHRアプリやオンラインサービスを積極的に活用する一方で、高齢者は操作への不安や理解不足から利用をためらう傾向があります。こうした格差が続くと、医療情報の活用度や健康管理の機会に差が生じ、結果的に健康格差の拡大を招く可能性があります。
セキュリティとプライバシー保護への懸念
パーソナルヘルスレコード(PHR)は、個人の健康や診療履歴といった極めて機微な情報を取り扱うため、強固なセキュリティ対策が欠かせません。データの暗号化やアクセス制御、多要素認証などの仕組みを導入し、第三者による不正アクセスを防ぐことが求められています。
しかし、プライバシー保護とデータ利活用の両立は常に難しい課題です。医療情報を共有・分析することで医療の質向上や効率化が期待される一方で、その過程でサイバー攻撃や情報漏洩のリスクが高まる現実もあります。万が一、PHRから情報が流出すれば、個人のプライバシー侵害にとどまらず、事業者や医療機関の社会的信用を失墜させる深刻な事態にも発展しかねません。
パーソナルヘルスレコード課題解決に向けた対策
パーソナルヘルスレコード(PHR)の普及には、技術面だけでなく運用や意識面にもさまざまな課題があります。データの標準化や連携体制の整備、医療機関や利用者の理解度の差、さらにはセキュリティ対策など、克服すべき壁は多岐にわたります。
データ連携の壁を突破する標準化の推進
パーソナルヘルスレコード(PHR)の普及に向けては、医療機関やPHRアプリ間でのデータ相互運用性を高める「標準化」の推進が欠かせません。現在、国際的にはFHIR(Fast Healthcare Interoperability Resources)という共通仕様が採用されており、これにより異なるシステム間でも健康・医療情報のやり取りがスムーズに行える環境が整いつつあります。
また、日本では厚生労働省主導のデータ標準化実証事業が進められており、全国的に共通プラットフォームを構築する取り組みが進行中です。さらに、異なるシステム同士でも情報を安全かつ自動で共有できるオープンAPIの開発と普及が進み、医療機関とPHRサービス間のシームレスな接続が実現しつつあります。
医療・利用者間の格差を解消する取り組み
パーソナルヘルスレコード(PHR)の普及を進めるうえで重要なのが、医療機関や利用者間の格差を解消する取り組みです。近年では、自治体が中心となって高齢者向けのデジタルリテラシー向上プログラムを実施しており、IT相談窓口やスマートフォン講習会を定期的に開催しています。これにより、操作に不安を抱える高齢者でもPHRや健康アプリを安心して利用できる環境が整いつつあります。
さらに、地方医療のアクセス改善策として、ウェアラブルデバイスやIoT機器を活用した健康モニタリング、遠隔診療(テレヘルス)などの導入も進んでいます。加えて、自治体主導で電子処方箋や医療・健康情報連携システム(PHR等)を構築し、病院・薬局・介護施設間の情報共有を効率化する動きも活発になっています。
セキュリティとプライバシー対策の強化
パーソナルヘルスレコード(PHR)では、個人の医療・健康情報という極めて重要なデータを扱うため、セキュリティとプライバシーの強化が最優先課題とされています。近年では、通信経路を保護するエンドツーエンド暗号化の導入や、ログイン時の多要素認証(MFA)、さらに職種や権限に応じてアクセス範囲を制限するロールベースアクセス制御(RBAC)など、技術的な安全対策が整備されています。
また、ビッグデータ解析やAIによる健康予測モデルの構築時には、個人を特定できないようにする差分プライバシーが適用され、匿名化技術の高度化が進んでいます。さらに、個人情報保護法やPHR取扱指針に基づき、データ利用ルールが明確化され、違反時には罰則を強化することで、事業者の遵守を徹底しています。こうした取り組みにより、PHRの安全性と信頼性が一層高められています。
パーソナルヘルスレコードの利用者・事業者向け支援
パーソナルヘルスレコード(PHR)の普及を妨げる課題を解決するには、国・自治体・企業・医療機関が連携して取り組むことが欠かせません。ここでは、PHRの課題解決に向けた具体的な対策や取り組みを紹介します。
パーソナルヘルスレコードの公的な支援
パーソナルヘルスレコード(PHR)の普及を加速させるため、国や自治体による公的支援が積極的に進められています。厚生労働省や総務省は、医療機関・自治体・企業間の連携を強化するために、PHRの標準化や普及を目的としたモデル事業や実証実験を全国で展開しています。
特に厚生労働省は、健康・医療・介護情報のデータ基盤整備を推進し、共通プラットフォームの構築やマイナポータルとの連携を支援。これにより、医療機関や住民が安全かつスムーズに情報を共有できる環境づくりが進んでいます。また、自治体レベルでも、地域医療連携システムを整備し、PHRの導入を後押しする補助金や支援プログラムが拡充されています。
民間の相談窓口・サポート体制
パーソナルヘルスレコード(PHR)や健康管理アプリでは、利用者が安心してサービスを活用できるように、電話・メール・チャットなど複数の相談窓口が設けられています。これらの窓口では、操作方法の案内や初期設定のサポート、データ連携の手順説明、さらにはログイントラブルやデータ不具合への対応まで、幅広いサポート体制が整っています。
相談時には、氏名・登録メールアドレス・利用端末やアプリのバージョン・発生している問題の詳細などをあらかじめ準備しておくと、やり取りがスムーズになります。これらの情報を正確に伝えることで、サポート担当者が状況を正しく把握し、迅速かつ的確な対応を受けることが可能です。
パーソナルヘルスレコード(PHR)とSDGsの関係
続いて、パーソナルヘルスレコード(PHR)とSDGsの繋がりについて解説していきます。
PHRが健康づくりを支える
PHRは、健康診断やワクチン履歴、服薬情報などを一つにまとめ、自分で管理できる仕組みです。日々の体調記録と合わせて自分の健康状態を把握しやすくなるため、病気の早期発見や生活改善につながります。「主体的に健康を守る」ことはSDGs目標3が目指す根幹のひとつです。PHRは、年齢に関係なく誰でも使える “自分専用の健康ノート” のようなもので、健康情報がまとまっていることにより、自分の体をより理解し、必要なときに適切な医療を受けやすくなります。
その結果、地域や家庭のちがいによって「健康の差」が生まれにくくなり、みんなが安心して暮らせる社会づくりにつながります。
医療の質と公平性を高める
PHRがあれば、病院を変えたり引っ越したりしても、これまでの検査結果や服薬の記録を新しい医師にすぐに見せられます。「初めての病院だから情報が伝わらない」という不安が減り、どこでも同じように質の高い医療を受けやすくなります。これにより、「情報がないために必要な医療が受けられない」という状況を避けられ、地域差や環境差による医療格差の縮小に寄与します。
また、医師が過去の正確なデータを把握できることで、診断の質が向上し、無駄な検査や重複処方を減らすことも可能です。情報の公平なアクセスと医療の効率化という点で、SDGs目標10「不平等をなくそう」に深く貢献します。
災害に強い社会づくりに貢献
災害や緊急時は、日常の医療記録が失われたり、医療機関の情報共有が難しくなったりします。PHRはクラウド上で健康情報を保管できるため、避難所や見知らぬ場所でも必要な医療情報にアクセス可能です。アレルギーや服薬履歴が迅速に分かれば、適切な処置を受けやすく、命を守る大きな助けになります。
これはSDGs目標11の「災害に強いまちづくり」に直結し、より安全でレジリエントな社会の実現に寄与します。
パーソナルヘルスレコードよくある質問
パーソナルヘルスレコード(PHR)に関して、多くの人が抱く疑問や不安にお答えします。
Q1. パーソナルヘルスレコードを導入する際の初期設定や登録方法は?
パーソナルヘルスレコード(PHR)の導入は、アプリやサービスの公式サイトからアカウントを作成し、本人確認を行うことから始まります。次に、マイナポータルや医療機関の電子カルテと連携設定を行い、健康診断結果や服薬履歴などのデータを自動取得できるようにします。スマートフォンやウェアラブル機器を利用して日常の健康データを記録することも可能です
初期設定が完了すれば、日々の健康状態を一元的に把握できる環境が整います。
Q2. 海外で受診した医療データもパーソナルヘルスレコードに登録できますか?
現状、国内のパーソナルヘルスレコード(PHR)サービスは、海外の医療機関との自動連携には対応していません。そのため、海外で受診した診療情報や検査結果を日本のPHRへ自動的に取り込むことは難しい状況です。海外での診療データを反映させたい場合は、検査結果や診断書を写真撮影してアップロードするか、手動で入力する方法が一般的です。
今後は、国際的な医療データ標準(FHIRなど)を活用した連携強化が期待されています。
Q3. パーソナルヘルスレコードのデータはどのようにバックアップ・復元されますか?
パーソナルヘルスレコード(PHR)のデータは、クラウド上に自動で保存される仕組みが一般的です。これにより、端末の紛失や故障が発生してもデータが消えるリスクを最小限に抑えられます。新しいスマートフォンやパソコンに切り替えた場合でも、登録したアカウントにログインするだけで簡単に復元が可能です。一部のサービスでは、定期的なバックアップ設定やエクスポート機能も備えており、より安心して利用できます。
Q4. パーソナルヘルスレコードの利用をやめたい場合、データはどうなりますか?
パーソナルヘルスレコード(PHR)の利用を停止する際は、サービス提供者によってデータの保管期間や削除ポリシーが異なります。そのため、事前に利用規約やプライバシーポリシーを確認することが重要です。一般的には、アカウントを削除すると登録した個人データも同時に完全に削除される仕組みが採用されています。ただし、一部のサービスでは一定期間バックアップを保持する場合もあるため、削除手続きの詳細を確認しておくと安心です。
Q5. パーソナルヘルスレコードを利用することで将来的にどのような新サービスが期待できますか?
AI技術の進歩により、パーソナルヘルスレコード(PHR)のデータを活用した個人最適化された健康アドバイスや病気のリスク予測が可能になると期待されています。さらに、医療機関と連携した遠隔医療の高度化や、生活習慣の改善を支援する予防医療プログラムの拡充も進む見込みです。これにより、利用者一人ひとりに合わせた、より効率的で質の高い医療サービスの提供が実現していくでしょう。
まとめ
パーソナルヘルスレコード(PHR)は、個人の健康情報を一元的に管理し、医療機関や家族と共有できる仕組みです。自分の健康データを把握することで、生活習慣の改善や病気の予防に役立ちます。一方で、導入や運用にはコストやセキュリティの課題もあります。今後はAIやマイナポータルとの連携が進み、より精度の高い医療や予防サービスが期待されます。健康管理の新しいスタンダードとして、活用の幅はさらに広がっていくでしょう。
まずは、自分に合ったPHRサービスを調べ、日々の健康データを記録することから始めてみましょう。
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS