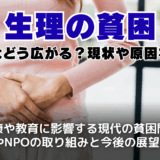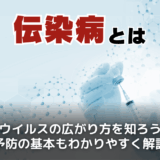過重労働は、心身の健康を脅かす深刻な社会問題として注目されています。長時間労働や過度な業務負担は、うつ病や心疾患などの健康障害を引き起こすだけでなく、家族との時間を奪い、社会全体にも大きな影響を及ぼします。
政府や企業が対策を進めている一方で、現場の実態や従業員の意識改革も欠かせません。本記事では、過重労働の基準やリスク、健康障害防止のための総合対策をわかりやすく解説します。
過重労働とは?

「過重労働」とは、単なる残業の多さだけではなく、心身の健康に深刻な影響を及ぼす長時間労働を指します。
過重労働と長時間労働の違い
過重労働(かじゅうろうどう)と長時間労働は似た言葉ですが、意味合いには明確な違いがあります。長時間労働は単純に労働時間が長い状態を指し、残業や休日出勤が常態化している働き方を表します。一方で過重労働は、労働時間の長さだけでなく、その内容や強度によって心身に著しい負担を与えている状態を含みます。
| 長時間労働 | 過重労働 | |
|---|---|---|
| 定義 | 労働時間が長い状態 | 労働時間の長さに加え、内容や負担が重く健康障害の恐れがある状態 |
| 判断基準 | 残業・休日出勤の多さ | 時間+作業の強度、疲労の蓄積、メンタル・体調への影響 |
| 例 | 月60時間の残業 | 月80時間超の残業(過労死ライン)や高ストレス業務 |
| 労災認定 | 直ちには対象にならない | 健康被害があれば認定対象 |
| 行政の対策 | 時間外労働の上限規制 | 「過重労働による健康障害防止総合対策」 |
例えば、月に80時間を超える残業は「過労死ライン」と呼ばれ、労災認定の基準にもなります。つまり長時間働いていても本人に負担が少なければ直ちに過重労働とは言えませんが、心身の疲労が積み重なり健康障害に至る可能性がある場合は「過重労働」と判断されるのです。
近年は厚生労働省も「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を掲げ、時間だけでなく労働環境やメンタルヘルス面も含めて対策を求めています。この違いを正しく理解することは、自分や職場の働き方を見直す第一歩になります。
英語での表現と用語の読み方
「過重労働」は英語で一般的に“excessive overtime”や“overwork”と表現されます。特に“karoshi(過労死)”は日本特有の社会問題として海外メディアでもそのまま使われることが多く、日本の働きすぎ文化を象徴する言葉として広まっています。
また、労働関連の国際的な議論では“working excessively long hours”や“hazardous overwork conditions”といった表現が用いられ、健康障害や社会リスクとの関連が強調されます。用語の読み方を正しく理解することで、国内だけでなく海外の研究や報道にも触れやすくなり、過重労働に関する知識を広く得ることができます。さらに、英語での表現を知ることは、外資系企業での労働環境改善の取り組みや、国際的な労働基準の動向を把握する際にも役立ちます。
社会的背景としての「働きすぎ文化」
日本における過重労働の根底には、「働きすぎ文化」とも言える社会的背景があります。高度経済成長期から続く「長時間働くことが美徳」という価値観は、現在も多くの企業風土に残っています。そのため、成果よりも労働時間の長さが評価基準になりやすく、社員が自ら進んで残業をする、あるいは断れない状況が常態化しているのです。
さらに過重労働には明確な法的定義が存在しないため、何をもって「過重」とするかが曖昧であり、このあいまいさが社会問題を深刻化させています。例えば「過労死ライン」は行政が労災認定に用いる目安でしかなく、法的に拘束力がある基準ではありません。
その結果、企業や個人の判断によって基準がばらつき、是正が遅れるケースが後を絶ちません。過重労働を防ぐには、文化的背景と制度的なあいまいさの両面から改善を進める必要があります。
なぜ過重労働が起きるのか?
過重労働の背景には、業務量の偏りや企業文化、制度の不備など複数の要因が絡み合って存在しています。
業務量と人員配置のアンバランス
過重労働が発生する大きな要因の一つが、業務量と人員配置の不均衡です。現場の業務量に対して適切な人員が確保されていない場合、少人数で多くのタスクを抱えることになり、長時間労働が常態化します。特にIT業界やサービス業など繁忙期が明確な業種では、臨時の人員補充が難しく、結果的に既存の従業員に過度な負担が集中します。また、業務効率化が十分に進んでいない職場では、本来削減できるはずの作業が温存され、労働時間がさらに膨らむ悪循環に陥ります。
このような「人員不足 × 業務過多」の状況は、過重労働時間を増大させる温床となり、心身の健康障害を引き起こすリスクを高めます。組織として業務量の適正化や人員配置の見直しを怠れば、従業員の疲弊、離職率の上昇、さらには企業全体の持続性を脅かす深刻な問題につながります。
「美徳」としての長時間労働文化
日本社会に根強く残る「長時間働くことが美徳」という文化は、過重労働を生み出す大きな要因となっています。成果よりも「どれだけ会社にいるか」が評価につながる職場風土では、効率的な働き方よりも滞在時間の長さが重視されやすくなります。これにより、無駄な会議や残業が常態化し、本来削減できる過重労働時間が放置されるのです。また、勤勉さや責任感を重んじる価値観が強調される結果、従業員自身が「早く帰るのは悪いこと」と考え、必要以上に業務を抱え込む傾向が見られます。
こうした文化は組織の生産性を下げるだけでなく、心身の疲弊や過労死のリスクを高める深刻な問題です。労働基準や働き方改革が整備されても、この文化が温存される限り、真の意味で過重労働を防ぐことは難しいと言えるでしょう。
上司・管理職の無理解と制度不備
過重労働が解消されない背景には、上司や管理職の意識不足と制度の不備が大きく関わっています。まず、現場を統括する管理職が「長時間働くのは当然」という価値観を持っている場合、部下の労働時間に配慮せず、過重労働を放置する傾向があります。さらに、労働時間の適正な把握や休暇取得の促進が行われず、実際の働き方と制度の理想が乖離している職場も少なくありません。
制度自体が存在していても、運用が徹底されなければ意味をなさず、形骸化したルールは従業員を守る力を失います。その結果、過重労働時間が積み重なり、健康障害や労災リスクが高まります。上司や経営層が労務管理の重要性を理解し、制度を実効性ある形で運用することが不可欠であり、ここを軽視すると組織全体の持続可能性を損なう要因となるのです。
過重労働の基準と判断ライン
過重労働を理解するには、具体的な基準や判断ラインを把握することが重要です。
| 区分 | 内容 | 上限時間 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 法定残業時間 | 労働基準法で定められた原則的な残業の上限 | 月45時間/年360時間 | 36協定を締結した場合に適用。臨時的な事情がなければこの範囲内で運用される。 |
| 特別条項付き36協定 | 臨時的・特別な事情に限り残業を延長できる制度 | 年720時間以内、複数月平均80時間以内、単月100時間未満 | 2019年の法改正で導入。理由を明記し、労使合意が必要。違反時は行政指導・罰則対象。 |
| 過労死ライン | 労災認定の判断基準として厚労省が示す目安 | 月80時間超の残業(または2~6か月平均で80時間超) | 法的拘束力はないが、裁判や労災認定で重視される。脳・心疾患のリスクが大幅に上昇。 |
ここでは代表的な基準を解説します。
時間外労働の上限(原則月45時間・年360時間)
日本では過重労働を防ぐために、労働基準法で時間外労働の上限が明確に定められています。原則として時間外労働は「月45時間以内、年360時間以内」とされています。これは2019年の働き方改革関連法の改正により、中小企業を含めて順次適用された重要なルールです。例外として臨時的・特別な事情がある場合には、36協定の特別条項を結ぶことで延長が可能ですが、その場合でも上限は「年720時間以内、複数月平均80時間以内、単月100時間未満」と厳格に制限されています。
この基準は、長時間労働による健康障害や過労死を未然に防ぐ目的で設けられており、過労死ラインと呼ばれる目安とも密接に関連しています。過重労働とは、単なる労働時間の長さだけでなく心身の負担も含む概念ですが、この法的基準を超える働き方は健康リスクが高く、企業には遵守義務が課せられています。労働者にとっても、自身の労働時間を客観的に把握し、法で守られている基準を意識することが重要です。
36協定と特別条項の条件
時間外労働を可能にする「36協定(サブロク協定)」は、労働基準法第36条に基づき、労使間で書面による合意を行い、労働基準監督署に届け出ることで成立します。原則として、協定があっても残業は月45時間・年360時間を超えてはいけません。
しかし、2019年の法改正以降は「特別条項付き36協定」を結ぶことで、臨時的・特別な事情に限り上限を超えることが認められています。その場合でも無制限ではなく、上限は「年720時間以内」「複数月平均80時間以内」「単月100時間未満」という厳しい条件が設けられています。また、特別条項を適用する際は、臨時的な理由を明記し、労使双方の合意を経る必要があります。
これらの条件は、過重労働による健康障害防止のための総合対策の一環として導入されたもので、法的拘束力を持つ明確な基準となっています。企業はこれを遵守しなければならず、違反した場合には行政指導や罰則の対象となる点に注意が必要です。
過労死ラインと労災認定の判断基準
「過労死ライン」とは、厚生労働省が労災認定の目安として定めている労働時間の基準を指します。一般的に、月80時間を超える時間外労働や2〜6か月間で月平均80時間を超える残業があると、脳・心臓疾患などの発症リスクが著しく高まるとされています。これはあくまで「目安」ですが、裁判や労災認定の場面で重視されるため、過重労働の実態を測る重要な指標となっています。特に2019年の働き方改革法改正以降は、労災認定の判断基準と法的上限がより連動し、過労死防止の枠組みが強化されました。
労災認定では、単なる労働時間だけでなく、業務の内容や精神的負荷、勤務シフトの不規則さなども総合的に評価されます。つまり、時間外労働が基準を下回っていても、過重な業務内容や突発的な負担によって健康被害が生じた場合は認定の対象になり得ます。過重労働とは時間だけでは測れない複合的な問題であり、この基準を理解することは、働く人が自らの健康を守るための大切な手がかりになります。
過重労働による健康障害防止のための対策・解決策
過重労働を防ぐには、国や企業が講じる制度的な取り組みと、現場での実践的な対策を知ることが欠かせません。
過労死等防止対策推進法の制定
過重労働による健康障害を防止するために、政府や厚生労働省はさまざまな政策やガイドラインを整備しています。特に2014年に施行された「過労死等防止対策推進法」は、過労死や過労自殺を社会全体で防ぐことを目的とし、国や地方自治体に対策を求めています。さらに、厚労省は「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を策定し、長時間労働の抑制、健康診断の実施、産業医や保健師による面接指導の強化などを企業に求めています。
働き方改革関連法による時間外労働の上限を規制
2019年の働き方改革関連法では、時間外労働の上限規制が法的に明文化され、違反企業には罰則が科される仕組みが導入されました。また、働き方改革実行計画に基づき、テレワーク推進や勤務間インターバル制度の普及も進められています。これらの政策やガイドラインは、単に残業時間を減らすだけでなく、心身の健康を守るための包括的な枠組みとして位置づけられており、過重労働の根本的な是正につながることが期待されています。
企業の過重労働に対する施策
過重労働による健康障害を防ぐためには、企業による具体的な取り組みが欠かせません。
医師による長時間労働者に対する面接
厚生労働省のガイドラインでは、まず長時間労働者に対する医師による面接指導が義務付けられています。これは、時間外労働が月80時間を超える従業員や、本人から申し出があった場合に実施され、心身の不調を早期に発見し、必要に応じて就業制限や治療につなげる仕組みです。
従業員の勤務時間の把握と環境整備
労働時間の客観的な把握も重要で、企業はICカードやPCログなどを用いた勤務時間の適正な管理を行うことが求められています。また、過重労働の根本的な是正に向けて、労働安全衛生法に基づく衛生委員会の設置や、労使で構成される委員会による労務環境の改善検討も有効です。これらの取り組みは形式的に導入するだけでは意味がなく、従業員が安心して相談できる体制づくりや、経営層の意識改革とともに実効性を持たせることが必要です。
こうした企業の取り組みが積み重なってこそ、過重労働を防ぎ健康的な職場環境を実現できます。
参考:過重労働による健康障害を防ぐために|厚生労働省
参考:職場のあんぜんサイト:過重労働対策[安全衛生キーワード]
過重労働がもたらす健康被害と社会的リスク
過重労働は個人の体調不良にとどまらず、家族や地域社会、さらには企業経営にも大きなリスクを及ぼします。
身体疾患・精神障害のリスク
過重労働は、脳や心臓に関わる疾患、さらには精神疾患を引き起こす大きな要因とされています。長時間労働による過度なストレスや睡眠不足は、自律神経の乱れや血圧上昇を招き、脳梗塞や心筋梗塞、狭心症などの循環器疾患のリスクを高めます。特に「過労死ライン」を超える時間外労働が続くと、発症確率が大幅に上昇するとされ、実際に労災認定の基準としても用いられています。
また、肉体的な負担だけでなく、終わりの見えない業務や成果プレッシャーはうつ病や不安障害などの精神疾患を発症させる大きな要因になります。これらは徐々に進行することが多く、気づかないうちに重症化する危険があります。最悪の場合、心身の限界を超えた状態が続くことで、突然死(過労死)や自殺に至るケースも少なくありません。過重労働は単なる長時間勤務ではなく、健康と命を脅かす深刻な社会問題であり、早期にリスクを理解し、対策を講じることが極めて重要です。
家族・地域への波及と介護負担
過重労働による影響は、労働者本人だけでなく家族や地域社会にも広がります。長時間労働が常態化すると、家庭での役割分担に偏りが生じ、家族関係に緊張が走りやすくなります。特に育児や介護を担う家族の負担は増加し、精神的ストレスや疲労が蓄積することで二次的な健康被害を生む可能性があります。また、労働者が脳・心臓疾患や精神疾患を発症すれば、家族は介護や看病に追われることになり、仕事や生活の両立が難しくなるケースも少なくありません。最悪の場合、過労死によって一家の生活基盤が失われ、遺族の経済的・精神的負担は計り知れないものとなります。
さらに、地域においても労働人口の減少や医療・福祉サービスへの需要増加が起こり、社会全体に波及する問題となります。したがって過重労働は、家庭の安定や地域社会の持続性を脅かす深刻なリスクを孕んでいるといえます。
企業の社会的信用や持続的成長を大きく揺るがす可能性
過重労働は従業員個人の健康や生活だけでなく、企業全体の経営にも深刻なリスクをもたらします。まず、長時間労働が常態化すると従業員の疲弊から生産性が低下し、ミスや事故の発生率が高まります。さらに、心身の不調による休職や離職が増えることで、人材の流出や採用コストの増大につながり、結果的に離職率の上昇を招きます。優秀な人材ほど働きやすい環境を求めて転職する傾向があるため、組織の競争力低下にも直結します。
また、過重労働や過労死が社会的に報じられれば、企業イメージの悪化やブランド価値の毀損を引き起こし、消費者や取引先からの信頼を失う危険性もあります。企業にとって過重労働を放置することは、法的リスクや労働基準監督署からの是正指導にとどまらず、社会的信用や持続的成長を大きく揺るがすリスク要因となるのです。
過重労働防止のための企業・個人の対策
過重労働を防ぐには、企業による環境整備と従業員自身のセルフケアの両面から取り組むことが不可欠です。
企業ができる主な対策
過重労働を防ぐためには、企業が組織的に仕組みを整えることが欠かせません。まず重要なのが面接指導です。厚労省のガイドラインでは、一定の残業時間を超えた従業員に対し、産業医による面接指導を実施することが推奨されています。心身の不調を早期に把握し、必要に応じて就業制限や医療機関への受診を勧めることで、深刻な健康障害を未然に防ぐ効果があります。
次に、労働時間管理の徹底が必要です。PCログや入退館記録を活用した労働時間の客観的な把握や、残業の上限を超えないようなシステム管理が有効です。単に「自己申告」に頼るのではなく、管理職が積極的にチェックし、過重労働時間の発生を抑制する仕組みを整えることが求められます。
さらに、過重労働対策委員会などの設置も有効です。人事部門や労働組合、産業医が連携し、労務環境を定期的に点検・改善する場を設けることで、制度の形骸化を防ぎ、従業員の声を反映させやすくなります。
従業員ができるセルフケアとSOS発信
過重労働による心身の不調を防ぐためには、従業員自身が意識的にセルフケアを実践し、必要な場面で早めにSOSを発信することが大切です。
まず基本となるのは、生活リズムの確保と睡眠の質改善です。深夜残業が続くと体内時計が乱れ、慢性的な疲労や精神的ストレスを蓄積します。可能な範囲で就寝・起床時間を一定にし、休日の寝だめを避けることが健康維持につながります。また、短時間でもリラックスできる休憩や軽い運動を取り入れることで、肩こりや集中力低下の予防が可能です。
さらに重要なのが、ストレスサインを見逃さないことです。食欲不振や気分の落ち込み、不眠などの兆候が出たら、早めに上司や人事部、産業医に相談することが求められます。過重労働時間が続く中で「我慢すれば乗り切れる」と考えるのは危険であり、放置するとうつ病や心疾患につながるリスクがあります。
そして、社内外の相談窓口を積極的に活用する姿勢も必要です。企業が設ける相談窓口のほか、厚労省やNPOが提供する外部のホットラインも利用可能です。セルフケアとSOS発信を両立させることで、過重労働による深刻な健康被害を未然に防ぎ、より持続的に働ける環境を自ら整えることができます。
厚労省やNPOの相談窓口紹介
専門的な相談窓口の活用も重要です。厚生労働省では「労働基準監督署」や「総合労働相談コーナー」を全国に設置し、労働時間や職場環境に関する相談を無料で受け付けています。匿名での相談も可能で、過重労働を訴えることに抵抗がある人でも安心して利用できる体制が整っています。また、深刻な健康障害が懸念される場合には、産業医やメンタルヘルス相談窓口への紹介も行われます。
さらに、NPOや民間団体が提供する支援サービスも有効です。たとえば「過労死110番」や労働問題に特化したNPOでは、弁護士や専門カウンセラーが過重労働基準や法的対応について具体的にアドバイスを行っています。
精神的に追い詰められた状況でも、こうした第三者の窓口を活用することで、法的権利や改善策を知るきっかけとなります。
過重労働時間が続く中で一人で抱え込むことはリスクが大きく、「早めに相談する」こと自体が最も大切な対策です。厚労省やNPOの窓口を活用することは、自分自身の健康を守るだけでなく、社会全体で過重労働問題を改善する大きな一歩となります。
参考:過重労働による健康障害を防ぐために|厚生労働省
参考:職場のあんぜんサイト:過重労働対策[安全衛生キーワード]
参考:過重労働による健康障害を防ぐために
SDGs視点で見る「過重労働」の課題
過重労働の問題は、個人の健康だけでなく持続可能な社会や経済成長にも影響を及ぼす重要な課題です。
SDGs8「ディーセント・ワーク」との過重労働の関係性
SDGs(持続可能な開発目標)の目標8「ディーセント・ワークと経済成長」は、すべての人にとって働きがいのある人間らしい仕事を確保することを掲げています。しかし、日本に根強く残る過重労働は、この目標達成を阻害する大きな要因です。過重労働時間の長さは、心身の健康を損なうだけでなく、生産性低下や人材流出を招きます。さらに、国際社会における労働基準とのギャップを広げ、経済的な競争力を失うリスクもあります。過重労働とは単なる個人の問題ではなく、持続可能な社会を築くうえで克服すべき構造的な課題であり、労働環境の改善を通じて初めて真のディーセント・ワークの実現につながります。
過重労働が経済成長を阻害する可能性
過重労働は一見すると労働時間の増加によって生産量が上がるように見えますが、実際には逆効果を生みます。長時間労働が続くと集中力や判断力が低下し、ミスやトラブルが増加するため、生産性全体が下がってしまいます。さらに、過労による体調不良や精神疾患は欠勤や離職を招き、企業にとって大きな人材損失となります。
こうした状況が続けば、労働人口の減少に拍車がかかり、経済の持続可能性そのものが危うくなります。過重労働とは単なる個人の健康問題にとどまらず、社会全体の成長を阻害する構造的なリスクであり、働きすぎを是正することが長期的な競争力強化と持続的発展の鍵となります。
ジェンダー平等・健康と福祉への波及
過重労働は、単に働く人個人の問題にとどまらず、ジェンダー平等や社会全体の福祉にも深刻な影響を与えます。長時間労働が常態化すると、家事や育児の分担が不均衡になりやすく、特に女性に負担が集中するケースが増えます。これはジェンダー平等の実現を妨げる要因となり、キャリア形成の機会格差を生み出します。
また、健康被害による医療費や介護負担の増大は、家庭や地域社会に重くのしかかり、福祉制度全体を圧迫します。過重労働とは労働環境の問題であると同時に、持続可能な社会の実現を阻害するリスク要因でもあるのです。
持続可能性を保つためには、働きすぎを是正し、誰もが健康で公平に活躍できる社会基盤を築くことが欠かせません。
参考:JAPAN SDGs Action Platform | 外務省
過重労働に関するよくある質問
過重労働については多くの疑問や不安が寄せられます。ここでは代表的な質問を取り上げ、分かりやすく解説します。
Q1.過重労働とは具体的にどのような状態を指しますか?
過重労働とは、労働者が心身に過度な負担を抱えるほど長時間労働や過密な業務を強いられている状態を指します。単に「忙しい」ことと異なり、法律で定められた時間外労働の上限を超えたり、休息時間が十分に確保されない状況が典型例です。
特に、月80時間を超える残業は「過労死ライン」と呼ばれ、脳や心臓疾患のリスクが高まるとされています。さらに、精神的なストレスや休日の減少も重なり、健康障害や家庭生活への影響につながるのが大きな特徴です。
こうした点から「過重労働とは」単なる繁忙期を超えた深刻な問題であり、働く人の安全と生活を守る観点で理解する必要があります。
Q2.過労死ラインはどのくらいの労働時間で判断されるのですか?
過労死ラインとは、長時間労働によって健康障害や死亡リスクが著しく高まる基準を指します。厚生労働省は「月80時間以上の時間外労働」を目安としており、これを超えると脳・心臓疾患や精神疾患の発症リスクが急増するとされています。特に「2〜6か月連続で月80時間を超える残業」や「月100時間超の残業」が確認されると、労災認定における重要な判断材料となります。
つまり、過労死ラインは単なる目安ではなく、過重労働による深刻な健康被害を防ぐための警告線と位置づけられており、企業も従業員も強く意識する必要があります。
Q3.過重労働が原因で体調を崩した場合、どこに相談すればよいですか?
過重労働によって体調を崩した場合、まずは産業医や会社の健康管理部門に相談することが基本です。勤務先に産業医がいない場合は、地域の労働基準監督署や労働局の「労災相談窓口」を利用できます。
また、厚生労働省が設置する「過重労働相談ダイヤル」や、NPO・労働組合による無料相談窓口も活用可能です。特に、過重労働時間が基準を超えて健康障害の兆候が見られる場合には、速やかな医療機関の受診と合わせて専門機関への相談が重要です。これにより、労災認定や適切な支援につながる可能性が高まります。
Q4.会社に対して「過重労働」を訴えることはできますか?
過重労働が疑われる場合、会社に対して訴えることは可能です。まずは労働基準法に基づき、労働基準監督署へ相談や申告を行う方法があります。過重労働時間が基準を超え、健康被害が出ている場合は労災認定の対象となる可能性もあります。また、労働組合やNPOの支援を受けることで、会社との交渉や法的手続きがスムーズに進む場合もあります。重要なのは、タイムカードや診断書などの証拠をしっかりと残すことです。これにより、適切な救済や改善を求めることができます。
Q5.過重労働を避けるために従業員自身ができるセルフケアはありますか?
過重労働を防ぐには、従業員自身のセルフケアも欠かせません。
まず、生活習慣の見直しが基本です。睡眠時間を確保し、バランスの取れた食事や適度な運動を心がけることで、心身の回復力を高められます。また、ストレスをため込まず、適切にリフレッシュする時間を意識的に持つことも大切です。業務中は「時間の切り分け」を意識し、長時間の連続作業を避けて短い休憩を挟む工夫が効果的です。
さらに、体調不良や過重労働時間が続く場合は早めに上司や産業医に相談し、SOSを発信する勇気を持つことが必要です。
まとめ
過重労働は、心身の健康や家庭生活、そして社会全体に深刻な影響を及ぼす問題です。本記事では「過重労働とは何か」から始まり、基準や過労死ライン、企業や政府の対策、従業員のセルフケアの方法まで幅広く解説しました。
過重労働は単なる長時間労働にとどまらず、生活の質や生産性の低下を招き、社会的損失を拡大させるリスクがあります。働く人一人ひとりが正しい知識を持ち、早めにSOSを発信すること、また企業や行政が総合的に取り組むことが必要です。
過重労働を避けることは、健康とキャリアを守り、持続可能な社会を築くための大切な一歩となります。
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS