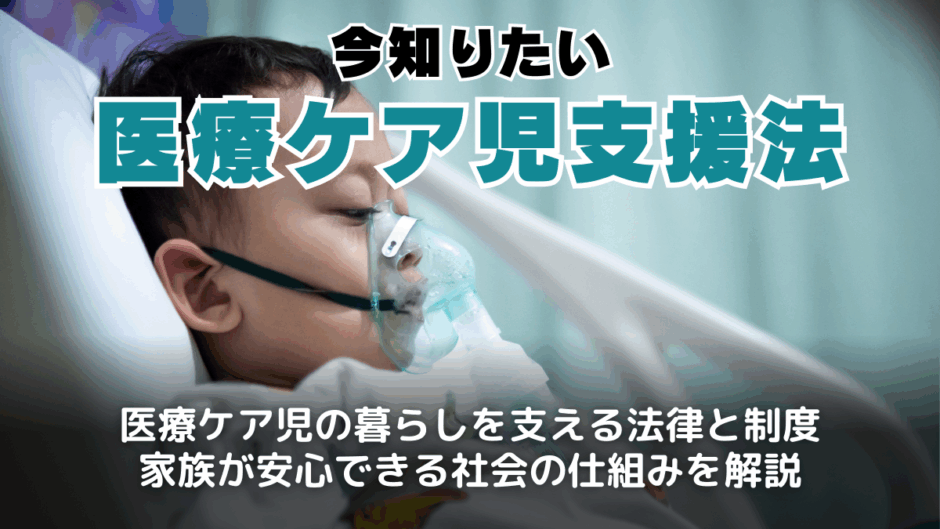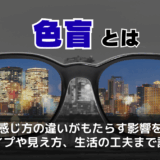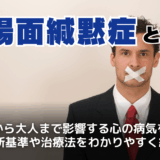医療ケア児の暮らしを取り巻く環境は、近年大きく変化しています。医療機器や支援制度の充実により、もっと安心して子どもが保育園や小学校に通え、家族と笑顔で日々を過ごす社会への一歩が進んできました。それでも、ケアや制度の「壁」や地域ごとの違い、不安や悩みは尽きません。
本記事では、医療ケア児支援法や福祉サービス、家庭や地域での医療ケアの現状から、具体的な制度活用や課題解決のヒントまで、最新の情報を網羅的に解説します。
家族みんなの安心と未来のために、本当に役立つ支援のすべてをご紹介します。
医療ケア児とは?

医療ケア児とは、日常生活の中で医療的なサポートが恒常的に必要な子どもを指します。
具体的には、人工呼吸器や吸引器、経管栄養などの医療機器を家庭や学校、保育園などで使用しながら生活している児童が該当します。医療ケア児は、病院だけでなく家庭や地域社会で成長していくため、医療と福祉、教育の連携支援が重要になります。
医療的ケア児支援法が施行されたことで、保育園や小学校などの教育現場でも医療的ケアに対応できる体制づくりが進められています。医療ケア児の特徴は、通常の育児や保育だけでなく、専門的な医療的処置や日々の観察、急変時の迅速な対応が求められる点です。家族や支援者は医療ケア児の成長発達を支えるために、行政の支援法や福祉サービス、地域の医療機関との連携を活用しながら、安心して社会に参加できる環境を整えています。社会的認知も広がりつつあり、医療ケア児を包括的に支援する動きが広まっています。
医療的ケア児支援法
医療的ケア児支援法は、医療ケア児が安心して生活し、家族が社会的に孤立しないようにするために制定された重要な法律です。2019年に議員立法として発議され、医療・福祉・教育の分野を横断した支援体制の構築が求められる中、家族や支援者から強い要望があがりました。その背景には、従来の制度の隙間により医療ケア児が十分な支援を受けられず、家族が孤立しやすい社会構造があったことが大きな要因です。こうした課題を解決するため、2021年に医療的ケア児支援法が施行されました。
この法律の基本理念は、「国や自治体の責務」と「共生社会の実現」にあり、国・自治体が積極的に医療ケア児とその家族を包括的に支援することが強調されています。医療ケア児が保育園や小学校に通いやすくなり、家族の負担軽減、地域格差の是正、支援サービスの拡充が大きく前進しています。また、支援法の成立により、「18歳の壁」や引っ越し時のサービスの途切れなど、家族が抱えていた不安にも対応するための新しい仕組み作りが進められています。社会全体で医療ケア児と家族を支える意義は非常に大きく、支援法はその第一歩として重要な役割を果たしています。
医療ケア児に必要とされる主な医療ケア
医療ケア児が日常的に必要とする主な医療ケアには、次のような内容があります。
- 経管栄養:口から十分な食事を摂れない場合、胃や腸に直接栄養を送る方法
- 喀痰吸引:呼吸を維持するため、気道にたまった痰を吸引機で取り除く
- 人工呼吸器管理:自力で呼吸が難しい場合、機械の力を借りて呼吸を補助
- 酸素療法:低酸素状態を防ぐため、鼻やマスクを通じて酸素を供給
- インスリンや薬剤の定時投与:慢性疾患や合併症管理のため定期的に薬を投与
- モニタリング機器の使用:心拍や呼吸数など生命兆候を常時監視
これらの医療ケアは、病院ではなく家庭や保育園、小学校、地域の施設でも日常的に行われています。家族や支援者は、専門的なスキルと連携体制を活かしながら、医療ケア児の安全と健康維持を担っています。現在では、訪問看護や福祉支援を取り入れることで、より安心して介護できる環境づくりも進んでいます。
日本で医療ケア児が増加している理由・背景
医療ケア児を取り巻く環境は年々変化し、制度やサービスも進化しています。ここでは現状や最新動向を見ていきます。
医療ケア児の人数
医療ケア児の人数は年々増加傾向にあります。最新版の厚生労働省や関連機関のデータによると、全国で医療的ケア児は2021年時点で約2万人と推計されていましたが、2025年6月現在も約2万人という数値で横ばいまたは微増という状況です。
この人数は、在宅で人工呼吸器や胃ろう、経管栄養・喀痰吸引など複数の医療的ケアが日常的に必要な児童(0〜18歳まで)が含まれています。
医療技術の向上に伴い、重症新生児がNICU(新生児集中治療室)で救命される例が増え、退院後も継続的な医療的ケアが必要となる子どもたちが増加しています。また、自治体ごとの調査や受け入れ体制の整備も進み、医療ケア児の実数把握や支援制度の拡充が社会的課題となっています。医療ケア児とその家族に対する支援は今後も重要性を増しており、支援法や福祉制度の充実が求められています。
参考:医療的ケア児、成人後を支援へ…「18歳の壁」解決へ受け入れ態勢を充実
参考:医療的ケア児について
医療技術の進歩とNICUの普及
医療技術の急速な進歩と新生児集中治療室(NICU)の普及により、以前は救えなかった命が多く助かるようになっています。NICUでは未熟児や重症新生児に対する高度な医療が提供され、人工呼吸器や経管栄養、酸素療法などの技術が現場で活用されています。特に人工呼吸器の小型化や高性能化、経皮的酸素モニターの導入などが、在宅での医療ケアの普及にも繋がっています。
こうした医療機器の進化により、退院後も家庭や地域で継続的な医療ケアが可能となり、医療ケア児の生活圏は病院から家庭・保育園・学校へと広がっています。医療と福祉、教育分野の支援が連携することで、医療ケア児と家族の生活の質の向上が実現しつつあり、社会全体のサポート体制が強化されています。
地域や家庭まで生活圏の広がり
医療ケア児の生活圏は、以前のように病院や医療施設に限定されることなく、家庭や地域社会へと大きく広がっています。現在は、保育園や小学校、地域の福祉施設などでも医療ケアが日常的に実施されるようになり、家族や支援者が連携して子どもの成長を支えています。訪問看護やレスパイトサービスの普及によって、在宅でも人工呼吸器や酸素療法、喀痰吸引などの主な医療的サポートが安全に行える環境が整いつつあります。
また、専門的な医療スタッフや福祉のプロが地域に配置されることで、医療ケア児と家族の負担軽減や社会参加機会が拡大しています。自治体や支援法が後押しする形で、医療・福祉・教育の連携も充実し、地域格差の解消や「18歳の壁」への対応など支援体制が年々強化されています。このように、医療ケア児が家庭と地域を中心に安心して暮らせる社会へ、一歩ずつ進化を遂げています。
なぜ日本では医療ケア児が増えているのか?
医療ケア児が増えている背景には、医療技術の進歩や新生児医療の充実があります。次に具体的な増加理由について見ていきましょう。
医療の進歩による救命率向上
医療ケア児が増加している背景には、医療技術の進歩による救命率の向上があります。新生児集中治療室(NICU)の普及によって、未熟児や重篤な症状を持つ新生児の救命が可能となり、以前は助けられなかった子どもたちが多く生きられるようになりました。また、人工呼吸器の小型化や経管栄養、酸素療法の高性能化など、医療機器の進化も医療ケア児の増加につながっています。
これらの技術発展により、病院退院後も家庭や保育園、学校など生活の場で医療的ケアを受けられる環境が整いつつあります。医療ケア児が社会で成長し、自分らしく暮らせる体制づくりは、医療・福祉・教育の連携支援や支援法の拡充にも影響を与えています。今後も医療の進歩と共に、支援体制もより強化されていくでしょう。
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(医療的ケア児支援法)」の成立・施行
医療ケア児の社会的認知が大きく広がったきっかけは、2021年に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(医療的ケア児支援法)」が成立・施行されたことです。
この法律によって、国や自治体が医療ケア児への支援を行うことが「努力義務」から明確な「法的責務」となり、これまで十分なサポートが受けられなかった状況が一新されました。
また、法施行により行政やメディアによる報道、医療ケア児の家族間での情報共有も活発化し、社会の関心が一気に高まりました。
この社会的認知の高まりによって、支援や調査の対象児童が「見える化」され、医療ケア児の実態把握が進みました。それまで統計上把握しきれなかった子どもたちも公的に数値化され、医療ケア児の人数が増加したように見える側面もあります。
今後も支援法を基盤として、医療ケア児への社会的理解と包括的な支援体制がさらに拡充されていくことが期待されています。
世界の医療ケア児の現状
世界の医療ケア児の現状を見ていきましょう。
家族や医療費の負担が大きい
世界でも日本と同じく致命率が向上しているため、医療ケア児は増加傾向にあります。助かる命が増えている一方で、医療ケア児に対する支援制度などが不足している現実があります。
日本だけでなく、アメリカなど先進国の中でも支援制度は不足していて、医療ケア児とその家族に大きな負担がかかっています。特にアメリカは自費診療が基本の国なので、介護の負担だけでなく金銭的な負担も重くのしかかっているのが現状です。
国民皆保険制度が導入されている国々でも、家族の負担が大きく在宅介護が難しいといった問題になっています。
支援体制の充実
国によっては、医療ケア児が自宅での介護が必要な場合に、介護保険などが利用できる場合があります。
例えばドイツでは、介護保険制度があるため介護サービス利用券が利用できたり、介護手当を受給できたりと保護が手厚くされています。
他にも専門の小児科看護師が自宅に派遣される制度も利用できる場合があり、手厚い補助により致命率が高くても、家族の負担になることなく育てられる場合があります。
医療や介護への補助が手厚い北欧諸国では、医療ケア児だけの補助ではなく、その家族への補助も受けられるなど充実している点が日本との大きな違いです。
医療ケア児支援の目的と求められる理由
医療ケア児支援は、安心した生活と成長のために欠かせません。ここでは、その具体的な目的や必要とされる背景を探っていきます。
医療ケア児支援の主な目的
医療ケア児支援の主な目的は、医療ケア児が健やかに成長できる環境を社会全体で整えることにあります。医療ケア児とその家族が安心して生活し、誰もが平等に必要な支援を受けられる仕組みを作ることが重要です。支援法や福祉制度の拡充により、医療・福祉・教育の連携支援が進み、保育園や小学校への通園・通学がしやすくなりました。
また、「18歳の壁」と呼ばれる成人への移行時にも支援が途切れないよう制度改善が求められています。家族の負担軽減や地域格差の解消も大きな目的のひとつです。これにより、支援が届きにくかった家庭にも手厚いサービスが提供され、訪問看護やレスパイト、制度の情報提供など多彩な支援が拡がっています。医療ケア児支援の根幹は「共生社会」の実現であり、すべての子どもが自分らしく生きることができる地域社会の構築を目指しています。
家族にかかる大きな負担解消
医療ケア児を育てる家族には、日々の介護や医療ケア、通院・通学の付き添いなど、精神的・身体的な負担が大きくのしかかります。さらに保育園・小学校への受け入れ体制や、行政手続きの煩雑さ、医療機関との連携による情報共有不足も悩みの種です。こうした負担は、ひとり親や両親共働き世帯では特に深刻化し、家族全体の生活に影響を及ぼします。
そこで、医療ケア児支援法や福祉サービスによる支援が拡充され、訪問看護やレスパイトサービス、ショートステイなどの利用で家族が休息できる環境の整備が進められています。自治体の取り組みによって、医療ケア児のいる家庭でも保育園・小学校に安心して通える体制も強化されており、家族への負担軽減と心身の健康維持が実現しつつあります。福祉・医療・教育が連携することで、支援の「切れ目」が生じず、家族みんなが笑顔で過ごせる社会づくりが目指されています。
地域格差の解消
医療ケア児支援の目的のひとつに「地域格差の解消」があります。これまで医療ケア児に対する支援は、自治体や地域によってサービスの内容や支援体制が大きく異なり、住む場所による「支援の差」や「サービスの途切れ」が社会問題となってきました。例えば、訪問看護やレスパイトなどの福祉サービスの利用しやすさ、保育園・小学校の受け入れ環境、専門スタッフの配置などは、都市部と地方、各自治体で格差が生じていました。
医療的ケア児支援法の施行や、国・自治体による本格的な支援体制の拡充により、こうした地域格差の是正が本格的に進められています。国レベルでのガイドラインや予算の確保、自治体間連携の強化によって、どこに住んでいても医療ケア児が平等に必要な支援を受けられる社会づくりが加速しています。これにより、医療ケア児と家族が安心して暮らせる環境が全国隅々まで広がりつつあり、共生社会の実現という大きな目標に向けて着実に歩みが進んでいます。
医療ケア児が直面する課題・問題点
医療ケア児は社会で支援の輪が広がる一方、通園・通学や社会参加、ケア体制や保護者負担、人員不足など様々な課題も残されています。これから直面する主な問題や解決への工夫を見ていきましょう。
希望する保育園や小学校への通園・通学の難しさ
医療ケア児が希望する保育園や小学校に通うには大きな壁があります。まず、医療的ケアが必要な子どもを受け入れる体制が整っている施設が限られており、地域や自治体によって対応状況や専門スタッフの配置にバラつきがあります。受け入れ可能な施設が見つかっても、医療機器の持ち込みやケアの内容に関する調整、各種手続き・書類作成が多く、家族と支援者、施設側の連携作業が欠かせません。
また、保護者がつきそいを求められるケースや、医療ケア児を理由に保育園・小学校への入園・入学が難航することも珍しくありません。現場では、医師や看護師、保育士、教師など多職種の協力が必要となり、自治体や支援団体の支援制度を積極的に活用する工夫も求められています。こうした課題を乗り越えるには、支援法や福祉サービスの活用、社会全体での理解と体制づくりが不可欠です。
成人後の「18歳の壁」と支援の途切れ
医療ケア児の課題のひとつに、成人後の「18歳の壁」と呼ばれる支援の途切れがあります。18歳までは医療ケア児向けの福祉サービスや支援制度が比較的充実していますが、成人になると多くの制度やサービスが終了し、受けられる支援が大幅に減少してしまう現状があります。この「18歳の壁」に直面すると、進学や就職などのライフステージに合わせた支援が十分に受けられず、本人・家族ともに不安が増します。
特に、訪問看護やショートステイ、情報提供など、日常生活の中で不可欠なケアが切れ目なく継続できるようにすることが重要です。医療的ケア児支援法や自治体の追加支援策によって、成人後も必要なケアや福祉サービスの提供体制強化が進められていますが、まだ地域差や制度の空白も残っています。今後は「18歳の壁」を乗り越える制度と支援の充実がさらに求められており、本人が社会に参加し続けられる環境づくりが社会的な課題となっています。
医療ケア児の具体的な支援とサービス
医療ケア児への具体的な支援やサービスは、家庭・地域・学校など様々な場面で展開されています。次に、利用できる具体的な支援内容やサービス例を詳しく見ていきましょう。
医療・福祉・教育の連携支援
医療ケア児の支援では、医療・福祉・教育の多職種が連携して取り組むことが不可欠です。例えば、医師・看護師・保育士・教員・ソーシャルワーカーなどが参加する「多職種連携会議」が定期的に開催され、子ども一人ひとりの状態や生活、学習環境に合わせた支援内容を協議します。ここでは、医療的ケアが必要な場面や緊急時対応、学校生活での配慮点など専門職の知見を活かした意見交換が行われます。
また、「個別支援計画の作成」にも連携体制が活用されており、医療・福祉・教育の担当者が家族と協力して具体的なケア内容や学校でのサポート方法を明文化。情報共有により、関係者全体が同じ認識でケア児に対応できるため、本人や家族の安心感も高まります。
こうした連携により、福祉制度の活用や保育園・小学校での医療機器利用の調整など、各分野の専門性が活かされたスムーズな対応が可能になります。医療ケア児とその家族は、相談先が明確になり、緊急時にも迅速かつ的確な対応を受けられるため、日常生活の負担が軽減され、地域と一体となった継続的なサポート体制の恩恵を受けられます。
訪問看護・レスパイト・ショートステイなどのサービス
医療ケア児と家族が安心して生活するためには、多彩な福祉サービスの活用が不可欠です。その代表が「訪問看護」で、看護師が自宅を定期的に訪れて、人工呼吸器管理や経管栄養、喀痰吸引などの医療ケアを実施し、保護者の安心感を支えています。緊急時や夜間にも対応可能な体制が広がり、専門的な助言や医療的観察も受けられるのがメリットです。
「レスパイト」(一時的休息)サービスは、家族が心身のリフレッシュを図るための重要な支援です。医療スタッフが家庭や施設でケア児を預かることで、保護者が休憩したり、仕事や用事を済ませる時間を確保できます。これに加えて「ショートステイ」は医療ケア児が一定期間、医療・福祉施設で安全に過ごせる仕組み。家族が急な予定や旅行をする際なども利用が可能です。
これらのサービスは自治体や支援法の充実によって利用しやすくなっており、訪問看護ステーションや地域包括支援センターが窓口となることが多いです。医療・福祉・教育の三分野が連携することで、医療ケア児の生活と家族の負担軽減を強力に支えています。
自治体・地域ごとの支援
医療ケア児の支援体制は自治体・地域によって様々な事例が実践されています。例えば、宮城県では「医療的ケア児支援センター」を設立し、地域の支援者や市町村と連携した個別相談、地域相談、理解啓発を実施。看護師など専門職による訪問指導や社会資源の調査、地域サイトによる情報公開など、多層的な支援環境が整っています。
東京都では、区部と多摩地域に「医療的ケア児支援センター」を設置し、医療的ケア児等コーディネーターを養成。保健・医療・福祉・教育領域の連携を推進し、自治体間での受け入れや保育士・看護師向け研修の案内を積極的に行っています。地域や行政と協働しながら、できない理由ではなく「どうしたらできるか」を考え、支援環境の拡充に努めています。
民間・NPOの事例としては、NPO法人アンリーシュが家族と支援者をリアルに繋ぐ座談会や講演会を年間20回開催し、自治体や企業へ当事者の声を直接届ける活動を進めています。また、日本財団は医療ケア児が利用できる拠点施設を全国的に整備し、日中支援・短期入所・きょうだい児支援や家族の就労支援など包括的な取り組みも実施しており、こうした取り組みが孤立しがちな家族を支える体制を地域密着で築いています。
参考:医療的ケアの必要なすべての人が安心できる暮らしのために
参考:助成事業例:医療的ケア児や重度心身障害児を支援する地域の拠点整備 | 日本財団
NPOの取り組み
医療ケア児の支援現場では、多くのNPOが独自の取り組みを進めています。例えば、NPO法人アンリーシュは医療ケア児の家族と支援者が交流できるリアルな座談会や講演会を年間20回以上開催し、自治体や企業などの関係機関へ当事者の声を直接届けています。これにより、行政の施策やサービス構築に家族の生の意見が反映されやすくなり、支援の質向上や社会参加の機会拡大にも寄与しています。
また、日本財団は全国各地で医療ケア児が利用できる拠点施設を整備し、日中支援や短期入所、きょうだい児支援、家族の就労サポートまで包括的なサービスを展開しています。現場では、ケア児本人だけでなく家族の孤立防止や心理的サポート、地域での居場所づくりにも力を入れており、自治体や医療機関、福祉団体と連携したネットワーク構築も進められています。
NPOの活動は、医療ケア児と家族の課題や悩みを社会に「見える化」し、制度拡充や地域支援の原動力となっています。こうした民間団体の積極的な取り組みが、医療ケア児支援の現場を大きく前進させています。
参考:NPO法人アンリーシュ
医療ケア児のよくある質問
ここからは、医療ケア児についてよくある質問とその回答を通して、より理解を深めていきます。
Q1. 医療的ケア児のきょうだいがいる場合、家族全体のサポートは受けられますか?
医療ケア児を育てる家庭では、きょうだいや家族全体を対象とした支援も充実しています。自治体や福祉サービスでは、兄弟児の保育補助や心理的サポート、きょうだい児向けのイベント・相談窓口などが設けられることが増えています。
また、医療ケア児の介護が主となる家庭には、家族全体の生活を支えるためのレスパイトや訪問看護、情報提供も広がっています。
Q2. 転居や引っ越しをした場合、支援やサービスはどうなりますか?
医療ケア児が転居や引っ越しをした場合も、自治体や関係機関による支援は継続して受けることができます。
まず新しい居住地の自治体窓口や福祉サービスセンターに相談することで、訪問看護やレスパイト、保育園・学校での医療的ケア対応など、必要なサービスの調整が行われます。支援法が施行されたことで、自治体間の連携が強化されており、手続きや情報引き継ぎもスムーズに進められる体制が整っています。
Q3. 緊急時や急な用事の際に、短期で預かってもらえる施設はありますか?
医療ケア児の家庭では、急な用事や家族の休息が必要な場合、「ショートステイ」や「レスパイト」などの一時預かりサービスを利用できます。自治体や福祉施設、医療機関が医療ケア児にも対応できる専用施設を設けており、看護師や専門スタッフが常駐している所もあります。
必要な医療的ケアに対応した体制が整っており、事前登録や相談窓口を利用することで、緊急時の預かりも可能です。
Q4. 18歳以降も利用できる支援サービスはありますか?
医療ケア児が18歳を迎えた後も、自治体や福祉サービスによって継続支援が提供されています。成人後は障害福祉制度が主な支援の窓口となり、訪問看護やショートステイ、就労支援なども利用可能です。また、医療的ケア児支援法に基づき、自治体による相談・調整・サービス情報の提供が続きます。
さらに、地域では医療・福祉・教育の連携体制が維持され、本人のライフステージやニーズに応じた支援へと移行できる環境が整いつつあります。
Q5. 保育園や学校で医療的ケアが必要な場合、どのような手続きや調整が必要ですか?
保育園や学校で医療ケアが必要な場合、まず医師の診断書やケア指示書の準備が一般的です。その後、施設・自治体・医療機関との多職種連携会議が開かれ、個別支援計画を策定します。医療機器持ち込みや対応スタッフの調整、保護者との事前打ち合わせも行われます。
書類提出や面談の他、緊急時対応方法・ケア内容の説明を施設側に詳しく伝え、安全な受け入れ体制を整えることが重要です。
まとめ
医療ケア児とその家族を支える社会の輪は、法律の成立や支援サービスの拡充により大きく広がっています。支援法の施行、自治体・NPOの連携、福祉サービスの充実によって、医療ケア児が安心して保育園や小学校に通い、家族が負担を減らしながら笑顔で過ごせる環境が整いつつあります。
今後も支援の質や制度の改善、地域間格差の解消を通じて、すべての子どもと家族が自分らしく暮らせる共生社会の実現を目指していくことが重要です。
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS