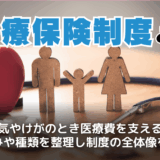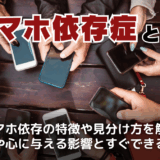LGBTQ+は、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クィアなど、性の多様性を表す総称です。近年、社会的認知は進んできましたが、その意味や背景を正しく理解できている人はまだ多くありません。
LGBTQ+のメリットとして、多様な価値観を認め合うことで人権意識が高まり、誰もが尊重される社会づくりに繋がります。
一方で、デメリットとしては、正しい情報が不足していることで偏見や誤解を生みやすく、当事者が孤立しやすい現実があります。
本記事では、LGBTQ+とは何かをわかりやすく解説し、lgbtq+ 一覧による用語の整理、lgbtq+診断の意義、人口のlgbtq+割合、健康課題への視点を紹介します。また、lgbtq+アライとしての行動や、フレンドリーな社会を実現するための具体策を取り上げていきます。
LGBTQ+とは?

LGBTQ+とは、多様な性の在り方や性自認、性的指向を示す言葉です。近年では、学校やメディアでも耳にする機会が増えており、社会全体で理解が求められるようになっています。特定の人だけの問題ではなく、すべての人にかかわる「人権」として捉える視点が求められています。
この言葉には、性の多様性を尊重し合い、誰もが安心して生活できる社会を実現するというメッセージが込められています。まずはその構成や意味を正しく知ることから始めてみましょう。
LGBTQ+の各頭文字の意味
「LGBTQ+」の文字には、それぞれ異なる意味があります。
(L)レズビアン
レズビアンは恋愛対象が女性である人のことを指します。日本語にすると「女性同性愛者」という言葉も用いられます。
ただレズという呼び方は侮蔑の意味が込められている場合もあるため、呼称する場合は「レズビアン」「ビアン」という呼び方が理想的です。
レズビアンの性自認は女性の場合も男性の場合もありますが、恋愛対象や性的対象が女性である場合をレズビアンと呼びます。身体的性は自由で、性自認が女性の人で恋愛対象は女性がレズビアンの定義となります。
ですが、身体の性が男性で性自認が女性で恋愛対象も女性というレズビアンのトランスジェンダーもいたりと、レズビアンの中でも複雑です。
(G)ゲイ
ゲイは同性愛者全般を示す言葉でもありますが、日本では身体的に男性の身体で生まれ、自分自身のことも男性と自認しており性的・恋愛対象が男性を指す場合が多いです。
ただゲイという言葉自体は、海外でも使用されていて「同性愛者」のことをまとめてゲイと呼んでいる場合もあります。
ゲイと聞くと、同性愛者だけでなく女性になりたがっている男性のこともゲイと勘違いしてしまいますが、ゲイが全員女装をしたり女性になりたいというわけではありません。
あくまでも男性の身体で男性が性的恋愛的対象という点で、ゲイと呼称されます。
(B)バイセクシュアル
バイセクシャルは、自分自身の性別にかかわらず、男女どちらも性的・恋愛対象として見られる人たちのことを指します。日本語でバイセクシャルは、「両性愛者」とも呼ばれています。バイセクシャルと公表している芸能人も多いのが印象的です。
男女どちらも性的恋愛的対象なために、遊び人だったり性に奔放なイメージを持たれてしまう場合もありますが、それは個人によるものでバイセクシャルだけに限ったことでもありません。
また男性の方が好きになりやすい・女性の方が好きになりやすいなど個人によって比重は異なり、バイセクシャルだからと言って必ずしも平等に好きになりやすいというわけではない点も注意が必要です。
(T)トランスジェンダー
トランスジェンダーとは、生まれ持った体の性と自分自身が認識している性が一致していない人全般のことを指します。
トランスジェンダーは基本的に本人たちが呼称する名称ですが、身体の性と自分自身の認識している性が異なることで、苦痛を感じてしまい、医療的処置が必要になった場合に医師が診断名として使用するのが「性同一性障害」という言葉です。
トランスジェンダーという言葉の中には、性同一性障害も含まれているのが一般的ですが、客観的に見た場合にもトランスジェンダーという言葉で表現するのが正しいとされています。
ただトランスジェンダーの中でも、医療的ケアを必要としているかは人によります。
(Q)クィア・クエスチョニング
LGBTQの「Q」はクィアまたはクエスチョニングという意味の頭文字をとっていて、クィア(Queer)の意味としては性的なマイノリティ全体をさす言葉の一つです。
Queerという言葉自体は元々「奇妙な」「風変わり」といった意味を持っていて、否定的な意味で利用されていました。しかし現在ではQueer本人たちが肯定的な意味で使用するようになっています。
クエスチョニングは自分自身の性が定まっていない人たちを指します。自分が異性を好きなのか同性を好きなのか、自分が男性なのか女性なのかに迷っている最中の人のことをクエスチョニングと呼びます。
(+)プラス
「+(プラス)」は、LGBTQ以外の多様な性のあり方を含むための記号です。
たとえば、ノンバイナリー(男性でも女性でもない性自認)や、アセクシュアル(他者に恋愛感情や性的欲求を持たない人)、パンセクシュアル(性別にとらわれず人に惹かれる人)などが該当します。
このように、性の在り方はひとつではなく、グラデーションのように多様なので、それを示すためにあるのが+表記です。
また+だけでなく、複数形である「s」をつけたLGBTsという言葉も存在します。いずれにしても、多様な性を包括して表現する言葉です。
SOGIの概念とLGBTQ+との関係
LGBTQ+を理解するうえで欠かせない考え方に「SOGI(ソジ)」があります。これはSexual Orientation and Gender Identityの略で、日本語では「性的指向および性自認」と訳されます。SOGIは、LGBTQ+当事者に限ったものではなく、すべての人に当てはまる普遍的な概念です。
性的指向とは、誰に恋愛感情を抱くのか個人の傾向を示します。性自認とは、自分の性別をどのように認識しているかを指す言葉です。性の多様性を社会全体で考える際、このSOGIの視点を共有することが大切です。行政や教育現場でもこの考え方を導入する動きが見られており、理解を深める手がかりとなっています。
LGBTQ+は一部の人の話題ではなく、すべての人が関係するテーマです。まずは基本的な用語の理解を深め、誰もが自分らしく生きられる社会の実現に目を向けることが求められています。
LGBTQ・LGBTQ+・LGBTsとの違い
LGBTQ・LGBTQ+・LGBTsとの違いを表で見ていきましょう。
| LGBTQ | LGBTQ+ | LGBTs |
|---|---|---|
| レズビアン ゲイ バイセクシャル トランスジェンダー クエスチョニング 上記の5つを表したのがLGBTQ | レズビアン ゲイ バイセクシャル トランスジェンダー クエスチョニング 上記の5つを表したのがLGBQ +は上記に当てはまらないアセクシュアル(無性愛者)など多様な性を包括して表しています。 | レズビアン ゲイ バイセクシャル トランスジェンダー 上記の4つを表したのがLGBT sはLGBTに複数形の意味をプラスしています。複数の性的マイノリティを指す際に使用されます。 |
ベーシックでよく利用されるのが、LGBTQです。これに+をつけると、多様な性を包括して表現できるようになるLGBTQ+となります。さらにsをつけると、複数形の意味が追加されるのでこちらも+とほぼ同じような意味合いとなります。
いずれも大きな違いはないため、状況に応じて使い分けるというよりは、LGBTQ+を使用しておくと安心です。
LGBTQ+の多様性とLGBTQ以外のセクシュアリティ
LGBTQ+という言葉は、多様な性の在り方を尊重する社会の象徴として広く知られるようになりました。もともとはL(レズビアン)、G(ゲイ)、B(バイセクシュアル)、T(トランスジェンダー)、Q(クィアまたはクエスチョニング)の頭文字から生まれた言葉ですが、現在ではその枠に収まらない、さらに多くのセクシュアリティやジェンダーが存在します。
LGBTQ+の「+」は、私たちが知っている以外にも、さまざまな性自認や性的指向があることを示しています。
| 用語 | 定義 | 特徴 | 該当する自己認識の例 |
|---|---|---|---|
| Xジェンダー | 男性・女性いずれにも属さない、または中間に位置すると感じる性自認 | 中性・両性・無性などと表現されることがある | 「男でも女でもない自分として生きたい」と感じる人 |
| アセクシュアル | 他者に対して恋愛的・性的な魅力を感じにくい、または感じない | 恋愛感情の有無も人により異なる(ロマンティック・スペクトラム) | 「恋愛に興味がない」「人を好きになることが少ない」と感じる人 |
| パンセクシュアル | 相手の性別にかかわらず、人としての魅力に惹かれる恋愛傾向 | 性別を恋愛対象の基準にしない | 「性別に関係なく惹かれる」「人間性を重視する」人 |
| ノンバイナリー | 「男性」「女性」のどちらにも明確に属さない性自認 | 性の二元論に縛られない柔軟な性の在り方 | 「男でも女でもない/両方ある」と感じる人 |
| デミセクシュアル | 強い信頼関係ができたときにのみ性的魅力を感じる | 関係性が恋愛感情の前提となる | 「深い絆がないと恋愛感情が芽生えない」と感じる人 |
| アロマンティック | 他者に対して恋愛感情を抱かない、または限定的である | 恋愛感情が希薄でも友情や絆は深く結べる | 「恋愛の気持ちが理解できない」と思う人 |
これにより、すべての人が自らの在り方を否定されずに生きられる社会を目指す姿勢が示されています。
代表的なセクシュアリティとジェンダー
「+」に含まれるアイデンティティの中でも、特に注目されているのがXジェンダー、アセクシュアル、パンセクシュアルです。Xジェンダーとは、男性や女性などの性別の枠に自分を当てはめない人々を指します。自分の性を「中性」や「両性」、「無性」などと表現することもあり、その捉え方は人によって異なります。
アセクシュアルは、他者に対して恋愛的または性的な魅力を感じにくい、あるいはまったく感じない傾向を持つ人を意味します。これもスペクトラムのように幅があり、恋愛感情は抱かないが性的欲求はある人もいれば、その逆も存在します。
パンセクシュアルは、相手の性別に関係なく、人としての魅力を感じて恋愛関係を築く人を指します。つまり「性別そのものを恋愛対象の判断基準にしない」あり方です。
これらの用語は一見すると複雑に感じるかもしれませんが、どれも「誰がどんなふうに自分自身を認識し、誰に惹かれるか」という問いに対する答え方の違いに過ぎません。知識を持つことが他者への理解と配慮の第一歩につながります。
セクシュアリティの4要素
性の多様性をより正確に理解するためには、「セクシュアリティの4要素」という考え方が効果的です。これは、人の性に関する特徴を以下の4つに分類して捉えます。
| 要素名 | 説明 | 例・補足 |
|---|---|---|
| ① 生物学的性(Sex) | 生まれたときの身体的特徴(外性器、染色体、ホルモンなど)をもとに割り当てられる性別 | ・男性、女性、インターセックス など |
| ② 性自認(Gender Identity) | 自分のことをどのような性だと感じるかという内面的な認識 | ・男性だと感じる・女性だと感じる ・どちらでもない など |
| ③ 性的指向(Sexual Orientation) | 恋愛感情・性的関心を向ける対象の性別 | ・異性愛(ヘテロ) ・同性愛(ゲイ、レズビアン) ・両性愛(バイ) ・全性愛(パンセクシュアル)など |
| ④ 性別表現(Gender Expression) | 言動・服装・しぐさなどを通じて他人に表す性のスタイル | ・フェミニン、マスキュリン、中性的 など |
1つ目は「生物学的性(Sex)」で、生まれたときに身体的な特徴をもとに割り当てられる性別です。2つ目は「性自認(Gender Identity)」で、自分のことを男性、女性、またはそれ以外と認識する内面的な感覚を指します。
3つ目は「性的指向(Sexual Orientation)」です。これは恋愛感情や性的関心をどの性別の人に抱くかを示すものであり、ゲイやレズビアン、バイセクシュアルなどが該当します。最後に4つ目の要素である「性別表現(Gender Expression)」は、服装や言葉遣い、振る舞いなどを通じて、周囲にどのような性を表現しているかを示す外的な特徴です。
これら4つの要素は相互に影響することもあれば、まったく異なる場合もあります。たとえば、生物学的には女性でも、性自認は男性であり、恋愛対象はすべての性別というケースもあります。人の性は単純なラベルで分類できるものではなく、多様で流動的である視点を持つことが大切です。
LGBTQ+を取り巻く課題・問題点
LGBTQ+の方々は、日常生活のさまざまな場面で困難や偏見に直面しています。近年では社会の理解が少しずつ進んでいるものの、まだ多くの人が自分の性のあり方を隠しながら生活しています。学校や職場、医療現場など、あらゆる環境で、当事者にとっての安心や尊重が十分に確保されているとは言えません。
こうした状況が続く背景には、誤解や無関心、制度の未整備などの複数の課題が存在します。また、本人の同意なしに性のあり方を暴露される「アウティング」など、精神的・社会的に深刻な影響をもたらす行為も後を絶ちません。LGBTQ+の人々が安心して生活できる社会を実現するためには、各分野の理解と制度の見直しが必要です。
学校・職場・医療現場での困難
教育や仕事、医療の場面では、LGBTQ+の人々が特有の困難に直面しています。学校では制服が男女の二択であることや、トイレ・更衣室の利用制限により、トランスジェンダーの生徒が不安や孤立感を抱えることがあります。クラス内での無意識な差別的言動も、大きな心理的負担を与えています。
職場でも、異性愛を前提とした雑談や「男性らしさ」「女性らしさ」などの価値観が、当事者にとっては苦痛となることがあります。性のあり方を周囲に明かせないまま働き続けることで、精神的な消耗やキャリアへの悪影響が生じるケースもみられます。
医療現場では、性別欄の記載や診療の扱いに戸惑う例が多く、必要な医療を安心して受けられない現実があります。性別適合手術やホルモン治療に関して、十分な理解を持つ医師が限られていることも問題の一つです。
アウティングとカミングアウトの違い
カミングアウトとは、本人が自らの意思で性自認や性的指向を伝えることを指します。対してアウティングは、当事者の了承なく他人が情報を第三者に伝えてしまう行為です。この違いを正確に理解していないことで、悪意のない一言が深刻な人権侵害につながる恐れがあります。
「冗談のつもりだった」「みんな知っていると思った」という軽い気持ちで情報を拡散することが、当事者にとっては大きなダメージとなることがあります。アウティングは、いじめや社会的孤立、さらには進学や就職への影響など、当事者の人生に深刻な影響を与えかねません。
他人のプライバシーに関わることは、どれほど親しい関係であっても、本人の同意を得ない限り絶対に口外すべきではありません。この意識を社会全体で共有していくことが大切です。
割合や調査結果からみる現状
LGBTQ+に関する理解は進みつつありますが、統計データからは、依然として多くの人々が困難な状況に置かれていることが明らかになっています。
2024年にアメリカのギャラップ社が実施した調査では、成人の約9.3%がLGBTQ+であると回答し、特に20代ではその割合が20%を超えました。
一方、日本では明確な国勢調査は行われていませんが、NHKや内閣府の資料では、全体の約5〜8%が該当する推計があります。ただし、実際にはカミングアウトできていない人も多く、表面に出ている数字は氷山の一角であるとも言われています。
こうしたデータをもとに、教育機関や企業、行政が現実を見つめ、制度や支援体制を整えることが求められます。理解を深めることは、すべての人にとって生きやすい社会をつくる第一歩です。
LGBTQ+に関連する日本の法律
LGBTQ+に関連する日本の法律を一部ご紹介します。
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(LGBT理解増進法)
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(LGBT理解増進法)は、2023年6月に制定された法律です。
その名の通り性的指向やジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるための法律です。理解増進のための法律なので、そのための施策を国や公共団体へ実施することを求めています。
他にも事業者などに求めるためにも必要な法律ですが、問題点もありあくまでも理解増進のための法律なので、実効性があるのかと不安に感じている当事者も多い法律です。
パートナーシップ制度
パートナーシップ制度は、2024年6月の時点で多くの市区町村が、同性のパートナーシップ(同性カップル)を公的に認める制度のことです。
パートナーシップ制度を利用してできることは、病院などで家族と同等の扱いを希望できたり、生命保険の受取人に設定できたりと、様々あります。
ただあくまでも各自治体が制定している制度なので、法的な拘束力はありません。異性の夫婦と異なる部分もあり、相続や社会保障など法的な保護は十分ではありません。
LGBTQ+アライ・フレンドリーな社会をつくるには
LGBTQ+の人々が安心して暮らせる社会を実現するためには、周囲の理解と協力が不可欠です。その中心的な存在となるのが「アライ(Ally)」と呼ばれる支援者です。アライは、LGBTQ+当事者ではないものの、多様な性のあり方を尊重し、偏見のない社会づくりに積極的に関わる人のことを指します。アライの存在が広がれば、当事者の孤立感を減らし、自分らしく生きられる環境を整えることができます。
また、LGBTQ+に配慮した企業や施設の増加も大切な要素です。職場や地域、学校など、さまざまな場面で「誰もが安心できる環境」を整える取り組みが求められています。
アライの定義と行動例
アライとは、LGBTQ+の理解者として支援の姿勢を示す人のことを指しますが、ただ「理解する」だけではなく、行動を伴うことが大切です。たとえば、差別的な発言を見かけたときに黙認せず注意すること、性自認に応じた呼称を尊重すること、自分の周囲で偏見を減らす努力をすることが挙げられます。
また、LGBTQ+に関する正しい情報を自ら学び、偏見を持たない姿勢を育むことも欠かせません。身近な存在として寄り添いながら、社会全体に理解の輪を広げていくことが、アライに求められる役割です。
LGBTQ+フレンドリーな企業・施設の特徴
LGBTQ+フレンドリーな環境を整える企業や施設では、具体的な制度や設備が導入されています。たとえば、性別にとらわれない多目的トイレや更衣室の設置、同性パートナーへの福利厚生の適用、LGBTQ+研修の実施などが代表例です。
こうした取り組みによって、当事者が不安や不快感を抱かずに過ごせる職場環境が生まれます。制度の整備だけでなく、日常の接し方にも配慮が行き届いているかが問われる時代になっています。
LGBTQ+に関する診断・セルフチェックの活用
自身の性自認や性的指向を考えたいと感じたとき、インターネット上で「LGBTQ+診断」や「セクシュアリティ診断」を検索する人が増えています。こうしたセルフチェックツールは、内面の違和感や戸惑いに気付き、自分の感情を整理するきっかけとして一定の役割を果たしています。特に若年層にとっては、自分のことばで説明しにくい気持ちを言語化する手助けになる場合もあります。
ただし、LGBTQ+診断はあくまでも簡易的な参考情報であり、診断結果がその人のすべてを決定するものではありません。質問に答える形式で提示される結果は、心理的な傾向や関心を示す目安に過ぎず、専門的なカウンセリングや医療的評価とは異なる性質を持ちます。結果だけに依存せず、自分自身の気持ちや経験を大切にしながら、ゆっくりと理解を深めていくことが大切です。
LGBTQ+診断とは?その意味と使い方
LGBTQ+診断とは、性のあり方を自己理解を深めるために設計されたオンライン形式のセルフチェックです。質問内容に答えることで、性的指向や性自認に関する傾向を知るきっかけになります。匿名で気軽に試せることから、インターネット上では多くの人が利用しています。
ただし、こうした診断は一つの指標に過ぎません。診断結果を受けて「自分はこうでなければならない」と思い込んだり、不安を感じすぎたりすることのないよう注意が必要です。多様な性の在り方は流動的であり、一人ひとりのペースで理解を深めていく姿勢が尊重されるべきです。
LGBTQ+診断に対する信頼できる情報源と支援
セルフチェックを受けたあと、心に引っかかる感情や疑問を抱いたときは、一人で悩まず、信頼できる情報源に触れたり相談機関を活用したりすることをおすすめします。たとえば、LGBTQ+に関する啓発活動を行う認定NPO法人や、自治体が設置している相談窓口では、当事者や支援者からの声をもとに情報提供やサポートが行われています。
また、個人のSNSや匿名掲示板だけに頼るのではなく、正確な知識を得るには公的機関や専門団体の情報を参考にすることが大切です。心のモヤモヤに寄り添ってくれる存在がいることは、自分を否定せずにいられる安心感へとつながっていきます。
LGBTQ+の割合と統計から見る現実
近年、LGBTQ+に対する関心が世界的に高まっており、どれほどの人が性的マイノリティとして自身を認識しているのかにも注目が集まっています。日本と海外では、割合の数値だけでなく、社会的背景や文化の違いにも注目する必要があります。ここでは、日本と海外の調査結果を比較しながら、その背景にある社会の変化を考えていきます。
日本・海外のLGBTQ+人口の割合
日本と海外では、LGBTQ+を自認する人の割合に違いがみられますが、その背景には調査方法やカミングアウトのしやすさなど、社会的条件の違いも影響しています。以下に、それぞれの状況を整理してみましょう。
日本のLGBTQ+人口の割合
日本で、LGBTQ+に該当すると回答する人の割合は、民間調査を中心に明らかになってきています。たとえば、電通が2020年に実施した全国調査では、「8.9%」の人が自らをLGBTQ+と認識していることが示されました。これはおおよそ11人に1人という割合であり、決して少数とはいえません。
また、NHKハートネットが紹介しているように、若年層の自己認識の割合はさらに高くなる傾向があります。10代から20代では、性の多様性を前提とした価値観がより強くなっており、自分の性自認や性的指向を積極的に表明する傾向が強まっています。これは、教育現場やSNSなどで多様性を認める意識が広がっていることの表れです。
海外のLGBTQ+人口の割合
一方、海外では統計データの整備が進んでおり、具体的な数字をもとに社会の変化を読み取ることが可能です。アメリカの世論調査機関ギャラップ社が2024年に発表した調査では、成人の約9.3%が自らをLGBTQ+と認識していることが報告されました。特に20代では、その割合が20%以上に達している結果もありました。
この背景には、社会全体の包摂性が進み、性的マイノリティが可視化されやすくなったことがあると考えられます。また、カナダやイギリスでも同様に約10%前後の人々がLGBTQ+を自認しているとされており、各国で性の多様性への理解が進展している様子がうかがえます。
割合の増加が示す社会の変化
LGBTQ+人口の割合が増えていることには、単なる統計的な意味以上の社会的意義が含まれています。これは、LGBTQ+の人々が「増えた」というよりも、声を上げやすくなった、あるいは社会が多様な性を認めるようになった結果です。
過去には、周囲の理解不足や偏見から、自分の性を語ることができず、沈黙を選ばざるを得なかった人が少なくありませんでした。しかし、現在ではメディアや教育機関、企業などの働きかけにより、性の多様性を受け入れる文化が少しずつ形成されてきています。
特に若年層の間では、自身のアイデンティティを肯定的に捉えることが一般的になりつつあり、調査に正直に回答する人が増えたことが、割合の上昇に影響していると考えられます。このように、LGBTQ+の割合が示す数字は、単なる数値ではなく、社会の成熟度や意識変化を表す鏡でもあります。
LGBTQ+を支援する団体・制度・相談先
LGBTQ+の方々が自分らしく暮らすには、理解ある社会だけでなく、必要なときに相談できる制度や団体の存在が大切です。近年では、性的マイノリティの声に寄り添う支援体制が少しずつ整いつつあります。この項目では、主な支援団体と、行政による取り組みをご紹介します。
主な支援団体とその活動内容
LGBTQ+の支援を目的とした団体は、全国各地で活動しています。なかでも「プライドハウス東京」は、誰もが安心して立ち寄れる常設施設を運営し、相談や交流の場を提供しています。イベントやセミナーも定期的に開催しており、当事者だけでなく、周囲の人も参加できる内容となっています。
また、「にじいろ学校」は、LGBTQ+の若者に向けた教育やメンタルサポートを実施しています。家庭や学校で孤立しがちな子どもたちにとって、安心して自分を語れる場所は大きな心の支えとなっています。こうした団体は、公式サイトなどを通じて相談先の案内も行っており、住んでいる地域に関係なく利用が可能です。
行政の窓口・相談制度
行政でもLGBTQ+に関する相談体制の整備が進んでいます。たとえば、東京都や札幌市では、同性カップルの関係を公的に認めるパートナーシップ宣誓制度を導入しています。この制度により、住居の契約や病院での対応など、生活のさまざまな場面で配慮が広がっています。
また、都道府県や市区町村によっては、多様性推進課や男女共同参画センターが相談窓口を設けており、電話やメールでの相談が可能です。具体的な支援内容や利用方法は自治体ごとに異なるため、詳細は公式ホームページを確認するとよいでしょう。
LGBTQ+の方との関わり方・私たちにできること
LGBTQ+の方々と共に暮らしていくうえで、最も大切なのは「特別扱い」ではなく「対等な理解」です。私たち一人ひとりが多様な性のあり方を知り、他者の尊厳を認める姿勢を持つことが、差別のない社会への第一歩につながります。
LGBTQ+の知識が乏しい場合、無意識のうちに当事者を傷つけてしまうことがあります。たとえば、性別に関する決めつけや不用意な質問、カミングアウトの強要などは、その人の心に深い傷を残すおそれがあります。大切なのは、相手の背景を理解しようとする姿勢と、何気ない言葉の選び方に注意を払うことです。
また、LGBTQ+の方への理解を深めたいと考える人は「アライ(Ally)」として行動することが求められています。アライとは、当事者ではない立場であっても、その権利を擁護し、共に差別のない社会を目指す支援者のことです。日常の中で多様性に配慮した発言を心がけたり、LGBTQ+に関する啓発イベントに参加したりすることも、アライとしての取り組みの一つです。
支援が必要な方にとって、相談できる窓口があることは大きな支えになります。NHKハートネットでは、全国の支援団体や相談機関の情報が掲載されており、電話やオンラインでの対応が可能な団体も紹介されています。誰かの悩みを受け止めるために、こうした公的な情報を事前に知っておくことも、私たちにできる行動のひとつです。
LGBTQ+とSDGsの関係性
LGBTQ+に関する課題は、国際社会が共有する持続可能な開発目標(SDGs)とも密接に関わっています。中でも「ジェンダー平等」や「不平等の解消」は、LGBTQ+の尊厳や権利を守るうえで不可欠な視点です。
目標5「ジェンダー平等を実現しよう」
この目標は、すべての人が性別にかかわらず、平等な機会を持つ社会をつくることを目的としています。LGBTQ+の方々は、性自認や性的指向により差別や不利益を受けやすい状況にあり、法的な保護や制度の整備が不十分な国も少なくありません。性の多様性を前提とした政策や教育がなければ、真のジェンダー平等は実現できないです。
目標10「人や国の不平等をなくそう」
この目標では、貧困や障がい、人種、性的指向などの属性による差別や排除をなくし、すべての人に平等な社会参加の機会を与えることが求められています。たとえば、同性カップルが法律上の家族として認められなかったり、トランスジェンダーの方が就職や医療で不利な扱いを受けたりするなど、LGBTQ+当事者の生活には依然としてさまざまな障壁があります。これらを解消する取り組みが、目標10の達成につながります。
LGBTQ+に関するよくある質問
LGBTQ+という言葉が日常に浸透しつつある一方で、社会にはまだ多くの疑問や誤解が残されています。ここでは、性の多様性にまつわる代表的な質問を取り上げ解説していきます。
Qは「クィア」?それとも「クエスチョニング」?
LGBTQ+の「Q」は、「Queer(クィア)」または「Questioning(クエスチョニング)」の頭文字です。
「クィア」は性自認や性的指向が伝統的な枠組みに当てはまらない人々が使うことが多く、「クエスチョニング」は自分自身の性の在り方を探している途中の人を指します。どちらも自己表現のひとつであり、個人が使いやすいほうを選ぶことが大切です。
カミングアウトはいつ、どのようにすべき?
カミングアウトのタイミングや方法は人それぞれです。無理に言う必要はありませんし、必ずしも周囲に伝えることが義務でもありません。安全と信頼が確保されていると感じたときに、自らの意志で行うことが望ましいとされています。
また、カミングアウトを受ける側も、驚きよりも「聞かせてくれてありがとう」という姿勢が求められます。
LGBTQ+に該当しないと支援してはいけない?
そんなことはありません。LGBTQ+当事者でなくとも、「アライ(Ally)」として支援の輪に加わることは可能です。
アライとは、差別や偏見のない社会を共につくる協力者のことです。正しい情報を学び、偏見のない言動を心がけること自体が、すでに立派な支援です。イベントへの参加や、日常会話の中で多様性を尊重する態度を持つことも、アライの一歩になります。
LGBTQ+の割合はどれくらいですか?
割合は国や世代によって異なりますが、日本ではおよそ8~10%の人がLGBTQ+に該当すると推定されています。
アメリカでは、2024年のギャラップ社の調査で、成人全体の約9.3%がLGBTQ+を自認していると結果が出ました。特に20代ではその割合が約2割と高く、若い世代ほど性の多様性に対する認識と自己表現が進んでいることが読み取れます。
子どもにLGBTQ+を教えるのは早すぎるのでは?
性の多様性を知ることは、思いやりや他者理解を育む教育の一環です。年齢に応じた言葉や表現を用いれば、子どもでも理解できる範囲があります。無理に教えるのではなく、相手の「ちがい」を尊重する大切さを伝えることが大切です。
実際に、学校現場でもSOGI(性のあり方)に配慮した授業が少しずつ広まり始めています。
まとめ
LGBTQ+は特別な誰かの問題ではなく、私たち一人ひとりの社会意識と深く結び付いています。性の在り方に正解はなく、多様性を認め合う姿勢が今の時代には必要とされています。
正しい知識を持ち、身近な違いに対して寛容でいること。それが、誰もが尊重される社会をつくる第一歩です。小さな理解の積み重ねが、よりよい未来につながっていきます。
参考:LGBTQ+とは | 特定非営利活動法人東京レインボープライド
参考:LGBTQを知ろう|春日井市公式ホームページ
参考:【解説記事】「LGBTQ+」とは|Stories|協和キリン
参考:LGBTQ+ | NHK ハートネット
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS