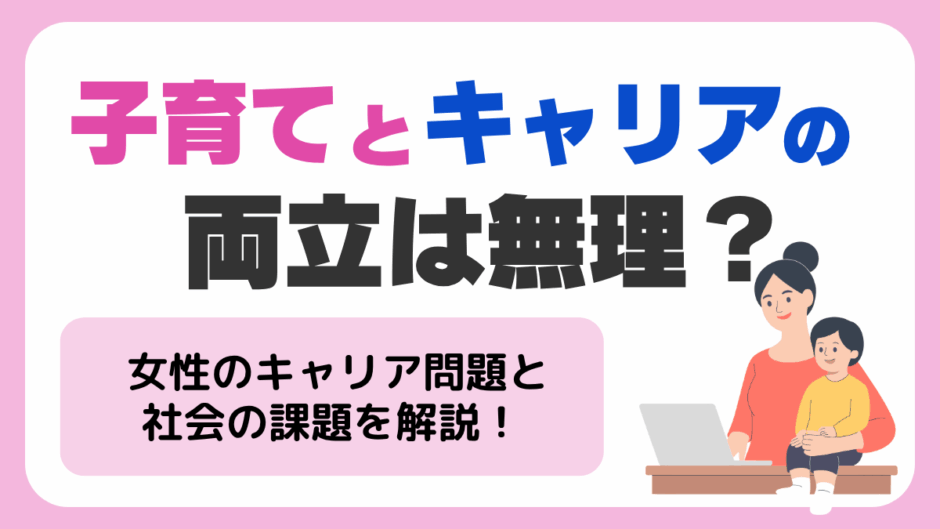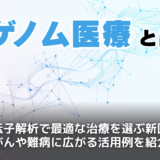育児とキャリアの両立は、多くの家庭が直面する大きなテーマです。かつては「母親が育児、父親が仕事」という固定的な役割分担が主流でしたが、今では共働き世帯の増加や男性育休の普及、働き方改革の広がりによって、家庭と仕事の在り方は多様化しています。しかし現実には、長時間労働や保育環境の不備、家事・育児の負担偏りといった壁に悩む人も少なくありません。
本記事では、育児とキャリアを両立させるために知っておきたい社会的背景や課題、そして実践的な解決策を整理し、公的制度や企業の支援まで幅広く紹介します。家庭もキャリアも諦めず、未来につながる働き方を一緒に考えていきましょう。
育児とキャリアの両立とは?現代の新しいスタイルへ

育児とキャリアの両立は、女性だけの課題ではなく、男性も共に担う時代へと移り変わっています。家庭の形が多様化し、働き方もリモートワークや柔軟な制度が広がる中で、その本質は「家庭と仕事を無理なく調和させること」にあります。
育児とキャリアの両立の概念とは?
「育児とキャリアの両立」とは、単に仕事と子育てを同時進行でこなすことではありません。家庭では子どもと向き合い、職場では成果を出しながら、それぞれの領域で充実感を得て継続していく姿勢を指します。
かつては「家庭か仕事か」という二者択一の考え方が一般的で、特に女性に課題が集中しがちでした。しかし現代では、男性育休の普及や多様化する働き方の選択肢が広がり、両立はすべての働く親に共通するテーマとなっています。柔軟な働き方の導入や支援制度の整備により、「家庭もキャリアも大切にする」という価値観が浸透しつつあるのです。
育児とキャリアの両立とは、役割の押し付けや制約を超えて、自分らしい働き方と生活のバランスを追求する新しいスタイルへと進化しているといえます。柔軟な働き方や支援制度を取り入れながら、誰もが自分らしい両立のスタイルを築いていける社会が求められています。
家庭と働き方の多様化が生む、さまざまな両立スタイル
現代の家庭は共働きやひとり親、事実婚、ステップファミリーなど多様化しており、その背景によって「育児とキャリアの両立」の形も変わります。例えば、夫婦でフルタイム勤務をし保育園や学童を活用するケース、一方が在宅ワークを中心に家庭を支えるケース、シングルマザーやシングルファーザーが収入確保と育児を同時に担うケースなどがあります。さらに働き方も正社員だけでなく、フリーランス、パート、リモートワーク、時短勤務など多岐にわたります。リモートワークなら通勤時間を育児に充てられ、時短勤務は保育園のお迎えに間に合うなど具体的なメリットがあります。一方でフリーランスは時間の自由度が高い反面、収入の不安定さが課題になることもあります。
このように家庭環境と働き方の組み合わせによって、多様な両立スタイルが生まれているのです。
育児とキャリアの両立を取り巻く日本社会の現状
日本社会では共働き世帯の増加や男性の育児参加が進み、多様な家庭の姿が広がっています。しかし現実には、制度や意識の遅れから理想とのギャップが大きく、両立の難しさが浮き彫りになっています。
ここからは、具体的なデータを通して日本社会の育児とキャリアの両立の現状を見ていきます。
増える共働き・男性育休から見る育児とキャリアの両立
近年、日本では共働き世帯が主流となり、育児とキャリアの両立は社会全体にとって大きなテーマとなっています。厚生労働省が2024年8月に公表した「令和6年版厚生労働白書」によれば、2021年には共働き世帯が1247万世帯に達し、専業主婦世帯(566万世帯)を大きく上回りました。このデータは、経済的理由だけでなく、多様な働き方を求める人々の意識の変化を反映しています。
また、男性の育児参加も拡大しており、「令和5年度雇用均等基本調査」によると、2023年度の男性育児休業取得率は過去最高の30.1%に到達しました。前年度から大幅に増加したこの数値は、男性自身の育児への積極性に加え、企業の制度整備や社会全体の理解が進んできた証拠といえます。
共働きの増加と男性育休の広がりにより、家庭もキャリアも諦めない柔軟な働き方の実現が現実的なものとなりつつあります。
参考:令和6年版厚生労働白書-こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に-(本文)
参考:令和5年度雇用均等基本調査|厚生労働省
シングル・多様な家庭の育児とキャリアの両立事情
日本ではシングル家庭も増加しており、その多くが育児とキャリアの両立を日常的に実践しています。厚生労働省「全国ひとり親世帯等調査」によると、母子世帯の母親の就業率は86.3%、父子世帯の父親の就業率は88.1%に達しており、世界的に見ても高い水準です。
しかし、シングルマザーやシングルファーザーは経済的負担や時間的制約、精神的孤立といった特有の課題を抱えています。日中に子どもを預ける先が見つからない、常に収入面への不安を抱えるなど、支援制度の利用や柔軟な働き方の選択が不可欠です。
さらに、事実婚や再婚家庭、LGBTQ+カップルなど多様な家族の形でも、それぞれの「両立」の工夫が求められています。例えば、周囲の理解が得られにくいことや法的な制度が追いついていない現状が課題となるケースも少なくありません。
社会が多様な家庭を前提に制度や支援を整えることが、誰もが安心して育児とキャリアを両立できる社会の実現につながります。
働く親たちが直面する理想と現実
「育児とキャリアの両立」を目指す多くの親は、仕事も家庭も完璧にこなしたいという理想を抱きます。理想では夫婦が協力し、家事や育児を公平に分担しながら、それぞれがキャリアを諦めずに進めていくことです。しかし現実には、長時間労働や業務の忙しさから家事負担が妻に偏りがちで、均等な分担は難しい状況が続いています。さらに、子どもの急な発熱や保育園からの呼び出しで仕事を中断せざるを得ない場面も多く、職場で肩身が狭い思いをする人も少なくありません。
こうした「理想」と「現実」のギャップは、親に強いストレスや葛藤をもたらします。柔軟な働き方や支援制度の利用が広がっている一方で、依然として現場では限界を感じるケースが多く、誰もが安心して両立できる環境整備が今後さらに求められているのです。
なぜ今、育児とキャリアの両立が求められるのか?
育児とキャリアの両立は、少子高齢化による労働力不足や家計の安定、さらには個人の自己実現の観点からも社会全体で注目されています。
ここでは、育児とキャリアの両立が社会的に求められる理由を解説します。
少子高齢化・労働力不足と社会的背景
日本では少子高齢化が急速に進み、生産年齢人口の減少が深刻な労働力不足を引き起こしています。15〜64歳の生産年齢人口は年々減少しており、このままでは企業や社会全体の持続的な成長に影響を及ぼすと懸念されています。この状況を打開するためには、女性だけでなく男性も含め、あらゆる世代の国民が労働力として活躍できる仕組みづくりが求められます。その中で「育児とキャリアの両立」を可能にする支援制度や柔軟な働き方は不可欠です。
さらに、人生100年時代と呼ばれる現代では、長く働き続けることが経済的にも精神的にも重要になっています。育児によるキャリアの中断や停滞を最小限に抑えることは、個人の安定や自己実現につながるだけでなく、社会全体の人材確保や持続的な発展にも大きなメリットをもたらすのです。
個人の自己実現
育児とキャリアの両立が求められる背景には、働く親自身の「自己実現」への思いがあります。子どもとの時間を大切にしたい一方で、仕事を通じて自分の能力を発揮し、成長や達成感を得たいと考える人は少なくありません。社会とのつながりを持ち続けたい、自分の専門性を磨きたい、キャリアアップを諦めたくないといった思いが強く、これらは単なる収入確保にとどまらない大きなモチベーションになっています。
柔軟な働き方や支援制度の整備は、親が家庭とキャリアを両立しつつ、自分らしく生きるための基盤であり、自己実現を叶える上で欠かせない要素となっているのです。
家計安定の必要性
育児とキャリアの両立が求められる大きな理由の一つに、家計の安定があります。現代社会では子どもの教育費や住宅ローン、さらには老後資金の準備まで、長期的に大きな支出が見込まれます。収入が一馬力の場合、病気や転職といった予期せぬリスクに直面すると家計が不安定になりやすいですが、共働きであれば収入源を分散でき、生活の安定性が高まります。
また、働き続けることで教育費を十分に確保でき、子どもの進学や習い事など将来の選択肢を広げることが可能です。さらに、夫婦それぞれがキャリアを築くことで老後に受け取れる年金額も増え、将来的な安心感につながります。
育児とキャリアの両立は、個人の働き方やライフスタイルの選択だけでなく、経済的に持続可能な暮らしを実現するための重要な手段です。
企業の人材確保とダイバーシティの推進
企業にとって、育児とキャリアの両立を支援することは人材確保の観点から欠かせない取り組みです。特に優秀な人材ほど家庭と仕事のバランスを重視する傾向が強く、両立を支える制度や環境が整っていない企業では、転職や離職につながるリスクが高まります。逆に、在宅勤務や時短勤務など柔軟な働き方を導入することで、社員が安心して長く働ける環境を提供でき、人材の流出を防ぎ採用コストの削減にも直結します。
また、多様なライフスタイルを尊重するダイバーシティ&インクルージョンの推進は、社員のモチベーション向上だけでなく、企業の競争力を高める効果もあります。例えば、育児中の社員が抱える課題やニーズを商品やサービスに反映させることで新しい市場が生まれるケースもあり、結果として企業ブランドの向上や優秀な人材の獲得につながるのです。
育児とキャリアの両立を阻む課題
育児とキャリアの両立を目指す中で、多くの親が長時間労働や柔軟な働き方の不足、家事・育児負担の偏り、さらに保育など社会的サポート体制の不備などの障壁に直面しています。
長時間労働・柔軟な働き方の不足
日本社会では長時間労働が常態化しており、これが育児とキャリアの両立を難しくする大きな要因となっています。残業が前提の働き方では、保育園のお迎えに間に合わなかったり、子どもの寝顔しか見られない生活に陥りやすく、家庭との時間が犠牲になりがちです。本来はフレックスタイム制や在宅勤務、時短勤務といった柔軟な働き方が両立の支えとなるはずですが、導入が遅れている企業も多く見られます。
さらに、制度自体が存在しても「使いにくい雰囲気」や「周囲への遠慮」から実際には活用されず、形骸化している場合も少なくありません。このような状況では社員のモチベーションやキャリア形成にも悪影響を及ぼし、結果として離職や転職につながるリスクが高まります。
育児とキャリアの両立を現実的に進めるためには、長時間労働を是正し、制度を実効性のある形で運用できる環境づくりが必要不可欠です。
家事・育児負担の偏りとマミートラック
育児とキャリアの両立を阻む要因の一つが、家庭における家事・育児負担の偏りです。特に日本では、依然として女性が大半の役割を担うケースが多く見られます。例えば、夫の残業が多く育児を任せられない、家事全般が妻に集中してしまうといった状況は、女性の自由時間やキャリア形成に直接的な影響を及ぼします。結果として、昇進やスキルアップに必要な学習・挑戦の機会を失いやすくなります。
さらに、出産や育児を機に女性が「マミートラック」と呼ばれる立場に置かれる現状も問題です。これは、責任の少ない定型業務に回されることで昇進ルートから外され、キャリアの停滞を余儀なくされる状況を指します。こうした不平等は、個人の意欲低下だけでなく、企業全体にとっても人材の有効活用を妨げる大きな課題です。
保育インフラ・サポート体制の不足
育児とキャリアの両立を阻む大きな壁の一つが、保育インフラやサポート体制の不足です。都市部では待機児童の問題が長年解消されず、希望する保育園に入れないことで、仕事復帰や働き方の選択肢が大きく制限されます。また、地方では施設そのものが少なく、通園に長時間を要するケースもあります。さらに、病児保育や一時預かりといった柔軟なサービスが十分に整っていないと、子どもの急な発熱や行事に対応できず、親が仕事を休まざるを得ない状況に陥ります。
こうした環境は特に母親のキャリア形成に影響を与えやすく、転職や時短勤務を余儀なくされることも少なくありません。保育の充実は個人だけでなく社会全体の課題であり、企業と行政が協力して解決に取り組む必要があります。
育児とキャリアの両立を実現するための解決策
育児とキャリアの両立を実現するためには、個人の工夫に加え、家族との協力や外部サービスの利用が不可欠です。さらに柔軟な働き方やスキルアップ、副業など多様なキャリア形成の可能性にも注目が集まっています。
フレックス制・在宅勤務・時短勤務の活用
育児とキャリアの両立を実現するためには、フレックス制や在宅勤務、時短勤務といった柔軟な働き方の活用が欠かせません。フレックスタイム制を取り入れることで、子どもの送迎や習い事、病院受診などに合わせた働き方が可能になります。例えば、朝のコアタイムを避けて出勤し子どもと過ごす時間を確保したり、午後の早い時間に退社して迎えに行くといった調整ができます。在宅勤務は通勤時間を削減できるだけでなく、子どもの急な体調不良にも対応しやすい点が大きなメリットです。その際には集中できる作業環境を整え、オンとオフを切り替えるルールを持つことが効果的です。
また、時短勤務を利用する場合には、限られた時間で成果を出すためにタスク管理を徹底し、チームメンバーとの情報共有を積極的に行うことが重要です。
こうした柔軟な働き方の工夫は、家庭を大切にしながらキャリアを継続する大きな支えとなります。
家族・パートナーとの協力・役割分担
育児とキャリアの両立を実現するためには、家族やパートナーとの協力体制が欠かせません。まず役割分担を明確にするために、育児・家事分担表を作成するのがおすすめです。お互いの得意・不得意を考慮して担当を決め、定期的に見直しを行うことで不公平感を減らし、持続可能な協力関係を築けます。
また、パートナーの育児参加を促すには、メリットを共有することが有効です。例えば、子どもの成長を間近で感じられる、家庭への信頼が深まるといった効果を伝えると前向きになりやすいでしょう。
さらに、男性育休を取得した事例では、夫婦双方がキャリアを維持しやすくなり、家事や育児の分担も自然と進むケースが多く見られます。妻が積極的に育児を任せてみることで、夫の主体的な参加を促すことも可能です。
このような工夫が、家庭内の協力体制を強化し、育児とキャリアの両立を支える基盤となります。
外部サービスの利用
育児とキャリアの両立を支える手段として、外部サービスの活用は大きな助けになります。例えば、ベビーシッターは保育園の延長保育が利用できない時間帯や、夜間の急な用事の際に心強い存在です。病児保育は子どもが体調を崩したときでも安心して仕事を続けられるサポートであり、一時預かりは保護者のリフレッシュや突発的な予定に対応できます。さらに、家事代行サービスを利用すれば、料理・掃除・洗濯といった日常的な負担を軽減でき、親が子どもと過ごす時間や自分のキャリア形成に集中する余裕が生まれます。
こうした外部リソースを柔軟に取り入れることは、仕事と家庭のバランスをとるうえで効果的です。経済的な負担との兼ね合いを考えつつも、必要に応じて頼ることが、育児とキャリアの両立を長期的に持続させる大切な工夫となります。
スキルアップ・副業の実践
育児とキャリアの両立を持続させるためには、日々の限られた時間を活用してスキルアップに取り組むことが重要です。例えば、子どもが寝た後の数時間をオンライン講座や資格取得の学習に充てる、育休中にキャリアカウンセリングを受けて復帰後のキャリアプランを整理するといった工夫が効果的です。こうした取り組みはキャリア停滞を防ぎ、復帰後の選択肢を広げる助けになります。
また、副業や在宅ワークも有効な手段です。収入源の多様化につながるだけでなく、新たなスキル習得や実務経験の場となり、本業に活かせる知識を得られることも多いです。特にフリーランス案件やオンライン業務は柔軟に取り組めるため、子育てとの両立に適しています。小さな積み重ねが将来のキャリア形成につながり、安心して働き続ける土台を作るのです。
育児とキャリアの両立を支援する公的・民間サービス
育児とキャリアの両立を後押しするためには、公的な制度や行政のサポートだけでなく、NPOや企業の独自サービスも重要です。多様な支援を知り、上手に活用することが両立を実現させる鍵となります。
育児とキャリアの両立を支える国の支援
国は「育児とキャリアの両立」を後押しするために、複数の支援制度を用意しています。代表的なものとして、育児休業給付金があります。これは雇用保険の被保険者が1歳未満の子を養育する目的で育児休業を取得した際に支給される手当で、休業中の収入減を補う役割を担います。次に、出産育児一時金は、被保険者またはその扶養家族が出産したときに支給され、出産費用の負担を軽減する目的で設けられています。また、児童手当は0歳から18歳の子どもを養育している家庭に給付され、日々の養育費や教育費を支える制度です。これらは利用条件があり、勤務先の就業形態や加入している保険制度によって受給可否が異なります。
いずれも家庭の経済的負担を和らげ、安心して育児に向き合えるようにするための重要な仕組みであり、活用することでキャリアを諦めずに働き続けられる環境を整えられます。
行政の支援制度・相談窓口
行政も「育児とキャリアの両立」を支えるために多様な制度や相談窓口を用意しています。例えば、東京都では病児保育の利用料を一部助成する制度があり、急な子どもの体調不良にも柔軟に対応できるようになっています。また、多胎児家庭向けにはおむつやミルクの購入費助成、訪問支援サービスなど特化したサポートが設けられている自治体もあります。さらに、全国の子育て支援センターや母子保健センターでは、保育や発達に関する悩みを気軽に相談でき、専門職によるアドバイスや地域の支援情報を得ることが可能です。
これらの相談窓口は無料で利用できるケースが多く、孤立しがちな育児期に心強い存在となります。行政の支援は地域ごとに特色があるため、自分の住む自治体の制度を確認し、積極的に活用することが両立をスムーズにする鍵となります。
NPOの取り組み
NPO法人も「育児とキャリアの両立」を後押しする重要な存在です。例えば、子育て世帯を対象にしたキャリアカウンセリングや、育休中・復職前のスキルアップ講座を実施する団体があります。また、地域の子育てサロンや一時預かりを提供し、働く親が安心して仕事に専念できるよう支援しています。
近年では、男性育休の取得を促すためのセミナーや企業向け研修を行うNPOも増えており、家庭内の役割分担や働き方の多様化を広げる役割を担っています。
さらに、情報発信や相談窓口を通じて、孤立しがちな親の悩みに寄り添い、行政や企業と連携しながら包括的なサポート体制を整えているのも特徴です。
こうしたNPOの取り組みを活用することで、公的支援や企業制度だけではカバーしきれない柔軟なサポートを得られ、両立への不安を大きく軽減できます。
企業の育児とキャリアの両立支援制度
企業が導入する支援制度は、育児とキャリアの両立を現実的に後押しする重要な仕組みです。代表的なものには、在宅勤務やフレックスタイム制、短時間勤務といった柔軟な働き方を可能にする制度があります。
さらに、企業独自に病児保育やベビーシッターの費用補助、社内託児所の設置を行うケースも増えており、子育て世帯にとって大きな安心材料となります。近年は男性育休の取得促進にも積極的な企業が増え、夫婦間での役割分担や働き方の多様化を実現しやすい環境が整いつつあります。また、復職支援研修やキャリア相談窓口を設け、育休明けの社員がスムーズに職場復帰できるようサポートする取り組みも進んでいます。
こうした制度を整備することで従業員の定着率や満足度が高まり、人材確保にもつながる点が大きなメリットです。
育児とキャリアの両立のよくある質問
育児とキャリアの両立を目指す中で、悩みや疑問を抱える方も多いでしょう。転職や職場での交渉方法、キャリア再構築の進め方など、実践的なヒントをQ&A形式で解説していきます。
Q1. 育児とキャリアの両立を考えたとき、転職は有効な選択肢ですか?
転職は「育児とキャリアの両立」を実現するための有効な選択肢になり得ます。特に、現職で柔軟な働き方制度が整っていない、また改善の見込みが薄い場合は、より育児支援に積極的な企業へ移ることで両立がしやすくなるでしょう。
ただし、焦って転職を決断すると、かえってサポートが手薄な職場へ移ってしまい状況が悪化する可能性もあります。現職での交渉や制度の活用をまず検討し、転職は慎重に判断することが大切です。
Q2. 両立のために職場でどんな交渉をすればよいですか?
育児とキャリアの両立を進めるには、職場での交渉が重要です。まずはフレックス制や在宅勤務、時短勤務など既存制度の利用可否を確認し、自分の状況に合わせて具体的に相談しましょう。業務内容や担当範囲を整理し、効率的に成果を出せる働き方を提案することも効果的です。
また、同僚や上司に業務共有の仕組みを依頼し、育児による急な休みにも対応できる体制を整えることで安心感が増します。
Q3. 育児中、また子どもが成長した後のキャリア再構築はどう進めるべき?
育児とキャリアの両立を考える際は、育児中と子どもが成長した後で戦略を分けることが大切です。育児中は柔軟な働き方を活用し、スキル維持や学習を続けることが将来につながります。資格取得やオンライン学習は、隙間時間でも取り組みやすい方法です。子どもの手が離れた後は、転職や部署異動などで新たな挑戦を検討し、過去の経験と学びを強みに再構築を進めましょう。焦らず段階的に進めることが成功の鍵です。
Q4. 両立を理由にキャリアアップを諦めないための工夫は?
育児とキャリアの両立を理由に成長を止めないためには、日常的な工夫が欠かせません。限られた時間でもスキルを磨けるオンライン学習や資格取得を活用すると、将来のキャリア再構築に役立ちます。また、業務効率化の工夫やチームへの役割共有を行うことで成果を見える化し、評価につなげることも大切です。さらに、育児支援制度や柔軟な働き方を積極的に利用し、自分のキャリア意識を周囲に伝えることで機会を広げられます。
Q5. 両立生活で自分の時間や心の余裕を確保するコツは?
育児とキャリアの両立を続けるには、意識的に自分の時間を確保することが大切です。
例えば、早朝や子どもの就寝後に短時間でも自分の趣味や学習にあてることで、心のリフレッシュと成長につながります。また、家事の外部サービス利用やパートナーとの役割分担を柔軟に調整することも効果的です。さらに、完璧を求めすぎず「できることに集中する」意識を持つことで、心の余裕を保ち、長期的に両立を持続しやすくなります。
まとめ
育児とキャリアの両立は、単なる個人の課題にとどまらず、社会全体に影響を与える重要なテーマです。柔軟な働き方や男性育休の普及、支援制度の充実は、働く親のQOL向上につながります。同時に企業にとっても人材定着や多様性の推進を通じて競争力を高める要素となります。
さらに、少子高齢化が進む日本社会において、両立支援は持続可能性を確保する基盤です。家庭、企業、社会が連携し合うことで、誰もがキャリアと生活を諦めずに歩める未来が実現します。
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS