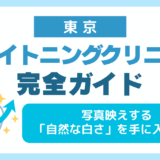イクメンプロジェクトは、男性の育児休業取得や積極的な子育て参加を推進する厚生労働省主導の社会的事業です。2010年の法改正をきっかけに、仕事と家庭の両立を目指す男性や家族を応援し、理想的なパートナーシップ構築や出産育児を支援してきました。企業へのアワードや参加型広報の取り組みを通じて、社会全体に新たな育児文化を発信・定着させ、ジェンダー平等や女性の就業継続にも大きく貢献しています。
イクメンプロジェクトとは
育児と仕事を両立する新しい社会づくりを目指した国の重要なプロジェクトです。まずはその概要について解説します。
厚生労働省によるイクメンプロジェクトの概要
イクメンプロジェクトとは、厚生労働省が2010年に開始した国家的な取り組みであり、男性の育児参加を後押しすることを目的としています。スローガンは「育てる男が、家族を変える」。この言葉が示す通り、子育てを女性だけの負担にするのではなく、父親も積極的に関わることで家族の在り方や社会全体の価値観を変えていくことを目指しています。
背景には少子化や長時間労働の問題、そして男女の役割固定観念の強さがありました。特に「育児休業=母親が取るもの」という意識が長く根強く、男性が育休取得を申し出るとキャリアへの不安や職場の理解不足によって断念するケースが多かったのです。そこで政府は企業や自治体と連携し、父親がより育児に関わりやすくする環境整備に乗り出しました。
「育てる男が、家族を変える」スローガンの意味
「育てる男が、家族を変える」というスローガンは、イクメンプロジェクトを象徴する言葉として広く知られています。このフレーズには、男性が積極的に育児に参加することで、家族の在り方や社会の価値観そのものを変えていこうという強いメッセージが込められています。従来、日本では「育児=母親の役割」とされてきましたが、この固定観念は働き方や家事・育児の負担を女性に偏らせ、少子化や家庭不和の要因のひとつにもなってきました。
厚生労働省が推進するイクメンプロジェクトは、この価値観を根底から覆し、男性が育児休業を取りやすい社会を作ることを目指しました。その中で掲げられたスローガンは、単なる家族内の役割分担を超えて、父親の関わりが子どもの健やかな成長に直結し、さらには職場の意識改革や地域社会全体の風土形成にもつながるという意図を示しています。
また、このスローガンは「イクメン」という言葉の普及にも大きな役割を果たしました。ポジティブな意味合いで父親の育児参加を表現する一方で、「イクメン」への過剰な期待や一部での反発も生まれました。しかし、その議論自体が「男性の育児参加」を社会全体で考える契機となったことは間違いなく、家庭、企業、地域が一体となって子育てを支える流れを加速させています。
参考:男性の育休に取り組む企業・管理職の方 | 育てる男が、家族を変える。社会が動く。イクメンプロジェクト
参考:「イクメンプロジェクト」サイトを開設しました|厚生労働省
イクメンプロジェクトの開始時期と背景
イクメンプロジェクト発足の経緯や社会的背景を解説します。
いつから始まったのか?法改正と連動した始動
イクメンプロジェクトは2010年から開始されました。厚生労働省が同年に本格的にスタートさせた取り組みであり、その背景には改正育児・介護休業法の施行がありました。この改正により、男性が育児休業を取得しやすくする制度的な整備が進められ、同時に社会的な意識改革を後押しする目的でプロジェクトが始動したのです。
当時、日本における男性の育児休業取得率はわずか数パーセントに過ぎず、多くの職場では「男性が育休を取る」という概念自体が珍しい状況でした。そのため、制度の整備だけではなく、父親たちが育児に関わることをポジティブに受け止められるだけの社会的なムーブメントが必要とされ、イクメンプロジェクトが広報的な役割を担うことになったのです。
さらに、プロジェクト開始の背景には、少子化対策や女性の社会進出を支えるための施策もありました。家庭内で父親が積極的に育児に参加することで、母親のキャリア継続を後押しし、共働き家庭がより持続可能となる社会を築く意図が含まれています。
なぜ今「男性の育児参加」が必要とされたのか
イクメンプロジェクトが厚生労働省によって打ち出された背景には、社会構造と家庭環境の大きな変化があります。まず挙げられるのは少子化の進行です。子どもの数が減少し労働人口も縮小する中で、男女問わず安心して子育てできる社会を整備することが急務とされました。さらに、女性の社会進出が進む一方で、育児や家事の負担が依然として母親に偏っている現状が企業や家庭の課題となっていました。
また、男性が長時間労働を強いられる従来の働き方では、家族と過ごす時間が限られ、子どもの健やかな成長の機会が損なわれることも指摘され始めました。こうした課題を克服するために「男性の育児休業の取得促進」や「働き方改革」と連動する形でイクメンプロジェクトが動き出したのです。
さらに、「男性が育児に参加することは家庭だけでなく社会全体にメリットをもたらす」という発想も広まりました。父親の関わりは家族の絆を深め、母親のキャリア継続を支え、職場には多様な働き方を受け入れる柔軟性を促す効果があります。つまり、男性の育児参加は単なる家庭内の役割分担ではなく、社会の持続可能性を支える重要な要素と位置づけられたのです。
イクメンプロジェクトの主な取り組み内容
イクメンプロジェクトでは、具体的にどんな制度や広報活動が展開されているのか、主要な取り組み柱を中心に解説します。
育児休業の取得促進(法改正と連携)
イクメンプロジェクトの中心的な取り組みのひとつが「男性の育児休業の取得促進」です。これは単なる意識改革キャンペーンにとどまらず、改正育児・介護休業法と連動する形で進められました。2010年の法改正により、企業は従業員が育休を取りやすい環境を整備する義務を負い、男性も積極的に制度を活用できるよう下支えが進められました。
しかし当初は「制度はあるが利用されない」という状況が大きな課題でした。そこで厚生労働省はイクメンプロジェクトを通じて、「男性も育休を当たり前に取得できる社会風土」の醸成を狙いました。具体的には、イクボス(育児に理解のある上司)の存在が重要であることを周知し、企業による取り組みや好事例を広く紹介。さらに、SNSや広報活動を活用して、実際に育休を取得した父親の声を社会に届けることで前向きなロールモデルを発信しています。
イクメン企業アワード・イクボスアワード
イクメンプロジェクトの大きな取り組みのひとつが「イクメン企業アワード」と「イクボスアワード」です。これらは厚生労働省が創設した表彰制度で、男性の育児参加を積極的に支援する企業や、部下の育児を応援する上司(イクボス)を顕彰することを目的としています。単なる制度利用の奨励ではなく、社会全体に「男性の育児休業・育児参加は当たり前であり、企業にとっても有益である」という価値観を広める狙いがあります。
例えば「イクメン企業アワード」では、男性の育休取得率や長時間労働の改善、柔軟な働き方の実現に取り組む企業が表彰されています。過去の受賞事例としては、全社員が育児休業を取りやすい制度を構築した大手機械メーカーや、在宅勤務や時短勤務を柔軟に導入したIT企業などが選ばれています。また「イクボスアワード」では、部下の育児とキャリアを応援しつつ、自らも仕事と家庭のバランスを実践する上司の姿が紹介されました。こうした取り組みは、育児を理由としたキャリアの停滞を防ぎ、社員の定着率やモチベーション向上にもつながっています。
表彰制度によって可視化された成功事例は企業間で共有され、全体として「育児にフレンドリーな職場文化」を定着させるきっかけとなっています。
セミナー・講座・SNS発信や地域連携事例
イクメンプロジェクトでは、企業だけでなく一般市民や自治体を巻き込む広報・啓発活動も積極的に展開されています。その中心となるのがセミナーや講座の開催です。育児休業の取得方法やワークライフバランスの工夫を学べる機会を全国各地で提供し、父親たちが実践的なノウハウを身につけられるよう支援しています。また、これらの講座は育児中の母親や企業の人事担当者も対象に含まれ、家庭と職場の両方向から男性の育児参加を後押しする仕組みになっています。
さらに、SNSやYouTubeを活用した情報発信も大きな特徴です。実際に育児休業を取得した男性の体験談や、家事・子育ての工夫を共有することで「自分もできる」と感じさせ、ロールモデルの可視化を図っています。ハッシュタグを通じた広がりやコミュニティ形成も効果的で、共感と学びを同時に得られる場となっています。
地域連携の観点では、自治体と協働したキャンペーンや、保育園・子育て支援センターとの連携事例も増えています。例えば「イクメンの日」を設ける自治体キャンペーンや、父親参加イベントなどが代表的な取り組みです。これにより、育児は家庭内の個人的努力にとどまらず「地域全体で支える仕組み」として広がり、社会全体の育児観を変革する効果を生み出しています。
参考:男性の育休に取り組む企業・管理職の方 | 育てる男が、家族を変える。社会が動く。イクメンプロジェクト
イクメンプロジェクトが推進される社会背景
イクメンプロジェクトが推進される背景には、男性の育休取得率の低さや少子化など、多くの社会課題が存在します。
男性の育児休業取得率の推移と課題
イクメンプロジェクトが始まった2010年当時、日本の男性の育児休業取得率は2%にも満たない水準でした。厚生労働省による統計では、女性の取得率が8割を超える一方で、男性は依然として極めて低い状況にあり、大きな格差が続いていました。その後、制度改正やイクメンプロジェクトによる啓発活動の影響で徐々に改善が見られ、2019年度には7.48%、2022年度には17.13%と過去最高を更新しています。しかし、政府目標である30%には依然として遠く、国際比較でも北欧諸国と比べて低い数字にとどまっています。
育児休業の低取得率の背景には複数の社会的要因があります。まず、長時間労働が一般的な日本の職場文化では、男性が長期にわたって現場を離れることに対する心理的・組織的なハードルが高い点が挙げられます。また、育児休業を取得しても昇進やキャリアに悪影響を与えるのではないかという不安も根強く存在します。さらに、中小企業では代替要員を確保しにくいことから、制度自体があっても運用が難しいという課題も見逃せません。
このように数値的には改善の兆しがあるものの、男性の育児参加を阻む「職場風土の改善」や「企業規模による格差解消」といった構造的課題が、今後のイクメンプロジェクトの大きな焦点となっているのです。
少子化・人口減少と家族構造の変化
日本社会は深刻な少子化と人口減少に直面しています。2025年時点の総人口は約1億2065万人となり、前年から0.75%減少しました。出生数も65万人程度まで落ち込み、過去最低を更新しています。この現象は家族構造にも大きな影響を及ぼしており、ひとり親世帯や共働き家庭が増える一方で、核家族化の進行によって子育ての負担が家庭内に集中する傾向が強まっています。
少子化の加速と人口減少により、将来的な経済成長や社会保障の安定が危ぶまれる状況になっています。そのため、育児支援や男女共同参画の重要性が国全体で再認識されており、父親の積極的な育児参加を推進する「イクメンプロジェクト」は、こうした時代背景を踏まえた社会的な喫緊の課題への対応策と言えます。
イクメンプロジェクトの成果と課題
イクメンプロジェクトの成果は男性育休取得率の急上昇や制度定着、職場の意識改善など多岐に渡る一方で、課題も残っています。
家庭・企業・社会にもたらしたポジティブな効果
イクメンプロジェクトは、家庭・企業・社会の各領域に多くのポジティブな変化をもたらしてきました。家庭においては、父親の育児参画が進むことで夫婦間のパートナーシップが強化され、育児の精神的負担や孤立感が軽減する場合が多いでしょう。
企業面では、男性育児支援や柔軟な働き方の実現が定着しつつあり、育児休業を取得した社員の定着率・満足度が向上するなど職場環境の質的向上にも寄与しています。実際、育児休業経験がキャリアやリーダーシップに好影響をもたらし、働き方改革推進のロールモデルとなった実例も多数あります。
社会的には「家事・育児は女性の仕事」という固定観念の是正につながり、男女共同参画や多様な家族のあり方の推進に貢献。支援団体や自治体との連携事例も増加し、地域ぐるみの育児推進体制構築など次世代に向けた社会基盤づくりが進んでいます。
制度の限界と職場環境がもたらす育休取得の壁
「イクメンプロジェクト」や法制度の整備によって男性の育児休業取得は進んでいますが、実際には多くの現場で限界や課題が存在します。特に、業務が忙しい中小企業や現場系の職種では、人員不足や業務調整の難しさから育休取得が敬遠される傾向が根強く残っているのが現状です。職場の上司や同僚から「評価が下がるのでは」「仕事を休むだけで迷惑をかける」といった無理解や偏見が障壁となり、利用したくても使えないという「制度と実際のギャップ」が生まれています。
また、昇進・昇格や将来的なキャリアへの悪影響を不安視する男性従業員は今なお多く、「育児休業=マイナス評価」といった意識が根付いている職場も少なくありません。働き方改革や政府の後押しがあっても、現場レベルでは制度の定着が進みにくいケースが存在するなど、現実の壁は依然として厚いのです。
特に中小企業においては、代替要員確保や業務分担面での課題も顕著。制度は整っていても「取得しづらい」という根本的な問題の解決には、職場風土の変革・経営層の理解などさらなるアプローチが不可欠です。
「イクメン」という言葉の功罪と世間の反応
「イクメン」という言葉は父親の育児参加推進の象徴として広く浸透しましたが、その扱いには賛否両論があります。ポジティブな側面としては、育児に積極的な男性が「カッコいい父親像」として社内や世間で肯定的に評価される機会が増えました。実際、多くの企業や自治体が表彰・広報活動を通して理想的なロールモデルを発信しています。
一方で、「イクメンだから特別」「自己責任で頑張るべき」といった過剰な特別視や自己責任論、あるいはSNS等で炎上や揶揄の対象になる負の側面も見逃せません。本質的には、育児は男女ともに担うべき社会的責務であり、過度な「イクメン」礼賛や個人への期待がプレッシャーや孤立感につながるリスクがあります。
そのため近年では、「イクメン」という言葉だけで語るべきではなく、「誰もが育児に関われる社会」への構造的転換の重要性が強調されています。世論は、言葉の使い方や現実的な支援策のあり方を継続して再考する段階へと進みつつあるのです。
日本企業のイクメンプロジェクトの導入事例
日本企業が実践する多様な取り組み内容を分かりやすくご紹介します。
積水ハウス株式会社
積水ハウスでは2018年から「男性社員1ヶ月以上の育児休業完全取得」を掲げ、育休取得率100%を実現しています。最初の1ヶ月は有給扱い、分割取得や事前研修の導入、妻のサポート方法の教育など制度設計も充実しています。トップのコミットメントと業務調整の仕組みで社内・社会変化をけん引しています。
参考:IKUKYU.PJT(男性の育児休業・育休取得推進) | 積水ハウス
伊藤忠商事株式会社
伊藤忠商事は2024年から男性育休の「必須化」を社内制度としてスタート。配偶者の出産後1年以内に5日以上の有給育児休業取得を義務付け、4週間以上取得した社員には両立手当も支給。育児・健康コンシェルジュの設置などサポート体制も整備しています。
富士ソフト株式会社
富士ソフトは「スマートワーク制度」や選択的週休3日制、ネットワーク構築支援、社内ノウハウの共有など柔軟で先進的な働き方を推進。育児期社員へのプログラムや職場の理解促進により、男性社員による育児参加が着実に進んでいます。
参考:ワーク・ライフ・バランス
SDGsとの関係性:なぜイクメンプロジェクトが重要なのか
イクメンプロジェクトは、企業や社会が多様性・持続可能性向上を目指すうえで重要な役割を果たしています。
目標5「ジェンダー平等」との連携
SDGsの目標5「ジェンダー平等」の実現は、イクメンプロジェクトの理念と深く結びついています。ジェンダー平等は、単に女性の活躍推進に留まらず、男性も家事・育児に主体的に関わり、家庭と社会における役割や機会が均等に与えられることを目指す考え方です。イクメンプロジェクトは「男のくせに」「女のくせに」といった性別によるステレオタイプを打破し、家事・育児の分担や働き方を柔軟に変革する取り組みを後押ししてきました。
従来の日本社会では、家事・育児が「母親=女性の仕事」とされる傾向が強く、父親が育児に積極的に関わると「イクメン」と特別視される現象が見られました。この認識自体がジェンダーの不平等を助長する一因でもあります。イクメンプロジェクトは、職場・家庭・社会の各場面で「誰もが希望に応じて仕事・家事・育児を両立できる社会」を目指しており、男女がパートナーとして対等に家庭生活を担えるようになる変革を後押ししています。
また、父親の育児参加が進むことで女性の就業・キャリア形成も支援され、パートナーシップや企業文化の多様化にも寄与。育児支援を充実させる企業が増え、働きやすさや組織の持続可能性も高まります。実際、SDGs目標の一つ「誰一人取り残さない」という理念は、社会的・経済的背景の違いに関わらず家族が協力し合う仕組み作りと直結しており、イクメンプロジェクトの実践は家庭・職場の両面でその達成に貢献しています。
このように、イクメンプロジェクトはジェンダー平等の実践例として国内外からも評価されており、「育児は女性だけのものではない」「男女が共に働き、育てる」という時代の価値観を象徴する事業となっています。
目標8「働きがいも経済成長も」との関係
SDGsの目標8「働きがいも経済成長も」は、イクメンプロジェクトの実現によって生産性向上・人材確保・持続可能な社会創出に直結します。近年の育児休業取得促進施策によって、男性育休を推進する企業では離職率や定着率が向上し、社員の満足度も高まる傾向が確認されています。特に働き方改革を進めた企業では、残業削減や有給取得率の向上など労働環境そのものが改善し、従業員の健康・モチベーション向上に寄与しています。
また、育児支援を充実させた企業は優秀な人材の獲得・定着の面でも有利です。若年層やZ世代は「育休取得実績がある会社」を企業選びの重要ポイントと捉えるようになってきており、採用競争力・ブランド力の源泉となっています。さらに、男性育休の義務化や産後パパ育休制度の創設を背景に、多様な働き方が認められることで組織の生産性と創造性が向上。IT企業や製造業などでは、属人化の解消・業務の効率化も進み、営業利益やイノベーションの創出面でもポジティブな効果が実証されています。
イクメンプロジェクトに関するよくある質問
ここからは、イクメンプロジェクトについてよくある質問と具体的な回答を通して、より理解を深めていきます。
Q1.イクメンプロジェクトとは何ですか?具体的にどんな活動・取り組みが行われているのでしょうか?
イクメンプロジェクトとは、厚生労働省が推進する男性の育児参加と育児休業取得を促す全国的な取り組みです。主な活動内容には育児休業取得促進、啓発イベントの開催、イクメン企業アワードやイクボスアワードの表彰、セミナー・講座、SNSによる情報発信、地域連携事例の紹介などが含まれます。近年は後継事業「共育プロジェクト(トモイク)」として男女共同参画や家庭・職場改革も進めています。
Q2.男性が育児休業を取得しづらい理由は何ですか?
男性が育児休業を取りづらい理由は、職場の人手不足や業務量、上司や同僚からの無理解、キャリアへの不安などが挙げられます。特に中小企業や現場職では代替要員を確保しにくく、制度があってもなかなか利用できない現状があります。また、育休取得による収入減や「男性は仕事優先」といった根強い固定観念も障壁となっています。
Q3.「イクメン」という言葉について、世間での反応はどうですか?
「イクメン」という言葉は父親の子育て推進を象徴していますが、世間では賛否両論があります。ポジティブには「育児する父親=かっこいい」と認識されますが、特別視や形式的取得への違和感、SNS炎上の原因になる場合もあります。近年は男性の育児を「当然」とする時代へ移行しつつあり、言葉の使い方を再考する意識も高まっています。
Q4.育児休業を申請しても職場が認めない場合、企業や本人はどうすればよいのでしょうか?
育児休業の申請が認められない場合、まずは職場の人事部や労働相談窓口へ相談し、法律上の権利と制度内容を再確認しましょう。社内だけで解決できない場合は、各自治体の労働相談や外部の育児支援団体など第三者機関のサポートを受けることも選択肢です。労働基準監督署への相談も有効な手段です。
Q5.イクメンプロジェクトのデメリットや課題は何ですか?
イクメンプロジェクトには「取るだけ育休」など制度形骸化の懸念や、実際の家庭内・職場での男女負担格差が残る課題、育児参加を特別視することの精神的負担などのデメリットも指摘されています。後継の「共育プロジェクト」では男女ともに両立できる仕組みづくりが進められています。
まとめ
イクメンプロジェクトは、男性の育児参加・育児休業取得促進により、家庭・職場・社会全体に新たな価値と可能性をもたらしてきました。法整備や啓発活動をきっかけにパートナーシップや働き方改革が進展した一方、現場では取得の壁や制度の限界、男女間の負担格差など課題も残されています。今後は「共育プロジェクト」へと発展しながら、男女誰もが協力して育児・仕事を両立できる社会づくりに、さらに挑戦が続いていくでしょう。