聴覚障害は、音による情報の受信が困難になることで、生活や仕事にさまざまな支障をもたらす障害です。聞こえにくさは、他者との意思疎通を妨げるだけでなく、社会的な孤立や誤解を招きやすく、心理的な負担が大きくなることもあります。
一方で、障害の程度に応じた等級制度により、福祉機器の支給や交通費の助成といった支援が受けられるほか、聴覚障害者マークの掲示によって周囲の配慮を得やすくなるというメリットもあります。
さらに、運転免許制度では特定の条件を満たせば取得が可能であり、自立した移動手段を持つことができる点も見逃せません。加えて、無料で使える文字起こしアプリや音声認識ツールなどの普及も進み、聴覚に障害がある人でも快適に暮らせる環境が徐々に整ってきています。
聴覚障害とは?
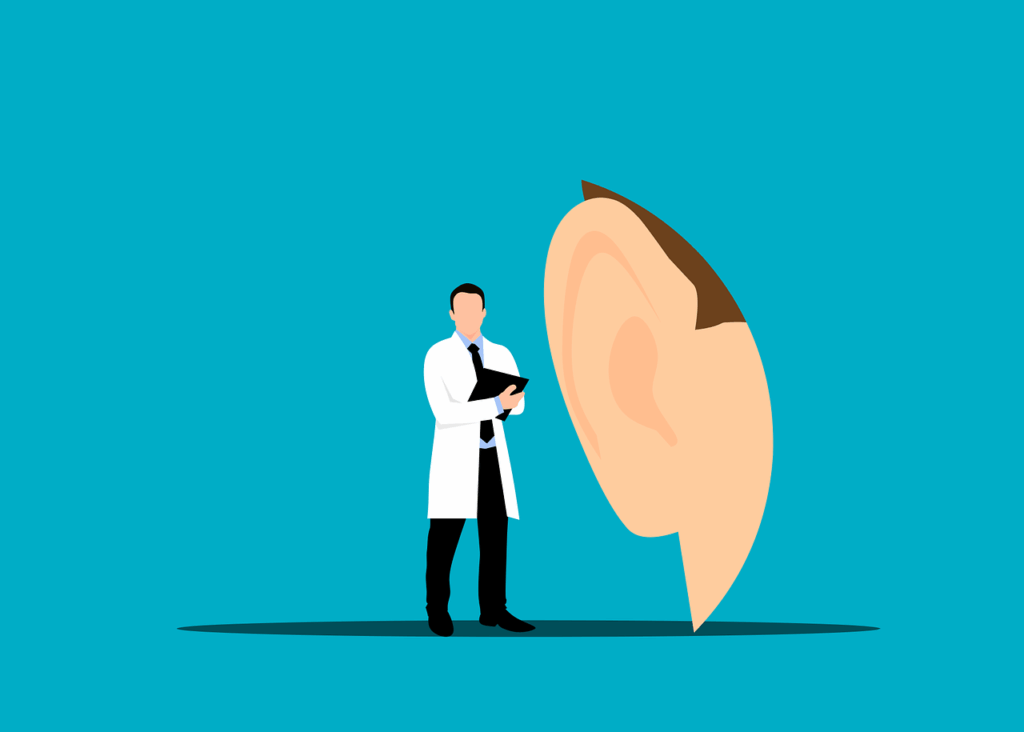
聴覚障害とは、音や話し声が聞こえにくい、またはまったく聞こえない状態を指します。音に対する感覚や認識力が低下することで、会話の内容を正確に受け取ることが難しくなり、アナウンスや警報といった音による情報の把握にも支障が出ることがあります。
日本学生支援機構(JASSO)や厚生労働省では、耳のどこに障害があるかによって「感音性難聴」「伝音性難聴」「混合性難聴」に分類しています。感音性は内耳や聴神経に問題がある状態、伝音性は外耳や中耳に障害がある状態、混合性はその両方が関係しているものです。
また、この障害は、生まれつき音が聞き取りづらい「先天性」と、病気や事故によって聴力を失う「後天性」に大別されます。症状の出方は個人によって異なり、まったく音を感じ取れない方もいれば、大きな声や特定の音域だけが認識できる方もいます。
聴覚に制限があることで、日常生活や社会活動の中で多くの困難に直面しやすくなります。そのため、早い段階での気付きと支援がとても大切です。補聴器や人工内耳の利用、要約筆記や手話通訳の導入など、適切な支援手段を選ぶことで、コミュニケーションの負担を軽減することが可能です。
多様な聞こえ方を理解し、相手に配慮した接し方を広げていくことが、誰もが安心して暮らせる共生社会の実現につながります。
聴覚障害の種類
医学的には、聴覚障害は「伝音難聴」「感音難聴」「混合難聴」の三つに分類されます。
| 分類 | 特徴 | 主な原因 | 改善・対応方法 |
|---|---|---|---|
| 伝音難聴 | 外耳~中耳の「音の通り道」に異常がある | 鼓膜の損傷、中耳炎など | 補聴器や手術で改善できる場合がある |
| 感音難聴 | 内耳や聴神経の障害で、音がゆがんで聞こえる | 加齢、騒音、内耳の疾患など | 補聴器の効果は限定的なことが多い |
| 混合難聴 | 伝音難聴と感音難聴が両方みられる | 上記の原因が複合的に関与 | 複数の治療・支援を組み合わせる必要がある |
伝音難聴は、外耳から中耳にかけて音の通り道に異常がある状態で、鼓膜の損傷や中耳炎などが原因となります。このタイプは、補聴器や手術によって改善される場合があります。
感音難聴は、内耳や聴神経に問題があるもので、音そのものがゆがんで聞こえることが特徴です。音の大きさだけでなく、明瞭度にも影響が出るため、補聴器の効果が限定的なこともあります。伝音難聴と感音難聴が両方みられる場合は「混合難聴」と呼ばれ、複数の治療や支援を組み合わせる必要があります。
このように、聞こえ方にはさまざまなパターンがあり、ひとくくりにはできません。適切な診断と理解が求められます。
聴覚障害の原因
聴覚障害の原因を見ていきましょう。聴覚障害は、生まれつきの場合と、生後に発症する場合の二つに分けられます。
生まれつきの聴覚障害の原因
先天性のケースでは、生まれつきの遺伝子異常や妊娠中の母親がサイトメガロウイルスに感染したりといった原因があります。他にも分娩時のトラブルが要因になることが多いです。
先天性の聴覚障害は、6割から7割程度が遺伝的なもので、遺伝的ではない場合が3割~4割とされています。音を耳で聞くためには様々な部位が正常に機能して、聞こえるようになっているので、いずれかの遺伝子に異常があれば聴覚障害を抱えてしまう可能性は十分にあります。
日本では、新生児1000人に1〜2人の割合で難聴が確認されており、生まれつきの聴覚障害は、耳の機能が悪く聞こえない場合も多々ありますが、脳や神経に異常が発生して聞こえづらかったりということも考えられます。
そのため早い段階で気付けるよう新生児スクリーニングが必ず産院で行われるようになっており、検査費用も県や市が負担してくれる場合がほとんどです。
後天的な聴覚障害の原因
中途失聴は、言葉の習得後に聞こえが低下するもので、病気や事故、薬剤の副作用、さらには加齢などが原因として挙げられます。
中でも一番多いのが、加齢による聴覚障害です。他にもストレスによる突発性難聴や、ライブなどの大きな騒音によって聴覚障害が後天的に発症してしまう場合も最近では増えていて、若年性の難聴患者も多数います。
耳垢や中耳炎などから聴覚障害に発生してしまうこともあるのを、ご存知でしょうか?意外と耳掃除をしていなかったり、中耳炎を放置してしまうと、耳が聞こえづらくなってしまうことも十分に考えられるので、不安に思うことがあれば早めに耳鼻科を受診しましょう。
思春期や成人後に発症すると、これまで築いてきたコミュニケーション手段が急に使えなくなることがあるため、心理的な負担も大きくなりがちです。
原因を明確にすることは、今後の支援方針を決めるうえで重要です。治療やリハビリの選択にも関わるため、医療機関での精密な検査が欠かせません。
聴覚障害の程度と等級制度
聴覚障害には、障害の程度に応じて1級から6級までの等級が設けられており、身体障害者手帳の交付を受ける際の基準となっています。等級は、聞こえの程度を「純音聴力レベル」や「語音弁別能」などで測定した結果に基づいて判定され、数値が大きいほど重度とされます。等級に応じて、受けられる支援やサービスも異なり、補聴器などの補装具費助成、税制優遇、公共交通機関の割引、就労支援制度の利用などが可能になります。
等級の分類と測定基準
等級は、1級から6級までの6段階に分けられており、数字が小さいほど障害の程度が重いことを示します。判定には主に「純音聴力レベル」と「語音弁別能」という2つの数値が用いられます。
| 等級 | 判定基準(聴力レベル) | 対象となる聴力状態 | 該当するケース例 | 主な支援内容 |
|---|---|---|---|---|
| 等級 | 判定基準(聴力レベル) | 対象となる聴力状態 | 該当するケース例 | 主な支援内容 |
| 2級 | 両耳の聴力レベルが 90dB以上 | 日常会話が不可能な状態 | 耳元での大声も聞こえない | 医療費助成、税控除、公共交通の割引、重度障害者福祉制度など |
| 3級 | 両耳の聴力レベルが 80dB以上 | 補聴器を使用しても会話困難 | 静かな場所でも言葉の判別が困難 | 補装具費支給(補聴器)、就労支援制度の一部対象 |
| 4級 | 両耳の聴力レベルが 70dB以上 | 会話の聞き取りに著しい支障がある | 補聴器を使用してやっと日常会話が可能なレベル | 一部医療助成、交通機関割引、地域支援制度など |
| 6級 | 下記いずれかの条件に該当:① 片耳が 90dB以上 かつ 他方が 50dB以上② 両耳で 軽中度難聴の合算で条件を満たす | 一方の耳が機能していない状態 | 片耳のみで生活する人、聴力の左右差が大きい | 補聴器の助成、一部自治体支援、障害者手帳交付 |
純音聴力レベルは、どの程度の音まで聞こえるかをデシベル(dB)単位で示す指標で、通常はオージオメーターという機器を使って測定されます。語音弁別能は、音は聞こえていても言葉の意味をどれほど正確に理解できるかを測るものです。
たとえば、両耳の平均純音聴力レベルが100デシベル以上で、語音の理解が困難な場合は1級とされます。反対に、70デシベル程度であれば4級や5級と判断されることがあります。評価では左右両耳の聴力を総合的に判断し、音の聞こえ方だけでなく、日常生活にどのような支障があるかも考慮されます。医師の診断書に基づき、自治体が最終的な等級を認定します。
等級によって受けられる支援の違い
等級が決まると、それに応じた支援が受けられるようになります。たとえば、補聴器などの補装具を購入する際、一定の条件を満たせば自治体から補助金が支給されます。1級から3級のような重度の障害がある方には、日常生活を支えるための支援がより手厚く用意されています。
通院費や交通費の助成、所得税や住民税の控除、医療費の一部免除、公共料金の割引などがあります。また、障害者手帳を提示することで、各種公共施設の利用料が減免されることもあります。職業訓練や就労支援を受けられる制度もあり、社会参加を促進するための取り組みが進められています。
支援内容は自治体によって異なる部分もありますが、等級が高いほど対象となる制度は広がります。そのため、診断を受けた際には、正しい情報に基づいた申請手続きを行うことが大切です。
参考元:聴覚障害とは?難聴の等級や特徴、仕事上のコミュニケーションの工夫などご紹介|LITALICOワークス
参考元:聴覚障害者の認定基準やどんな支援が受けられるのかについてご紹介します!|厚生労働省
新生児聴覚スクリーニング検査の推奨
新生児聴覚スクリーニング検査は、赤ちゃんの難聴を早期に発見し、適切な療育へつなげるために欠かせない検査です。実際、産婦人科診療ガイドライン産科編2017では推奨度がCからBに引き上げられ、分娩を扱うすべての医療機関において、保護者への説明と検査実施が必須とされています。
検査が行われなかったことで発見が遅れ、結果的に言語発達の遅れにつながるケースも報告されており、医療機関には責任が伴います。自施設で検査ができない場合には、地域の紹介先を把握し、速やかに他施設を案内する体制を整えておくことが求められます。
難聴は早期介入が何より重要であり、言語発達や生活の質を大きく左右することが明らかになっています。したがって、すべての新生児にスクリーニング検査を受けさせることが強く推奨されているのです。
参考元:公益社団法人 日本産婦人科医会
聴覚障害が生活に及ぼす影響と抱える問題
音の情報が制限されると、日常生活の安全やコミュニケーションに大きな影響を及ぼします。会話が円滑に進まなかったり、周囲の声かけに反応できなかったりすることで、誤解や孤立につながることもあるのです。
さらに公共施設のアナウンスや非常ベルに気付けないと、安全確保が難しくなる場面も少なくありません。以下に、具体的な影響を整理します。
コミュニケーションの取りづらさ
会話の聞き取りが不十分だと、返答の行き違いや誤解が生じやすくなります。雑音の多い場所や集団での会話では特に困難が大きいです。
結果として会話に入れない孤立感を抱き、人間関係の構築や維持に影響を与えることがあります。長期的には人間関係の形成や社会的参加の機会を狭める要因にもなります。
さらに、意思疎通の制約が続くと、自己表現の機会が減少し、自信や自己肯定感の低下につながることも珍しくありません。
単に会話ができないだけでなく、その先への影響も大きいのです。さらに音による注意喚起を受け取りにくいことで、自宅内や外出先でも不測の事態に対応しづらくなります。結果として、安全の確保において大きな課題が残
加えて、周囲の人が障害に気付かず助言や支援が遅れると、リスクがさらに増大する可能性もあります。
安全を確保することが難しい
自動車のクラクション、避難を促す非常ベル、駅や空港のアナウンスなどに気付けないと、事故や災害時にリスクが高まります。特に高齢者では、難聴が転倒や事故の一因になることも報告されている状況です。
安全の確保という点で大きな課題になります。たとえば音による注意喚起を受け取りにくいことで、自宅内や外出先でも不測の事態に対応しづらくなります。結果として、安全の確保において大きな課題が残るのです。
加えて、周囲の人が障害に気付かず助言や支援が遅れると、リスクがさらに増大する可能性もあります。
勉強や仕事に支障が出る可能性
学校や職場など音声中心の環境では、情報を受け取る機会が限られます。授業内容や会議のやりとりを理解しづらく、学習や業務に支障が出るケースも珍しくありません。
適切な支援がなければ、能力を十分に発揮できず不利な立場に置かれてしまいます。教育・就労の場での支援不足は、将来的なキャリア形成にも影響を及ぼすのです。
さらに、職場や学校での配慮が不十分だと、周囲との摩擦や誤解が生じ、ストレスや心理的負担が増すこともあります。
学業が学習への支障だけでなく、心の傷も負うことになるのです。
社会的孤立が心身に影響するリスクがある
聴覚障害は外見からはわかりにくいため、周囲に理解されにくく孤独感やストレスにつながることがあります。近年では難聴と認知症の関連も指摘され、社会的孤立が心身の健康に悪影響を及ぼす可能性も否定できないのです。
心理面でのサポートも欠かせません。実際、見えにくい障害ゆえに誤解されやすく、「努力不足」と捉えられることも少なくありません。その結果、本人は精神的な負担を強く抱えやすくなります。
そのため、心理面での支援や社会的サポートは、健康や生活の質を維持するうえで欠かせない要素となります。
以上のような状況を防ぐには、本人だけでなく、社会全体が聴覚障害への理解を深め、伝わる工夫を重ねることが求められます。 手話や筆談、字幕の活用、音声を可視化する技術などを取り入れながら、すべての人が安心して生活できる環境づくりが必要です。
聴覚障害者に対する教育現場や職場での支援状況
聴覚障害を持つ人が安心して生活するためには、社会全体での理解と支援が必要です。制度や取り組みは少しずつ広がってきましたが、まだ十分とはいえない部分もも多く、地域差や支援の質の問題が残されています。日常の暮らしから教育、職場でのキャリア形成に至るまで、多方面での継続的な改善が求められています。
ここでは、社会・教育・職場などの場面ごとに、聴覚障害者に対する支援状況を詳しくみていきましょう。
社会における支援
公共機関や医療現場では、手話通訳や要約筆記の導入が進められています。テレビ番組の字幕放送や電話リレーサービスも普及し、情報を得やすい環境が整いつつあるのも事実です。に災害時の情報提供においても、字幕や音声以外の手段を併用する試みが広がっており、命を守る観点からも支援の重要性が高まっています。
ただし地域による格差は依然として大きく、都市部に比べ地方では支援が十分に整っていないケースも少なくありません。また、サービスの存在自体を知らない人も多く、利用できる制度や手段をより広く周知することが大きな課題とされています。
教育における支援
特別支援学校や難聴学級など、子どもの聞こえの状態に応じた学習環境が用意されています。近年は通常学級で学ぶ子どもへの支援も重視され、FM補聴システムや字幕付き教材の利用が広がって来ている状況です。インクルーシブ教育の推進により、障害の有無にかかわらず一緒に学ぶ環境づくりが進んでいるのも特徴です。
とはいえ教員側の理解不足やサポート体制の限界から、学習機会に差が生じることもあります。特に個別対応のノウハウ不足や、学校全体での支援意識の格差が課題とされており、今後は教員研修や支援員の配置拡充など、制度的なバックアップが欠かせません。
職場における支援
障害者雇用促進法により、企業は一定割合の障害者を雇用する義務があります。聴覚障害者向けには、チャットツールやメールを活用した業務連絡、会議での要約筆記や通訳の利用などが広がってきました。最近ではリモートワーク環境においても、文字情報を活用したコミュニケーションが取り入れられ、働きやすさが少しずつ改善しています。
しかし、実際の職場では配慮が不十分な場合もあり、キャリア形成に制約がかかることも否めません。特に昇進や専門スキルの習得の場面で情報格差が生じることがあり、本人の能力を十分に発揮できない例もあります。企業側の理解促進と制度の柔軟な運用が、今後の大きな課題となっています。
聴覚障害とコミュニケーション手段
聴覚に制限のある人が社会の中で自分らしく生活するためには、意思や情報を正確に伝え合える環境づくりが欠かせません。音声によるやり取りが難しい場合でも、視覚や文字、技術を活用すれば、さまざまな方法で人とつながることができます。手話や筆談、口話のような伝統的な手段に加え、近年では音声認識や字幕生成を活用したアプリ、遠隔通訳などのICT支援も普及しています。
これらの手段は、場面や相手に応じて柔軟に選ぶことが大切です。本人の特性に合わせたコミュニケーション方法を用いることで、社会参加の機会が広がり、生活の質も向上します。誰もが安心して情報をやり取りできる環境づくりは、共生社会の実現に向けた大切な一歩といえるでしょう。
手話・筆談・口話
手話は、視覚的な言語で、手の形や動き、表情を組み合わせて情報を伝えます。独自の文法を持ち、ろう文化に根づいた方法ですが、すべての人が理解できるわけではありません。相手が手話を知らない場合には通じにくいため、使う場面は慎重に見極める必要があります。
筆談は、紙やスマートフォンなどに文字を書いてやり取りする方法です。学校や病院、公共施設でも広く活用されています。文字を使うため、多くの人にとって分かりやすい一方、会話のスピードは遅くなりやすく、緊急時には不向きな場面もあります。
口話は、相手の口の動きを読み取り、何を話しているかを推測する方法です。音声言語の理解が求められるため、音声による経験がある人には適していますが、口の動きが不明瞭な場合や、口元が見えない状況では難しさが生じます。マスクの着用が一般的になった近年では、口話の実践に支障をきたすこともあります。
ICT・アプリによる支援
近年は、音声をリアルタイムで文字に変換できるアプリや、映像を使った手話通訳サービスが登場しています。たとえば「UDトーク」や「こえとら」は、会話を音声認識し、自動で字幕を表示することができます。授業や医療現場、ビジネスの打ち合わせなど、幅広い場面で使われています。
さらに、「SureTalk」のような遠隔手話通訳サービスでは、専用アプリを通じて画面越しに通訳者とつながることができ、窓口や接客の場面でも安心して対話を行うことが可能です。このようなツールの活用によって、外出先でも情報を正確に受け取りやすくなり、聴覚に制限のある人がより自立した生活を送りやすくなります。
こうした支援は、国連が提唱する「誰ひとり取り残さない」というSDGsの理念にも通じます。すべての人が安心して生活できる社会の実現には、多様な手段が選べる環境の整備が欠かせません。情報への平等なアクセスは、個人の尊厳を守るための基本条件の一つです。
参考元:聴覚障がいとは? 等級や種類、コミュニケーション時に配慮すべきこと | SureTalk
参考元:聴覚障害者 – Wikipedia
聴覚障害者でも運転免許が取得できる
聴覚に障害がある人が自動車を運転する際には、周囲の車両や歩行者との円滑な意思疎通が難しい場面が想定されるため、特別な配慮が求められます。その一環として導入されているのが「聴覚障害者マーク」です。このマークは、運転者が聴覚に制限があることを周囲に伝え、安全運転への理解を促す役割を担っています。
運転免許制度にも一定の配慮がなされており、補聴器やワイドミラーの使用など、障害の程度に応じた条件付きで免許を取得・更新できる仕組みが整備されています。
法律の整備により、聴覚障害がある人も自立して移動手段を確保しやすくなっていますが、その安全性を支えるためには、正しい制度理解と、社会全体の思いやりが欠かせません。聴覚障害者マークは、そうした共生の姿勢を象徴する重要な制度のひとつです。
聴覚障害者マークの意義とルール

「聴覚障害者マーク」は、補聴器を使用しても10メートルの距離で警音器(クラクション)の音が聞こえない人が、自動車を運転するときに表示することが義務づけられた標識です。図柄は黄色地に青い蝶が描かれたデザインで、道路交通法施行規則第9条の8で定められています。この標識の表示対象となるのは、運転免許証に条件として「補聴器使用」や「ワイドミラー装着」が指定されている人です。
誤解されやすいものに「耳マーク」がありますが、こちらは聴覚障害者であることを周囲に知らせるための福祉マークであり、運転に関する義務表示ではありません。両者は目的が異なるため、使い分けが重要です。聴覚障害者マークは、車両の前後の見やすい位置に貼付する必要があります。表示しないまま運転すると、道路交通法違反と見なされることもあるため注意が必要です。
運転免許と法制度の関係
かつては聴覚障害があることで運転免許の取得が大きく制限されていましたが、現在は法制度の見直しが進み、障害の程度に応じた条件付きでの取得が認められるようになっています。たとえば、聴力の低下がある人でも、補聴器や広角ミラー(ワイドミラー)を使用することで、一定の安全基準を満たせば普通自動車の運転免許を得ることが可能です。
警察庁が示す基準では、10メートルの距離でクラクションの音が聞こえない場合でも、補聴器装用や視野補助機器を併用することで、適性があると判断されれば免許が交付されます。実際の免許証には、「補聴器使用」「ワイドミラー使用」などの条件が記載され、これらに従った運転が義務付けられます。違反があった場合は、行政処分や罰則の対象となることもあります。
また、聴覚障害があることだけを理由に免許の更新を拒否されることはありません。ただし、更新の際には医師の診断書や聴力の再確認が求められることもあるため、事前に手続き内容を確認しておくことが大切です。運転するうえでの制限を理解し、制度を正しく活用することで、聴覚障害があっても安全で円滑な移動が可能になります。
参考元:聴覚障害者 – Wikipedia
参考元:聴覚障害 障害特性|ハートシティ東京
聴覚障害とSDGsの関係
聴覚障害は、個人の生活だけでなく社会全体の構造にも深く結び付いています。特に国連が提唱するSDGs(持続可能な開発目標)では、障害をもつ人々の権利や生活の質を向上させることが明確に示されています。
その中でも目標4(質の高い教育をすべての人に)、目標10(不平等をなくす)、目標11(住み続けられるまちづくりを)、目標17(パートナーシップで目標を達成しよう)は、聴覚に障害がある人が学び、働き、暮らすうえで欠かせない内容です。
社会の中で誰もが公平に生活できる環境を整えることは、障害の有無に関わらず共通の課題といえます。
教育制度を整備し情報を正しく取得できる環境をつくる必要性
目標4は、すべての人が質の高い教育を受けられることを掲げています。
聴覚に障害がある児童や生徒にとって、情報を正しく受け取れる環境の整備は不可欠です。教室での授業が音声中心で進められる中、字幕を付けた教材や手話通訳の導入は、学習機会を保障するうえで重要な支援となっています。
また、聴覚特別支援学校や通級による指導体制の強化も、ひとりひとりに適した教育環境の提供につながります。これらの配慮は、「障害によって分断されない学び」の実現に向けた具体的な取り組みとして、社会に大きな意義を持ちます。
今後も合理的配慮を前提とした教育制度の充実が求められます。
社会のバリアフリー化とユニバーサルデザイン(UD)の活用
目標11では、誰もが安心して移動や生活を送れる都市づくりが重視されています。聴覚障害をもつ人が社会参加する際、情報伝達の手段に偏りがあると日常生活に支障をきたします。
そこで注目されているのが、ユニバーサルデザイン(UD)技術の活用です。音声を文字に変換する「電話リレーサービス」や、警報音を光や振動で知らせる機器などは、情報格差を埋める効果があります。
また、駅や公共施設での電光掲示板や視覚案内も、移動時の安全性を高めています。こうした取り組みは、すべての人が共に安心して暮らせる社会の実現を後押しするものです。
聴覚障害者に対して私たちができること
聴覚障害は外見からは分かりにくいため、周囲が気づかずに誤解や不便が生じやすい特徴があります。ちょっとした配慮や工夫で、生活のしやすさは大きく変わります。ここでは、日常で私たちができる支援を整理しました。
コミュニケーションでの配慮
まず大切なのは「どの方法が伝わりやすいか」を本人に尋ねることです。手話、筆談、口話など、使いやすい手段は人によって異なります。表情や口の動きを見て理解している人も多いため、顔を見せて話すことは基本です。
雑音の少ない場所を選び、ゆっくり区切って話すと理解しやすくなります。もし伝わらないときは、繰り返すよりも紙に書いたり、スマートフォンに入力して見せる方が確実です。「わかろうとする姿勢」が相手の安心感につながり、円滑なやり取りを生みます。
公共の場でのサポート
駅や病院、役所などでは、音声だけに頼らず文字や表示で案内できる工夫が重要です。利用者が戸惑っていたら「お手伝いしましょうか」と声をかけることも支援の第一歩になります。説明が必要なときは、メモや図を添えて伝えると確実性が増すでしょう。
緊急時には、周囲の状況を伝える一言が大きな助けとなります。聴覚障害のある人は自分から支援を求めるのをためらう場合もあるため、気づいた人がさりげなく行動することが欠かせません。日常の小さな気配りが、安全で安心な環境づくりにつながります。
職場や地域での取り組み
会議や打ち合わせでは、一度に複数人が話すと内容を把握しにくくなります。
発言者が順番に話すよう工夫したり、要点を要約して共有するなどの配慮が求められます。オンライン会議なら字幕機能やチャットを併用すると効果的です。
地域活動やサークルでも同様に、一人ずつ発言するルールを取り入れると参加しやすくなります。職場では「配慮が必要かどうか」を本人に確認する姿勢も忘れてはいけません。小さな工夫の積み重ねが、能力を発揮しやすい環境を育て、孤立を防ぐ力になります。
聴覚障害に関するよくある質問
聴覚障害に関しては、日常生活や教育、社会参加との関わりの中で、多くの疑問や不安を抱える人が少なくありません。
特に身近に接する機会が少ない人にとっては、支援の方法や適切なコミュニケーション手段について正確に理解することが難しい場合もあります。
以下では、よく寄せられる質問の中から代表的な5つの疑問を取り上げ、それぞれ丁寧に解説します。
聴覚障害の人は手話が使えるのですか?
手話を使用する聴覚障害者は多い一方で、すべての人が手話を使えるとは限りません。
幼少期から手話に親しんでいる人もいれば、補聴器や人工内耳を活用し、音声言語中心で生活している人もいます。中には、筆談や音声認識アプリなどを併用しているケースもあります。
そのため、一律に「聴覚障害者=手話利用者」と考えるのではなく、相手の希望する方法を尊重する姿勢が大切です。
聴覚障害があると電話や会話は難しいのでしょうか?
電話での通話は、音声情報に大きく依存するため、聴覚障害者にとって大きな壁となることがあります。
しかし、最近では文字起こし機能付きの電話サービスや、スマートフォンのアプリを活用して内容をリアルタイムで表示する仕組みも普及しています。
また、ビデオ通話による手話のやりとりや、メール・チャットを通じた連絡手段も活用されています。技術の進展により、会話や情報交換の手段は大きく広がっています。
障害者手帳があればどのような支援が受けられますか?
聴覚障害が一定の基準を満たしている場合、「身体障害者手帳」が交付されます。これにより、各種公共料金の割引、補聴器の購入助成、通訳者派遣制度の利用など、生活支援の幅が広がります。
手帳の等級によって利用できる制度に違いがあり、自治体ごとに実施内容が異なるため、詳細は市区町村の窓口で確認する必要があります。手帳の交付は申請制で、医師の診断書などが必要です。
聴覚障害があると就職や職場で不利になるのですか?
聴覚障害があることで、就職活動や職場でのやりとりに制約を感じる場面があるのは事実です。ただし、障害者雇用促進法により、企業には合理的配慮を提供する義務があります。
実際には、チャットツールの活用や手話通訳の配置、会議資料の事前共有などによって、職場でのコミュニケーションを補う環境づくりが進んでいます。
また、ハローワークや地域の就労支援機関では、聴覚障害に配慮した職業相談やマッチングも行われています。
周囲の人ができるサポートにはどんなものがありますか?
聴覚障害を持つ人に対しては、まず相手が理解しやすい方法で話しかける工夫が必要です。
口元を見やすい位置で話す、ゆっくり明瞭に発声する、筆談をためらわずに使うなど、簡単な配慮が大きな助けになります。また、会話中に背後から声をかけるのは避け、必ず視線を合わせてから話しかけるようにします。
日常的な配慮が積み重なってこそ、互いに安心できる関係性が築かれます。何よりも大切なのは、相手の立場に立って考え、必要に応じて支援を申し出る気持ちです。
まとめ
聴覚障害は、聞こえにくさの程度や発症の背景によって影響の現れ方が異なります。音の情報が制限されることで、生活や社会活動に支障が生じやすく、本人だけでなく周囲の理解も大切になります。
聴力の程度に応じて等級が定められており、それぞれに対応する支援や福祉制度の活用が可能です。
手話や筆談のほか、音声認識アプリや補助装置といった技術も、日常生活の選択肢を広げる手段となります。
運転に関しては、聴覚障害者マークの活用や制度面の整備が進んでおり、安心して移動できる環境づくりが求められています。また、教育や就労の機会確保はSDGsの目標にも関わっており、今後も誰もが参加しやすい社会の形成に向けた取り組みが必要です。
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS 


