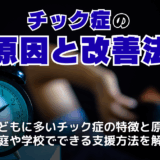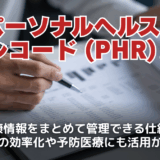ジェンダーレストイレは、性別に関係なく誰もが利用できるトイレとして注目されています。トランスジェンダーやノンバイナリーの人々をはじめ、育児中の親や介助が必要な方にも安心を提供できる点が大きなメリットです。
一方で、プライバシーや防犯への懸念、設置コストやスペース確保といった課題も指摘されています。海外や日本での導入事例、反対意見、そして解決策を整理しながら、社会的共存のために求められる多様性配慮の空間設計について考えていきます。
ジェンダーレストイレとは?

最近、駅や商業施設、大学などで「ジェンダーレストイレ」という表示を見かけることが増えました。簡単に言えば、ジェンダーレストイレは性別に関係なく誰もが使えるトイレのことです。従来の男女別トイレでは、自分の外見と心の性別が一致しない人にとって「入るのが怖い」「変な目で見られるかもしれない」という不安が常にありました。私の知人も「トイレに行くだけで緊張する」と話していたことがあります。
ジェンダーレストイレは、そうした不安を少しでも軽くしようという取り組みとして注目されています。
ユニセックストイレや多目的トイレとの違い
似たような言葉に「ユニセックストイレ」や「多目的トイレ」がありますが、実際には目的が違います。
ユニセックストイレは男女共用で使えるトイレですが、必ずしも性的少数者への配慮を前提にしているわけではありません。スペースやコストの関係で作られることも多いです。
多目的トイレは、車いすを利用する人、赤ちゃん連れの保護者、介助が必要な人などを想定して設計されます。広さがあり、オストメイト対応の設備やベッド、手すりなどが備わっているのが一般的です。
ジェンダーレストイレはこのどちらとも違い、「性別を理由に使いづらい」と感じてきた人のために作られます。個室は天井までしっかり壁で仕切られ、入口から中が見えない設計が多く、マークも男女を想起させないものが採用されます。
| 種類 | 設置目的 | 主な対象者 | 構造・設備 |
|---|---|---|---|
| ジェンダーレストイレ | 性別に関係なく誰もが安心して使える空間を提供 | トランスジェンダー、ノンバイナリー、男女別トイレに入りづらい人 | 個室完全仕切り、性別を示さないマーク、防犯配慮設計 |
| 多目的トイレ | 身体的な理由や介助が必要な人の利用支援 | 車いす利用者、介助者、乳幼児連れ | 広いスペース、ベッドや手すり、オストメイト設備など |
| 男女別トイレ | 性別ごとの利用 | 男性、女性 | 男女別入口、男性用小便器・個室、女性用個室 |
ジェンダーレストイレが注目される理由と社会的背景
このトイレが注目される大きな理由は、LGBTQ+の人々への配慮です。とくにトランスジェンダーやノンバイナリーの人たちは、公衆トイレを使うときに「どちらに入ればいいのか」と迷う場面が多いそうです。場合によっては「不審な人」と誤解されることすらあります。実際、SNSでも「トイレが怖い」という声が少なくありません。
ただ、利便性の面で考えてみてもメリットがあります。たとえば、父親が小さな娘を連れているときや、母親が息子を連れているとき、男女別トイレには入りづらいことがあります。介助が必要な高齢者と付き添う人の性別が違う場合も同じです。こうした日常の困りごとにも役立つのです。
社会的な背景も見逃せません。国連が掲げるSDGs(持続可能な開発目標)では、目標5に「ジェンダー平等を実現しよう」があり、すべての人が平等に過ごせる社会を目指しています。日本の自治体や企業もこの動きを受けて、空港や大学、商業施設などで導入を進めています。海外ではすでに普及しており、日本も追随する形になっているのが現状です。
ジェンダーレストイレは、単なる新しい種類のトイレではなく、「誰もが安心して使える社会をどう作るか」というテーマにつながっています。もちろん、防犯面や利用マナーなど課題は残ります。しかし、小さな工夫や議論の積み重ねが、安心して暮らせる社会を支える基盤になるはずです。トイレという日常的な場所だからこそ、多様性を考えるきっかけになるのではないでしょうか。
参考: ジェンダーレストイレ事情は?現状と事例、メリット・デメリットも解説 | ELEMINIST(エレミニスト)
ジェンダーレストイレの日本と海外の導入事例
ジェンダーレストイレは、まだ新しい取り組みですが、日本だけでなく世界でも徐々に広がっています。背景には「性別にとらわれずに安心して利用できる環境を作りたい」という考え方があり、近年の多様性尊重の流れとも重なります。
ここでは、日本と海外の事例を取り上げ、それぞれの特徴や利用者の声を紹介していきます。
日本の事例
まず日本のジェンダーレストイレの事例について説明していきます。
大学での導入事例
日本の大学では、トランスジェンダーやノンバイナリーの学生が安心して使えるよう、完全個室型のジェンダレストイレが導入されています。東京大学や明治大学では、入口から個室内が見えない設計や、男女表示のないシンプルなマークを採用。これにより「視線が気になる」といった不安を減らし、誰もが安全に利用できる環境を整えています。思春期の学生や多様な性自認を持つ学生への配慮として、教育現場でも注目される取り組みです。
商業施設での導入事例
ドン・キホーテなど一部の商業施設でもジェンダレストイレの導入が進んでいます。訪日外国人客や多様な利用者に対応することで、買い物や施設利用のストレスを軽減しています。完全個室型で他者の視線を気にせず使える設計が特徴です。利用者からは「安心して入れる」と好意的な声がある一方、「表示がわかりにくい」「まだ使い方が浸透していない」といった課題もあり、案内方法や設計の改善が今後のポイントとなります。
空港での導入事例
羽田空港や関西国際空港では、国際的な利用者を意識してジェンダレストイレを整備しています。明るい照明や防犯カメラ、広い通路など安全面にも配慮されており、旅行客が安心して利用できる環境です。海外の基準に合わせた設計で、言語や文化の違いによる戸惑いを減らす工夫も施されています。国内空港の先進事例として、今後の公共施設への展開にも影響を与えています。
実際の利用者の声を拾うと、「安心して利用できるようになった」「人目を気にせず入れる」といった肯定的な意見が目立ちます。ただ一方で、「表示がわかりにくい」「使い方がまだ浸透していない」といった声もあり、案内方法や設計の工夫が今後の課題といえるでしょう。
海外の事例
海外では日本よりも早く普及が進んでいます。
アメリカの事例
アメリカでは、州によっては法律で公共施設や学校に性別を限定しないトイレ設置を義務づけています。特にカリフォルニア州では2017年から「オールジェンダー」表示のトイレを設置することが法律で定められ、トランスジェンダーやノンバイナリーの人が安心して施設を利用できるようになっています。
大学や企業では、ジェンダー多様性を尊重する取り組みの一環として、キャンパス全体やオフィス内のトイレを改修する動きが進んでいます。観光地や空港でも表示を統一する事例が増えており、「誰もが使いやすい空間づくり」が社会的なスタンダードになりつつあります。
一方で、保守的な州では導入に反対する声もあり、地域間での温度差が課題となっています。
スウェーデンの事例
ヨーロッパ、とくにスウェーデンでは文化的背景もあり導入が自然に進んでいます。学校やオフィスビルで男女別を設けないトイレが一般的になっており、完全個室型や共用洗面台など、防犯やプライバシーを両立させる設計が普及しています。さらに公共施設のガイドラインにジェンダーレストイレの基準が盛り込まれるなど、制度としても整っています。
スウェーデンでは男女平等の意識が社会全体に根付いており、行政だけでなく企業や市民も協力して環境整備を進めています。利用者の多くがジェンダーレストイレは「快適で清潔」「性別を意識せずに利用できる」と評価しており、観光施設や病院でも設置されています。
台湾の事例
台湾もアジアの中では先進的な事例です。同性婚を認めた背景もあり、台北市では駅や大学でジェンダーレストイレを設置しています。政府が「誰もが安心して使えるトイレ」を掲げ、案内表示や安全対策のガイドラインを作成しており、その結果観光客や留学生も使いやすい環境が整えられています。
公共交通機関や大型商業施設では、視覚的に分かりやすいピクトグラムや多言語表記を導入し、外国人利用者への配慮も強化されていたり、大学では学生の意見を反映した設計や防犯カメラの設置など、安全性への工夫も進んでいたりと、社会的にもジェンダー平等の意識が高まっており、ジェンダーレストイレが「多様性の象徴」として広く受け入れられつつあります。
ジェンダーレストイレの導入についての利用者の反応を見ると、海外では「心理的負担が減った」「施設の印象が現代的になった」という肯定的な意見が目立ちます。ただし、「一部の地域では文化的に受け入れられていない」「古い建物では防犯面が不十分」という課題も残されています。
日本の導入は大学や空港、商業施設など一部に限られているのに対し、海外では法整備や文化的背景に支えられて広く普及しているのが大きな違いです。海外のように制度や設計基準が整えば、日本でもさらに導入が進む可能性があります。今後は利用者の安心感をどう確保するか、また社会全体でどう受け入れていくかがポイントになりそうです。
ジェンダーレストイレは、単なる「新しいトイレの形」ではありません。多様な人が安心して公共空間を使える社会づくりの一歩です。日本はまだ試行段階にありますが、海外の事例から学ぶことは多いはずです。法律や制度、文化の違いはあっても、根底にあるのは「誰も排除しない」という考え方に基づきます。今後も日本社会がどう取り入れていくのか注目されます。
ジェンダーレストイレ導入のメリット
ジェンダーレストイレは、性別に関係なく誰でも安心して利用できることを目指して設計された新しいタイプのトイレです。近年、大学や空港、商業施設を中心に導入が広がっており、その背景には社会全体で進む多様性への理解や、誰もが快適に過ごせる空間づくりがあります。
続いて、導入によって得られるメリットを2つの観点から掘り下げてみましょう。
誰もが使える安心空間の実現
まず大きなメリットは、安心感を利用者に提供できることです。従来の男女別トイレでは、トランスジェンダーやノンバイナリーの人が強いストレスを感じる場面がありました。どちらのトイレを使っても周囲の目が気になる、誤解やトラブルにつながるかもしれない等、こうした不安から外出を控える人もいたといわれます。ジェンダーレストイレは、その心理的負担を軽くします。個室が壁で完全に仕切られ、入口から内部が見えない設計が採用されることが多いため、「誰かに見られているのでは」という心配が和らぎます。実際に大学で導入された際には、「ようやく安心して授業に集中できるようになった」と学生が語った事例もあります。
このように安心して使える環境は、性的少数者に限らず一般利用者にも好意的に受け止められています。夜間に女性が一人で利用しても照明や防犯カメラの配置に配慮されている場合が多く、安全面でもプラスになります。つまり、ジェンダーレストイレは「特定の人のため」だけでなく、誰にとっても快適で安心できる空間を実現する取り組みといえます。
育児・介助・障害のある人への配慮
もう一つの大きなメリットは、多様な生活場面に対応できる柔軟さです。たとえば、父親が幼い娘を連れて外出したとき、従来の男性トイレでは利用が難しいことがありました。逆に母親が息子を連れている場合も同じです。ジェンダーレストイレなら、親子が一緒に安心して利用できます。また、介助が必要な高齢者と付き添いの性別が異なる場合にも役立ちます。付き添いの人が「どちらのトイレに入るべきか」と悩む必要がなくなり、スムーズにサポートができます。障害を持つ人や車いす利用者にとっても、個室が広めに設計されているケースでは利用の選択肢が増えるというメリットがあります。
海外でも同様の事例が報告されています。アメリカでは、公共施設で「オールジェンダー」と表示されたトイレが普及し始め、保護者や介助者から「誰にとっても利用しやすい」という評価が寄せられています。日本でも地方自治体の小中学校で導入が進み、思春期の子どもが性別を理由にトイレを避ける状況を改善する取り組みが始まっています。このようにジェンダーレストイレは、性的少数者への配慮だけでなく、子育て世帯や高齢者、障害のある人まで、多くの人の生活を支える仕組みとして機能しているのです。
ジェンダーレストイレの導入は、単に新しい設備を整えることではなく、「誰もが安心できる社会」をどう実現するかという課題に応える取り組みです。利用者が心理的な負担を抱えずに使える空間は、多様な人々の生活の質を高めます。さらに育児や介助といった日常的な場面でも大きな助けとなり、結果として社会全体の利便性と包摂性を向上させます。
今後、設計や案内方法に工夫を加えながら導入が進めば、日本でもより広く社会に根づいていくでしょう。
参考:セクシュアリティは多様、 みんなが心地よく使えるパブリックトイレとは?
ジェンダーレストイレ導入により想定されるデメリットと反対意見
ジェンダーレストイレは多様性に配慮した画期的な取り組みとして注目を集める一方で、懸念や反対意見も少なくありません。利用者の安心や社会的な受け入れを考える上では、利点だけでなく問題点をきちんと整理しておく必要があります。
ここでは導入に伴って指摘される主なデメリットを3つの観点から取り上げます。
プライバシーや防犯への懸念
最も多く聞かれるのは「安心して使えるのか」という点です。個室型であっても、男女が同じ空間を出入りする構造に抵抗を感じる人は少なくありません。特に女性利用者からは「見知らぬ男性と同じエリアを通るのは不安」という声が寄せられています。防犯面でも課題があります。トイレはもともと人目が届きにくい場所であり、待ち伏せや盗撮といった犯罪リスクが指摘されています。実際に導入施設では防犯カメラの設置や照明の強化が行われていますが、「それでも完全に安全とはいえないのでは」と懸念する意見は根強いです。
また、子どもを一人で利用させる場合に「大丈夫なのか」と心配する保護者もいます。利用者が安心できるよう、ガイドラインの明示や警備体制の強化といった工夫が欠かせません。
導入におけるコスト・スペース問題
次に課題となるのがコストとスペースです。ジェンダーレストイレは完全個室や防犯設備を備える必要があるため、従来型トイレより建設費が高くつきます。特に古い施設では配管や壁の改修が必要になる場合も多く、導入のハードルは決して低くありません。
スペースの確保も簡単ではありません。多目的トイレや男女別トイレとのバランスを考えると、限られた面積の中で新たな設備を加えることは容易ではないのです。その結果、「ジェンダーレストイレを設置するなら他のトイレ数を減らさざるを得ないのでは」という懸念も出ています。
実際、自治体や企業が導入を検討する際には「利用者数に見合った効果が得られるのか」「予算に対して優先度が高いのか」といった議論が繰り返されています。つまり理念だけでなく、現実的なコストの問題が大きな壁となっているのです。
SNS炎上や廃止事例(歌舞伎町・万博)
さらに注目されるのが、導入後に生じたトラブルや反発です。代表例として新宿・歌舞伎町に設置されたジェンダーレストイレがあります。性別を問わず使えることを目的に設置されましたが、一部で「治安が悪化するのではないか」「犯罪の温床になるのでは」といった批判が噴出し、SNSでも激しい議論が巻き起こり、結局わずか数か月で廃止に追い込まれました。
また、2025年大阪・関西万博でもジェンダーレストイレの導入が検討されましたが、一部から「利用者が混乱する」「かえって差別を助長するのでは」という反対意見が強まりました。結果として規模の縮小や設置場所の限定が行われ、当初の計画から修正されています。
こうした炎上や廃止の事例は、社会的な合意形成の難しさを示しています。多様性への配慮という理念が理解されても、実際の運用で不安やトラブルが広がれば逆効果になりかねません。そのため、施設管理者は「どのように周囲に説明し、利用者に受け入れてもらうか」という点を重視する必要があります。
ジェンダーレストイレの導入は、社会的に意義深い一歩であると同時に、課題の多い取り組みでもあります。プライバシーや防犯の懸念、費用やスペースといった現実的な問題、さらにはSNSを通じた世論の反発まで、多方面にわたるリスクが存在します。
今後の導入にあたっては「安全性の確保」「分かりやすい案内」「利用者への理解促進」が欠かせません。メリットとデメリットを冷静に整理し、利用者一人ひとりが安心できる仕組みを整えることが、社会的共存に向けた第一歩となるでしょう。
参考: 「ジェンダーレストイレ」わずか4カ月で廃止 新宿・歌舞伎町タワー 「安心して使えない」抗議殺到の末に
参考:タレント・アレン トランスジェンダー受け入れ女子大学に苦言「不安を助長する可能性」ネットでは賛否両論
ジェンダーレストイレ問題の解決策
ジェンダーレストイレは、多様な人々が安心して利用できる空間をつくるための重要な取り組みですが、その普及にあたっては課題も少なくありません。利用者のプライバシーや防犯上の不安、導入コスト、さらには社会的な理解不足といった問題が指摘されています。
こうした課題を乗り越えるためには、単に設備を設置するだけでなく、工夫を凝らした設計や利用者への丁寧な周知が欠かせません。ここでは、具体的な解決策を2つの観点から考えていきます。
マークの工夫や導線の分離設計
まず必要なのは、利用者が安心して入れるようなデザイン上の工夫です。現在、日本では「オールジェンダー」と書かれた英語表記や、シンプルな図形を用いたマークが使われています。しかし、利用者の中には「意味が分かりにくい」「男女トイレとの違いが伝わらない」と感じる人もいます。そのため、誰にでも直感的に理解できるピクトグラムや、施設ごとに統一された分かりやすい表示が求められています。
また、トイレの導線設計も重要です。入口から個室が直接見えないように配置することで、安心感を高められます。さらに、男女別トイレと並列に配置するのではなく、やや離れた位置に独立させることで「視線が気になる」という不安を軽減することができます。海外では、個室を一列に並べるのではなく、独立したブース型として配置し、共用の洗面台を外側に設ける設計が増えています。
こうした工夫を取り入れることで、「誰でも使える」という理念と「誰もが安心して使える」という現実の両立が可能になります。
参考: ジェンダーレストイレの問題点とは|建築事例も紹介 – BuildApp News
防犯対策と利用者教育の重要性
防犯上の懸念を完全に消すことは難しいですが、設備面での対応によってリスクを大きく下げることができます。例えば、照明を明るく保ち、共用スペースを死角のない設計にすること、防犯カメラを出入口に設置することなどが挙げられます。個室内部にカメラを置くことはできませんが、利用者が不審な行動を取りにくい環境を整えることで、安心感を高めることができます。
さらに、緊急時に利用者が助けを呼べるよう、通報ボタンや音声アラームを設置する方法も有効です。海外の一部施設では、個室ごとに小型の非常ボタンを備え、利用者が危険を感じたときに即座に警備員や施設スタッフへ知らせられる仕組みを採用しています。こうした設備投資はコストがかかりますが、利用者の安心を確保するためには欠かせません。
加えて、利用者自身の理解と協力も大切です。ジェンダーレストイレはまだ一般的に浸透していないため、利用ルールが分からず戸惑う人も少なくありません。施設側が分かりやすい説明を掲示したり、利用マナーを啓発することで、トラブルを未然に防げます。例えば「個室を必要以上に長時間占有しない」「共用スペースでは譲り合う」といった基本的なルールを明示するだけでも、利用しやすさは向上します。
ジェンダーレストイレの必要性を説明する機会
学校や職場といったコミュニティの場で「なぜジェンダーレストイレが必要なのか」を説明することもジェンダーレストイレを普及するために有効です。単に設備を置くだけではなく、背景にある多様性や人権への配慮を共有することで、利用者同士が互いに尊重し合える環境が生まれます。こうした教育的アプローチは、社会全体に理解を広げる大きな力となるでしょう。
ジェンダーレストイレを安心して利用できる環境にするためには、設計と運用の両面から工夫が必要です。マークの分かりやすさや導線設計といったハード面の改善に加え、防犯対策や利用者教育といったソフト面の取り組みが不可欠です。導入に反対する声があるのも事実ですが、それは裏を返せば「安心して使いたい」という利用者の切実な思いの表れでもあります。その声に耳を傾けながら、具体的な対策を積み重ねていくことが、ジェンダーレストイレを社会に定着させるための鍵になるはずです。
ジェンダーレストイレとSDGsの関係
持続可能な社会の実現をめざすSDGs(持続可能な開発目標)は、17の大きな目標で構成されています。その中でも、ジェンダーレストイレの導入は「平等」「安全」「不平等の是正」といった複数の目標と深く結びついています。
トイレは誰もが日常的に利用する公共インフラであるため、ここに多様性や公平性の視点を反映させることは、社会全体に持続可能性を根付かせる第一歩といえるでしょう。
目標5「ジェンダー平等を実現しよう」すべての人に配慮した空間設計
目標5は「ジェンダー平等の実現」を掲げています。トイレの利用という身近な場面でも、男女の区分にとらわれる仕組みが続けば、性自認が一致しない人やノンバイナリーの人々が排除される状況が生まれます。ジェンダーレストイレは、その壁を取り払うための具体的な解決策のひとつです。日本の大学や商業施設で導入が進んでいる背景には、「誰もが自分らしく社会生活を送れるように」という理念があります。
例えば、トランスジェンダーの学生が安心して利用できるトイレを整備することで、学びや生活の機会を奪わないことにつながります。これは教育や雇用の機会均等とも直結し、SDGsが掲げる「女性や女児だけでなく、すべての人に対して不平等をなくす」という目標を体現しています。
また、設計段階で性別を示さないマークを採用したり、個室を完全に仕切る構造にしたりすることは、目に見えない差別や偏見をなくす取り組みの一環です。平等の理念を公共空間に落とし込むことが、SDGsの実現に向けた社会的な実践となっています。
参考: JAPAN SDGs Action Platform | 外務省
目標6「安全な水とトイレを世界中に」誰もがアクセスできるトイレ環境へ
SDGsの目標6では「安全な水とトイレをすべての人に」という課題が掲げられています。世界にはまだ、安全で衛生的なトイレを利用できない人が数十億規模で存在するとされ、国際社会が解決すべき大きな問題です。ジェンダーレストイレの整備は、先進国だけの議論にとどまらず、「誰もが排除されずに使えるトイレをつくる」という意味でこの目標に通じます。特に、災害時の避難所や大規模イベント会場など、性別や国籍が入り混じる場面では「どのトイレに入っていいか分からない」という不安が生じやすいため、共通して使える設備は重要です。
また、衛生的で安全な環境を整えることは、女性や子ども、高齢者にとっても安心材料となります。海外では、学校にトイレが整備されていないために女子生徒が通学を断念するケースがありますが、性別を問わず使える衛生的なトイレを設けることで教育の機会を守ることにもつながります。ジェンダーレストイレの思想は「誰もが等しくアクセスできる公共サービス」というSDGsの理念と重なっているのです。
参考:国連UN-Water公式
目標10「人や国の不平等をなくそう」多様性に配慮した社会インフラの整備
目標10では、社会的・経済的・文化的な不平等を是正することが掲げられています。ジェンダーレストイレはまさに、日常生活における「目に見えにくい不平等」を減らすための社会インフラです。トランスジェンダーやノンバイナリーの人々は、男女別のトイレしか存在しない環境では、常に不安やリスクに直面します。ときには「不審な人」と誤解されることもあり、社会参加の障壁になってきました。ジェンダーレストイレの設置は、この不平等を是正する具体的な手段であり、社会の包摂性を高める役割を果たします。
さらに、外国人観光客や文化的背景の異なる人々にとっても、ジェンダーレストイレは安心の拠点となります。多様性を尊重する姿勢を示すことで、国際社会からの評価も向上し、結果的に地域や国全体の魅力を高める効果も期待されます。このように、トイレという身近な施設をきっかけに「誰もが居場所を持てる社会」をつくることは、目標10が求める「不平等を減らす」という課題に直結しているのです。
ジェンダーレストイレの導入は、SDGsの複数の目標と結びついています。目標5ではジェンダー平等を、目標6では安全なトイレ環境を、目標10では不平等の是正を、それぞれ実現するための手段となり得ます。トイレは単なる生活設備ではなく、社会が多様性と包摂をどのように実践しているかを示す象徴的な存在です。SDGs達成への道のりは一朝一夕では進みませんが、身近な公共空間の改善から取り組むことが、持続可能で誰一人取り残さない社会づくりの基盤になるでしょう。
参考: SDGs市民社会ネットワーク
ジェンダーレストイレに関するよくある質問
最後にジェンダーレストイレに関してよくある質問をまとめて解説していきます。
Q1. ジェンダーレストイレとは何ですか?
ジェンダーレストイレとは、男女を分けずに誰でも利用できるトイレのことを指します。従来のように「男性用」「女性用」と分かれていないため、性自認(自分が感じている性別)や見た目にとらわれず、誰もが安心して入れるのが大きな特徴です。対象はトランスジェンダーやノンバイナリーの人だけではありません。異性の介助が必要な高齢者や障害者、また小さな子ども連れの保護者など、幅広い利用者にとっても便利な設備です。
日本では個室型や多目的トイレを応用したタイプが多く、海外では「ユニバーサルデザイン」(誰にとっても使いやすい設計)の一環として整備が進んでいます。
Q2. なぜジェンダーレストイレが必要なのですか?
最も大きな理由は「誰もが安心できる環境を整える」ことです。男女別トイレでは、自分の性自認と異なる方を利用せざるを得ないケースがあり、その際に強い不安を感じる人が少なくありません。特にトランスジェンダーの方は、周囲の視線や心ない言葉に傷つき、外出をためらうこともあります。
また、異性の子どもと一緒に入る必要がある保護者や、介助を行う家族にとってもジェンダーレストイレは助かります。加えて、多目的トイレに人が集中しがちな現状を緩和できるという副次的な効果もあります。つまり特定の人のためだけではなく、社会全体にとって利便性と包容力を高める仕組みといえるのです。
Q3. プライバシーや安全面は大丈夫ですか?
利用者からもっとも多く寄せられる懸念がこの点です。性別に関係なく使えるため、「着替えや化粧がしにくいのでは」「防犯上の問題が出るのでは」といった声があります。
こうした不安に対応するため、多くの施設では設計段階から工夫をしています。例えば、個室の壁や扉を床から天井まで覆い、すき間をなくす設計が一般的です。さらに、出入口や共用部分には防犯カメラを設置し、緊急通報ボタンを備え付ける例も増えています。
また、化粧や着替えをしたい人向けに専用のスペースを別に設けることもあります。つまり、適切な設計と設備投資を行えば、安全性やプライバシーは十分に確保可能です。
Q4. 導入コストやスペースはどれくらいかかりますか?
ジェンダーレストイレは個室の防音やプライバシー確保、防犯機器の導入、案内マークの工夫などが必要になるため、一般的な男女別トイレより初期費用は高くなることがあります。また、共用洗面台や通路を広めにとる必要があり、スペースを多めに使う場合もあります。ただし、新築や大規模改修と同時に計画すれば大きな負担にはなりにくいといわれます。
長期的に見ると、多目的トイレの混雑を減らしたり、施設の評価が高まったりするメリットも期待でき、コスト以上の効果をもたらす可能性があります。
Q5. 実際に問題が起きた事例はありますか?
東京都新宿区の歌舞伎町に設置されたジェンダーレストイレでは、防犯やプライバシーの問題が指摘され、一部が廃止や改修となりました。また、2025年の大阪・関西万博でも、計画段階で反対意見が寄せられ、設計を見直す事態が起きています。一方で、事前に利用ルールを丁寧に説明し、住民や利用者との意見交換を重ねた施設では、比較的スムーズに受け入れられています。つまり、物理的な設備の整備に加え、社会的な理解や合意形成が成功のカギとなるのです。
ジェンダーレストイレをめぐる疑問の多くは「安全性」と「必要性」に集中しています。確かに課題はありますが、設計や運用の工夫次第で解決可能です。大切なのは、施設側が一方的に設置するのではなく、利用者や地域と意見を交わしながら進めていく姿勢です。その積み重ねによって、ジェンダーレストイレは「誰もが安心して使える公共空間」として社会に定着していくでしょう。
まとめ
ジェンダーレストイレは、安全面やプライバシーへの懸念など賛否が分かれるテーマです。しかし、その根底には、性別や背景に関係なく誰もが安心して利用できる空間をつくるという社会的な使命があります。課題を無視するのではなく、防犯対策や利用ルールの明確化、設計の工夫を通じて不安を解消することが重要です。多様な人々が共に過ごす社会において、互いの立場や視点を尊重し合う空間設計は、共存の基盤を築く第一歩となります。
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS