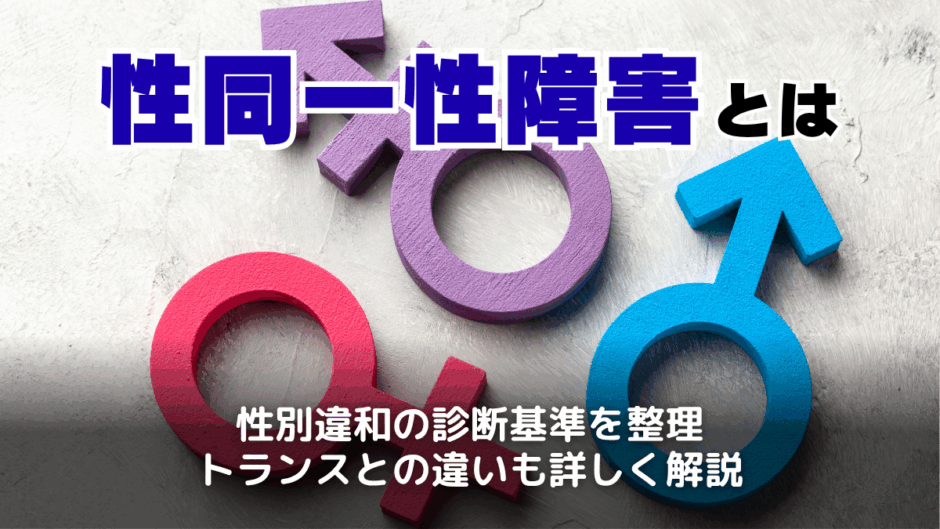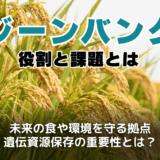性同一性障害は、身体の性別と自己認識する性(性自認)が一致しないことで、本人にとって強い違和感や苦痛をもたらす状態です。メリットとしては、診断書を取得することで戸籍変更やホルモン治療、手術などの支援につながる制度が整備されつつある点が挙げられます。
一方で、特例法により性別変更に厳しい条件が課せられており、手術の義務化や生殖不能の要件など、本人の自由意思や人権を制限するというデメリットもあります。また、「生まれつきじゃない」などの誤解も社会的障壁の一因です。本記事では、性同一性障害の定義、診断テストの流れ、トランスジェンダーとの違い、特例法や手術の制度的背景まで、正確かつ実用的に解説します。
性同一性障害とは?

性同一性障害とは、自分が認識している性別(性自認)と、出生時に割り当てられた身体的な性別との間に強い不一致を感じる状態を指します。この違和感が継続的かつ深刻なストレスとなり、日常生活に支障をきたす場合、医療の対象となることがあります。
以前は精神障害の一種として分類されていましたが、現在では人権への配慮や国際的な理解の進展により、病気や障害とは異なるものとして再定義されつつあります。医療・法律・社会制度など多角的な視点が必要とされるこの概念は、今なお変化の過程にあります。
性同一性障害の定義とICD/DSMにおける分類
かつて「性同一性障害」は、アメリカ精神医学会の診断基準DSM-IVや、WHOのICD-10で精神障害の一種とされていました。しかし、2019年に改訂されたICD-11では、「Gender Incongruence(性別不合)」という新しい名称が採用され、精神疾患の分類から除外されました。
これは、性自認と身体的性別の不一致が必ずしも病的であるとは限らず、社会的・身体的な支援の必要性に注目した結果です。DSM-5でも「Gender Dysphoria(性別違和)」として再分類されており、「個人の苦痛」に焦点を当てた表現へと変化しています。こうした診断体系の変化は、性の多様性を尊重する国際的な潮流を反映しています。
性同一性障害とトランスジェンダーとの違い
性同一性障害と混同されがちな用語に「トランスジェンダー」がありますが、この2つは本質的に異なる概念です。トランスジェンダーは、自身の性自認が出生時に割り当てられた性別とは異なると感じる人すべてを含む、広義の社会的・文化的なカテゴリーです。
一方で性同一性障害は、医学的・臨床的に診断される概念であり、医療的介入が必要とされるケースに限られます。
| 性同一性障害 | トランスジェンダー | |
|---|---|---|
| 定義 | 医学的・臨床的に診断される状態 | 広義の社会的・文化的なカテゴリー |
| 範囲 | 医療的介入が必要とされるケースに限定 | 性自認が出生時の性別と異なる人全般 |
| 診断の有無 | 医師による診断が必要 | 診断は不要、自己認識による |
| 本人の選択 | 診断を受けるかどうかは本人が決定 | 自己の性自認に基づく |
| 社会的理解 | 医療・法律分野で扱われることが多い | 多様な性のあり方として広く社会に存在 |
つまり、すべてのトランスジェンダーの人が性同一性障害と診断されるわけではありませんし、診断を受けるかどうかは本人の選択に委ねられています。この違いを理解することは、誤解や偏見をなくすためにも大切です。
性同一性障害と性別違和や性別不合との違い
性同一性障害と性別違和や性別不合との違いは、同じ状態や症状を指すうえで呼び方の違いがあります。性同一性障害という呼び方は障害というイメージが強く、病気を強くイメージさせてしまうということから、現在ではあまり使用されていない言葉です。
対して性別違和はアメリカの精神科医が使用している診断名で、体の性と性自認が異なることから精神的に負荷がかかっていたり、機能障害が起こっている状態の時に診断・使用される場合が多い言葉です。
性別不合も基本的には性別違和とほぼ同じ意味合いで使用されますが、性別不合はWHOが主に使用している言葉です。性別不合は精神疾患といった意味合いは含まれていません。
LGBTQと性同一性障害の関係
LGBTQは概念としてとても広い意味を持っているため、性同一性障害もLGBTQに含まれています。
性同一性障害はあくまでも診断名として呼称される場合が多く、自分自身で名乗る際にはトランスジェンダーと伝える場合が多々あります。
LGBTQと伝えても自分自身の性別に違和感があるという感覚を持っている人だと伝えることはできますが、より理解してほしい場合は、性同一性障害もしくはトランスジェンダーであると伝えるとスムーズです。
性同一性障害の原因と脳・ホルモンの影響
性同一性障害の原因はひとつではなく、脳の構造的特性、胎児期のホルモン環境、さらには遺伝的要素など、生物学的に複雑な要因が関与していると考えられています。近年では、こうした医学的・神経学的背景を理解することが、偏見や誤解をなくす第一歩として重要視されています。
「性自認の違和感は生まれつきのものではなく、育ち方や親子関係が影響している」などの誤った見解も一部に残っていますが、国際的な医療機関や研究機関の見解では否定されており、むしろ生物学的な根拠の解明が進んでいます。
脳の性分化の変異
人間の脳は、胎児期のある段階で「性分化」と呼ばれるプロセスを経て、男性型または女性型の脳構造に発達していくとされています。この時期に影響を与える要因のひとつが、胎児期のホルモン環境です。性ホルモンの分泌バランスや作用が神経回路の形成に影響を及ぼすことで、自己の性別に関する認識、つまりジェンダーアイデンティティが確立されていきます。
脳の性分化の異常や変異は、性同一性障害の発症と関連している可能性があるとされており、実際に性別不一致を示す人々の脳をMRIなどで調べた研究では、生物学的性別と異なる性の脳構造的特徴が見られることがあります。こうした研究成果は、性同一性障害が心理的な「思い込み」ではなく、脳の発達に関わる神経学的要素に基づいている可能性を示しています。
ホルモン環境と遺伝要因
胎児期のホルモンの量や分泌タイミングも、性自認の形成に大きな影響を与えます。例えば、男性胎児のテストステロンの分泌が十分でなかった場合や、脳がその作用を正しく受容できなかった場合には、出生時に割り当てられた性別とは異なる性自認が形成されるリスクが高まるという指摘があります。また、出生後もホルモン環境がジェンダーアイデンティティの安定性に影響する可能性があるとされ、ホルモンの影響は胎児期に限定されるものではありません。
加えて、遺伝子レベルでの研究も進みつつあります。一部の研究では、性同一性障害を持つ人々の間に共通する遺伝的マーカーの存在が示唆されており、特定の遺伝子変異やホルモン受容体の感受性に差異がある可能性があると報告されています。もっとも、遺伝要因だけで性同一性障害が生じるとは限らず、環境や心理的要素との相互作用によって複雑に形成されていると考えられています。
参考:日本精神神経学会
性同一性障害の特徴
続いて、性同一性障害の特徴をご紹介します。
性別に対する違和感が強い
性同一性障害の人は自分が思っている性別と、自分の身体の性別が一致していないと感じているため、性別に対する違和感が強い点が特徴として挙げられます。
第二次性徴期には身体的な変化もあるため、自分の身体に嫌悪感を強く覚えたり、鏡に映った姿に強い違和感を覚えたりします。それにより精神的に苦痛を感じたり、抵抗感がある場合もあります。
反対の性別になろうとする
身体的性別とは逆の精神的性別の肉体になろうとする点も、性同一性障害の特徴として挙げられます。
肉体が男性なら女性的な服装を選んだり、女性なら筋トレを始めてみたりといった行動をしたりと、自身とは反対の性別になるような行動が見られます。
性同一性障害の人々が感じる問題・課題
性同一性障害の人々が感じる問題・課題を見ていきましょう。
差別や偏見の目にさらされる
LGBTへの理解が進んできているとはいえどうしても性同一性障害の人々は、差別や偏見の目にさらされることは免れません。
一部の人たちから差別であったり、ハラスメントを受けたりといったこともまだまだ起こりえます。そういった経験から性同一性障害の人は集団に属すことが怖くなり、孤独にも陥りやすいです。
生きづらさを感じる
上記で解説したようなハラスメントや偏見、差別によって生きづらさを感じる場合も多々ありますが、それだけでなく家族の無理解や社会通念上の男女恋愛が一般的という概念も、問題や課題として挙げられます。
また肉体的性別のふるまいを求められる場面が多い点も、性同一性障害の人たちが感じている課題として挙げられます。
周りの無理解や一部の性同一性障害を偽って女子トイレに侵入したり女湯に入ったりといった男性によって、より生きづらさを感じることになってしまっています。
医療サービスの受けづらさ
性同一性障害の人は肉体に違和感があるため、病院での検査などにも違和感がある場合があります。自認している性別と戸籍上登録されている性別に違和感があるため、受診をためらってしまったり健康診断に抵抗がある人もいます。
性転換手術をしている場合は、戸籍上の性別と見た目が異なるため、さらに受診のハードルが上がってしまう場合もあり、医療サービスの受けづらさは問題点として挙げられます。
性同一性障害の診断の流れと診断テスト
性同一性障害は、本人が長年抱える「性別の違和感」を中心に判断されますが、診断には慎重なプロセスが必要です。なぜなら、単なる一時的な違和感や思春期の不安とは異なり、医療的・法的手続きに関わる重大な診断であるためです。
特に、日本では「性別変更」を申請する際、精神科医からの診断書の提出が法的に必要とされており、そのためには正確で多角的な診断が求められます。ここでは、初期相談から診断書取得に至るまでの流れと、補助的に使われる自己診断チェックリストを紹介します。
初期カウンセリング・精神科受診
性別に関する強い違和感を持ち続けている場合、まずは精神科や性同一性障害に対応している専門外来を受診するのが第一歩です。一般的には、初回の診察で詳細な聞き取りが行われ、幼少期から現在までの性に関する意識や行動、違和感の程度などを確認されます。
この段階では、単に「男になりたい」「女になりたい」という表現だけで判断されることはありません。むしろ、「いつから」「どのように」感じてきたのかという時間軸での一貫性や継続性、そしてその状態が本人にとってどれほどの苦痛になっているかが診断のポイントになります。
一定期間にわたるカウンセリングや経過観察を通じ、医師は性同一性障害かどうかを総合的に判断していきます。場合によっては、発達障害や精神疾患との区別が必要なため、複数回の受診や心理検査が必要となることもあります。
DSM-5やICDなどによる国際的診断基準
性同一性障害で診断書は、医療的な治療や法的手続きを進めるうえで不可欠な書類です。特に日本では、戸籍上の性別変更を認める「特例法」で、精神科医など専門医による正式な診断書の提出が義務づけられており、ホルモン療法や性別適合手術(SRS)を受ける際にも必要となることがほとんどです。
この診断書は、患者本人の性別違和が継続的かつ著しいものであることを医学的に証明するものであり、その根拠として使用されるのがDSM-5やICDなどの国際的診断基準です。以下の表は、2つの診断基準の違いをわかりやすくまとめます。
画像引用元:LITALICO
DSM-5は、性別違和(Gender Dysphoria)という用語を用い、「性自認と身体的性の不一致によって生活機能に支障が出ている状態」に焦点を当てます。一方、ICDでは「性別不合(Gender incongruence)」という用語が使われ、精神障害の一種としてではなく、「性的健康の課題」として分類されている点が特徴です。このような国際的動向は、「性同一性障害=精神疾患」とみなす旧来の考え方からの脱却を促進しています。
診断書を取得するには、まず専門医とのカウンセリングや心理検査を受け、DSMやICDの基準に沿って評価される必要があります。その後、医師が総合的に判断したうえで、診断が確定し、診断書が発行されます。一般的には複数回の通院と一定期間の経過観察が求められ、即日で発行されることはほとんどありません。
なお、この診断書は単なる医療文書ではなく、戸籍変更や就労上の配慮、医療機関での治療申請などさまざまな制度的手続きでは法的効力を持つ大切な文書となるため、信頼できる医療機関での取得が推奨されます。
自己チェック形式の診断テスト
近年、インターネット上には性同一性障害の傾向を測る自己診断チェックリストが多数公開されています。これらはあくまで参考的なツールであり、正式な診断ではありませんが、自分の感じている違和感や傾向を可視化する手段として活用されています。
たとえば、「自分の体に違和感があるか」「他者からの性別の扱いに苦痛を感じるか」「反対の性別で生活することを望むか」などの質問に回答する形式で、自認と社会的役割の不一致度を測ります。
ただし、自己診断はあくまできっかけにすぎず、最終的な診断は医師による専門的評価が必要です。自己チェックによって不安が強まったり、確信が持てたとしても、それを根拠に治療や法的申請を進めることはできません。違和感が続く場合は、早めに専門医に相談することが望ましいでしょう。
性同一性障害の治療・ホルモン療法・手術の進め方
性同一性障害の治療は、単一の処置で完結するものではありません。心と体の調和を図るために、医療現場では段階的な治療アプローチがとられています。一般的には、まず精神療法によって本人の性自認や生活への影響を丁寧に確認し、その後にホルモン療法、さらには必要に応じて性別適合手術(SRS)へと進みます。どの段階でも本人の意思が最優先され、医療者は慎重かつ継続的に寄り添いながら治療を進めていきます。
ホルモン療法の効果と注意点
ホルモン療法は、身体的性徴を希望する性別に近づけるための医療措置であり、多くの当事者にとって生活の質(QOL)を大きく向上させる治療法です。たとえば、男性から女性(MTF)への移行を希望する場合にはエストロゲンや抗アンドロゲン剤が、女性から男性(FTM)の場合にはテストステロンが使用されます。
この療法により、体毛や筋肉の付き方、皮膚の質感、乳房の発達、声質などに変化が現れます。ただし、その効果には個人差があり、完全に望んだ外見に変わるわけではないことや、一部の変化は不可逆的であることも理解しておく必要があります。また、ホルモンの継続使用は肝機能や血栓リスクなどの副作用を伴うため、定期的な血液検査や医師の指導のもとで実施することが必須です。
性別適合手術(SRS)の種類・費用・リスク
性別適合手術(SRS)は、身体的性の修正を目的とした外科的治療です。これは精神療法およびホルモン療法の後、十分な経過観察と本人の強い意思が確認された段階で選択されます。
MTF(男性→女性)では、陰茎・睾丸の摘出と膣の形成が主な手術となり、FTM(女性→男性)では、乳房切除、子宮・卵巣の摘出、さらには陰茎形成術などが行われます。ただし、特に陰茎形成は技術的・費用的に大きな負担があり、日本では実施できる施設が限られています。
費用は内容や施設によって異なりますが、保険適用外の場合には数十万円から200万円を超えることもあり、手術費用の問題は依然として大きなハードルとなっています。また、麻酔リスクや術後の感染症、長期にわたる疼痛や感覚変化などのリスクも存在します。医療機関との十分な説明・合意が必要不可欠です。
術後の生活
性別適合手術を終えたあとも、治療は完了ではありません。術後には長期的なフォローアップが必要とされ、これは身体面・心理面の両方に関わる継続的なケアを意味します。たとえば、MTFでは膣の開存維持のためにダイレーション(拡張器具の挿入)が日課となるほか、FTMでも尿道機能や性器感覚の調整が必要となるケースがあります。
また、外見が変化した後も社会生活上の課題(職場での呼称、書類上の性別など)が残りやすく、これらに対処するためにはカウンセリングや支援団体との連携が欠かせません。手術をもって「すべてが終わる」わけではなく、その後の生活も医療と社会が支えるべき領域です。
参考:日本女性心身医学会
性同一性障害と社会制度の壁と現状
性同一性障害に関する理解は、近年ようやく広まりつつありますが、法制度や社会インフラは依然として不十分です。性別違和を抱える人々にとって、日常生活や社会参加の不便さ、制度の壁は深刻な問題です。
特に、戸籍上の性別を変更する際には、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(通称:特例法)」の厳しい要件を満たす必要があり、多くの人が制度の狭間で困難を抱えています。ここでは、制度的背景とともに、教育現場・職場・家庭での配慮や支援の現状を見ていきます。
「性同一性障害特例法」と戸籍変更の5つの条件
日本では、2004年に施行された特例法によって、戸籍上の性別を変更するための法的枠組みが整備されました。しかし、その要件は現在でも厳格で、すべてを満たさなければ変更申請は認められません。以下の5条件が代表的な基準です。
画像引用元:日本経済新聞
これらの条件に対しては、国連や人権団体から「人権侵害の恐れがある」との批判も上がっており、特に「強制不妊手術」や「親になる権利を否定する条件」は見直しが求められています。現行法のままでは、自己決定権や家庭を持つ自由との矛盾が解消されません。
教育・職場・生活の中で求められる合理的配慮
戸籍上の問題に加え、トランスジェンダーの人々は教育や職場、日常生活のあらゆる場面で「性別の扱い」による不都合を感じています。学校では制服の選択やトイレの使用に制限がかかることが多く、自認する性別のままで安心して通学することが困難なケースもあります。
職場では、採用時に戸籍上の性別が問題視されたり、性別変更後の呼称や名札が旧名のまま使用され続けるなどの問題もあります。また、性別を理由に部署異動や昇進が制限されるなどの差別的対応が、依然として見受けられるのが現状です。
こうした状況に対し、トランスジェンダー当事者が安心して学び、働き、生活できるようにするためには、「合理的配慮」が必要です。具体的には、ジェンダーに配慮した制服の選択自由・中立的トイレの設置・通称名使用の柔軟な対応などが求められます。
家庭と支援団体によるサポート
トランスジェンダーや性同一性障害の人々を支えるうえで、医療制度や職場制度と並んで大切なのが、家庭と地域社会の理解・支援です。ここでは、本人の生活を支えるための家族と団体の役割を2つの視点で見ていきます。
家族ができるサポートとその困難
性自認をカミングアウトされた家族は、戸惑いや混乱を感じることも少なくありません。しかし、家族の無条件の受容と理解こそが、本人の安心と自己肯定感の基盤になります。とくに未成年の場合、保護者が性別移行に伴う学校や医療機関との調整を担うケースが多く、家族の支援が不可欠です。
一方で、保守的な家庭観や周囲の目を気にして支援をためらうケースもあり、親自身が相談できる場や情報にアクセスできるかどうかが分かれ道になります。
支援団体・相談窓口の活用
全国には、性同一性障害やトランスジェンダーに関する悩みに対応している支援団体やNPO、医療機関主導のネットワークが存在します。たとえば、「日本性同一性障害と共に生きる人々の会」「にじいろかぞく」「GID学会」などは、本人と家族の両方に情報提供や相談機会を提供しています。
また、地方自治体によっては、性的マイノリティに特化した電話相談や来所相談を設けているところも増えており、こうした公的リソースの活用も効果的です。
SDGsと性同一性障害|目標5「ジェンダー平等」との接点
SDGs(持続可能な開発目標)の中でも「目標5:ジェンダー平等」は、性別にかかわらず全ての人が平等に生きる権利を保障することを目的としています。しかし、性同一性障害やトランスジェンダーの人々は、現在も社会制度や生活環境の中で数多くの差別や不平等に直面しており、この目標の実現を阻む大きな課題となっています。
差別がもたらす社会的損失と課題
職場では性自認に基づいた服装やトイレの利用が制限されることがあり、本人が能力を発揮できずに離職する例もあります。教育現場でも制服や更衣室の制約がいじめや不登校の要因となることがあり、医療の現場では戸籍上の性別と異なる性自認の患者が適切な支援を受けられないケースも見られます。これらの不平等は、個人の尊厳を損なうだけでなく、社会全体の人材活用や生産性にも悪影響を与える重大な損失です。
多様性を前提とした制度改革・政策提案
性の多様性を前提とした制度改革は、SDGsの理念を実現するために不可欠です。性別変更の法的要件の見直しや、性別欄・通称名の柔軟な運用、医療・教育機関の慮の徹底など、具体的な制度改善が求められています。日本でも「LGBT理解増進法」が成立しましたが、理念法にとどまっており、今後はより実効性のある政策が必要です。誰もが安心して暮らせる社会の実現こそ、目標5の本質であり、性同一性障害のある人々もその中に確実に含まれるべきです。
参考:外務省
性同一性障害の方々に対して私たちができること
性同一性障害の方々に対して私たちができることをご紹介します。
性同一性障害への理解を深める
性同一性障害の人が身近にいる場合、性同一性障害への理解を深めることがまずは私たちができることのひとつです。
性別はグラデーションであることを理解し、男だから女だからといった決めつけをするのをやめてみましょう。
男女の恋愛が一般的という認知でいることも、普通の感覚だと思ってしまいがちですが、男性同士女性同士の恋愛も当然ある普通のこととして想定しておくと、性同一性障害の人たちも安心して自分の性をカミングアウトできます。
本人が自認している性別として接する
性同一性障害の人たちと接する時には、本人が自認している性別として接することが重要です。
身体の性別と精神的な性別が異なるので、周りの人も混乱してしまいますが、本人の自認している性別に合わせて生活できることがベストです。
ただお風呂やトイレといった場面では、無理して合わせる必要はなく身体の性別に合った方を利用してもらうことが共生の道でもあります。
性同一性障害に関するよくある質問
性同一性障害に関する理解は少しずつ広がってきているものの、今もなお多くの人が疑問や不安を抱えています。ここでは、実際によく寄せられる質問に対し、医学的・社会的な観点からわかりやすく回答します。
性同一性障害は病気なのですか?
かつては「精神疾患」として分類されていた時期もありましたが、現在ではそのような見方は見直されつつあります。WHOの国際疾病分類(ICD-11)では「性別不合(Gender Incongruence)」という新しい名称が導入され、精神疾患の枠からは除外されました。つまり、性同一性障害は「病気」ではなく、性の多様性のひとつと捉えられるようになってきています。
自分の子どもが性同一性障害かもしれません。どう対応すべきでしょうか?
子どもが自分の性別に違和感を抱いていると感じた場合、まずは否定せずに話を丁寧に聞くことが大切です。無理に性別を矯正しようとしたり、決めつけたりすることは、本人にとって深刻なストレスになります。必要に応じて、性同一性障害に詳しい医療機関やカウンセリングの場に相談し、専門的なサポートを受けるのが望ましい対応です。
性同一性障害の人は全員が手術を希望するのですか?
必ずしも全員が手術を望んでいるわけではありません。ホルモン療法だけを受ける人もいれば、社会的な性別移行(名前や服装など)のみで生活している人もいます。本人の希望や体調、経済的状況などにより、治療の進め方はさまざまです。性別の在り方は個々人により異なるため、外科的手術の有無でその人の「本当の性別」が決まるものではありません。
性別変更にはどのような手続きが必要ですか?
日本では「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(特例法)」に基づき、家庭裁判所の審判を通じて戸籍上の性別を変更できます。ただし、現行制度ではいくつかの条件(20歳以上、未婚、生殖不能など)を満たす必要があります。これらの条件を、国際的な人権の観点から見直しが求められている部分もあります。
周囲の人に打ち明けるべきか迷っています。
カミングアウトは本人のタイミングと意思を最優先すべき問題です。無理に打ち明ける必要はありませんし、安心して話せる環境や信頼できる相手がいる場合にのみ行うのが理想です。また、学校や職場では、理解のある第三者(スクールカウンセラーや人事担当など)を介することで、トラブルを避けやすくなります。自分の身を守ることを第一に考えましょう。
まとめ
性同一性障害は、心理的な問題ではなく、生物学的・神経学的背景を持つ性の在り方のひとつです。正しい理解と多様性の尊重は、当事者が自分らしく生きるために欠かせません。また、戸籍や医療制度、教育や職場環境でも、個人の尊厳を守る仕組みが求められています。社会全体が偏見を取り払い、法や制度の整備を進めることが、SDGsの掲げる「誰一人取り残さない社会」の実現につながります。
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS