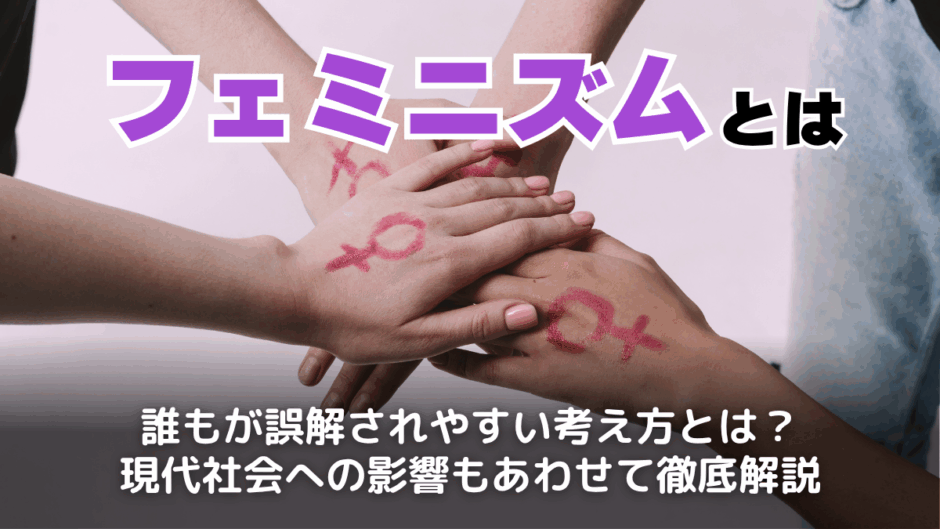フェミニズムは、女性だけの権利運動ではなく、社会に存在する構造的な性差別を問い直し、性別にとらわれず自由に生きられる環境を目指す思想です。ジェンダーに基づく不均衡を可視化し、法制度や職場、メディア表現の改善を促すなど、現代の社会課題に多くの影響を与えてきました。そのメリットは、誰もが自分らしく生きることを尊重される社会の実現に寄与する点にあります。
教育現場や企業でもその価値が再認識されつつあり、SDGsの目標とも一致しています。一方で、極端な主張への誤解や、フェミニズムを過剰に敵視する動きもあり、社会的な分断を引き起こすケースも存在します。正確な理解と冷静な議論が今、求められています。
フェミニズムとは?

フェミニズムは、性別に起因する不平等を解消し、あらゆる人が尊厳を持って生きられる社会を目指す思想です。歴史的には、女性の権利向上運動として始まりましたが、現代ではジェンダー全体の問題を扱う広義の概念へと広がっています。
社会に根付いた差別的な構造を可視化し、それに抗う姿勢を持つことがフェミニズムの核です。これは個人の生き方にとどまらず、制度や文化、経済など幅広い領域に波及しています。
性別による格差は、教育機会の不均衡や所得の違い、政治参画の低さなど、数値としても現れています。こうした実態を踏まえ、フェミニズムは単なる「思想」ではなく、現実の課題解決の糸口として重要視されています。
フェミニズムの目的
フェミニズムの目的は、性差別を是正し、平等な社会を築くことです。とくに歴史的に抑圧されてきた女性や性的少数者が、対等な立場で社会に関与できる環境づくりが求められています。
ただし、フェミニズムは「女性のため」だけの運動ではありません。男性に対しても「男らしさ」を強いる社会構造を問い直す機会となり、性別にかかわらず自由な選択ができる社会の実現を目指しています。
この思想は、家庭内の役割分担から企業の人事制度、学校教育、さらにはメディア表現にまで影響を与えています。つまり、私たちの暮らしのあらゆる場面で、フェミニズムの視点は欠かせないものになってきているのです。
フェミニズムの語源と思想的背景(femina=女性から)
「フェミニズム」という言葉の起源は、ラテン語で「女性」を意味する”femina”に由来しています。19世紀後半、フランスで”féminisme”という言葉が登場し、女性の法的権利や社会的地位の向上を訴える概念として定着しました。
思想的な背景としては、啓蒙主義の影響が色濃くみられます。とくに自由や平等といった近代的価値観を軸に、男性中心だった社会制度の見直しが進められていきました。
初期のフェミニストであるメアリ・ウルストンクラフトは、1792年に著書『女性の権利の擁護』を発表し、女性も理性を持つ存在であると主張しました。この主張は、その後のフェミニズム運動の思想的礎となっています。
フェミニズムはその後、個人の尊厳や主体性を尊重する価値観と結びつきながら、次第に国際的な思想運動としても広がっていきました。
フェミニズムとSDGs目標5「ジェンダー平等」との関係
国際連合が定めた持続可能な開発目標(SDGs)のうち、目標5は「ジェンダー平等を実現すること」を掲げています。この目標は、フェミニズムの理念と深く重なっており、すべての人が性別に関係なく平等な権利と機会を持つ社会を目指すものです。
具体的には、児童婚や性暴力、教育や医療の不平等など、世界中に残る構造的な性差別をなくすための政策が求められています。
2023年時点でも、世界の国会議員に占める女性の割合は平均26.5%にとどまり(IPU調査)、政治・経済分野での平等は道半ばです。こうした現実に対して、フェミニズムの視点が注目されています。
さらに、企業のCSR活動や地方自治体の取り組みにおいても、SDGsの目標と連動する形でフェミニズム的アプローチが導入される事例が増えています。社会全体の価値観を変えていくためには、制度だけでなく意識の改革も不可欠です。
フェミニズムとジェンダーギャップとの関係
フェミニズムとジェンダーギャップの関係は、「フェミニズムが目指すもの=ジェンダーギャップを無くすこと」と言えるでしょう。フェミニズムは男女間の差別をなくすこと・男女平等を目指しています。
元々のフェミニズムとは、女性の権利を獲得するための活動のことを指していましたが、現在では女性の権利を獲得するだけでなく、性別に基づく差別全般をなくそうという運動に発展しています。
フェミニズムの歴史と思想の変遷
フェミニズムは、単に「女性のための運動」ではなく、性別にとらわれず平等を求めてきた社会的変革の積み重ねです。その思想は時代背景とともに変化し、4つの大きな潮流、いわゆる「4つの波」と呼ばれる運動の段階に分けて語られています。
| 波 | 時期 | 主な目的・焦点 | 主なキーワード・出来事 |
|---|---|---|---|
| 第1波 | 19世紀後半〜20世紀初頭 | 女性参政権や財産権の獲得、法の下での平等 | サフラジェット運動、女性参政権、法的権利 |
| 第2波 | 1960年代〜1980年代 | 性の自由、職場・教育の平等、身体の自己決定権 | リプロダクティブ・ライツ、『第二の性』、『新しい女性の創造』 |
| 第3波 | 1990年代〜2010年代初頭 | 多様性の尊重、カルチャー・メディア批判 | インターセクショナリティ、カルチュラル・フェミニズム |
| 第4波 | 2010年代以降 | SNS時代の連帯、性被害の告発と可視化、ジェンダーの流動性 | #MeToo運動、オンラインフェミニズム、Z世代、ボディポジティブ |
以下では、それぞれの波がどのような課題に取り組み、社会にどのような影響を与えてきたのかを振り返ります。
第1波:女性参政権と市民権の獲得
第1波フェミニズムは19世紀後半に始まり、女性の政治的・法的な権利の確立を目的とした運動です。最も象徴的なのは、選挙権を求める活動で、アメリカやイギリスでは「サフラジェット」と呼ばれる女性たちが逮捕されながらも抗議活動を展開しました。
当時、女性は社会的に従属的な立場にあり、財産の保有や教育の機会にも大きな制限がありました。1920年にはアメリカで女性参政権が法的に認められ、日本でも1945年にようやく女性の選挙権が確立しました。法の下で男女の基本的な権利が同等に保障される出発点となったのがこの第1波です。
第2波:性の自由・職場・教育の平等(1960年代)
1960年代から1980年代にかけて広がった第2波フェミニズムは、より日常的な領域に目を向ける運動へと発展しました。家庭内にとどまることなく、女性が自由に働き、学び、自分の人生を選べるようにすることが目標とされました。
この時代の特徴的なキーワードには、「性の自由」や「リプロダクティブ・ライツ(生殖に関する権利)」があります。避妊や中絶の自由を求める声が高まり、身体の自己決定権という視点が重視されました。また、家庭内暴力や性的差別の可視化も進み、法制度の整備と意識改革の両面から変化を促しました。
ベティ・フリーダンの『新しい女性の創造』や、シモーヌ・ド・ボーヴォワールの『第二の性』は、こうした運動を思想的に支える書籍として大きな影響を残しています。
第3波:多様性の尊重とカルチャー批判
1990年代以降に広がった第3波フェミニズムでは、女性の中にも多様な立場や背景があることが意識されるようになりました。人種、階級、宗教、性的指向などの違いが複雑に交差する「インターセクショナリティ(交差性)」の視点が重視され、誰のためのフェミニズムなのかという問い直しが進みました。
また、この時代はポップカルチャーとの結びつきが顕著でした。映画、音楽、ファッションなどにおける女性像が批判され、ジェンダー・ステレオタイプを覆す作品やアーティストが台頭しました。一方で、フェミニズムの商業化やブランド化に対する疑問の声も上がり、「文化の中でどのように抵抗し、表現するか」が問われました。
第4波:SNS時代の運動(MeTooなど)
2010年代に入り、SNSを駆使したフェミニズム運動が新たな段階に入ります。とくに注目されたのが、2017年に世界中へ広がった「#MeToo」運動です。この動きは、性被害を受けた人々が声を上げ、加害者を告発することで、社会の無関心や沈黙の構造に変化をもたらしました。
第4波は、リアルの場だけでなくオンライン上でも活発に展開される点が特徴です。SNSによって情報が可視化され、従来は表面化しにくかった問題が瞬時に拡散されるようになりました。
その影響で企業やメディアの対応も問われ、社会の隅々にまでフェミニズム的な視点が入り込んでいます。
フェミニズムの目的を達成するメリット
フェミニズムの目的を達成するメリットを見ていきましょう。
女性の労働参加
女性が今よりももっと様々な職に就けるようになるのは、フェミニズムの目的を達成する大きなメリットとして挙げられます。男性は外で仕事をして金を稼ぎ、女性は家庭を守り子育てや家事をするという時代は、今では古いと考えられています。
ただ実際就きたくても職に就けない女性は多数いて、特に子育てが終わった女性はパートやアルバイトの職しかないため、正社員としての働き口が見つからないというのは昔からの課題です。
少しでもフェミニズムの目的を達成して、女性が今よりも職に就ける可能性が高まれば、日本のGDPも大幅にアップするといわれています。
性別に対する決めつけがなくなる
フェミニズムの目的を達成すると、女性だけでなく性別を基にした仕事の割り振りがなくなることが、期待されています。
男性だからお茶くみはしなくて良い、お茶を出すのは女性だけといった性別による決めつけがなくなるため、多くの人が性別にとらわれずに働けるようになる点も大きなメリットです。
また子どもがいる家庭では、父親が育休を数か月にわたって取得できたりと、性別にとらわれず子育てに集中できるようになる点も期待されています。
現代におけるフェミニズムの現状と課題
現代社会は、法的な男女平等が一応は保障されているものの、実際の暮らしの中には多くのジェンダー不均衡が残されています。女性の社会進出が進んでも、無意識の偏見や性別に基づく役割の押しつけは根強く存在します。そのため、フェミニズムは過去の運動ではなく、今も必要とされる社会的な取り組みとして、多様な形で続けられています。
フェミニズムが今も必要とされる理由
職場での昇進機会や賃金格差、家事・育児負担の偏りなど、目に見えにくい差別は依然として女性の生き方を制限しています。国際労働機関(ILO)の報告では、同じ職種に就いていても女性の平均賃金は男性よりも低い傾向があるとされています。また、日本の政治分野では、女性の国会議員比率はわずか10%台と先進国の中でも特に低い水準にとどまっています。このような状況が続く限り、フェミニズムは現実的な課題に向き合う重要な思想です。
さらに、性暴力やハラスメント問題も深刻です。被害を受けた女性が声を上げにくい雰囲気や、加害者側に甘い社会的対応が被害の再発を助長しています。フェミニズムの運動は、こうした構造的問題に目を向けることで、誰もが安心して生活できる社会の実現を目指しています。
フェミニズムに対する反発や誤解
近年、フェミニズムに対する強い反発や誤解も目立つようになってきました。SNSを中心に「フェミニズムは男性を敵視している」といった誤った見方が広まり、意見を述べただけで激しい批判や揶揄の対象となるケースもあります。こうした現象の背景には、男性側の不安や「既存の立場を奪われる」といった意識が影響しているとされます。
また、フェミニズムに対抗する形で、ミソジニー(女性蔑視)の言動が拡散されることもあります。たとえば、メディアで女性の発言が過剰に取り上げられたり、SNSで特定の女性が集中的に攻撃を受けたりする事例が多く報告されています。これにより、本来のフェミニズムの意義や目的がゆがめられて伝わるリスクも生じています。
誤解と偏見を解消するための対策が必要
フェミニズムは、決して女性だけのものではありません。性別を問わず、すべての人が自分らしく生きるための思想です。男性もまた、伝統的な「男らしさ」に縛られた結果、生きづらさを抱えることがあります。そうした状況を変えるためにも、フェミニズムは重要な視点を提供しています。
誤解をなくすためには、教育の充実と丁寧な対話が求められます。学校教育でジェンダーの多様性や社会構造の問題を学ぶ機会を増やすこと、メディアが偏見のない情報を発信することが大切です。また、SNSなどで意見が対立した際には、感情的にならず、背景や文脈を理解しながら冷静に議論する姿勢が必要です。
フェミニズムは特定のイデオロギーではなく、人権と自由を大切にするための社会的な姿勢です。誰かを批判するための道具ではなく、すべての人に開かれた対話のきっかけとして、今後もその意義を問い直していく必要があります。
参考元:フェミニズムとは?定義や社会運動の歴史、現在抱える問題などを解説 – PATCH THE WORLD
フェミニズムと文化・映像・メディアの関係
フェミニズムは、政治や社会運動にとどまらず、映画や音楽、ファッション、広告など多くの文化領域に影響を与えてきました。これらのメディアが伝えるジェンダー表現は、時に偏見や固定観念を助長し、時にその価値観を問い直すきっかけにもなっています。近年では、こうした文化的表象を批判的に読み解く視点として、フェミニズムが重要な役割を果たしています。
映画やドラマにおける女性像の変遷(例:フェミニズム映画)
20世紀中盤までの映画やドラマでは、女性はしばしば男性の補助的な存在として描かれてきました。従順で美しく、家庭を守ることが当然とされる女性像は、多くの作品に共通していました。しかしフェミニズムの思想が浸透し始めると、女性が主体性を持ち、自らの意思で行動する姿が描かれるようになります。
1991年に公開された『テルマ&ルイーズ』は、女性が自分の人生を選び取る姿を描いた先駆的な作品として広く知られています。また近年では、『プロミシング・ヤング・ウーマン』のように、性暴力や加害者擁護の構造を批判する内容も登場し、多様な視点からのフェミニズム的表現が増えています。
アート・音楽・広告とジェンダー表現
視覚芸術や音楽、広告でもジェンダーの表現は長らく問題視されてきました。とくに広告の分野では、「痩せていることが美しい」「女性は家事を担う存在」といったイメージが繰り返し使用され、消費文化の中に根付いてきました。これは人々の無意識に偏った価値観を刷り込む要因となります。
しかし1990年代以降、こうした一面的な描写に対する批判が高まり、多様な身体や生き方を肯定する表現も登場しています。音楽業界では、ビヨンセやレディー・ガガのように、女性の主体性や社会へのメッセージを強く打ち出すアーティストが登場しました。広告でも、「ジェンダーにとらわれない美しさ」や「多様な家族像」を描いたキャンペーンが支持を集めるようになっています。
SNSでの映像表現炎上とフェミニズム視点の登場
近年はSNSの発達により、映像や広告が瞬時に拡散し、批判されるケースが増えています。家庭用商品のCMで「女性=家事をする人」という構図を前提とした内容が公開され、消費者から「時代遅れ」として批判を受けた事例は少なくありません。こうした炎上は一過性のものではなく、社会における価値観の変化や、表現の責任について考える契機となっています。
同時に、SNSは個人が批評を発信する場としても機能しています。市民の視点から「どのような描写が偏見につながるのか」を可視化する動きが広がっており、フェミニズムの視点が日常的なメディア消費のなかに根付きつつあります。こうした流れは、映像や広告の制作者にとっても、より慎重かつ多角的な視点を求める大切な要素となっています。
参考元:NHK出版 学びのきほん フェミニズムがひらいた道 | NHK出版
自治体や企業のフェミニズムに対する取り組み事例
自治体や企業のフェミニズムに対する取り組み事例をご紹介します。
ラッシュジャパン
ラッシュジャパンは、可愛いバスボムなどで有名な企業ですが、フェミニズムに対する取り組みも行っています。
採用ポリシーにおいて2015年から採用時のエントリーシートなどに性別を記載する必要がなく、差別の禁止も制定されています。年齢はもちろん、性別、宗教などにかかわらず、その人個人と向き合って採用などを決めていくのが特徴です。
性別にかかわらず個人を重視してもらえる点が、多くの評価を高めています。入社後も全社員がダイバーシティの理解を深めるための研修などに参加しているので、不安になることなく働けると評判です。
出典:福利厚生ナビ
大林グループ
大林グループは、女性でも働きやすい環境を作っています。女性専用の更衣室やトイレはもちろん、現場の作業服なども女性が着やすいデザインに変更しています。
女性用トイレにはナプキンも設置してくれたりと、本当に女性が働きやすく負担を減らしてくれている企業です。
男性に対しても、男性に向けて育児セミナーを行っていたり、男性の育休取得を促進していたりと、わかりやすい男性に対するサポートも充実しています。
出典:福利厚生ナビ
気仙沼市
気仙沼市では、気仙沼市ジェンダーギャップ解消プロジェクトを開催していて、女性だけでなく誰もが働きやすい環境を作るため、就労環境の構築を目指しています。
経済界・産業界からジェンダーギャップ解消のための取り組みを行っています。
他にも働く女性のためのキャリア応援プログラムや市民向けのセミナーなども行われています。
フェミニズムに関するよくある質問
フェミニズムという言葉を目にする機会は増えていますが、その意味や目的について十分に理解されているとは限りません。SNSや報道で取り上げられる一方で、「女性だけの運動なのでは?」「なぜ批判されるのか」といった声も根強くあります。
この章では、フェミニズムをめぐって多くの人が抱く代表的な疑問に対し、事実にもとづいた視点から順に解説します。
フェミニズムは女性のためだけの思想なのですか?
フェミニズムは、女性の権利拡大を中心に発展してきた思想です。
しかし、現代においては性別を問わず、すべての人がジェンダーによる差別を受けずに生きるための枠組みとして広く共有されるようになりました。男性が「男らしさ」を強制されることや、LGBTQ+の人々が抱える困難もまた、フェミニズムが指摘する社会構造の問題に含まれます。その意味で、誰にとっても大切な視点といえます。
なぜフェミニズムに対する批判があるのですか?
フェミニズムに反対する意見が生まれる背景には、誤解と偏見があります。たとえば、フェミニズムを「男性否定」や「過激な思想」と捉える風潮が根強く、事実と異なるイメージが先行していることが多いです。また、現状の利益構造が変化することへの不安も一因とされます。
実際には、フェミニズムは社会全体の平等を求める思想であり、誰かを排除するものではありません。
フェミニズムに明確な対義語はありますか?
フェミニズムの対義語は、明確に定義されているわけではありません。ただし、思想的に反する立場として「男尊女卑」や「性差別主義」、あるいは「アンチフェミニズム」という言葉が用いられることがあります。中でも「ミソジニー(女性嫌悪)」は、女性に対する敵意や蔑視を示すもので、フェミニズムと真逆の価値観といえます。
こうした構造を可視化し、是正しようとするのがフェミニズムの役割です。
男性でもフェミニストになれますか?
性別に関係なく、誰でもフェミニズムを支持し、実践することができます。現代のフェミニズムでは、性別に基づく不平等の問題を「社会構造の課題」として捉えており、特定の立場や属性に限定するものではありません。実際、男性フェミニストとして発言する著名人や研究者も世界各地に存在しています。
男女の区別にとらわれず、社会をより公正にしたいと考える人ならば、誰でもその担い手になれます。
フェミニズムは今後どのように変わっていきますか?
フェミニズムは時代の変化とともに柔軟に進化してきました。現在は第4波と呼ばれ、SNSを通じて声を上げる動きが活発化しています。性暴力への問題提起や、生理の貧困、トランスジェンダーの権利など、多岐にわたる課題に対応しながら発展を続けています。
今後は、人種や階級、障害など複数の社会的要因が交差する「交差性(インターセクショナリティ)」の視点がいっそう重視されるでしょう。
まとめ
フェミニズムは、女性だけの運動ではなく、性別にとらわれず誰もが尊重される社会を築くための視点です。時代の変化とともに主張の内容も進化し、今ではジェンダー平等というより広い枠組みの中で語られるようになりました。特に、SNSや映像文化の発展によって、新たな表現の場でも議論が深まっています。誤解や対立が生じる背景には、フェミニズムの多様性と社会の変化への戸惑いがあるのかもしれません。だからこそ、まずは正しく知り、対話を重ねることが欠かせません。
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS