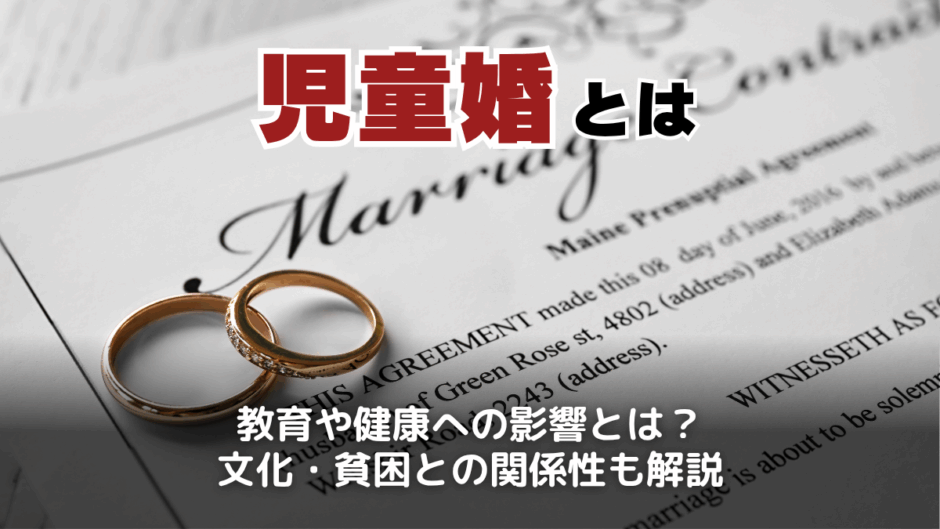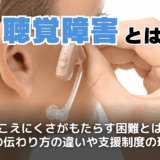児童婚は、18歳未満の子どもが親や地域社会の都合で結婚を強いられる行為であり、世界中で今なお多くの子どもたちの人生を左右しています。児童婚の最大のデメリットは、教育の機会を奪われ、将来的な就労や自立が困難になる点です。
加えて、若年での妊娠・出産による健康リスクや家庭内暴力、人格形成への深刻な影響も懸念されています。
一方で、児童婚が文化・宗教・貧困の解決手段とされる地域では、「家族を守る手段」として認識されることもあります。
これは一部の保護者にとって「生活の安定」なので一時的メリットになる場合がありますが、長期的には持続可能な社会の構築を妨げる深刻な人権問題です。
本記事では、児童婚の定義から国際的・日本の現状、事例や対策、意識啓発の取り組みまで幅広く掘り下げます。
児童婚とは?世界が向き合う子どもの人権問題

児童婚は、18歳未満の子どもが社会的または法的に婚姻関係を結ばされる行為を指します。
これは「子どもの権利条約」によって、18歳未満のすべての人を「子ども」と定義しているためです。たとえ法的に婚姻登録されていない事実婚や、宗教・慣習に基づく婚礼であっても、本人が未成年である場合は児童婚とみなされます。
とくに女子に多く見られ、本人の自由意志に基づかないケースが大半です。
教育の継続が断たれ、若年での妊娠・出産を強いられることで、健康や安全な暮らしにも深刻な影響を及ぼします。児童婚は単なる家庭の問題ではなく、世界規模の人権課題として国際社会が注目しています。
国連児童基金(UNICEF)のデータによれば、世界では毎年約1,200万人の少女が児童婚に直面しているとされています。
アジアやアフリカの一部地域では、貧困や教育機会の欠如、社会的慣習などが要因となり、今なお児童婚の慣行が根強く残っています。結婚によって少女たちの人生設計が大きく変えられてしまう現実が、多くの国で問題視されています。
児童婚問題の現状
児童婚問題の現状を見ていきましょう。
毎年約1200万人の少女が犠牲になっている
国連の統計によると、世界では毎年約1200万人以上の少女が18歳未満で結婚しているとされています。南アジアやサハラ以南アフリカを中心に高い割合が続いており、2030年までに児童婚を根絶するには、現在の取り組みをさらに加速させる必要があります。
ただ2018年の統計と比べると数自体は減少傾向にあります。ただSDGsの目標を達成するためにはさらなる努力が世界的に必要になります。
新型コロナウイルス感染症の流行によって、教育や医療、生活支援が途絶えた地域では、児童婚が増加傾向にあるという報告も出ています。今後は国際社会が協力して、教育支援や貧困対策、法整備などを総合的に進めることが求められています。
児童婚は10代の妊娠出産の温床
妊娠出産に適している年齢は生物学的に20代〜30代前半とされています。児童婚の場合は、20代~30代前半まで待ってもらえることはなく、10代のうちに妊娠出産を経験せざるを得ない場合があります。
児童婚をさせられた数多くの少女は、多くの場合10歳未満で結婚初夜を迎えさせられる場合も多々あります。その際少女の心はもちろん、身体にも大きな傷が残り人によっては死に至ってしまう場合もあります。
その証拠に世界中の15歳~19歳頃の少女の死因でもっとも多いのは、妊娠出産に伴う合併症です。
また児童婚をさせるために、レイプして妊娠させて結婚に持ち込むという場合もあります。レイプされてしまった少女は本人だけでなく、家族も周りから悪い印象を持たれたり、妊娠した少女とその子どもが経済的に生きていけない場合があるので、相手がレイプ犯であっても結婚せざるを得なくなってしまいます。
なぜ児童婚はなくならないのか?背景にある複合的な要因
児童婚は国際的に人権侵害として非難され、国連機関をはじめとする多くの組織が撤廃を目指して取り組んでいます。それにもかかわらず、世界各地では今も年間1200万人以上の少女が18歳未満で結婚していると報告されています。その背景には、貧困や教育機会の不足、宗教・文化的な慣習、そして近年ではパンデミックや紛争などの要因が複雑に絡み合っています。
児童婚を引き起こす構造的な要因を理解することは、持続的な解決策を実行したうえで不可欠です。以下では、主に4つの観点からその根本原因を掘り下げます。
貧困と家庭の経済的事情が与える影響
貧困は児童婚のもっとも深刻な要因のひとつです。経済的に厳しい家庭では、娘を早く結婚させることで食費や学費の負担を減らせるのは考え方が根強くあります。
とくに農村部では、婚姻が家族にとっての経済的「戦略」としてみなされることが少なくありません。ユニセフの統計によれば、最も貧しい世帯に生まれた少女は、最富裕層に比べて児童婚に至る確率が4倍以上高いとされています。
教育機会の欠如と女性に対する期待値
教育が保障されていないことも、早期婚のリスクを高める大きな要素です。学校に通い続けられない子どもほど、早い段階で結婚の対象とされる傾向があります。
また、一部の地域では「女の子に高等教育は不要」などの価値観が根付いており、女性には結婚して家庭を守ることが求められます。国連人口基金によると、中等教育を修了した少女は、初等教育のみを受けた少女よりも児童婚に至る割合が半減するとされています。
伝統・宗教的慣習とジェンダー規範
児童婚が根強く残る背景には、宗教的あるいは文化的な価値観も影響しています。とくに「娘の純潔は家の名誉」などの考えが支配的な地域では、少女の結婚を急ぐ傾向があります。
女性は家族に従う存在であるジェンダー規範も、児童婚を容認する空気をつくってしまっています。こうした慣習は法律だけでは変えにくく、教育や地域の対話を通じた意識改革が求められます。
パンデミックや紛争による児童婚の増加
近年、児童婚が再び増加している要因のひとつが、新型コロナウイルスの影響です。パンデミックによって学校が閉鎖され、経済的に困窮した家庭では、娘を結婚させる決断を迫られることが多くなりました。
UNICEFは、コロナ禍の影響により新たに1000万人以上の少女が児童婚のリスクに直面していると警告しています。
また、シリアや南スーダンなどの紛争地域では、安全確保の手段として幼い娘を結婚させる家庭もあり、早期婚がより深刻な問題として顕在化しています。
参考:UNFPA(国連人口基金)
参考:ユニセフ
児童婚がもたらす影響と問題
児童婚は、18歳未満の子どもが配偶者とされる行為であり、単に結婚年齢の問題にとどまらず、少女たちの将来を深く傷つける構造的な課題です。
世界中の多くの国では、いまだに宗教・文化・貧困の要因が複雑に絡み合い、このような結婚が慣習的に行われています。国連児童基金(UNICEF)や世界保健機関(WHO)は、児童婚がもたらす悪影響を、教育・健康・精神・経済の観点から詳細な調査と警鐘を発しています。
学業中断と将来の機会損失
児童婚によってもっとも直接的な影響を受けるのが教育の機会です。少女たちは結婚を機に学校を退学しなければならないことが多く、ユニセフの報告によれば、15歳未満で結婚した女性のうち約60%が初等教育すら修了していません。
教育を受けられないことは、その後の就業選択を狭め、経済的な自立を困難にします。さらに教育の中断は、知識やスキルの獲得機会を喪失することにもつながり、本人だけでなく家族や次世代にも長期的な影響を及ぼします。
若年妊娠と健康被害(フィスチュラなど)
身体的にも、児童婚がもたらす影響は深刻です。WHOは、10代前半での妊娠・出産が母体および新生児の健康にとって大きなリスクとなることを明らかにしています。骨盤の成長が未熟な時期の出産では、出血や難産などの合併症を引き起こす可能性が高まります。
中でも「フィスチュラ」と呼ばれる産科的損傷は、長時間の分娩によって膣と膀胱や直腸の間に穴が開いてしまう状態を指し、深刻な失禁症状を引き起こします。このような健康問題は身体的な痛みにとどまらず、当事者を社会的に孤立させる要因にもなっています。
精神的トラウマ・DV・社会的孤立
児童婚には精神的な影響も伴います。年齢差の大きい配偶者との生活では、少女が十分な意思決定権を持てず、家庭内での暴力や抑圧にさらされることも珍しくありません。
国連女性機関の分析では、児童婚を経験した女性は、そうでない女性に比べてうつ病や自殺願望を抱える割合が有意に高いと報告されています。とくに同世代の友人や学校などの社会との接点が断たれてしまうことは、少女の心に深い孤独と不安を植え付けます。
声を上げる手段がないまま、支援を受けられずに苦しむ少女は少なくありません。
貧困の連鎖とジェンダー格差の固定化
児童婚は一時的に家庭の経済的負担を減らすようにみえますが、長期的にみれば逆に貧困の再生産を助長します。教育を受けられずに経済的に自立できない女性は、非正規・低賃金の労働に就く割合が高く、その結果、家族全体の生活水準も向上しにくくなります。
このような状況が続くと、次世代もまた十分な教育や医療にアクセスできず、貧困から抜け出せない「負の連鎖」が生まれます。さらに、「女性は家庭に入るべき」などの社会規範が強化され、ジェンダー格差が固定化されてしまう現状も見逃せません。
日本における児童婚の実情と法制度の変遷
児童婚という言葉を聞いても、遠い国の話のように感じる人も多いかもしれません。しかし日本でも、かつては法的に18歳未満の結婚が認められていた時代が存在します。戦後の民法では、女性は16歳、男性は18歳で婚姻が可能とされており、若年での結婚が法制度のもとで行われてきました。これは国際的な人権基準と比べて大きな乖離があり、長らく見直しが求められていた分野です。
民法改正により児童婚の制限は強化されたものの、日本国内には今もなお、法律の枠組みだけでは対応しきれない課題が残っています。宗教的な儀式や地域の慣習の中で、実質的な早期結婚に近い状況が継続しているケースもあるためです。
以下では、日本の過去の制度的背景と、法改正の意義、そして今なお残る制度の限界を見ていきます。
かつて認められていた16歳婚の実態
旧民法のもとでは、女性が16歳で婚姻することが法的に許されていました。地方では特に早婚が珍しくなく、家庭の事情や妊娠などを理由に未成年で結婚に至るケースも存在していました。法務省のデータによれば、2021年時点でも16歳から17歳の女性が婚姻届を提出する事例は少なくありませんでした。
この制度には、本人の同意能力の未成熟や教育の中断などの懸念がありました。学業や社会経験が不十分なまま結婚生活に入ることは、心理的・経済的に大きな負担となります。さらに若年出産のリスクや家庭内での孤立、暴力の温床になる可能性も指摘されていました。そのため、婚姻年齢の引き上げは長らく検討されていたのです。
民法改正(2022年)による年齢統一の背景
こうした背景を受けて、2022年4月、婚姻年齢が男女ともに18歳に統一されました。この改正は約120年ぶりの見直しであり、日本の婚姻制度にとって大きな節目です。これまで女性だけが16歳から結婚できたことは、ジェンダー平等の観点から問題視されており、国際社会からも是正を求められていました。
民法改正の目的は、男女平等を法的に保障すること、そして18歳未満の結婚を原則禁止とすることで、若年婚によるリスクから子どもたちを守ることにあります。これはSDGs目標5「ジェンダー平等」にも整合するものであり、児童婚の根絶に向けた日本の明確な姿勢を示すものとなりました。
宗教・地域事情における事例と法の限界
民法改正により、法的な児童婚は大きく減少することが期待されていますが、現実には法律の網の目をすり抜けるような事例も存在します。一部の宗教団体では、民間的な儀式を通じて未成年の婚姻関係に近い形が続けられていることがあります。また、家庭内での「事実婚」状態が社会的に黙認されるケースも否定できません。
特に閉鎖的な地域社会では、親族や地域の合意のもと、若年の結びつきが法に反しない範囲で続くことがあります。これらは統計に現れにくく、実態把握が難しい問題です。法律は大きな抑止力となりますが、それだけでは十分とは言えません。今後は地域福祉、教育、医療など多方面からの連携が求められています。法の整備とともに、社会全体がこの問題を根本から考えていく必要があります。
世界の児童婚の実態|ネパール・ベトナム・インドのケース
児童婚は、世界各国で子どもたちの未来を脅かす深刻な課題です。地域ごとに背景は異なりますが、根底には貧困、教育機会の格差、宗教的な慣習、そしてジェンダーに関する固定観念が横たわっています。
画像引用元:UNICEF Global Databases 少女の児童婚
ネパール、ベトナム、インドなどの国では、文化や社会の仕組みの中で児童婚が根深く残っていることが課題です。
ネパール|農村部の貧困と教育格差
ネパールでは農村地域を中心に、未成年の結婚が今なお広く行われています。ユニセフの報告によると、18歳未満で結婚した女性の割合は約40%にのぼり、地域によっては50%近い数字も報告されています。
貧しい家庭では娘を早く結婚させることで、生活の負担が軽減されると考えられる傾向があります。また、教育を受けられる学校が近くにないことも多く、女の子は中退し、その後結婚する流れが固定化されています。
参考:ユニセフ
ベトナム|少数民族地域に残る慣習的婚姻
ベトナムでは国全体で児童婚が減少している一方、少数民族が暮らす北部や中部高原地域では、その傾向が根強く残っています。とくにモン族をはじめとする山岳地帯の民族社会では、伝統に基づいた年齢での結婚が重視されており、国家の法制度よりも地域の慣習が優先されがちです。家族ぐるみで児童婚を行う場合、外部からは実態が把握しづらく、取り締まりが難しい課題も存在しています。
参考:NHK 国際ニュースナビ
インド|宗教と家父長制が支える児童婚の構造
インドでは、児童婚の件数が世界最多とされています。ユニセフによれば、世界中で児童婚した女性の約3人に1人がインド出身とされ、特にビハール州やラジャスタン州で割合が高いことが報告されています。
法的には禁止されていますが、宗教儀式に基づく婚姻や「名誉」のための早期結婚が社会的に容認されており、法の実効性が問われています。持参金制度や男性優位の価値観が背景にあることで、少女たちの自由な選択が認められにくい状況が続いています。
参考:ユニセフ
児童婚に対する日本・世界の取り組み具体例
児童婚に対する日本・世界の取り組み具体例をご紹介します。
日本の児童婚に対する取り組み具体例
まず2022年4月まで日本では女性の婚姻可能年齢が16歳でした。しかし民法が改正され2022年の4月には、婚姻最低年齢が女性も男性と同じく18歳に変わりました。
性差がなくなり、男女ともに18歳に変更されたのは重要な変化です。
また日本政府はJICAといった団体を通じて、児童婚が行われているインドやアフリカなど児童婚全体の45%を占めている南アジアやサハラ以南に対して、教育などの支援活動や経済支援を行ってきました。
しかし世界的にみると、日本の支援はまだ足りないという見方をされてしまう場合もあります。
世界の児童婚に対する取り組み事例
世界的な取り組みを見ていくと、ユニセフとUNFPAの『児童婚を終わらせよう-行動促進のためのグローバル・プログラム』が挙げられます。
児童婚を終わらせよう-行動促進のためのグローバル・プログラムは、2016年から始まったプログラムで、10代の女の子1,400万人以上に支援を届けています。
ユニセフ以外にも、児童婚対策に取り組むワールド・ビジョンといった法人もあり、国際社会に対して結婚できる年齢をすべての国で18歳以上にするよう促しています。
ワールド・ビジョンは1日150円の支援で子どもの未来が変えられるため、世界からの寄付も多々受け入れています。
児童婚とSDGsのつながり
児童婚は一部地域の伝統や文化に起因するものと思われがちですが、実際には国際的な開発課題と深く結びついた問題です。特にSDGs(持続可能な開発目標)では、複数の目標が児童婚の撤廃と関係しています。児童婚をなくすことは、子どもや女性の人権を守るだけでなく、貧困の解消や教育の普及、健康の改善にもつながる大切な取り組みです。
このような背景から、SDGsを理解するうえで児童婚との関連性を知ることは欠かせません。ここでは、SDGsの中でも特に関係の深い目標を取り上げ、そのつながりを整理していきます。
SDGs目標5「ジェンダー平等」との関係性
SDGsの目標5では、「ジェンダー平等を実現し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図ること」が掲げられています。この中でも特に大切なターゲットが5.3で、「児童婚や強制結婚などの有害な慣行を撤廃する」ことが明記されています。
児童婚は、結婚の意思が本人にないまま決められる場合が多く、女性が自分の人生を自由に選ぶ権利を著しく制限する行為です。結婚によって学校を辞めざるを得なくなり、経済的自立や社会進出の機会も失われがちです。
その結果、女性が家庭内で従属的な立場に置かれる構造が続いてしまいます。こうした背景からも、児童婚の解消はジェンダー平等の実現に直結しています。
SDGs目標5.3「児童婚・強制結婚の撤廃」
国際連合が定めた持続可能な開発目標(SDGs)でも、児童婚の撤廃は大切なテーマとして位置付けられています。目標5「ジェンダー平等を実現しよう」の中で、ターゲット5.3では、「児童婚、早期結婚および強制結婚を含むあらゆる有害な慣行の撤廃」が掲げられています。
この目標は、児童婚が個人の自由や将来を奪うだけでなく、地域社会の持続的な成長を妨げる要因なのは認識に基づいています。児童婚をなくすためには、教育機会の拡充、女性の社会参加支援、そして家庭や地域に根付く価値観の変革が必要です。国際社会は、2030年までにこの問題を根本から解決することを目指し、各国と連携して取り組んでいます。
参考:ユニセフ
教育(目標4)、健康(目標3)、貧困(目標1)との連携
児童婚は、他の複数のSDGs目標にも悪影響を及ぼしています。まず、目標4「質の高い教育をみんなに」では、すべての子どもが無償で初等・中等教育を受けられることが理想とされています。しかし児童婚によって、学校を途中で辞める少女が後を絶ちません。
また、目標3「すべての人に健康と福祉を」では、若年妊娠による健康リスクや出産時の合併症の防止が重要視されています。未成熟な体での出産は、母体・胎児ともに危険が伴ううえ、医療体制が脆弱な地域では命に関わるケースも少なくありません。
さらに、目標1「貧困をなくそう」との関連では、教育や職業訓練を受けられないまま家庭に入ることで、貧困が次世代へと連鎖していく原因になっています。児童婚はこのように、社会のあらゆる基盤に影響を与える問題です。
児童婚に関するよくある質問
児童婚という言葉を耳にしても、自分の暮らしや日本の社会には関係がないと思われることが多いかもしれません。しかし、これは世界中の子どもたちに今なお大きな影響を及ぼしている深刻な人権問題です。ここでは、読者から特に多く寄せられる質問を取り上げ、事実に基づいてお答えします。
今も児童婚は行われているのでしょうか?
はい、児童婚は今も世界各地で実際に起こっています。国連人口基金の報告によると、毎年約1200万人の少女が18歳未満で結婚させられています。特に南アジアやサハラ以南のアフリカでは、農村部を中心に高い割合が継続しています。
法的に禁止されている国でも、慣習や宗教、地域社会の価値観に基づいて事実婚のような形がとられ、公式の記録に残らないケースも多く存在します。
法律で禁止されているのに、なぜ児童婚はなくならないのですか?
児童婚を禁止する法律があっても、それを取り締まる仕組みが地域社会の実態に追いついていないことが多くあります。
貧困や教育の欠如、女性に対する社会的期待の低さなどの複数の要因が絡み合い、「娘を結婚させたほうが生活が安定する」という考えが根付いている地域もあります。結果として、親の判断や伝統的な慣習により、法の目が届かないところで結婚が行われてしまう現状があります。
日本でも児童婚はあるのでしょうか?
日本では2022年に民法が改正され、結婚年齢は男女ともに18歳以上に統一されました。それ以前は、女性は16歳から結婚できる法律が存在していたため、若年での結婚も一定数行われていたのが実情です。
現在は法整備が進んでいますが、宗教的背景や家庭事情から、法律上の婚姻届を出さずに同居する若年層の事実婚のような状態も一部で報告されています。そうした事例も含め、児童婚的状況が完全になくなったとは言い切れません。
まとめ
児童婚は、教育・健康・経済など多方面に深刻な影響を及ぼす人権侵害です。特に少女たちが学ぶ機会や人生の選択肢を奪われ、貧困やジェンダー格差が固定化される要因にもなっています。
国連やユニセフでは、SDGsの目標5.3を軸に2030年までの撤廃を目指す動きが続いており、国際社会の連携が不可欠です。日本でも過去に存在した児童婚の制度を見直したように、法律だけでなく意識の変革が求められています。
ひとりひとりがこの問題を理解し、行動することが未来を守る第一歩となります。
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS