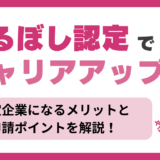バイセクシュアルは、異性にも同性にも惹かれる可能性を持つ人を指します。ただ「両方好き」という単純な話ではなく、恋愛感情と性的な関心の向き方は人によって異なります。
自由に恋愛の幅が広がるという魅力がある一方で、「浮気っぽいのでは」「迷っているだけ」といった誤解を受けやすいのも事実です。実際、周囲の無理解から自分の気持ちを語りにくいと感じる人も少なくありません。
本記事では意味や特徴、種類、割合を整理し、さらにパンセクシュアルとの違いも解説しながら、多様な性のあり方を前向きにとらえるヒントを紹介します。
バイセクシュアルとは?
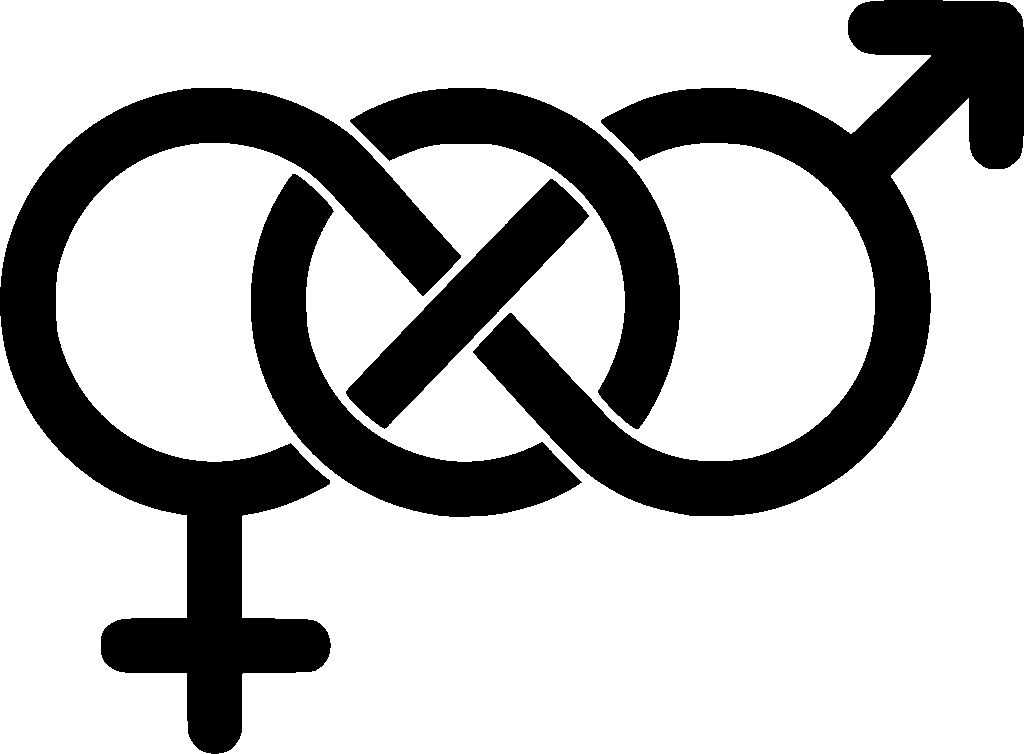
バイセクシュアルという言葉を耳にする人は増えましたが、「男女両方に惹かれる人」と短く説明されてしまうことが多いでしょう。
ところが実際はもっと幅があり、人によって感じ方も選び方も違います。単純な二択では語れない、柔らかな連続性を持ったセクシュアリティのひとつなのです。本稿では基本的な意味から歴史、現代の理解までを整理し、LGBTQ+における位置づけを考えてみます。
バイセクシュアル(両性愛)の定義と意味
バイセクシュアルは、同性と異性の両方に対して恋愛感情や性的な関心を持つ可能性のある人を指します。ただし「どちらにも同じように惹かれる」というわけではありません。たとえば、恋愛対象は同性・異性どちらにも広がっているけれど、性的な魅力を感じやすいのは異性に偏っているという人もいます。逆に性的な関心は同性に強いが、恋愛関係を結ぶのは異性が多いという人もいるのです。
つまり、バイセクシュアルと一口に言ってもその形は非常に多様で、割合や方向性は人によって異なります。この幅の広さを理解することが、偏見を取り除き、当事者のリアルな姿に近づくために欠かせません。
バイセクシュアルの語源と歴史的背景
「バイセクシュアル」という言葉は、ラテン語の「bi(二つの)」と「sexual(性的な)」から生まれました。20世紀に入ると欧米でセクシュアリティ研究や市民運動が活発になり、その中で広がっていきます。日本では「両性愛」という訳語とともに紹介され、社会に浸透しました。
しかし歴史を振り返ると、当事者が必ずしも歓迎されていたわけではありません。しばしば「どっちつかず」「信頼できない」といった偏見にさらされ、恋愛の場面でも社会生活の中でも誤解を受けてきました。こうしたイメージは今も完全には消えておらず、カミングアウトに悩む人も少なくありません。それでも、近年は若い世代を中心に「自分はバイかもしれない」と表明する人が増えており、状況は確実に変わり始めています。
バイセクシュアルの特徴と種類
バイセクシュアルと一口に言っても、その姿は一様ではありません。「男女どちらも好きになる」という単純な説明だけでは、実際の当事者の感覚を表しきれないのです。
ここでは主な特徴や恋愛傾向、個人差、そして種類の多様さについて紹介し、より立体的に理解できるように整理してみましょう。
バイセクシュアルの主な特徴
バイセクシュアルの特徴としてよく語られるのは「異性・同性どちらにも惹かれる可能性がある」という点です。ですが、誰にでも同じ強さで惹かれるわけではありません。ある人は同性に強く心を寄せながら、異性とも自然に恋愛できるかもしれません。逆に、異性と過ごす時間が多いものの、同性に対して特別なときめきを抱くこともあるのです。
こうした「揺れ動き」が特徴といえます。恋愛感情と性的欲求が必ずしも一致しないことも多く、恋愛対象と性的対象がずれるケースも珍しくありません。例えば「同性と付き合うのは自然だけれど、性的な欲求は異性に向く」といった形です。
また、バイセクシュアルの人は恋愛観やパートナー選びに柔軟さを持ちやすい傾向があります。とはいえ、それが「誰とでも付き合える」という意味ではなく、むしろ相手の人柄や価値観を重視する人も少なくありません。
バイセクシャルとバイロマンティックの違い
自分の気持ちを説明するうえで、「恋愛感情」と「性的感情」を区別して考えると理解しやすくなります。ここでよく使われるのが「バイロマンティック」と「バイセクシュアル」という言葉です。
| 用語 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| バイロマンティック | 恋愛感情を異性・同性の両方に抱く | 「恋愛関係は性別を問わず築けるが、性的関心は片方に強い」 |
| バイセクシュアル | 性的関心を異性・同性の両方に持つ | 「性的魅力を感じるのは男女どちらも対象になる」 |
このように、自分は「恋愛感情が広いのか」「性的な魅力を感じる対象が広いのか」を整理すると、自分に合った言葉を見つけやすくなります。
さらに、人によっては「そのときの環境や相手との関係性」で対象が変わることもあります。バイセクシュアルは固定的なラベルというより、柔軟な枠組みとして捉えた方がしっくりくる人も多いのです。
パンセクシュアル・ポリセクシュアルとの違い
バイセクシュアルに近い概念として「パンセクシュアル」と「ポリセクシュアル」があります。似ているようで少しずつ意味が異なるので、混同されやすい部分を整理しましょう。
パンセクシュアル(全性愛)
性別にとらわれず、人そのものに惹かれる指向です。相手の性別が男性でも女性でも、あるいはノンバイナリー(男女どちらにも当てはまらない性)であっても関係ありません。「性別ではなく人柄や相性で好きになる」という人が当てはまります。
ポリセクシュアル(多性愛)
複数の性に惹かれる指向を指します。ただし「すべて」ではなく、いくつかの性に対して恋愛や性的関心を持つという点が特徴です。
バイセクシュアル(両性愛)
異性・同性という二つの枠組みを基本に対象が広がる指向です。ただし現代では「男女どちらも」とだけ区切るのではなく、「複数の性に惹かれる」という広義で使う人もいます。
このように見ていくと、バイセクシュアルはパンセクシュアルやポリセクシュアルと重なる部分もあれば、異なる部分もあることがわかります。
| 用語 | 特徴 | 惹かれる対象 |
|---|---|---|
| バイセクシュアル(両性愛) | 異性・同性の2枠を中心に惹かれる。ただし現代では「複数の性に惹かれる」という広い意味で使う人もいる。 | 男性、女性(+人によっては他の性も含む) |
| パンセクシュアル(全性愛) | 性別に関係なく「人そのもの」に惹かれる。性別よりも人柄や相性を重視。 | すべての性(男性・女性・ノンバイナリーなど) |
| ポリセクシュアル(多性愛) | 複数の性に惹かれるが「すべて」ではない。自分が関心を持つ性の範囲が限定されている。 | 複数の性(ただし一部に限る) |
バイセクシュアルの特徴や種類を見てきましたが、共通していえるのは「人によって感じ方や表現の仕方が大きく違う」という点です。恋愛対象と性的対象の一致・不一致、比率の偏り、そして時間による変化──こうした多様性こそがバイセクシュアルの本質だと考えられます。
大切なのは「誰がどんな形で好きになるか」に正解はないということです。用語や枠組みを知ることは理解を深める手助けになりますが、最後に尊重されるべきなのはその人自身の感覚や選び方でしょう。バイセクシュアルの幅広さを理解することは、性の多様性を受け入れる第一歩でもあるのです。
バイセクシュアルの割合と社会的認知
バイセクシュアルの割合は、国や世代、調査方法によって大きな幅があります。そのため「正確な数値」を示すことは難しいのですが、各種の調査結果を照らし合わせることで、社会における認知度や受け止め方の傾向を読み取ることができます。
ここでは、日本と海外の比較、若年層に見られる意識変化、そして調査そのものが抱える限界と課題を整理していきます。
日本と海外のバイセクシュアル割合
まず日本国内の状況を見ると、いくつかの調査で「自分をLGBTQ+のいずれかに含める」と答えた人が約8〜10%存在するとされています。その中でもバイセクシュアルに該当する人の割合は3〜4%前後という報告が目立ちます。
ただし調査対象の世代や設問の仕方によっては、数値がやや上下する点に注意が必要です。
一方で海外では、もう少し高い割合が示されています。例えばアメリカのピュー・リサーチセンターやイギリスの公共調査では、バイセクシュアルを自認する人の比率が5%前後に達するという結果が出ています。特に英語圏では、メディアや教育の場でセクシュアルマイノリティに関する情報発信が比較的早い段階から行われてきたため、回答者が自己認識を示しやすい土壌が整っていると考えられます。
この比較から見えてくるのは、日本ではまだ「回答をためらう人」が一定数存在する可能性が高いということです。つまり実際の割合は調査数値より大きいかもしれません。日本特有の文化的な抑制や社会の同調圧力が、数値に影響を及ぼしているとも言えるでしょう。
参考:国連開発計画(UNDP)とジェンダー平等 | United Nations Development Programme
若年層における自己意識の変化
次に注目すべきは若年層の回答です。日本でも20代以下では「自分をバイセクシュアルと考える」と答える割合が高まっている傾向が見られます。これはインターネットやSNSを通じて性的多様性に関する情報が身近になったこと、また学校教育やメディアの中で「LGBTQ+」という言葉が以前より日常的に取り上げられるようになったことが背景にあります。
一方、海外の若者ではさらに顕著な変化が見られます。例えばイギリスの調査では、18〜24歳の回答者の中で「自分は異性愛者ではない」と認識している人が30%近くに達したというデータもあります。必ずしも全員がバイセクシュアルではありませんが、「性的指向は一つに固定されるものではない」という考え方が広まりつつあることを示すものです。
若年層の間で意識の幅が広がることにはメリットとデメリットがあります。肯定的に捉えれば、自分の感情をより柔軟に表現できる環境が整いつつあるということです。しかし同時に、学校や家庭の理解が追いついていない場合、本人が孤立を感じるリスクも残ります。特に地方や伝統的な価値観の強い地域では、世代間のギャップが課題となるケースが目立ちます。
バイセクシャルが抱える問題と課題
バイセクシャルが抱える問題と課題を見ていきましょう。
異性も同性も恋愛対象になることで起きる問題
バイセクシャルとして、異性も同性も恋愛対象になるということを周りに公言していると、男性も女性も恋愛対象になるなら、自分も恋愛対象か聞かれてしまったり、周りから避けられてしまう点は問題点として挙げられます。
また他にも家族や友人などから、異性との結婚を進められる場合もあります。
バイセクシャルの人にとっては、その時々で好きになるのが異性もしくは同性なので、自分でコントロールできるものではありません。
そのため家族や友人にそう言われるのは、バイセクシャル当事者にとってとても辛いことです。
教育の場での課題
バイセクシャルの人が自分がLGBTQだと気付く年齢は、思春期が多いといわれています。学生の期間に気付くことが多いため、周りの理解がない環境で、自分の恋愛対象が男性なのか女性なのか、悩んでいるバイセクシャルは多くいます。
そのため、教育の場でLGBTQに対する理解を深める講座などを広く行っていくことが求められますが、実際には差別などがあるのが実情です。
思春期はLGBTQではない子どもたちも、不安定になりやすく誰かをターゲットにしたがる傾向もあり、バイセクシャルの子どもがターゲットになってしまうことも十分にあり得ます。
教育の場でもより理解を深めて、誰もが過ごしやすい環境を整えることが大きな課題の一つです。
バイセクシュアルに関するよくある誤解と偏見
バイセクシュアルに対しては、正しい理解が広まりつつある一方で、根強い誤解や偏見も残っています。その多くは当事者の実際の思いとはかけ離れたイメージであり、結果的に本人を傷つけたり孤立させたりする原因となっています。ここでは代表的な三つの誤解を取り上げ、それぞれにどのような問題があるのかを整理します。
「バイセクシュアルは浮気性」という偏見
最も多く聞かれる偏見のひとつが「男女どちらも好きになれるなら、恋人がいても他の人に目移りしてしまうのでは」という見方です。しかしこれは誤解に基づく偏見です。浮気や不誠実な行動は性的指向とは関係がなく、異性愛者や同性愛者にも同じように起こり得ます。
この偏見が厄介なのは、当事者が「信頼されにくい存在」として扱われる点です。実際に恋人やパートナーがいても、「きっと他の人にも惹かれているはず」と疑われることで、関係が不必要に不安定になることがあります。当事者は「自分の気持ちを証明し続けなければならない」というプレッシャーにさらされやすく、そのことが大きな心理的負担となります。
また社会全体に広がると、バイセクシュアルは恋愛関係の対象として避けられる傾向が生まれかねません。つまり、偏見は個人の人間関係だけでなく、社会的な孤立を強める要因ともなるのです。
「混乱しているだけ」という誤解
次によく言われるのが、「本当はどちらか一方に決めるべきなのに、まだ迷っているだけだ」という認識です。しかし実際には、バイセクシュアルは一時的な迷いや過渡期ではなく、安定した性的指向の一つです。
確かに、若い時期には自分の恋愛感情や性的関心を探る中で揺れ動くことがあります。しかし、それは異性愛者や同性愛者にとっても同じことです。恋愛経験を重ねて自分を理解していく過程は誰にでも存在し、その途中で「自分はバイセクシュアルかもしれない」と気づく人も多いのです。
「混乱しているだけ」という言葉は、本人の気づきを否定するものになりがちです。その結果、当事者は「自分の気持ちを信じてはいけないのか」と不安を抱えやすくなります。特に家族や友人からそのように言われると、自己否定に結びつくことも少なくありません。社会の理解が十分でない中で、自分の存在を肯定できなくなる人がいることは深刻な問題といえるでしょう。
「ゲイになる途中」として見られる問題
もう一つ根強い見方に「バイセクシュアルは最終的に同性愛者になるのでは」というものがあります。つまり「中間地点」としての存在とみなされ、独立した指向として認められていないのです。
この見方の背景には、「人は必ず異性愛か同性愛かのどちらかに落ち着く」という固定的な発想があります。しかし現実にはそうした二分法では捉えきれない人々が存在します。恋愛や性的関心は流動的で、異性にも同性にも自然に惹かれることがある。それがバイセクシュアルであり、決して「途中段階」ではありません。
この偏見の問題は、当事者のアイデンティティを軽視する点にあります。「最終的にはゲイになるのだろう」と言われ続けると、自分の指向を正しく理解してもらえない感覚が強まり、社会から取り残されているように感じてしまいます。また、LGBTQ+コミュニティの内部でさえも「本物の同性愛者ではない」と排除される場合があり、二重の孤立を経験することもあります。本来、多様な指向はすべて同じように尊重されるべきです。「途中」や「未完成」というラベルを貼るのではなく、一つの確立した在り方として認識することが、社会に求められています。
バイセクシュアルに向けられる誤解や偏見は、「浮気性」「混乱している」「途中段階」という三つに代表されます。いずれも当事者の現実を反映したものではなく、社会的な無理解から生まれたイメージにすぎません。こうした誤解が広がることで、本人が人間関係やコミュニティから排除されやすくなり、自己肯定感を失うきっかけにもなっています。
偏見をなくす第一歩は、誰もが「性的指向は人それぞれであり、どれも正当なものだ」と理解することです。誤解を解きほぐし、対話を通じて受け止めていくことで、多様な人が安心して自分らしく生きられる社会に近づくでしょう。
SDGsとバイセクシュアルとの関係
持続可能な社会をつくるための国際的な目標であるSDGs(持続可能な開発目標)は、環境や経済だけでなく、人権や多様性にも深く関わっています。その中でも「ジェンダー平等を実現しよう」(目標5)や「不平等をなくそう」(目標10)、「平和と公正をすべての人に」(目標16)は、バイセクシュアルを含む性的少数者に直結する課題です。性の多様性を理解し尊重することは、誰もが安心して生きられる社会の土台になります。
なぜ今「性の多様性」がSDGsと関係するのか
SDGsの目標は一見すると「途上国の課題」「環境保護」といった大きなテーマに見えます。しかし実際には、身近な人権や社会のあり方に深く結びついています。たとえば目標5のジェンダー平等は、女性の地位向上だけを意味しません。性別や性的指向にかかわらず、すべての人が平等に尊重されることを目指しています。
バイセクシュアルの人々は、異性愛者や同性愛者のどちらにも当てはまらないため、社会的に見えにくくなることがあります。そのため支援や理解が後回しになりやすく、差別や孤立を経験する人も少なくありません。こうした現状を放置すれば「誰一人取り残さない」というSDGsの理念に反してしまいます。だからこそ、性の多様性をテーマとして扱うことが不可欠なのです。
法的・社会的課題と当事者の生きづらさ
日本では、同性婚がまだ法的に認められていません。また、職場や学校でのハラスメント対策も十分とはいえない状況が続いています。バイセクシュアルの場合、同性と異性の両方が恋愛対象になるため、パートナーの性別によって周囲からの反応が大きく変わることがあります。
たとえば異性のパートナーと一緒にいると「普通の異性愛者」とみなされ、逆に同性のパートナーといると「急に同性愛者になったの?」と驚かれる。本人からすると何も変わっていないのに、社会の側が勝手に解釈し、場合によっては否定的な態度を示すのです。これが当事者にとって大きなストレスとなります。
また職場では「結婚していないのはなぜ?」という雑談が圧力のように感じられることもあります。制度や環境が整っていないために、自分の指向を隠して生活せざるを得ない人も多いのが現実です。このような生きづらさをなくすには、法的な整備とともに、日常の中での理解と配慮が欠かせません。
学校・企業でできるインクルーシブな取り組み
社会を変えていく上で、学校や企業の果たす役割は非常に大きいといえます。教育の場では、性教育の一環として「異性愛だけが当たり前ではない」という事実を伝えることが重要です。小中学生のうちから多様な生き方を学ぶことで、偏見を持たずに人と接する姿勢が育まれます。
企業においても同じことが言えます。たとえば、採用や人事評価での公平性を徹底する、福利厚生制度に同性パートナーを含める、ハラスメントの相談窓口を整えるなどの取り組みが考えられます。実際に先進的な企業では「ダイバーシティ研修」を導入し、社員が多様な背景を持つ人と協働する力を養っています。
こうした取り組みは、単にバイセクシュアルやLGBTQ+のためだけではありません。多様な人を尊重できる組織は、結果的に働くすべての人が安心して力を発揮できる環境になります。つまりインクルーシブな姿勢は、社会全体の持続可能性を高める投資でもあるのです。
バイセクシュアルをめぐる課題は、個人の問題ではなく社会全体の仕組みとつながっています。SDGsの視点から見ると、ジェンダー平等や不平等の是正、そして公正な社会の実現に直結するテーマです。法制度の整備はもちろん、学校や企業での教育や職場環境の改善を進めることで、誰もが自分らしく生きられる社会に近づいていくでしょう。
参考:JobRainbow
バイセクシャルの方に対して私たちにできること
バイセクシャルの方に対して私たちにできることをご紹介します。
性的指向は個人によると理解すること
基本的なことですが、自分の性別はもちろん恋愛対象となる性別も、個人の自由ですし人によるということを理解することが、私たちにできることの第一歩です。
誰が誰を好きになっても自由であることを、まずは理解していきましょう。
バイセクシャルだからと言って必ずしも異性を好きになるとは限らないので、異性を好きになって結婚したらいいといった決めつけもNGです。
性別を決めつけないこと
多くの人は見た目で性別を決めつけてしまいがちですが、あくまでも性はグラデーションがあるということを理解しておきましょう。
見た目では性別がいまいちわからない人に対して、女性っぽい部分が少しでもあったから女性として接するのではなく、一人の人間として接することが、私たちにできることの一つです。
男性だから女性だからと決めつけることなく、相手の性的指向も男性だから女性が好き、女性だから男性が好きと決めつけた発言は避けましょう。
偏見を持たないこと
バイセクシャルと聞くと、男性でも女性でも恋愛対象となるなら、選び放題であると決めつけられたり実際に遊んでいるのでは、と思われてしまう場合があります。
そういった偏見を持たないようにすることも私たちにできることの一つです。
男性でも女性でも恋愛対象になるからと言って、誰とでも恋愛をするかといえばそんなことはありません。異性が好きな人と同じく、たまたま好きになった人が同性だっただけという場合がほとんどです。
偏見を持たずに一人の人間として、性的対象の話題になった際は無理に決めつけたりしないことが大切です。
バイセクシュアルに関するよくある質問
バイセクシュアルに関する情報はまだ十分に広まっていないため、誤解や疑問が多く存在します。ここでは特によく寄せられる5つの質問を取り上げ、分かりやすく解説します。
Q1. バイセクシュアルは「結局どちらかに決まる」のですか?
A. よく聞かれる疑問の一つが「最終的には同性か異性、どちらかに決まるのでは?」というものです。しかし、バイセクシュアルは単なる「過渡期」ではありません。異性にも同性にも恋愛感情や性的関心を抱く可能性があり、その状態は一時的ではなく継続的に存在します。
例えば、ある人は異性の恋人と長く付き合った後に同性と恋愛関係になることもあります。その場合、「同性愛者に変わった」と考える人もいますが、本人にとっては元々どちらも恋愛対象であり、その時の相手がたまたま異性か同性だったというだけの話です。つまり「どちらかに決まる」わけではなく、バイセクシュアルという指向そのものが揺るぎないアイデンティティなのです。
Q2. バイセクシュアルとパンセクシュアルの違いは何ですか?
A. バイセクシュアルは主に「同性と異性の両方に惹かれる可能性がある」人を指します。一方でパンセクシュアルは「相手の性別に関係なく、人そのものに惹かれる」という考え方です。
例えばバイセクシュアルの人が「異性と同性の両方に恋愛感情を抱く」と説明するのに対し、パンセクシュアルの人は「その人がどんな性別であっても好きになれる」と答えることが多いです。最近ではジェンダーの多様性が広く認識され、性別の二分法にとらわれないパンセクシュアルという概念が注目を集めています。
ただし、両者は境界が曖昧な部分もあり、本人がどちらの言葉を心地よく感じるかは人それぞれです。
Q3. バイセクシュアルだと告白すると、偏見を持たれませんか?
A. 実際、偏見を恐れて自分のセクシュアリティを打ち明けられない人は多くいます。よくあるのは「浮気性ではないか」と疑われたり、「気持ちが安定していないのでは」と誤解されたりするケースです。しかし、これは完全な思い込みです。恋愛において一途であるかどうかは、その人の性格や価値観によるものであり、性的指向とは関係ありません。
また、カミングアウトするかどうかは本人の自由です。信頼できる友人や理解のあるコミュニティにだけ話すという選択も十分に尊重されるべきです。最近ではSNSやオンラインコミュニティを通じて、安心してつながれる場も増えてきました。そうした環境に支えられることで、孤独感を減らし、自分らしさを肯定できる人も少なくありません。
バイセクシュアルについては「どちらかに決まるのでは」「パンセクシュアルとの違いは?」「偏見が怖い」といった疑問がよく出ます。いずれの問いに対しても共通して言えるのは、当事者一人ひとりの感じ方や選択を尊重することが何より大切だという点です。
性の多様性を理解する姿勢が広がれば、誰もが自分の指向を隠さずに安心して生きられる社会に近づいていくでしょう。
Q4. バイセクシュアルは結婚できますか?
もちろん結婚できます。恋愛対象が同性にも異性にも広がっているだけで、結婚に関しては「好きになった一人の人と関係を築く」点は変わりません。
異性と結婚する人もいれば、同性パートナーと事実婚やパートナーシップ制度を選ぶ人もいます。社会的にまだ理解が十分でない場合もありますが、法律や制度の選択肢が増えており、自分らしい形で家庭を築くことも決して難しいことではありません。
また、今後の進展によって、異性間の結婚と同様の法整備や制度の整備が進んでいくはずです。
Q5. 自分がバイセクシュアルかどうか分からない時は?
「同性も異性も気になる」「恋愛感情か友情か分からない」という悩みは自然なことです。無理にラベルをつける必要はなく、自分の気持ちを少しずつ理解していけば大丈夫です。時間をかけて恋愛の中で気づく人も多くいます。
さらに、オンライン診断や心理学的なチェックを活用して自分の傾向を知ることも可能です。大切なのは、誰かに急かされず、自分の感覚を尊重することです。
押し付けられたものではなく、自分らしさを重視することが最も意識すべきことです。
まとめ
バイセクシュアルの存在を理解することは、性の多様性を尊重する第一歩です。人を好きになる気持ちは一人ひとり異なり、正解も不正解もありません。偏見や誤解が減れば、自分らしさを隠さずに生きられる人が増え、社会全体がより温かくなります。これは個人の自由を守るだけでなく、誰もが安心して自分の居場所を見つけられる未来につながります。
小さな理解の積み重ねが、誰にとっても暮らしやすい社会を築いていくのです。
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS