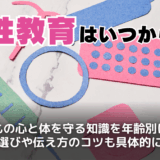布おむつは、繰り返し洗って使える育児アイテムとして、近年再び注目を集めています。赤ちゃんの肌にやさしい天然素材を使っているものが多く、通気性が高いため、おむつかぶれを防ぎやすいのが特長です。
また、使い捨ての紙おむつと比べてゴミを減らせることから、環境に配慮した育児をしたい方にも選ばれています。とはいえ、「洗濯が大変そう」「外出先での扱いが不安」など、導入に不安を感じる声も少なくありません。
本記事では、布おむつの特徴や種類、正しい使い方や洗濯方法、メリット・デメリット、保育園での対応やSDGsとの関係まで、初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。紙おむつとの違いを知り、自分に合った育児スタイルを見つける参考にしてください。
布おむつとは?

布おむつとは、綿やガーゼなどの天然素材を使って作られた、繰り返し洗って使えるおむつのことです。使い捨てのおむつとは異なり、1回使ったら捨てるのではなく、洗濯して何度も再利用できる点が大きな特徴です。
布おむつは大きく分けて2つの構造から成り立っています。ひとつは「吸収体」と呼ばれる布部分で、おしっこやうんちを吸収します。もうひとつは「おむつカバー」で、水分が漏れないように防水性のある素材で作られています。このカバーを外側に重ねて使うことで、衣類が濡れるのを防ぎます。
使い捨ての紙おむつと比べて、布おむつは自然素材のため通気性が良く、赤ちゃんの肌にやさしいのが特徴です。また、繰り返し使うことでゴミを減らすことにもつながります。衛生面を心配される方もいますが、正しい使い方と洗い方を守れば、清潔に保つことができます。
紙おむつとの比較で見える布おむつのメリット・デメリット
布おむつと紙おむつにはそれぞれに良い点と課題があります。
| 布おむつ | 紙おむつ | |
|---|---|---|
| 肌への影響 | 天然素材で刺激が少なく、かぶれや湿疹を起こしにくい | 高い吸収力があり交換頻度が少ないが、化学素材やポリマーが肌に合わない場合もある |
| コスト面 | 初期費用は高いが、繰り返し使えるため長期的に経済的 | 毎日使用するため月ごとの費用がかさみやすい |
| 環境負荷 | 洗って再利用でき、ごみを大幅に減らせる | 使用後は廃棄され、家庭ごみ増加や焼却処理による環境負担がある |
| 手間と時間 | 洗濯や準備の手間がかかり、忙しいと負担になりやすい | 交換後すぐ捨てられるため、外出時や深夜に便利 |
ここでは、主な違いをいくつかの観点から見ていきましょう。
肌への影響
布おむつは天然素材を使っているため、肌への刺激が少なく、かぶれや湿疹を起こしにくいとされています。
一方で、紙おむつは高い吸収力を持ち、交換の頻度が少なくて済む反面、化学素材や吸収ポリマーが使われており、肌に合わない赤ちゃんもいます。
赤ちゃんの肌はデリケートなので、紙おむつが合わない場合も多々あり、かぶれてしまう場合も多く、メーカーによって大丈夫だったり合わない場合もあります。その点布おむつならかぶれる心配が少なく、安心して利用できるという声が多く聞かれます。
コスト面
初期費用は布おむつのほうが高くつきますが、長期的に見ると繰り返し使えるため経済的です。布おむつは1度買ってしまえば、繰り返し洗って使用できるためランニングコストが抑えられます。
紙おむつは1日に何枚も使うため、月ごとの費用がかさむ傾向にあります。また薬局などで購入しようとしても、値引き対象外だったりする場合もあるので、どこのお店が安いか、切らさないように考えながら購入する必要があるなど、手間もかかります。
廃棄量と環境負荷
紙おむつは使用後にすぐ捨てるため、家庭ごみが増える原因になります。焼却処理により環境への負担も無視できません。一方、布おむつは洗って再利用するため、ごみの量を大幅に減らすことができます。
SDGsが叫ばれている昨今では、環境に配慮した育児をしたい方にとって、大きなメリットです。紙おむつはどうしても使用量を減らすことができない点もデメリットとなります。
手間と時間
ただし、布おむつは洗濯の手間がかかるため、忙しい保護者にとっては負担に感じることもあるでしょう。紙おむつは取り換えてすぐ捨てられるので、外出時や深夜には便利です。
このように、布おむつと紙おむつにはそれぞれに特徴があり、家庭のライフスタイルや価値観に応じた選択が求められます。布おむつを上手に取り入れることで、赤ちゃんの肌にも地球にもやさしい育児が実現できます。
布おむつの種類と素材の違い
布おむつにはいくつかのタイプがあり、それぞれ形や使い方が異なります。また、おむつの外側に重ねて使う「おむつカバー」にもさまざまな素材があります。ここでは、主な布おむつの種類と、おむつカバーの選び方についてわかりやすくご紹介します。
輪おむつ・成形おむつ・一体型の特徴
輪おむつは、1枚の布を縫い合わせて輪の形にした最もシンプルなタイプです。使用時には折りたたんでおむつカバーにセットします。乾きやすく、洗濯がしやすいのがメリットですが、折り方を覚える必要があります。
成形おむつは、赤ちゃんのおしりに合わせた立体的な形をしていて、折りたたむ手間がありません。初めての方でも使いやすく、吸収力もしっかりしています。輪おむつに比べて乾きにくい面がありますが、使い勝手のよさが魅力です。
一体型おむつは、吸収部分とカバーが一体化しているタイプです。紙おむつのようにセットする必要がなく、使い方が簡単です。ただし、乾くまで時間がかかることと、洗濯の際にかさばるというデメリットもあります。
| 輪おむつ | 成形おむつ | 一体型おむつ | |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 1枚の布を輪に縫い合わせたシンプルなタイプ。折りたたんでカバーにセットして使用 | 赤ちゃんのおしりに合わせた立体的な形 | 吸収部分とカバーが一体化したタイプ |
| メリット | 乾きやすく、洗濯がしやすい。コストも比較的安い | 折りたたむ必要がなく使いやすい。吸収力もしっかり | 紙おむつのように簡単に装着でき、初心者でも扱いやすい |
| デメリット | 折り方を覚える必要があり、慣れるまで手間がかかる | 輪おむつに比べて乾きにくい | 乾くまで時間がかかり、洗濯時にかさばる |
このように、布おむつには使いやすさ・乾きやすさ・準備の手間などで違いがあるため、家庭のライフスタイルに合ったタイプを選ぶことが大切です。
布おむつカバーの役割と素材の違い
布おむつカバーは、吸収体から漏れ出るおしっこやうんちを防ぐ役割があります。直接肌に触れるものではありませんが、素材によって通気性や防水性が異なるため、赤ちゃんの快適さに影響します。主な素材は以下の3つです。
綿(コットン)素材は、肌ざわりがやさしく、通気性にすぐれています。肌が敏感な赤ちゃんにも向いていますが、防水性が低いため、漏れやすい場面には注意が必要です。
ウール素材は、天然の防水性と通気性を兼ね備えた素材です。調湿機能があり、冬は暖かく夏は蒸れにくいという特徴があります。ただし、洗濯にやや手間がかかり、専用のケアが必要です。
ポリエステル素材は、防水性が高く、繰り返しの洗濯にも強いのが特徴です。速乾性があるため、忙しい家庭でも扱いやすい素材ですが、通気性は他の素材に比べて劣ります。
カバーは赤ちゃんの肌に直接触れる機会が多いため、素材の特徴を理解したうえで選ぶことが大切です。通気性や肌ざわりを重視するか、防水性やお手入れのしやすさを優先するかは、使用シーンによって変わってきます。
布おむつの使い方|初心者にもやさしい基本ステップ
初めて布おむつを使う方にとっては、準備や使い方が難しそうに感じるかもしれません。しかし、ポイントを押さえれば誰でも無理なく始められます。ここでは、布おむつを使うために必要な道具や初期準備、さらに外出時や夜間の工夫についてご紹介します。
使用前に揃える道具と初期準備
布おむつを始めるには、いくつかのアイテムをそろえる必要があります。主な道具は以下のとおりです。
- 布おむつ本体(輪おむつ、成形おむつなど)
吸収体となる布部分です。最低でも10〜15枚はあると安心です。 - おむつカバー
布おむつの外に重ねて使う防水カバーです。サイズや素材によって異なるため、数種類試してみるのがおすすめです。3〜5枚ほど用意すると便利です。 - おむつ用バケツ
使用済みの布おむつを一時的に保管する容器です。フタ付きでにおいが漏れにくいものが良いでしょう。つけ置き用としても使えます。 - おしりふき(布または市販品)
赤ちゃんのおしりをやさしく拭くために使います。 - 洗剤とネット
布おむつ専用の洗剤や、傷みにくいネットがあると洗濯もスムーズに行えます。
初期費用としては、おむつ類とカバー、バケツや洗剤などを含めて5,000〜10,000円程度が目安です。最初は少なめに揃えて、使い勝手を見ながら買い足していくと無駄がありません。
外出時や夜間の使い方の工夫
布おむつは、自宅だけでなく外出時や夜間にも使うことができます。ただし、少し工夫をすることで、より快適に使用できます。
外出時には…防水性のある「ウェットバッグ」を用意しておくと、使用済みのおむつを持ち帰る際に便利です。布おむつの枚数は行き先や時間に応じて2〜4枚程度持参しておくと安心です。また、おむつ替えのタイミングがつかみにくい場合は、念のため紙おむつを数枚併用する方法もおすすめです。
夜間には…夜は交換回数が減るため、吸収力の高い成形おむつや、一体型タイプを使うと漏れにくくなります。また、布おむつ2枚重ねにして対策する家庭もあります。寒い季節や肌荒れが気になる場合は、通気性の良いカバー素材を選ぶと赤ちゃんが快適に眠れます。
どうしても不安な方は、夜だけ紙おむつを使用する「ハイブリッド育児」もひとつの方法です。負担を減らしつつ、布おむつの良さを取り入れることができます。
布おむつの洗い方と衛生管理
布おむつは洗って繰り返し使えるため、経済的で環境にもやさしい育児アイテムです。ただし、衛生面をきちんと保つには、正しい洗い方がとても大切です。ここでは、布おむつを清潔に保つための洗濯手順や、においや雑菌を防ぐためのポイントをご紹介します。
洗濯ステップとにおいや雑菌を防ぐコツ
布おむつを清潔に保つためには、「つけ置き」「予洗い」「本洗い」の3つのステップを順番に行うのが基本です。それぞれのポイントを見ていきましょう。
1. つけ置き
使用後のおむつは、すぐにバケツなどにためておきます。このとき、水またはぬるま湯にひたしておくと、汚れが落ちやすくなります。うんちのついたおむつは、できるだけトイレで汚れを落としてからつけ置きすると衛生的です。
2. 予洗い
つけ置きしたおむつは、洗濯機に入れる前に軽くすすいで予洗いします。においや雑菌のもとになる汚れを先に落としておくことで、本洗いがより効果的になります。
3. 本洗い
本洗いでは、他の洗濯物と分けて布おむつだけで洗うのが理想です。40℃程度のぬるま湯を使うと汚れが落ちやすくなります。洗剤は香料や着色料のない、無添加のものを選ぶと安心です。赤ちゃんの肌はとても敏感なので、肌トラブルを防ぐためにも自然派の洗剤や「ベビー用洗剤」を使うとよいでしょう。
また、柔軟剤は吸収力を落としてしまう可能性があるため、使わないことをおすすめします。
洗濯後はしっかりと天日干しをしましょう。太陽の光には自然な殺菌効果があり、においを防ぐのにも役立ちます。室内干しの場合は、風通しのよい場所や除湿機を使って、なるべく早く乾かすようにしてください。
正しい洗い方を続けることで、布おむつは清潔に長く使うことができます。毎日の手間は多少ありますが、赤ちゃんの肌と地球の未来を守ることにつながる大切なステップです。
布おむつの保管方法
布おむつを清潔に保つためには、使用前・使用後の保管方法も大切です。
雑菌の繁殖やにおいを防ぐためにも、日々の管理を正しく行いましょう。
使用前のおむつの保管
洗濯後の布おむつは、完全に乾かしてから保管することが基本です。湿ったまましまうとカビやにおいの原因となるため、必ず日光や風通しのよい場所でしっかり乾燥させましょう。
乾いたおむつは、引き出しや専用の収納ボックスに入れたり、布製の袋やカゴを利用して通気性を保つと安心です。また、直射日光を避けた風通しのよい場所に置くことで、長期的にも清潔に保てます。日常的に清潔に管理することで、赤ちゃんの肌トラブル予防にもつながります。
使用後のおむつの保管
使用済みのおむつは、そのまま放置せず、必ずフタ付きのバケツや専用のおむつポットに入れて一時的に保管します。方法としては、水につけ置きする「つけ置き式」と、乾いたままためる「ドライバケツ式」がありますが、どちらを選ぶ場合も清潔さを保つことが大切です。
特に夏場はにおいが強くなりやすいため、できるだけ毎日洗濯することが理想です。さらに、保管容器自体も定期的に洗浄・乾燥させることで、雑菌やにおいの発生を予防できます。
布おむつを使うメリット・デメリット
布おむつには、紙おむつにはない魅力がたくさんあります。その一方で、使い方によっては手間がかかると感じることもあるでしょう。ここでは、布おむつの良い点と注意したい点をわかりやすく解説します。赤ちゃんにも地球にもやさしい育児を考えるうえで、参考にしてみてください。
布おむつのメリット
布おむつのメリットを見ていきましょう。
環境に優しい
まず布おむつの大きなメリットとして挙げられるのは、環境にやさしいことです。
紙おむつは1日に何枚も使い、すべてがゴミになります。廃棄するのもにおいが気になる場合も多々あり、捨てるまでにも袋に入れたりおむつ専用のゴミ箱を用意したりと、意外と手間がかかります。
一方、布おむつは洗って何度も使えるため、ゴミの量が大幅に減ります。特に環境への配慮を大切にしたい家庭にとっては、大きなポイントです。
また紙おむつと比較しても、生産段階でも環境負荷が少ないという調査結果もあるので、環境に配慮して布おむつを選択する人も多々います。
赤ちゃんの肌に優しい
次に、赤ちゃんの肌にやさしいことも布おむつの大きなメリットです。布おむつには通気性があり、湿気がこもりにくいため、かぶれや赤みが出にくいといわれています。
オーガニックコットンでできているような自然素材の布おむつを使えば、敏感肌の赤ちゃんでも安心です。最初は紙おむつで大丈夫だと思っていても、季節が変わったり成長とともに肌に合わなくなってしまうことも考えられます。
肌が落ち着くまで布おむつを使用していたという場合も多く、併用する場合もありますし、併用するだけでも肌の赤みが改善したという場合もあります。
経済的にも優れている
さらに、布おむつには経済的にも優れているという特徴があります。初期費用として何枚か一気に購入する必要があるので最初こそお金がかかりますが、布おむつは繰り返し何度でも使えるため、長い目で見ると紙おむつよりも費用が抑えられます。
紙おむつはサイズが上がるごとに1枚当たりの値段が上がっていくのに対し、布おむつはサイズ調節ができる場合が多く、長期的に利用できる点も経済的なメリットです。
また兄弟がいる場合は、おさがりとして再利用することも可能です。
布おむつのデメリット
布おむつのデメリットも見ていきましょう。
手間がかかる
一方で、布おむつは手間がかかるのは間違いなく、それをデメリットと感じる方も多いでしょう。
使用後は洗濯が必要で、うんちの処理にはつけ置きや予洗いが欠かせません。忙しい日々の中で、この作業が負担になることも多々あります。
また厚みもあるので乾くまでに時間がかかってしまい、次の交換に間に合わないといったことも考えられます。
最初のうちは特に何度も布おむつを換える必要があるので、何度も洗う必要があります。慣れるまでは紙おむつの方が楽と思ってしまう人も多く、最初に挫折してしまうことも十分考えられます。
漏れやすいので外出時も工夫が必要
また、布おむつは漏れやすいと感じることがあるのも注意点です。特に交換のタイミングが遅れると、カバーから漏れてしまうことがあります。こまめなチェックと、吸収力の高いタイプの併用が対策になります。
外出時の扱いも工夫が必要です。使用済みのおむつを持ち帰るためのバッグや、防臭対策を考えておかないと、荷物が増えてしまうことも。外では紙おむつを使い、自宅では布おむつというように、シーンによって使い分けるのも良い方法です。
布おむつは、手間はかかるものの、肌・環境・お財布にやさしい選択肢です。無理なく取り入れられる範囲で始めることが、長続きのコツになります。
布おむつは保育園でも使える?
布おむつを家庭で使っている場合、保育園でもそのまま使えるのか気になる方は多いです。実際のところ、保育園によって対応はさまざまで、「持ち帰り方式でOK」という園もあれば、「紙おむつのみ対応」という方針のところもあります。ここでは、保育園での布おむつ使用の実態や注意点について解説します。
保育園での布おむつ対応状況
保育園によって布おむつへの対応には違いがあります。大きく分けると、以下の3つのパターンが見られます。
①布おむつOK(持ち帰り方式)
園で使った布おむつを、保護者が洗濯する前提で使用を許可しているケースです。この場合、使用後のおむつはビニール袋などにまとめて入れて持ち帰る形式が多く、家庭と同じように布おむつを続けられます。
②園で洗濯してくれるケース(少数)
一部の小規模な保育園や認可外保育施設では、園で洗濯まで対応してくれる場合もあります。ただし、衛生管理や人手の関係で、このような対応はごく限られています。
③紙おむつ限定の園
園の方針で「紙おむつのみ」と決められている場合もあります。衛生面や手間の問題、他の園児との対応を平等にする目的で導入されています。特に大規模な保育園では、このパターンが多い傾向にあります。
園を選ぶ際には、布おむつの使用可否を事前に確認しておくことが大切です。
保育園で使う場合の持参物・注意点
布おむつが使える保育園に通う場合は、いくつかの準備と工夫が必要です。
持参物の例:
- 布おむつ(予備を含めて5〜7枚程度)
- おむつカバー(2〜3枚)
- 使用済みおむつを入れる防臭袋またはウェットバッグ
- 替えのおしりふきや着替え
園によっては、おむつに名前を書いたり、たたみ方を統一するよう指示されることもあります。園側が混乱しないように、保育士さんとこまめに連絡をとることが大切です。
また、においや衛生面で迷惑をかけないよう、使用済みのおむつはしっかり密閉できる袋に入れて持ち帰るようにしましょう。週末は持参品の点検や補充を忘れずに行い、常に清潔で準備の整った状態を保つことが求められます。
布おむつを保育園で使うには、園との協力が必要不可欠です。無理なく続けるためには、柔軟に紙おむつとの併用を考えるのも一つの方法です。
布おむつとSDGsの関係
近年、持続可能な社会を目指す世界的な取り組みとして「SDGs(持続可能な開発目標)」が注目されています。SDGsは、2030年までに世界が取り組むべき17の目標で構成されており、日本でも官民が連携して推進しています。この章では、布おむつがSDGsの達成にどのように貢献するのか、3つの目標を中心に解説します。
布おむつが「つくる責任・つかう責任」に貢献する理由
SDGsの目標12「つくる責任・つかう責任」は、限りある資源を有効に使い、環境負荷を減らすことを目的としています。布おむつは、まさにこの考え方に合った育児アイテムです。
紙おむつは使い捨てであるため、大量の資源を消費し、使用後はゴミとして処分されます。一方で布おむつは、洗って繰り返し使うことができる「再利用可能な資源」です。赤ちゃん1人が使う紙おむつは、2〜3年間で約5,000枚とも言われており、それがすべてゴミになると考えると、環境への影響は大きなものです。
布おむつを選ぶことで、必要な資源を減らし、廃棄物の量も大幅に抑えることができます。このような選択は、私たちが「つくったものに責任を持ち、無駄なく使い切る」というライフスタイルの実践にもつながります。
気候変動と布おむつの関係
目標13「気候変動に具体的な対策を」では、地球温暖化や異常気象への対応が求められています。紙おむつの製造・輸送・焼却には多くのエネルギーが使われ、結果として温室効果ガスを排出する原因となります。
布おむつは製造回数が少なく、使用後も洗って再利用するため、長期的に見ればCO₂(二酸化炭素)排出量の削減に貢献できます。もちろん洗濯にもエネルギーは必要ですが、紙おむつの大量生産や廃棄と比べると、環境への影響は小さいとされています。
気候変動が進むなか、日々の選択を少しずつ見直すことが大切です。布おむつは、家庭で簡単にできる「エコ育児」の第一歩として、地球を守る行動につながります。
赤ちゃんの健康と福祉を守る選択
目標3「すべての人に健康と福祉を」では、年齢や地域にかかわらず、誰もが健康に過ごせる社会の実現を目指しています。布おむつは、赤ちゃんの肌にやさしい天然素材を使用していることが多く、通気性にもすぐれています。
そのため、おむつかぶれや湿疹などの肌トラブルが起きにくいという声も多く聞かれます。また、布おむつはおしっこの感覚が分かりやすくなるため、トイレトレーニングがスムーズに進むきっかけにもなるといわれています。
赤ちゃんの体にやさしいだけでなく、保護者が育児に丁寧に向き合う姿勢を育むという面でも、布おむつは健康と福祉に貢献する選択肢です。
布おむつを選ぶことは、単なる育児スタイルではなく、環境や社会全体に目を向けた「持続可能な未来づくり」の一歩になります。毎日の小さな行動が、SDGs達成に向けた大きな力になるのです。
参考:日本SDGs協会
布おむつに関するよくある質問
布おむつに興味はあるけれど、実際に使い始めるとなると「手間がかかりそう」「洗濯が大変そう」といった不安の声も多く聞かれます。ここでは、布おむつについてよくある質問を5つ取り上げ、わかりやすくお答えします。導入を迷っている方の参考になれば幸いです。
Q1. 洗濯は毎日しないといけませんか?
必ずしも毎日洗う必要はありませんが、夏場は特に衛生面を考えて、1〜2日に1回の洗濯が推奨されます。においを防ぐためには、通気性のあるバケツでの「ドライ保存」や、洗濯前に水で軽くすすいでおくと良いでしょう。数日間ためてしまうと雑菌が繁殖しやすくなるため、できるだけ早めに洗うのがおすすめです。
Q2. 布おむつを使うと、かぶれにくくなりますか?
布おむつは通気性がよく、湿気がこもりにくいため、かぶれにくいという声もあります。ただし、長時間交換しないとどんなおむつでも肌トラブルの原因になります。こまめに交換することと、赤ちゃんの肌に合った素材を選ぶことが大切です。天然素材の綿やオーガニックコットンなどは、敏感肌の赤ちゃんにもやさしいです。
Q3. 布おむつの初期費用はどれくらい?
最初に必要なアイテムをそろえる場合、5,000円〜10,000円ほどかかることが多いです。布おむつ本体10枚前後、おむつカバー3〜5枚、バケツや洗剤などを含めた金額です。ただし、長く使えば使うほど1枚あたりのコストは下がり、紙おむつより経済的になる場合が多いです。
Q4. 夜や外出時にも布おむつは使えますか?
使えますが、場面に応じた工夫が必要です。夜間は吸収力の高い成形おむつや一体型タイプ、または布おむつの2枚重ねなどを使うと安心です。外出時は、防臭性のあるウェットバッグを持参し、使用済みおむつを自宅に持ち帰るようにします。不安があるときは、紙おむつと併用する「ハイブリッド育児」も選択肢の一つです。
Q5. 途中から紙おむつに戻してもいいですか?
もちろんです。布おむつにこだわりすぎる必要はありません。赤ちゃんや保護者の体調、生活スタイルに合わせて柔軟に選ぶことが大切です。「平日は紙おむつ、週末だけ布おむつ」など、できる範囲で取り入れる方法もあります。無理なく続けることが、心地よい育児につながります。
布おむつにはさまざまな疑問がありますが、使いながら少しずつ慣れていけば大丈夫です。大切なのは、自分と赤ちゃんにとって無理のないスタイルを見つけることです。
まとめ
布おむつは、赤ちゃんの肌にやさしく、環境や家計にも配慮できる育児アイテムです。種類も豊富で、ライフスタイルに合わせた使い方ができる点が魅力です。最初は手間に感じることもありますが、コツをつかめば無理なく取り入れられます。
また、SDGsの観点からも、布おむつは「つくる責任・つかう責任」に貢献する選択といえるでしょう。保育園での対応や外出時の工夫など、状況に応じて柔軟に使い分けることが大切です。
紙おむつとの併用も含め、自分と赤ちゃんにとって心地よい方法を選ぶことが、ストレスのない育児への第一歩になります。布おむつを通して、赤ちゃんとの時間をより丁寧に、そして楽しく過ごしてみてはいかがでしょうか。
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS