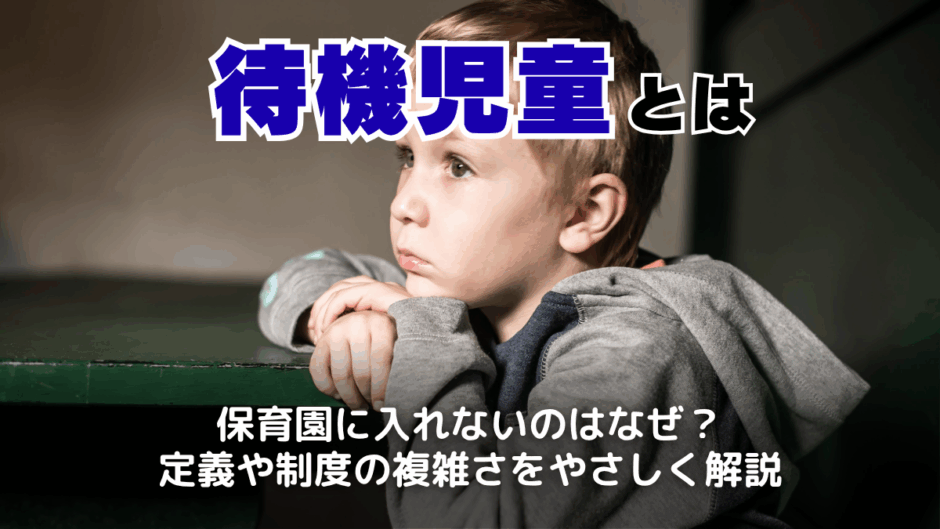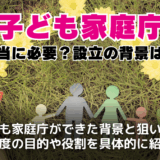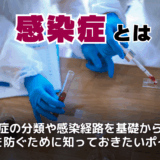待機児童は多くの家庭が直面する切実な課題です。特に都市部では、保育園の申し込みをしても入園できないケースが後を絶ちません。仕事復帰のタイミングが読めず、認可外保育園の費用負担や育休延長による収入減など、家族の生活設計にも大きな影響を及ぼします。
本記事では、そもそも待機児童とは何か、その定義やカウント方法、なぜ問題が解消しきれないのかといった背景をわかりやすく解説します。さらに、制度の仕組みや保活のポイント、今後の課題についても詳しく紹介。
これから保育園探しを始める方や情報を整理したい方に役立つ内容をお届けします。
待機児童とは?
待機児童とは、保育園に入りたくても入れない子どもたちのことを指します。しかし、この言葉の背景には、単なる定員オーバーだけでなく、保育施設の種類や行政のカウント基準、家庭の事情などさまざまな要素が絡んでいます。まずはその定義から詳しく見ていきましょう。
待機児童のカウント方法
実際の待機児童数は自治体ごとにカウント方法が異なり、その定義や数値が分かりづらいという声も多くあります。
一般的に、待機児童のカウントは厚生労働省の基準に基づいて行われています。カウントの対象は、認可保育所や認定こども園などの利用を希望し、自治体に入所申請を出しているにもかかわらず、入所できなかった児童です。
ただし、認可外保育施設や企業主導型保育施設を利用している場合や、家庭での保育を希望している場合は原則として待機児童に含まれません。これにより、実際には保育施設に入れず困っている家庭があっても、統計上は待機児童としてカウントされないケースも発生しています。
また、「隠れ待機児童」という言葉が使われることもあります。これは、希望する認可保育施設に入れず、やむなく認可外保育施設に通わせたり、親が仕事復帰を諦めたりしているものの、公式な待機児童数には含まれていない子どもたちのことを指します。
こうした状況は、自治体ごとのカウント方法の違いが原因となり、問題の実態を把握しにくくしています。
さらに、カウント方法の基準となる「保育の必要性認定(支給認定)」の取得状況も影響します。この認定は、就労状況や介護・疾病などの家庭状況をもとに保育の必要性を判断する制度です。支給認定を受けていない場合、たとえ保育施設の利用を希望していても待機児童としてはカウントされません。
こうした制度の複雑さが、待機児童問題の実態を把握しづらくしている要因の一つです。カウント方法が自治体によってバラバラであるため、国全体の待機児童数が減少していると報道される一方で、現場の保護者からは「入れない」という切実な声が上がり続けています。
「保留児童」との違い|隠れ待機児童とは?
保留児童という言葉がありますが、待機児童との違いはどのようなものでしょう。また、隠れ待機児童という言葉もあります。ここではそれらについて解説します。
最初に比較表を見てみましょう。
| 待機児童 | 保留児童 | |
|---|---|---|
| 定義 | 保育所に入所を希望して申し込みをしたが、入所できていない子ども。 | 保育所に申し込んでおり、入所の意思が継続しているが、まだ入所先が決まっていない子ども。 |
| 統計上の扱い | 厚生労働省が発表する待機児童数にカウントされる(ただし運用により除外あり)。 | 基本的に「待機児童」としてカウントされるべき対象。 |
| 除外されるケース | 認可外保育施設を利用している、育休を延長している等で除外されることがある。 | 上記と同様の理由で、「保留児童」扱いにもならないケースがある。 |
| 現場での実態 | 統計上「ゼロ」とされても、実際には困っている家庭が存在。 | 形式上は申請が継続されているが、入所先が決まらず困っている状態。 |
| 例 | ・認可保育園に入れず育休延長中の家庭・認可外にやむを得ず預けている家庭 | ・認可園に申請中で入所先未定のまま順番待ちしている家庭 |
| 問題点 | 統計に反映されない「隠れ待機児童」の存在が可視化されない。 | 統計上カウントされても、入所までの期間が長期化しがち。 |
これらについて詳しく見ていきましょう。
「保留児童」とは?
「保留児童」とは、保育施設への利用申し込みをしており、なおかつ入所の意思も継続しているにもかかわらず、入所先がまだ決定していない子どもを指します。
厚生労働省の定義に沿えば、本来は「保留児童=待機児童」であるべきですが、実際の自治体運用ではズレが生じることがあります。
たとえば、一時的に家庭での育児を選択している世帯や、認可外保育施設を利用している世帯などは、申請を出していても「保留児童」としてカウントされず、結果的に待機児童からも除外される場合があります。
「隠れ待機児童」とは?
「隠れ待機児童」とは、統計上は待機児童に含まれていないものの、実質的に保育施設に入れず困っている世帯のことです。
たとえば、認可保育所に申し込んだが入所できず、やむを得ず認可外や企業主導型保育施設に預けているケースや、復職を断念し家庭保育をしているケースが該当します。
自治体が「待機児童ゼロ」を実現するために、認可外施設の利用者や育休延長者を統計から除外することがあります。このような運用により、表面的な統計では待機児童が減って見える一方、実態と乖離が生じています。
特に都市部では、共働き世帯の増加や保育定員不足により、隠れ待機児童の存在がより顕著になっています。兄弟枠や加点制度の影響を受けにくい家庭では、早期から保活をしても入所が難しい状況が続いています。
「保留児童」「隠れ待機児童」の概念を理解することは、待機児童問題の本質を捉えるうえで重要です。単なる統計数値だけでなく、カウント基準や行政の運用実態を知ることで、より現実的な保活戦略が可能になります。
行政には、定員拡充や認可外施設への支援など、柔軟で実効性ある対策が求められています。
待機児童が生まれる原因と背景
育休からの復帰や共働き世帯の増加に伴い、保育園への入園希望者は年々増え続けています。しかし、希望通りに入園できない「待機児童」の問題は依然として解消されていません。ここでは、待機児童が生まれてしまう背景や、その原因について詳しく解説していきます。
保育施設の数・定員の不足
都市部では定員に対する需要が逼迫し、待機児童のリスクが高い一方、地方では空きがあるものの、施設そのものが減少しつつある状況です。
都市部では保育所等の定員充足率が91.6%と高水準を維持していますが、過疎地域では76.2%と大きな差があります。令和6年4月時点で施設全体の定員数は約304万人、利用率は全国平均88.8%で、都市部は91.6%、過疎地は76.2%と地域格差が鮮明です。
また、施設数は39,805か所と過去最多ですが、定員充足率は全国で微減傾向。都市部は4年間で2.9ポイント下落に対し、過疎地域では6.8ポイントも下落し、施設統廃合の進行が懸念されています。
保育の「受け皿の偏在」により、共働き世帯を含む多様な保育ニーズに応えきれていないのが現状です。保育施設の数・定員の不足は、待機児童を減らすうえで根本的な課題となっています。
保育士不足による受け入れ制限
待機児童問題の大きな原因の一つが、保育士不足による受け入れ制限です。保育施設の建設や拡充が進んでも、そこで働く保育士の人数が足りなければ定員を増やすことはできません。国の基準では、子どもの年齢ごとに必要な保育士の配置数が定められていますが、現場では慢性的な人手不足が続いています。
保育士不足の背景には、過酷な労働環境や低賃金、長時間労働などの課題があります。特に都市部では家賃や生活費が高く、保育士として働き続けることが難しいケースも多いです。そのため、保育士資格を持ちながら現場を離れている「潜在保育士」の存在も問題視されています。
この保育士不足により、保育施設は十分な定員を確保できず、申込みが殺到しても受け入れ枠を広げられないのが実情です。結果として、保育施設の定員不足が解消されず、待機児童の増加を招いています。保育士の処遇改善と働きやすい職場づくりが、待機児童解消のカギを握っています。
参考:保育士不足の解消にむけて!保育士さんの人数の推移と問題点 | 保育士の転職・採用は【保育士バンク!】
共働き世帯の増加と多様化する保育ニーズ
待機児童問題の背景には、共働き世帯の急増が大きく関係しています。近年、女性の社会進出が進み、結婚や出産後も働き続ける夫婦が増えたことで、保育施設への需要が一気に高まりました。特に都市部では、共働き世帯が当たり前となり、保育施設の定員が追いつかない状況が続いています。
さらに、保育ニーズも年々多様化しています。従来のようなフルタイム勤務だけでなく、パートタイム、フレックス、リモートワーク、シフト勤務など働き方が多様になったことで、早朝保育や延長保育、一時保育といった柔軟な保育サービスのニーズが高まっています。しかし、こうした多様なニーズに対応できる保育施設はまだ限られており、結果的に利用希望者が集中する原因となっています。
また、0歳児や1歳児など低年齢の保育枠は特に限られており、育休明けのタイミングでの保育所探しは激戦となります。こうした保育施設の不足と多様なニーズのミスマッチが、待機児童の増加をさらに深刻化させているのが現状です。
参考:2 0 4 0年に向けた福祉サービスとの共通課題等に係る現状と課題・論点について
自治体によるカウント基準の違いと“見せかけのゼロ”問題
待機児童数が発表されると「過去最少」「ゼロ達成」といった報道を目にすることがあります。しかし、その数字の裏側には自治体ごとのカウント基準の違いが存在し、実態を正確に反映していないケースも少なくありません。これが「見せかけのゼロ」問題と呼ばれる要因です。
厚生労働省は待機児童の定義を設けていますが、自治体ごとに運用の解釈が異なる場合があります。例えば、認可外保育施設を利用している家庭や育休を延長して家庭保育を続けている家庭は、待機児童としてカウントされない自治体が多いです。つまり、本来は希望する保育施設に入れず困っているにも関わらず、統計上は待機児童に含まれていないのです。
自治体の中には、待機児童数を減らすためにカウントの対象を意図的に狭めているケースも指摘されています。こうした運用により、待機児童ゼロを達成したと公表しやすくなる一方、実際の保育ニーズとの乖離が生じています。特に都市部では、認可施設の定員不足や入所倍率の高さが依然として深刻であり、現場の保護者の負担は続いています。
このように、表面的な待機児童数の減少だけを見て安心するのではなく、隠れ待機児童を含めた実態把握が必要です。カウント方法の統一や、保護者のニーズを正確に反映した政策づくりが今後の課題となっています。
参考:保育所等利用待機児童数調査に関する自治体ヒアリング
参考:待機児童問題「見える化」プロジェクト:朝日新聞デジタル
政府・自治体・民間による対策の現状
待機児童問題を解決するため、政府・自治体だけでなく民間も含めた多角的な取り組みが進行中です。新設保育園の開設や保育士確保、企業主導型保育の拡充など、現状の対策をまず整理し、その効果と課題を探っていきます。
政府による主な対策
最初に政府主導の動きを見ていきましょう。
エンゼルプラン(1994年)
政府は1994年、「エンゼルプラン」を策定し、待機児童解消のための第一歩として保育所の増設、延長・休日保育や一時保育の導入を推進しました。
このプランでは、女性の社会進出に対応するため、多様な保育サービスの整備が始まりました。
新エンゼルプラン(1999年)
1999年には「新エンゼルプラン」が導入され、待機児童対策がさらに強化されました。
保育所の受け入れ体制拡充に加え、子育て支援センターや地域子育て支援拠点の設置など、地域全体で子育てを支える仕組みが進められました。
待機児童ゼロ作戦(2001年)
2001年には「待機児童ゼロ作戦」がスタート。
2002年までに5万人分、2004年までに合計15万人分の保育受け入れ枠の整備を目標とし、定員規制の緩和も実施されました。
しかし、保育の質の低下や「隠れ待機児童」の存在など、新たな課題も顕在化しました。
子育て安心プラン(2018〜2020年)
2018年からは「子育て安心プラン」が展開され、1~2歳児の受け皿拡充を重点に置きました。
小規模保育・家庭的保育・企業主導型保育など多様な保育形態を活用し、女性の就業率向上と待機児童解消の両立を目指す施策が整備されました。
新子育て安心プラン(2021年度〜)
2021年度からは「新子育て安心プラン」が始動。
保育の受け皿をさらに約14万人分拡充するとともに、保育士の確保や保育の質の向上、地域の子育て支援資源との連携にも重点が置かれました。
その結果、2024年4月時点の待機児童数は約2,567人となり、ピーク時の10分の1にまで減少したと報告されています。
自治体による保育枠拡大の取り組み
自治体でも多様な取り組みが行われています。
認可保育所の新設・増設
自治体は待機児童の多い地域を中心に、認可保育所の新設や既存施設の増設を進めています。
都市部では特に土地の確保が難しいため、公共施設の空きスペースやマンション・商業ビルの低層階を活用するなど、限られた用地でも柔軟に対応しています。
認可外・小規模保育の活用
認可外保育施設や小規模保育事業を活用する自治体も増加しています。
一定基準を満たした認可外保育施設に補助金を交付し、保護者の負担を軽減する制度を設けるなど、利用しやすい仕組みづくりが進められています。
特に0~2歳児のニーズが高まる中で、小規模保育は地域に密着した柔軟な受け皿として注目されています。
保育士確保のための支援制度
深刻な保育士不足に対応するため、自治体は保育士確保策を独自に実施しています。
家賃補助、就職奨励金、奨学金返還支援などを通じて、保育士の経済的負担を軽減。
これにより、他地域からの人材確保や潜在保育士の現場復帰を後押しし、一定の成果を挙げています。
成功事例の共有と全国的支援の重要性
自治体によって取り組みに差があるのも現状です。
今後は、効果的な事例を他の自治体にも広げ、国による横断的な支援体制の強化が求められています。
地域格差を縮小し、すべての家庭が公平に保育サービスを受けられる環境の整備が課題です。
企業主導型保育施設とその役割
企業主導型保育施設は、待機児童問題の解消に向けた新たな選択肢として注目されています。これは企業が主体となって設置・運営する保育施設で、2016年度に内閣府が制度化しました。
政府の補助金を活用し、企業の従業員だけでなく地域住民の子どもも受け入れ対象とすることで、認可保育園の定員不足を補う役割を担っています。
企業主導型保育施設の最大の特徴は、柔軟な運営体制にあります。認可保育園に比べて開設までの準備期間が短く、職場に併設するなど通勤と育児の両立がしやすい環境を整備できます。また、勤務シフトに合わせた保育時間の設定が可能であり、夜勤や交代制勤務の職場にも対応できる点が評価されています。
さらに、地域の保育ニーズにも貢献しています。定員に余裕がある場合は地域枠として一般家庭の子どもも受け入れており、認可保育園に入れなかった家庭にとって貴重な受け皿となっています。特に都市部では認可園の入園競争が激しく、企業主導型保育施設が実質的に待機児童対策の一翼を担っています。
一方で、保育の質や安全管理への課題も指摘されており、制度開始当初に比べ運営基準は年々厳格化されています。政府は定期的な監査や指導を通じて質の確保に努めていますが、今後さらに信頼性を高める取り組みが求められます。
企業主導型保育施設は、国・自治体・企業が連携して多様な保育ニーズに応える重要な仕組みです。働き方が多様化する現代において、待機児童問題の解決に貢献し続けることが期待されています。
参考:仕事・子育て両立支援事業(企業主導型保育事業 等)|こども家庭庁
保育士確保・処遇改善に向けた施策
保育士確保や処遇改善に向けた施策も行われるようになりました。
給与面での処遇改善
保育士の平均給与は、全産業平均より低く、離職率の高さが長年の課題でした。
これを受けて国は「処遇改善加算」を導入。経験年数に応じた手当や、リーダー保育士への加算制度により、キャリアを積むほど収入が安定する仕組みを整備しました。
潜在保育士の復職支援
資格を持ちながら現場から離れている「潜在保育士」の活用も重要視されています。
復職支援研修やブランク解消のための実習制度が設けられ、安心して現場に復帰できる環境づくりが進められています。
資格取得支援制度の拡充
将来の保育士確保のため、資格取得に向けた支援も強化中です。
養成校の学費補助や、資格取得後の奨学金返還免除制度などにより、保育士を目指す人材の経済的負担を軽減し、志望者の増加を後押ししています。
住宅支援など自治体独自の対策
特に家賃が高い都市部では、住宅支援が保育士確保の鍵となっています。
多くの自治体で家賃補助制度が導入されており、中には新規就業者に対する引越し費用の支援制度もあります。
これにより、他地域からの人材流入や定着が促進されています。
今後に向けた課題と展望
保育士確保策は単なる「数の確保」にとどまらず、保育の質の維持・向上にも密接に関わります。
今後は、現場で長く働きたいと思える職場環境やキャリアパスの整備がより重要になり、持続的な人材確保の鍵となるでしょう。
待機児童ゼロへの課題と私たちにできること
待機児童ゼロに向けて、多くの課題が今も存在します。このような中、私たちにできることはどんなものがあるのでしょうか。
待機児童ゼロに向けた課題
待機児童ゼロに向けた課題を挙げていきます。
保育の「量」だけでなく「質」も問われている
これまでの対策は主に保育施設の新設や定員拡大といった“量”の拡充に重点が置かれてきましたが、それだけでは不十分です。
子どもが健やかに育つ環境として「保育の質」も重要であり、保育士の専門性向上や配置基準の見直し、保育プログラムの改善などが求められています。
都市部と地方の格差
都市部では用地不足や地価の高騰により新設が難航し、地方では保育ニーズと施設数のミスマッチが課題となっています。
地域ごとの状況に応じた柔軟な制度設計と支援が不可欠です。
多様化する保育ニーズへの対応
家庭の形や働き方が多様化する中、企業主導型保育や在宅勤務と連動した保育、短時間保育など、柔軟な選択肢の整備が必要です。
一律の仕組みでは対応しきれない現実が広がっており、制度の多様化がカギとなります。
ジェンダー平等と育児の分担
SDGs目標5「ジェンダー平等」の観点からも、育児が女性だけの負担となっている現状を見直す必要があります。
男性の育児参画や企業による育休取得支援の強化が、保育ニーズの構造変化につながります。
私たちにできること
現状存在する課題に対して私たちができることは何なのでしょうか。
保育を「社会全体の基盤」として捉える
保育は個人の問題ではなく、社会全体で支えるべきものです。
子育てをしていない人も含め、すべての世代が「子どもは社会の財産」と捉える意識を持つことが重要です。
地域ぐるみで子育てを支える
自治体やNPO、企業などと連携し、地域全体で子育て世帯を支援する体制づくりが求められます。
見守り・サポート体制や、地域ボランティアの活用など、身近な関わり方も広がっています。
保育に関する情報を正しく知る・発信する
待機児童や保育の問題について正しい情報を知り、周囲にも共有していくことが大切です。
誤解や偏見を減らし、社会的関心を高めることで、政策や制度の改善にもつながっていきます。
一人ひとりが行動することの大切さを意識する
行政任せではなく、私たち一人ひとりが「子育てしやすい社会」を実現する担い手として行動していく意識が重要です。
選挙での意思表示、地域の活動への参加、声を届けることなど、小さなアクションの積み重ねが社会を変えていきます。
待機児童に関するよくある質問
ここでは、待機児童に関するよくある質問を具体的に取り上げ、より理解を深めていきます。
Q1. そもそも待機児童とは何ですか?
待機児童とは、保育施設の利用を希望しているにもかかわらず、希望する保育所に入所できない子どものことを指します。多くの場合、認可保育園の入園を申し込んで不承諾となったケースが該当します。国の統計上、自治体が定める定義に基づいてカウントされますが、実際には「隠れ待機児童」と呼ばれるケースも存在します。
たとえば、育児休業を延長中の家庭や、やむを得ず認可外保育施設を利用している家庭の子どもは、待機児童に含まれないことがあります。そのため、表面上の待機児童数よりも、保育の受け皿不足の実態は深刻である場合も少なくありません。
Q2. 認可保育園と認可外保育園は何が違いますか?
認可保育園は、国や自治体が定める厳格な基準を満たした保育施設で、施設面積・保育士の配置基準・安全管理・保育内容などが細かく規定されています。保育料は世帯の所得に応じて自治体が設定し、比較的安価で利用できるのが特徴です。
一方、認可外保育園はこれらの基準に縛られず、事業者の裁量で柔軟に運営されています。保育時間やカリキュラムに自由度があり、多様なニーズに対応できますが、保育料は高めで自治体の助成が少ない場合もあります。ただし、質の高い認可外保育園も多く存在し、選択肢の一つとして検討する家庭も増えています。
Q3. 点数制度とは何ですか?
点数制度とは、認可保育園の入所希望者を公平に選考するために自治体が採用している仕組みです。主に「保育の必要性」を基準に各家庭の状況を点数化し、点数の高い家庭から優先的に入園が決まります。共働き世帯やひとり親家庭、介護・病気を抱える家庭などが高得点となりやすく、育休中や短時間労働の場合は点数が低くなる傾向があります。
さらに、きょうだいの在園や祖父母の支援状況などに応じた加点項目も設定されており、自治体ごとに細かな違いがあります。事前に自治体の保育課で詳細を確認し、自分の世帯状況を整理しておくことが重要です。
Q4. 待機児童ゼロと聞きますが、実際はどうですか?
「待機児童ゼロ」とは、自治体が公式に待機児童数ゼロを達成したと発表する状況を指します。ただし、これはあくまで統計上のカウント基準に基づく数字で、実際には希望する保育園に入れないケースや認可外・家庭内での保育を余儀なくされる「隠れ待機児童」が存在します。特に人気の高い認可保育園は依然として倍率が高く、自治体間でも基準の違いがあるため、実態と数字に乖離が生じることもあります。
保育需要の多様化が進む中、単純なゼロ宣言だけではなく、保護者が希望する保育環境を確保できる状況の整備が今後の課題となっています。
Q5. 育休延長する場合の注意点は?
育休延長は、保育所に入所できないなど特定の条件を満たせば可能ですが、申請期限に注意が必要です。延長手続きは自治体や勤務先への書類提出が必要となり、認可保育園の不承諾通知などの証明書類を揃える必要があります。
また、育児休業給付金の延長可否や支給額も確認しておきましょう。延長後は収入が減少するケースもあり、家計の見直しも重要です。さらに、復帰先の職場との調整も円滑に行うため、早めの相談と情報共有がカギとなります。
まとめ
待機児童問題は改善が進む一方で、保育士不足や制度の複雑さ、「隠れ待機児童」など新たな課題も表面化しています。保育園選びは情報の整理が難しく、保護者の不安や負担も大きいのが現状です。これは一部の家庭だけでなく、社会全体で向き合うべき課題です。制度や地域の特性を理解し、早めの準備をすることが安心につながります。今後も保育の質と量を両立させ、誰もが安心して子育てできる環境づくりが求められます。
また、企業や地域が連携し、柔軟な働き方や保育の選択肢を増やすことも重要です。保育を「自分ごと」として考える社会の意識が、よりよい未来を育む力になります。
そして社会全体でも、保育の質と量の両面を充実させ、すべての家庭が安心して子育てと仕事を両立できる環境づくりが求められているのです。
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS