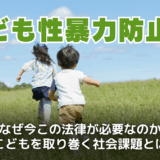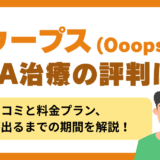産後ケア事業という単語は、産後の女性からすればよく耳にする単語ではあるが、「産後ケアって何だろう?」「産後ケア事業を利用するメリットは?」と気になっている産後ママは多いのではないでしょうか。
実は、産後ケア事業は、母子保健法に基づいた公的サービスで、出産直後の母子の心身のケアや育児サポートを行うことで、産後の不安や孤立感を和らげ、乳児死亡率の低下にも寄与しているのです。産後ケア事業の利用により、専門家のアドバイスを受けられるほか、同じ境遇の母親との交流で精神的な安定が得られ、自分の時間の確保にもつながります。
一方で、仕組みが複雑で理解するのが難しいという点があります。
この記事では、産後ケア事業の詳しい仕組みや種類、補助金制度、利用方法について解説します。
産後ケア事業とは?

産後ケア事業とは、地域子ども・子育て支援事業の一つで、出産後の母親と新生児の心身のケアや育児サポートを行う公的サービスです。母子保健法に基づいて実施され、国や都道府県からの交付金により運営されています。
産後ケア事業の目的は、出産直後の母子の健康管理や育児支援を通じて、産後うつや育児不安の予防、母子関係の形成、乳児の健全な発育を促進することにあります。
専門スタッフによる心身のケアや育児指導、同じ境遇の母親同士の交流の場の提供などにより、母親の不安や孤立感を和らげ、子育ての負担を軽減します。
産後ケア事業は、核家族化や地域のつながりの希薄化により、子育てに不安や孤立感を抱える母親が増加していることを背景に、近年注目が高まっています。
母親の心身の健康や子育ての質の向上は、乳児の健やかな成長や将来的にも大きな影響を与えるため、社会全体で支えていく必要があるとの認識が広がっています。
出産直後の母子を支える仕組みとしての目的
産後ケア事業は、出産直後の母子を心身ともにサポートする重要な役割を担っています。出産は母親にとって大きな身体的、精神的負担を伴うイベントであり、特に産後の数週間は、ホルモンバランスの変化や睡眠不足、育児の悩みなどから心身ともに不安定になりやすい時期です。
この時期に適切なケアを受けられることは、母親の回復や育児への適応を促し、産後うつや育児ストレスの予防につながります。産後ケア事業では、助産師や保健師等の専門スタッフが、母親の心身の状態をチェックし、必要に応じて休養や栄養指導、育児技術の指導などを行います。
また、新生児にとっても、生後間もない時期のケアは非常に重要です。適切な授乳や衛生管理、感染症予防などは、新生児の健やかな発育に欠かせません。産後ケア事業では、新生児の健康チェックや発達評価なども行われ、異常の早期発見・対応に役立てられます。
さらに、産後ケア事業は、育児の孤立化を防ぐ役割も果たしています。同じ境遇の母親同士が交流できる場を提供することで、悩みの共有や情報交換ができ、精神的な支えとなります。孤立感の解消は、虐待防止にもつながる重要な意義があります。
産後ケアの対象者
産後ケア事業の対象者は、出産後1年以内の母子が基本ですが、母親の年齢、出産状況、家庭環境などによって、ニーズや利用方法に大きな違いがあります。
母親の年齢に着目すると、10代の若年出産や高齢出産の場合、妊娠・出産に伴うリスクが高く、特に手厚いケアが必要とされます。一方、高齢母親は、妊娠合併症や流早産のリスクが高く、出産後の回復にも時間がかかる傾向があります。
法整備されているのは出産後1年以内と定められていますが、産後ケアの対象者としては、年齢問わず対象者となる可能性があります。
また出産状況によっても、産後ケアの対象者となる場合があります。早産であったり低出生体重児、多子多産であった場合にも同じく産後ケアが必要です。
産後ケア事業では、こうした出産状況に合わせて、医療機関と連携しながら適切なケアを提供しています。
他にも里帰り出産から戻った核家族世帯、父親が単身赴任などで育児への参加が難しいケースなども、対象となります。また、経済的に不安定な世帯である、ひとり親世帯や多子世帯なども、育児の負担が大きい傾向があります。
産後ケア事業は、対象者の属性やニーズに合わせて、柔軟できめ細かいサービスを提供しています。特にハイリスクな状況にある母子に対しては、保健医療機関や福祉機関と密接に連携し、包括的な支援を行っています。すべての母子が安心して子育てができるよう、年齢、出産状況、家庭環境に配慮したサポートを提供しているのです。(※1)
参考:※1:産後ケア事業について
産後ケア事業の歴史とこれまでの経緯
産後ケア事業の歴史とこれまでの経緯をご紹介します。これまで出産については出産一時金や妊婦検診費用の一部負担などの支援が行われていました。ただ産後ケアまでは触れられておらず、見過ごされてきたのが現実です。
日本の産後ケアが始まったのは、平成26年です。最初はモデル事業の開始から始まり、その一年後である平成27年度に補助事業として本格的に実施されました。
続いて平成29年度に、産後ケアのガイドラインが策定されました。その中には、市町村では産後ケア事業の実施に努めることと規定されています。
国だけでなく、自治体ごとで産後ケア事業が展開されることで、より寄り添った対応ができるようになりました。
産後ケア事業の内容
産後ケア事業の内容を見ていきましょう。
産後ケア事業でできること
産後ケア事業でできることは大きくわけて3つあります。まず挙げられるのは、産後の母親に対するケアです。産後の不安定な精神状態のケアや、休養時間の確保をしたり体調管理を手伝ったりといったことができます。
続いてできることは、赤ちゃんのケアです。赤ちゃんが健康に育っているかをチェックしたり、沐浴などお世話の方法を教えるといったことができます。実際におむつを替えたり、ミルクを作ったりといったサポートも行える場合があります。
3つ目は育児に関すること全般に対してケアができます。母子の健康管理から授乳方法であったり、授乳トラブル時の対応や、育児の不安を聞いて取り除くといったことができるのが、産後ケア事業です。
産後ケア事業の種類
産後ケア事業の種類は主に3つあります。
- ショートステイ型
- デイサービス型
- アウトリーチ型
上記の3種類に分けられるのが産後ケア事業です。ホームステイ型は、産後ケア施設や産院・助産院などに母子ともに入所して、ケアをしてもらうタイプで夜間の面倒も頼めば見てもらえるなど、メリットも大きいのが特徴です。
父親が不在であったり、仕事が忙しく育児に参加できない場合におすすめできるのが、ホームステイ型です。
デイサービス型は、母子が日中のみ産後ケア施設や産院などに訪れて、産後ケアを受けられるサービスです。短時間でも利用できる点がメリットで、日中だけ孤独が辛いといった場合にも利用できるので、産後のママたちに喜ばれています。
アウトリーチ型は家からでる気力も体力もないママに特におすすめで、助産師さんが自宅まで訪問してくれるのが大きなメリットです。
家から出る必要がないので、精神的・肉体的に動くのも大変なママにおすすめです。
産後ケア事業が必要とされている背景・普及し始めている理由
近年、産後ケア事業は全国で導入が進み、注目を集めています。育児における孤立や不安、社会的サポート不足など、現代ならではの課題が背景にあります。
ここでは、その必要性と普及が進んでいる理由を5つの視点から詳しく解説します。
核家族化・少子化による子育ての孤立化
現代の家庭は、祖父母と同居しない「核家族」が一般的になっています。
そのため、出産・育児に関する知識や経験を、家族から直接得られる機会が少なくなっています。また、少子化により周囲に子育て仲間が少ないケースも多く、悩みや不安を相談しにくい状況です。育児が「1人で抱えるもの」になりやすく、孤立感を深める要因になっています。
こうした背景から、出産後すぐの時期に専門的な支援を受けられる産後ケアのニーズが高まっています。
産後のお母さんが抱える心身の不調
出産直後の母親は、ホルモンの大きな変化により、情緒が不安定になりやすいとされています。さらに、授乳や夜泣きによる慢性的な睡眠不足、慣れない育児による疲労が重なります。
「ちゃんと育てられるか不安」「母親として失格ではないか」というプレッシャーや罪悪感を抱え、心のバランスを崩すケースも少なくありません。
こうした心身の不調を早い段階でケアすることで、育児放棄や産後うつの予防にもつながるため、産後ケアは重要な支援策として位置づけられています。
法改正で産後ケアが市町村の「努力義務」に
以前は、産後ケアは各自治体の任意事業として一部で実施されていました。
しかし、2019年の母子保健法改正により、全ての市町村に対して「産後ケア事業の努力義務」が明記されました。
この改正を契機に、各地で制度整備が急速に進みました。
具体的には、2014年時点で全国に29自治体しかなかった実施地域が、2021年には1,360自治体にまで増加。
今では多くの地域で、助産師や看護師による訪問ケアや宿泊型・通所型の支援が受けられるようになりました。法的な裏付けができたことで、持続可能なサービスとしての基盤が整ったといえます。
地域の支え合いによるサポート体制の強化
産後ケアの拡充にあたっては、地域の人的資源が大きな役割を果たしています。
保健師・助産師・保育士のほか、母子保健推進員や子育て経験者などがチームを組み、利用者に寄り添ったサポートを実現しています。
相談支援だけでなく、同じ地域で子育てする母親同士の交流の場をつくり、「孤育て」を防ぐ取り組みも行われています。こうしたつながりは、育児への自信や安心感を高める効果もあり、母親のメンタルヘルスにも良い影響を与えています。
地域全体で子育てを支える社会づくりが、今まさに進んでいます。
女性のキャリアと育児の両立を支援する観点
産後ケアの普及は、単なる育児支援にとどまらず、ジェンダー平等の推進にも関わっています。
日本では育児の大部分を女性が担うケースが多く、出産によってキャリアが中断されたり、非正規雇用に移行するなど、経済的なリスクを抱えやすい状況にあります。
こうした現状を少しでも改善するには、安心して育児と仕事を両立できる環境づくりが欠かせません。
産後ケアを通じて心身を整え、育児への自信を取り戻すことは、女性が社会に復帰する第一歩を支える重要な仕組みといえるでしょう。(※2)(※3)(※4)
参考:
法制度とガイドラインに基づく産後ケア事業の枠組み
産後ケア事業は、母子保健法第17条の2に基づく市町村の努力義務として位置づけられています。この法的根拠により、全国的な普及と質の確保が図られているのです。
市町村が産後ケア事業に取り組む背景には、少子化や核家族化による子育て環境の変化があります。身近な支援者が少なく、育児の知識や経験を得る機会も減っている中で、産後の母親の心身の負担は大きくなっています。産後ケア事業は、こうした状況下で母子の健康を守り、安心して子育てができる環境を整備するための公的サービスとして重要な役割を担っているのです。
また、厚生労働省の「産後ケア事業ガイドライン」は、母子保健法に基づく市町村の産後ケア事業の実施にあたって、参考となる指針を示したものです。ガイドラインでは、産後ケアを必要とする対象者の考え方や把握方法、サービス提供体制の整備、国や都道府県の役割などについて、具体的な論点が示されています。
市町村は、法律に基づく責務としてだけでなく、ガイドラインを参考にしながら、地域の実情に合わせた産後ケア事業の展開を図っています。妊娠期からの切れ目ない支援や関係機関との連携、ニーズに応じたサービス提供など、きめ細かな取り組みが求められます。
産後ケア事業は、法律という確かな基盤の上に、ガイドラインによる質の向上を目指す枠組みが構築されています。市町村は、この枠組みの中で、地域の実態を踏まえた効果的な事業展開を図ることが期待されているのです。
母子保健法に明記された産後ケア
産後ケア事業は、母子保健法第17条の2に明記されています。同法によると、市町村は、出産後1年以内の女性と乳児に対し、心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話、育児に関する指導、相談その他の援助を行うよう努めなければなりません。
具体的な事業内容としては、以下の3つが規定されています。
- 病院、診療所、助産所その他の施設(産後ケアセンター)に、対象者を短期間入所させて産後ケアを行う事業
- 産後ケアセンターその他の施設に、対象者を通わせて産後ケアを行う事業
- 対象者の居宅を訪問し、産後ケアを行う事業
市町村は、これらの事業を実施するにあたり、内閣府令で定める人員、設備、運営に関する基準に従わなければなりません。
また、産後ケア事業の実施にあたっては、妊娠中から出産後に至る切れ目ない支援の観点から、こども家庭センターその他の関係機関との連絡調整、母子保健に関する他の事業や児童福祉法等に基づく母性・乳児の保健福祉事業との連携を図ることが求められています。これにより、妊産婦と乳児に対する支援の一体的な実施その他の措置を講ずるよう努めることとされています。(※5)
参考:※5:母子保健法 | e-Gov 法令検索
厚生労働省の「産後ケア事業ガイドライン」とは
厚生労働省は、産後ケア事業の普及と質の向上を図るため、「産後ケア事業ガイドライン」を策定しています。このガイドラインは、母子保健法に基づく市町村の産後ケア事業の実施にあたって、参考となる指針を示したものです。
ガイドラインでは、産後ケアを必要とする対象者の考え方や把握方法、サービス提供体制の整備、国や都道府県の役割などについて、具体的な論点が示されています。
まず、産後ケアを必要とする対象者については、各市町村の実態調査を踏まえ、具体的な対象範囲の検討が求められています。自治体によって対象者の設定に差異があるという指摘もあり、ニーズに応じたサービス提供が課題となっています。
次に、対象者の把握方法については、各市町村の取り組み状況を調査し、効果的な手法や機会の特定が必要とされています。妊娠期からの継続的な関わりやスクリーニングの活用など、きめ細かなニーズ把握が求められているのが現状です。
最後に国や都道府県の役割についても言及されており、市町村が効率的かつ効果的にサービスを提供できるよう、広域的な観点から支援することが求められます。人材育成や情報提供、財政支援など、多角的な支援策が検討課題となっています。(※6)
参考:※6:産後ケア事業の実施状況及び今後の対応について
産後ケアの種類と補助金制度
産後ケア事業には、宿泊型、訪問型、デイサービス型の3つの種類があり、母子の状況に合わせて選択することができます。この章では、産後ケアを利用する際の流れや、3つの種類の違い、利用料金、補助金、自己負担額の仕組みと実例について解説します。
産後ケアを利用する際の流れは以下のようになっています。
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 1,サービス利用の申込み | 市区町村の母子保健担当部署や地域の保健センターや保健所で、利用者がサービスの利用を申し込みをする。 |
| 2,事前面接・アセスメント | 申込み後に母子の状況を把握し、個別のニーズを評価するために、事前面接とアセスメントを行う。 |
| 3,支援の開始 | 宿泊型、デイサービス型は施設で、アウトリーチ型は自宅での支援開始となります。 |
| 4,心身のケア・育児支援 | それぞれの形態で、母親の心身のケアと育児支援が提供されます。 |
| 5,フォローアップ | サービス終了後も、宿泊型は退所後、訪問型とデイサービス型は支援終了後に、母子の状況をフォローアップし、必要に応じて追加の支援を提供します。 |
宿泊型・訪問型・デイサービス型の違いと選び方
| 宿泊型 | デイサービス型 | 訪問型(アウトリーチ型) | |
|---|---|---|---|
| 内容 | 産後ケア施設に母子で短期入所し、24時間体制の支援を受ける | 日帰りで施設に通い、数時間単位でケアを受ける | 助産師などが自宅を訪問し、生活環境の中で支援を行う |
| メリット | ・専門スタッフによる手厚い支援・しっかり休める・集中的な育児指導が受けられる | ・費用が比較的安い・母親同士の交流ができる・気軽に利用しやすい | ・実生活に即した支援が受けられる・上の子の様子や家事の状況も考慮できる |
| 注意点 | ・費用が高め・空きが少ない場合も | ・1回のケア時間が短め・通う手間がある | ・訪問対象エリアが限られる・自治体によって非対応の場合あり |
| おすすめの人 | ・体調が不安でしっかり休みたい人・育児に自信が持てない人 | ・軽度な不安を抱えている人・交流やリフレッシュをしたい人 | ・外出が難しい人・自宅での育児に不安がある人 |
宿泊型は、産後ケアセンターなどの施設に母子が短期間入所し、24時間体制でケアを受けられるタイプです。ゆっくりと休養をとりたい、授乳指導や育児指導を集中的に受けたいといったニーズに応えることができます。また、助産師等の専門スタッフによる手厚いサポートが特徴で、他のサービスと比較すると利用料は高いですが、特に産後の心身の回復に不安を抱える母親におすすめです。
デイサービス型は、母子が施設に通いながらケアを受けるタイプで、日帰りや数時間単位の利用が可能です。他の母親との交流の機会が得られることも大きな特徴です。利用料が安く気軽に利用できる反面、一度で十分なケアを受けることが難しいという点があるため、母親の体調や家庭の事情を考慮して選択することが大切です。
アウトリーチ型では、実施担当者が母子の家族関係や住環境を直接見ることができるため、生活全般に関する具体的な助言がしやすくなります。例えば、家事や上の子の世話など、家庭内の役割分担や育児環境の調整について、実情に合わせたアドバイスが可能です。
また、生活の場で指導を受けられることで、その後の生活に活かしやすいというメリットもあり、授乳姿勢や沐浴の方法など実際の生活空間で具体的な手順を学べるため、自宅での育児にスムーズに移行できるため、自宅での育児に不安を感じている方や、日常生活に即した実践的なサポートを求める方におすすめです。(※7)
参考:※7:産前産後サポート事業・産後ケア事業ガイドライン
利用料金・補助金・自己負担額の仕組み
| 宿泊型 | デイサービス型 | 訪問型(アウトリーチ型) | |
|---|---|---|---|
| 利用料金の目安(1回あたり) | 4,000円〜10,000円程度 | 1,000円〜4,000円程度 | 500円〜2,000円程度 |
| サービス内容 | 24時間の入所支援、食事・授乳・育児指導など | 日帰りのケア、授乳・育児指導、母子交流など | 自宅訪問による授乳・育児指導、生活環境に応じた助言 |
| 補助・減免制度 | 一部自治体であり(例・全額補助、半額補助など) | 一部自治体であり | 一部自治体であり |
| 減免対象例 | 生活保護世帯住民税非課税世帯ひとり親家庭 など |
産後ケア事業の利用料金は、宿泊型、デイサービス型、アウトリーチ型のいずれも、利用者から徴収されます。利用料の目安は、宿泊型で4,000円〜10,000円、デイサービス型で1,000円〜4,000円、アウトリーチ型で500円〜2,000円が多いようです。ただし、生活保護世帯や低所得者世帯など、周囲からの支援が得られにくく社会的リスクが高い家庭に対しては、利用料の減免措置等の配慮が行われることが望ましいとされています。(※7)
また、産後ケア事業には国や都道府県からの補助金が交付されています。補助率は、令和6年以前は国が1/2、市町村が1/2でしたが、都道府県負担が導入され、現在は国が1/2、都道府県が1/4、市町村が1/4となっています。補助金の単価は、デイサービス・アウトリーチ型が1施設あたり月額1,788,000円、宿泊型が1施設あたり月額2,605,700円などと定められています。(※8)
さらに、住民税非課税世帯や支援の必要性の高い利用者への利用料減免、24時間365日受入体制整備、兄姉や生後4か月以降の児の受け入れ、夜間の手厚い職員配置など、サービスの充実に応じた加算も設けられています。
産後ケア事業利用に関する事例
産後ケア事業は、母子の心身の健康を守り、育児を支援するために重要な役割を果たしています。ここでは、ある初産婦の事例を通して、産後ケア事業がどのように機能しているのか見ていきましょう。
事例の母親は30代の初産婦で、新型コロナウイルスの影響で里帰り出産を断念せざるを得ませんでした。また、立ち合い出産もできなかったため、夫と二人での育児に大きな不安を抱えていました。産後3週目に保健師が乳児家庭全戸訪問事業で訪問した際、母親の不安を察知し、産後ケア事業の利用が必要だと判断しました。
産後ケア事業では、母親の身体回復のための休養、授乳指導、栄養指導、おむつ替えやだっこの仕方等の育児指導、乳房ケア、心理的支援等が行われました。母親は育児手技に自信がない様子でしたが、助産師が一つ一つ丁寧に説明し、できていることを認める言葉がけを繰り返すことで、少しずつ自信を取り戻していきました。
また、母乳分泌が過多傾向で軽度のうっ滞性乳腺炎症状があったため、乳房ケアと食事指導を行いました。その結果、症状は改善し、完全母乳への移行も実現しました。さらに、出産の振り返りを行い、母親の思いを傾聴することで、母親の心理的な負担も軽減されました。
このように、産後ケア事業は、母親の心身のケアと育児支援を包括的に行うことで、母子の健康と安心を守っています。専門職による寄り添い型の支援は、特に周囲からのサポートが得られにくい母親にとって、大きな助けとなります。(※9)
参考:
産後ケア事業の今後と課題
産後ケアは近年、全国的に普及してはいますが、それでも地域格差があることは否めません。この章では、産後ケア事業の都道府県別実施率の比較と、産後ケア事業と事業目的が似ているSDGsとの関係性についてご紹介します。
人材不足
産後ケア事業の課題として挙げられるのは、助産師などの人材不足です。自治体の多くで委託先が見つからずに、産後ケアが受けたくても受けられないという母子が多くいます。
産後ケア事業に力を入れている産院があっても、通常業務にも手が取られてしまうため、産後ケア専門施設は産院ではなく専門の業者が行っている場合もあります。
また母親が精神疾患を患っている場合などは優先的に産後ケアが受けられるよう、人材の確保が優先されます。
産後ケア施設の利用料の高騰
産後ケア施設は産院や助産院でも行っていますが、最近では産後ケア専門の施設も増えています。ただかかる費用が大きく、誰でも利用できる価格帯ではありません。
そのため貧困層は産後ケア施設を利用できません。産院や助産院が行っている産後ケア施設をであっても、デイサービス型で1回10時~15時30分の利用で33,000円と高額なのが現状です。
今後、自治体などから助成金がつけば値段が下がる可能性もありますが、現状すぐに出産して産後ケアを利用したい妊婦さんはお金をかけて利用せざるを得ません。
地域ごとの格差と利用率のばらつき
産後ケアに対する取り組みは全国に広まってはいますが、地域によって差が生まれているのが現状です。以下では産後ケア事業の都道府県別実施率に関して、「実施率が高い都道府県TOP10」と「実施率が低い都道府県TOP10」をご紹介します。
実施率が高い都道府県TOP10
| 順位 | 都道府県名 | 実施率 |
|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 100% |
| 1 | 栃木県 | 100% |
| 1 | 富山県 | 100% |
| 1 | 山梨県 | 100% |
| 1 | 鳥取県 | 100% |
| 1 | 広島県 | 100% |
| 1 | 山口県 | 100% |
| 1 | 香川県 | 100% |
| 9 | 愛知県 | 98.1% |
| 10 | 大阪府 | 97.7% |
実施率が低い都道府県TOP10
| 順位 | 都道府県名 | 実施率 |
|---|---|---|
| 1 | 熊本県 | 31.1% |
| 2 | 青森県 | 35.0% |
| 3 | 佐賀県 | 40.0% |
| 4 | 奈良県 | 48.7% |
| 5 | 埼玉県 | 55.6% |
| 6 | 宮城県 | 60.0% |
| 7 | 岩手県 | 60.6% |
| 8 | 北海道 | 61.5% |
| 9 | 新潟県 | 63.3% |
| 10 | 徳島県 | 66.7% |
参考:※10 産後ケア事業の実施状況及び今後の対応について
実施率が高い都道府県は、100%である8つの茨城県、栃木県、富山県、山梨県、鳥取県、広島県、山口県、香川県です。逆に、特に低い都道府県は熊本県で31.1%、青森県で35.0%となっています。
「都会の方が実施率は高いのでは?」と思いがちですが、都会は市町村の数が多く、これら8つの都道府県よりは実施率は低いのが現状です。しかし、比較的市町村数が多いかつ比較的都会の東京都では74.2%、千葉県は85.2%、福岡県は71.7%であり、圧倒的に低い数値ではないことが分かります。
産後ケアとSDGs
産後ケア事業は、単に母子の健康を守るだけでなく、持続可能な社会の実現に向けた重要な取り組みの一つとして位置づけられます。ここでは、産後ケアとSDGsの関連性について探っていきます。
産後ケアとSDGsの共通点
産後ケアとSDGsには、いくつかの共通点があります。まず、両者ともに、人々の健康を重視しています。
SDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」は、あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進することを目指しています。産後ケアは、出産後の母子の心身の健康を守り、育児を支援することで、この目標の達成に直接的に貢献しています。
また、産後ケアとSDGsは、ジェンダー平等の推進という点でも共通しています。SDGsの目標5「ジェンダー平等を実現しよう」は、女性と女児のエンパワーメントを図ることを目的としています。産後ケアは出産、育児による女性の社会的、経済的な不利益を緩和し、仕事と子育ての両立を支援することで、ジェンダー平等の実現に寄与しています。
さらに、産後ケアとSDGsは、パートナーシップの重要性を認識している点でも一致しています。SDGsの目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」は、持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバルパートナーシップを活性化することを目指しています。
産後ケアの普及がもたらす社会的影響
産後ケア事業の普及は、母子の健康だけでなく、社会全体に広範な影響をもたらします。
まず、産後ケアは、子育て家庭の孤立化を防ぎ、地域のつながりを強化することに役立ちます。核家族化や地域コミュニティの希薄化が進む中、産後ケアを通じて母親同士の交流や情報交換の場が提供されることで、子育ての不安や悩みを共有し、支え合うネットワークが形成されます。これは、地域の子育て力を高め、SDGsの目標11「住み続けられるまちづくりを」の達成にも寄与します。
また、産後ケアは、子どもの健やかな成長と発達を支える基盤となります。産後の母親の心身の健康は、子どもの愛着形成や情緒的な発達に大きな影響を与えます。
産後ケアを通じて、母親が安心して子育てに臨める環境を整えることは、子どもの権利を保障し、SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」の実現にもつながります。
さらに、産後ケアは、女性の社会参画を促進し、ジェンダー平等の実現に資します。出産・育児期の女性が、心身の健康を維持し、仕事と子育ての両立ができるよう支援することは、女性の就業継続や経済的自立を後押しします。
これは、SDGsの目標5「ジェンダー平等を実現しよう」や目標8「働きがいも経済成長も」の達成に不可欠な要素と言えます。
加えて、産後ケアは、少子化対策としても期待されています。子育ての負担感や不安が解消されることで、子どもを産み育てやすい環境が整い、出生率の向上にもつながる可能性があります。これは、SDGsの目標1「貧困をなくそう」や目標10「人や国の不平等をなくそう」の観点からも重要な意義を持ちます。
このように、産後ケアの普及はSDGsの多様な目標の達成に貢献し、その意義はかなり重要となるでしょう。
産後ケア事業に関するよくある質問
以下に、産後ケア事業に関する質問を5つピックアップしました。読者の方の疑問が少しでも解決しましたら幸いです。
Q1. 産後ケア事業の対象者は?
A1. 産後ケア事業の対象者は、出産後1年以内のお母さんと赤ちゃんです。ただし、お母さんの年齢や出産時の状況、家庭環境などを考慮し、特に支援が必要と判断された方は優先的に利用できる場合があります。
例えば、若年出産、多胎出産、低出生体重児の出産、産後の心身の不調、家族からのサポートが得られにくい状況などが該当します。
各自治体により優先条件が異なる場合があるので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
Q2. 産後ケア事業のサービス種類は?
A2. 産後ケア事業には、大きく分けて宿泊型、訪問型、デイサービス型の3種類があります。宿泊型は、母子が専用の施設に宿泊しながら、24時間体制でケアを受けられるサービスです。訪問型は、助産師や保健師等の専門スタッフが自宅を訪問し、母子の心身のケアや育児のサポートを行います。デイサービス型は、母子が施設に通いながら、日帰りでケアを受けられる形態です。それぞれの特徴やニーズに合わせて、利用するサービス種類を選択できます。
Q3. 利用料金の目安は?
A3. 産後ケア事業の利用料金は、自治体によって異なります。一般的な目安として、宿泊型は1泊あたり4,000円から10,000円程度、訪問型は1回あたり500円から2,000円程度、デイサービス型は1回あたり1,000円から4,000円程度です。
ただし、住民税非課税世帯や生活保護世帯等については、利用料が減免される場合があります。また、多子世帯や母子家庭、低所得者世帯等に対する優遇措置を設けている自治体もあります。
詳しい料金体系や減免制度については、各自治体の担当窓口にお問い合わせいただくのが確実です。
Q4. 利用期間はどのくらい?
A4. 産後ケア事業の利用期間は、自治体や利用者の状況によって異なります。一般的な目安として、宿泊型は連続5泊6日程度、訪問型とデイサービス型は1ヶ月に4回から8回程度の利用が可能です。ただし、母子の心身の状態や家庭環境等を考慮し、柔軟に対応されることが多いです。
例えば、母親の体調回復が遅れている場合や、育児に対する不安が強い場合などは、利用期間を延長したり、利用回数を増やしたりすることができます。
逆に、母子ともに安定している場合は、利用期間を短縮することもあります。利用者のニーズに合わせて、柔軟にサービス提供がなされるのが特徴です。
Q5. 申し込み方法は?
A5. 産後ケア事業の申し込み方法は、お住まいの自治体によって異なります。一般的には、自治体の母子保健担当窓口や保健センター、子育て支援センター等で受け付けています。
母子健康手帳の交付時や、生後4ヶ月までに行われる乳児家庭全戸訪問の際に、産後ケア事業の案内がなされることもあります。また、妊娠中の妊婦健診や母親学級等の機会に、事業の説明がなされる場合もあります。
申し込みの際は、母子健康手帳や身分証明書等の書類が必要になることが多いです。事業の利用を希望される方は、まずはお住まいの自治体の担当窓口に連絡を取り、申し込み方法や必要書類等についてご確認ください。
まとめ
産後ケア事業は、出産後の母子の心身の健康を守り、育児を支援するための重要な取り組みです。母子保健法に基づき、自治体が主体となって実施され、厚生労働省の「産後ケア事業ガイドライン」に沿って運営されています。
事業の対象は出産後1年以内の母子ですが、母親の年齢や出産状況、家庭環境などによって、ニーズや利用方法に違いがあります。核家族化や地域のつながりの希薄化により、産後の母親の孤立感や不安が高まっていることが、事業の必要性を高めています。
産後ケアには、宿泊型、訪問型、デイサービス型の3つの種類があり、利用者の状況に合わせて選択できます。国や自治体からの補助金により、利用料の負担軽減が図られています。
一方で、地域ごとの事業の普及状況には格差があり、今後の課題となっています。産後ケアは、SDGsの達成にも寄与すると期待されており、その重要性はますます高まっています。
産後ケア事業は、すべての母子が安心して子育てに臨める社会の実現に向けて、欠かせない取り組みです。地域のニーズに寄り添いながら、事業の充実と発展が求められています。
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS