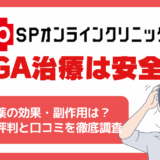アルコール依存症とは、長くお酒を飲み続けるうちに、心も体もお酒なしでは落ち着かなくなる病気です。お酒を飲むと気分がほぐれたり、ストレスが軽くなったように感じることもありますが、頼りすぎると健康を害し、仕事や人間関係など日常生活にも悪影響を及ぼすようになります。
依存症は「意志が弱いから」起こるのではなく、遺伝や心理的背景、社会環境などが複雑に関わって発症するものです。進行すると、自分の意思で飲酒をやめることが難しくなり、肝臓や脳をはじめとする臓器の病気、うつ病や不安障害など精神的な問題を併発します。
また、家族との関係悪化や仕事の喪失、経済的な困難など社会的な影響も避けられません。一方で、早期に気づき、適切な支援や治療を受けることで、回復し再び安定した生活を送ることは可能です。本記事ではアルコール依存症の定義や原因、症状、治療法や支援体制までを整理し、理解を深める手助けをします。
アルコール依存症とは?
アルコール依存症とは、アルコールを飲むことで心身に悪影響が出ているにもかかわらず、飲酒をやめられない状態を指します。意思の弱さや性格の問題ではなく、脳がアルコールを必要とするように変化してしまう「病気」です。
依存には「精神的依存」と「身体的依存」があります。精神的依存は、ストレスや不安を解消するために飲まずにいられなくなることを意味します。身体的依存は、アルコールを断つと手の震えや発汗、不眠などの「離脱症状」が出る状態を指します。このように、単なる嗜好の範囲を超え、アルコール中心の生活に変わってしまうことが、アルコール依存症の大きな特徴です。
飲酒習慣・アルコール乱用との違い
アルコール依存症と飲酒習慣、乱用は混同されがちですが、明確に異なります。飲酒習慣は、定期的にお酒を飲む生活スタイルのことを指し、必ずしも健康被害につながるわけではありません。アルコール乱用は、飲酒によって健康や人間関係に問題が起きているにもかかわらず飲み続ける状態です。
一方、アルコール依存症は乱用よりも進行した段階で、自分の意思で飲酒をやめられなくなり、心身ともに強く影響を受けている点が大きな違いです。つまり、依存症は「やめられない病気」であり、飲み過ぎや単なる酒好きとは区別して理解する必要があります。
アルコール依存症の症状
アルコールを大量に摂取し、依存状態になると身体にはもちろん精神面や日常生活に悪影響を及ぼします。アルコール依存による症状について解説します。
身体的な症状
アルコール依存症が進むと、身体にさまざまな変化が現れます。以下にアルコール依存による身体症状を説明していきます。
離脱症状
アルコール依存症では、飲酒を中断した際に多様な離脱症状が出現します。代表的なのは手指の震え、発汗、動悸、吐き気、強い不安、睡眠障害などです。重度になると「アルコール離脱せん妄(DT)」と呼ばれる状態に陥り、幻覚や意識障害が現れ、適切な治療を行わない場合、死亡率は10〜15%と報告されています。
多くの患者は「飲まないと体がもたない」という感覚に追い詰められ、症状の苦痛から飲酒を繰り返し、依存が深まってしまいます。
脂肪肝・肝炎・肝硬変
アルコールによる肝障害は、軽度な脂肪肝から始まり、アルコール性肝炎、さらに肝硬変へと進行します。長期間の過剰飲酒者の約90%が脂肪肝を発症し、そのうち10〜20%が肝炎や肝硬変に進展するとされます。進行すると黄疸、腹水、倦怠感などが慢性的に現れ、生命予後にも影響します。
肝機能は自覚症状が乏しいため、依存症に気付かないまま進行してしまう点が大きな問題です。
胃腸障害や膵炎
アルコールは胃粘膜を刺激し、胃炎や胃潰瘍、慢性的な消化不良を引き起こします。また、急性膵炎・慢性膵炎の大きな原因のひとつで、膵炎患者の約30〜40%はアルコールが背景にあるといわれています。
膵炎は激しい上腹部痛や発熱を伴い、重症化すれば命に関わるケースも少なくありません。慢性的な膵機能低下は下痢や栄養不良を引き起こし、体力の低下につながります。
しびれ・判断力低下・記憶障害などの神経系への影響
長期の飲酒は末梢神経のダメージを招き、手足のしびれ、痛み、力が入りにくいなどの「アルコール性末梢神経障害」を引き起こします。さらに、脳への影響も大きく、集中力・判断力・記憶力の低下が進行します。
ビタミンB1不足を背景に起こる「ウェルニッケ脳症」の場合、放置すると10〜20%が死亡し、記憶障害を残す「コルサコフ症候群」に移行することもあります。
免疫力の低下
大量飲酒は免疫細胞の働きを弱め、肺炎や結核、皮膚感染症などの発症・悪化リスクを高めます。実際、アルコール依存症患者は一般の人に比べて肺炎の罹患率が約3倍高いとされ、治療に対する反応も悪化しやすいことが知られています。
また、栄養不足や肝機能低下が重なることで体が感染症に抵抗しにくくなり、入院が必要となるケースも多くあります。
精神的な症状
精神面でも変化が生じ、イライラ、不安、抑うつ、集中力低下などが現れます。特に、飲酒できない状況になると強い不安感や落ち着かなさが出ることが多く、生活の中心がアルコールになってしまうこともあります。飲んでいるときだけ気分が安定し、飲まないと不調になる「アルコールによる気分調整」が習慣化することで、依存が深まる傾向があります。気分の波が大きく、家族や周囲とのトラブルを招くこともあります。
行動面の症状
アルコールを優先する行動が増え、飲酒量やタイミングを自分でコントロールできなくなります。「今日は飲まない」と決めても飲んでしまう、仕事前や朝から飲んでしまう、嘘をついて飲もうとするなどが特徴です。また、飲酒のために仕事や家庭生活に支障が出ても飲むことをやめられません。飲酒が原因で遅刻や欠勤が増えたり、人間関係が悪化したりと、日常生活全体が飲酒に左右されるようになります。
さらにアルコール依存症は、本人だけでなく周囲の人にも大きな影響を与えます。飲酒による暴言、暴力、金銭トラブルなどが増え、家族関係が壊れてしまうケースも少なくありません。また、仕事の能力が低下し、失職につながることもあります。飲酒運転のリスクや、ケガ・事故を起こしやすくなるなど、社会的にも危険を伴います。気づかないうちに生活のすべてがアルコール中心になってしまう点が深刻な問題です。
日本のアルコール依存症の現状
この章では、アルコール依存症の国内外における最新の患者数や有病率、また日本特有の飲酒文化や社会構造が依存症の発生にどのように影響しているかを具体的なデータや社会背景とともに掘り下げます。現状を知ることは、正しい理解や対策の第一歩になります。
国内のアルコール依存症の患者数
厚生労働省の「アルコール健康障害対策推進基本計画」によると、日本にはアルコール依存症の患者がおよそ107万人いると推計されています。しかし、実際に治療を受けている人はごく一部にとどまり、受診率は1割程度といわれます。「お酒は日本の文化だから仕方ない」といった意識や、依存症を病気と捉えにくい風潮もその一因とされています。
さらに、依存の手前にいると考えられる“予備軍”は約440万人にのぼるとされ、問題の広がりが懸念されています。近年は「断酒」だけでなく「減酒治療」も導入され、治療選択肢が増えています。数字からは、日本における依存症の深刻さと、早期発見・治療への取り組みの必要性が浮き彫りになります。
参考:アルコール健康障害対策推進基本計画(令和3年3月)
参考:依存症患者推計107万人! 注目される「減酒治療」
参考:アルコール依存症について | 同友会メディカルニュース
日本の飲酒文化・社会構造が与える影響
日本では「お酒は人間関係を円滑にするもの」という価値観が根強く、飲み会文化や接待が依存症の背景にあります。職場では「上司の誘いは断れない」という同調圧力が働き、過剰な飲酒を強いる「アルコールハラスメント(アルハラ)」も問題視されています。
また、大学生や若者に対して一気飲みを強要するケースもあり、急性アルコール中毒や依存症のリスクを高めています。このような社会的風潮が「飲める人が偉い」という誤った価値観を生み、依存症の発症を助長しています。依存症は個人の弱さではなく、社会構造と文化に強く影響される病気であることを理解することが重要です。
アルコール依存症の世界との比較
世界的にみると、アルコールが原因で年間約300万人が亡くなっているとWHOは報告しています。特にロシアや東欧諸国では死亡率が高く、日本は比較的低い位置にあるものの、依存症の患者が少ないとはいえません。海外では広告規制や販売制限が進んでおり、フランスではビールのテレビCMが禁止されています。
また、欧州の一部では飲酒可能年齢が厳格に定められ、違反には罰則があります。これに対して日本は規制が緩やかで、酒類広告も日常的に目に入ります。こうした環境の違いが、飲酒習慣や依存症のリスクに影響を及ぼしています。国際的な対策を参考にしながら、日本でも社会的ルールを整える必要があります。
参考:アルコール | 公益社団法人 日本WHO協会
参考:アルコール 国別死亡率
参考:「知らなかった」では済まされない!飲酒に関する海外のルール
アルコール依存症の原因と進行ステージ
アルコール依存症の発症には、遺伝や心理的な傾向、生活環境、社会文化など複数の要因が関わっています。この章では、発症リスクを高める要因を分類し、依存症がどのように段階的に進行していくのかを整理して解説します。自分や身近な人の飲酒と照らし合わせることで、早期の気づきにつながるかもしれません。
アルコール依存症の発症の主な原因
アルコール依存症の原因は単一ではなく、いくつかの要因が重なり合って発症します。主に次の4つに分けられます。
遺伝的要因
アルコールを分解する酵素に関わる「ALDH2遺伝子」には個人差があります。分解が遅い体質の人は顔が赤くなりやすく、依存症にはなりにくいとされます。一方、酵素がよく働く人は飲酒量が増えやすく、依存のリスクが高まります。家族に依存症の人がいる場合も注意が必要です。
心理的要因
うつ病や不安障害などの精神的な不調を抱える人は、気持ちを楽にするために飲酒に頼りやすくなります。また、ストレス解消の手段が限られていると、お酒に依存しやすい傾向がみられます。
環境的要因
孤独感や人とのつながりの薄さも依存症を進める要因です。家族や友人との関係が希薄な人ほど、飲酒に逃げやすくなると報告されています。
社会的要因
日本のように飲み会や接待が多い文化では、周囲に合わせて飲む機会が増えます。アルコールハラスメントのような強制的な飲酒も依存症の温床となります。
これらの要素が重なったとき、アルコール依存症へ進む可能性が高くなります。
アルコール依存症の進行ステージ
アルコール依存症は、徐々に進行していく病気です。次のような段階に分けて理解することができます。
依存症との境界線の時期
飲酒量が増え、二日酔いが頻繁になります。この時期は「まだ大丈夫」と思いやすいですが、危険信号が出始めています。
初期依存期
飲む量を自分でコントロールできず、隠れて飲むことが増えます。飲まないと手の震えや不眠など離脱症状が出ることもあります。本人は「やめたいのにやめられない」という葛藤を抱えます。
中期依存期
飲酒による遅刻や欠勤、家族とのトラブルが増加します。肝臓や胃腸の不調など身体症状も悪化し、社会生活に大きな影響が出ます。
末期依存期
生活の中心がお酒になり、健康や人間関係、経済状況が深刻に悪化します。仕事や家庭を失うケースも多く、強い孤立感や絶望感にとらわれやすくなります。
このように依存症は段階を経て悪化するため、早期に気づき専門的な支援を受けることが重要です。
アルコール依存症による主な問題点と影響
アルコール依存症は、単にお酒をやめられない状態にとどまりません。身体や精神に深刻な影響を与えるだけでなく、家族や職場にまで悪影響を及ぼし、社会全体にも大きな負担を生み出します。本章では健康被害や社会的影響、さらには医療や経済に関わるコストまで、多角的に解説します。
身体・精神への悪影響
アルコール依存症は体のさまざまな臓器や神経に障害をもたらします。肝臓では、初期のアルコール性脂肪肝から炎症を伴うアルコール性肝炎へ進行し、さらに肝硬変、最終的には肝がんに至ることがあります。これらは進行性で、治療が難しくなるほど生命予後に影響します。
アルコールが神経に及ぼす影響は深刻です。長期にわたる多量飲酒によって、記憶があいまいになる「アルコール性認知症」や、手足のしびれを感じる「末梢神経障害」などが見られます。さらに、ビタミンB1の欠乏が引き金となる「ウェルニッケ・コルサコフ症候群」は、意識が混乱し、記憶の回復が難しい病気として知られています。
また、循環器系にも影響は及び、「アルコール性心筋症」による心不全や高血圧、不整脈を引き起こすケースもあります。飲酒による身体の負担は、一見わかりにくくても、時間をかけて確実に蓄積していくのです。さらに、消化器系では食道がんや胃潰瘍、膵炎が発症しやすくなります。骨粗しょう症や免疫低下も見られるため感染症リスクも高まります。
精神面では、うつ病や不安障害、睡眠トラブル、パニック発作などを併発しやすくなります。アルコールは一時的に気分を落ち着かせるように感じても、実際には抑うつや不安を強め、さらに飲酒に頼ってしまう悪循環を生み出します。
家族や職場、社会への影響
家庭や職場にも影響は広がります。家庭内では暴力(DV)や子どもへの虐待、心理的な放置(ネグレクト)が起こることがあり、関係の断絶や離婚に発展することも少なくありません。職場では遅刻や欠勤が増え、集中力や判断力が低下することで、生産性の低下につながります。
このように、アルコール依存症は本人だけでなく、周囲の人々や社会全体にも大きな影響を及ぼすのです。職場では遅刻や欠勤が増え、生産性が低下します。集中力の欠如や判断力の低下により業務中の事故やトラブルも増え、企業にとっては損失や訴訟リスクを抱えることになります。
さらに、飲酒運転による死亡事故や人身事故、窃盗や暴力といった犯罪行為に発展するケースもあります。多重債務やギャンブル依存と併発することもあり、借金問題は家族を巻き込み深刻化します。こうした問題は本人だけでなく家族の精神的負担や生活不安を大きくし、子どもの健全な育成にも悪影響を及ぼします。アルコール依存症は社会全体が抱える課題といえます。
医療コスト・社会コストの増加
アルコール依存症は医療や経済に大きな負担をもたらします。患者本人の治療費に加え、肝疾患や心疾患、がんなどの合併症治療や救急搬送の費用がかさみます。さらに、長期的には入院やリハビリの費用も必要となり、医療制度への圧迫が続きます。
経済面では、欠勤や離職による労働力の損失、生産性の低下が顕著で、企業や社会全体に大きな損害を与えます。社会保障費も増加し、生活保護や失業手当、犯罪者の矯正費用などが税金として国民に跳ね返ってきます。また、数字では表せない社会的コストも無視できません。家族が抱える精神的苦痛や、子どもが不安定な環境で育つことによる教育・福祉への追加的な支援が必要となります。
つまり、アルコール依存症は個人の健康問題にとどまらず、国全体の持続可能性にも影響を及ぼす深刻な社会的課題なのです。
アルコール依存症の診断基準・治療方法と予防対策
アルコール依存症を防ぐためには、個人の意識や生活習慣だけでなく、社会全体での理解と支援が欠かせません。セルフチェックによる早期気づき、専門的な治療、そして職場や学校での啓発活動まで、多角的な取り組みが必要です。本章ではそれぞれの方法を具体的に解説します。
セルフチェック方法
アルコール依存症の対策で最も大切なのは、まず自分の飲酒を冷静に見つめ直すことです。どれくらいの量を、どんな頻度で飲んでいるのかを知ることが、改善への出発点になります。
その手助けとなるのが、世界保健機関(WHO)が作成した「AUDIT(アルコール使用障害識別テスト)」と、日本で広く活用されている「KAST(久里浜式アルコール症スクリーニングテスト)」です。これらは簡単な質問に答える形式で、自分の飲酒傾向を振り返り、依存のリスクを把握することができます。紙やWebで受けられるため、自宅でも気軽にチェックできます。
たとえば、飲酒量が増えている、やめようと思ってもやめられないといった傾向を点数化して示してくれるため、早めに問題を意識する助けになります。ただし、セルフチェックはあくまで自己評価であり、正直に答えにくい項目があったり、回答が甘くなったりすることもあります。そのため、結果は「目安」であり、疑いがある場合は必ず医師や専門機関に相談することが重要です。
参考:AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)
参考:KAST-M (久里浜式アルコール症スクリーニングテスト男性版)
アルコール依存症の診断基準
アルコール依存症かどうかを判断するためには、国際的に定められた診断基準が用いられます。代表的なものに「DSM-5(アメリカ精神医学会の診断基準)」があります。診断では、飲酒をコントロールできない、飲むために多くの時間を費やしている、飲酒をやめると離脱症状が出る、飲酒のために家庭や仕事に支障が出ているといった点が確認されます。
これらの項目のうち一定数に該当すると「アルコール使用障害」と診断され、その中でも重症度に応じて「軽度・中等度・重度」に分類されます。自己判断だけでは正確に見極められないため、心配な場合は医師や専門機関に相談することが重要です。
アルコール依存症の治療
アルコール依存症の治療は、単にお酒を絶つだけでは終わりません。心身の回復を促しながら、再び依存に戻らないようにする長いプロセスです。一般的には、次の3段階で行われます。
最初の段階では、アルコールを体から抜き、断酒の状態に慣れることが目標です。この時期には、手の震えや発汗、けいれんなどの離脱症状が出ることもあるため、医師の管理のもとで治療を受ける必要があります。
お酒を飲まない生活を定着させる期間です。なぜ依存が生まれたのか、飲酒が人生や人間関係にどんな影響を与えたのかを振り返り、心理療法やグループプログラムなどを通して、再発を防ぐ力を育てます。
断酒を続けていくためには、治療が終わった後もサポートが欠かせません。医師やカウンセラーと定期的に面談を行い、再飲酒の兆しを早めに見つけることが大切です。また、家族や仲間の支えが大きな励みになります。
このように、治療は一朝一夕で終わるものではありませんが、焦らず根気よく取り組むことで、再発を防ぎ、落ち着いた生活を取り戻すことが可能です。
職場や学校での予防教育と啓発活動
アルコール依存症の予防には、個人の努力だけでは限界があります。職場や学校など、社会全体での取り組みが重要です。企業では、従業員が過度に飲酒しないように啓発を行い、飲酒が原因で仕事に支障をきたす前に相談できる体制を整えることが求められます。安全面からも、飲酒による労働災害や業務上の事故を防ぐ仕組みが不可欠です。
学校では、若いうちから飲酒のリスクを正しく理解させる教育が進められています。厚生労働省の資料でも、中高生を対象とした授業や啓発活動の必要性が強調されています。さらに、地域や企業が協力してシンポジウムや講習会を行うことで、社会全体の意識を高めることができます。アルコールを「楽しむもの」から「危険を伴うもの」として正しく理解する環境づくりが、依存症予防の基盤となります。
アルコール依存症の予防と対策には、早期に気づくセルフチェック、根気強く進める治療、そして社会全体での啓発活動がそろって初めて効果を発揮します。お酒は身近な存在であるからこそ、正しい知識と支援体制を整えることが不可欠です。一人ひとりが自分や周囲の飲酒習慣に目を向けることが、依存症を減らし健全な社会を築く第一歩となります。
参考:アルコール関連問題への取り組み サントリーグループのサステナビリティ サントリー
参考:アルコール依存症と職場での対応|企業が取るべき対策と支援策
参考:学校における飲酒防止教育
アルコール依存症の患者に対して私たちができること
アルコール依存症の患者に対して私たちができることをご紹介します。
アルコール依存症の人の家族や友人ができること
まずアルコール依存症の方の家族ができることをみていきましょう。重要なのは、アルコール依存症は回復できる病気であるということを知っておいてください。
また話し合いの場を設ける時には、アルコール依存症の本人がアルコールを摂取していないタイミングを見計らって、話し合いを行いましょう。
口論であったり暴力であったり、家族間や周りの方とのことでトラブルが起こってしまった場合には、無理して家族間で解決しようとせず、専門家などに頼ることも忘れないでください。
アルコール依存症の人の周囲の人ができること
アルコール依存症の人の周囲の人ができることは、まずアルコール依存症は本人の意思が弱いせいではなく、治療が必要な病気であることを知っておくことです。
病気であることを理解してあげることが重要です。またアルコール依存症であることを責めることも、アルコール依存症の人にとっては、悪化につながる可能性があるのでやめましょう。
コミュニケーションをする時は、必ず主語を「自分自身」にすることも、アルコール依存症の人のためになります。接触すること自体を控えてしまうよりは、コミュニケーションを続けていくことが重要です。
アルコール依存症の支援体制と相談先
アルコール依存症の本人や家族を支えるためには、適切な支援先を知っておくことが大切です。保健所や精神保健福祉センター、自助グループ、専門医療機関など、相談できる場所は多岐にわたります。ここでは、それぞれの役割や特徴を紹介し、困ったときにどこへ相談すればよいのかを分かりやすく解説します。
保健所の相談窓口
保健所は地域に根ざした公的な相談窓口として、アルコール依存症に関する幅広い支援を行っています。たとえば、飲酒習慣が気になる段階から、依存症が進行して生活に支障をきたしている段階まで、症状の程度に応じた相談が可能です。保健師や精神保健福祉士などの専門スタッフが対応し、必要に応じて医療機関や専門施設への紹介を行ってくれます。
さらに、本人だけでなく家族からの相談も受け付けており、依存症に伴う不安や悩みを共有できるのも特徴です。厚生労働省の資料によると、保健所は「飲酒に関して困ったときの最初の相談先」と位置づけられており、身近で安心して利用できる窓口といえるでしょう。
参考:アルコール依存症について – 東京都多摩府中保健所
参考:保健所の活用の仕方 ~どんな時に頼れば良いの?~
精神保健福祉センター
精神保健福祉センターは、都道府県や政令指定都市に設置されている専門的な相談機関です。ここでは、アルコール依存症をはじめとする心の病について、より専門的で総合的な支援が受けられます。医師や心理士、精神保健福祉士といった多職種のスタッフがチームを組み、依存症の診断や治療の必要性を判断します。
また、再発防止のための生活指導や、家族に対するカウンセリングも行われます。保健所が一次的な相談窓口だとすれば、精神保健福祉センターは「専門的なアドバイスを受ける場所」といえます。必要に応じて専門病院への紹介も行うため、依存症に悩む方やその家族にとって心強い支えとなります。
参考:アルコール依存症について – 東京都多摩府中保健所
参考:精神保健福祉センター
アルコール依存症の自助グループ
アルコール依存症の回復には、同じ経験を持つ仲間とのつながりが大きな力になります。その代表例が「AA(アルコホーリクス・アノニマス)」です。AAは、飲酒をやめたいと願う人々が集まり、体験を語り合うことで回復を目指す自助グループです。匿名性が守られるため、安心して参加できるのも特徴です。
また、本人だけでなく家族を支えるためのグループも存在します。それが「アラノン(Al-Anon)家族グループ」です。依存症の影響を受けて苦しむ家族同士が集まり、悩みを分かち合い、互いに支え合う場を提供しています。これらの自助グループは全国各地で活動しており、対面の集まりに加えてオンラインでのミーティングも増えています。孤独を感じがちな依存症の問題に対し、仲間とのつながりは大きな安心感をもたらします。
アルコール依存症専門医療機関
アルコール依存症が進行して日常生活に深刻な支障をきたしている場合は、専門医療機関での治療が必要になります。代表的なのが、神奈川県にある久里浜医療センターのアルコール科です。ここでは、解毒治療(体内からアルコールを抜く治療)や、再発防止のための精神療法、生活リズムを整えるためのプログラムなど、体系的な医療が提供されています。
また、全国各地にもアルコール依存症を専門的に扱う病院やクリニックがあり、入院治療から外来でのサポートまで幅広い選択肢があります。厚生労働省や支援団体のウェブサイトでは、地域ごとの専門医療機関の一覧が公開されているため、自分や家族が利用しやすい施設を探すことが可能です。医療の専門的な介入は、依存症から回復するための大きな一歩となります。
アルコール依存症は、本人だけでなく家族や社会にも大きな影響を及ぼします。しかし、支援を受けられる窓口は数多く存在します。保健所は身近な相談先として利用でき、精神保健福祉センターでは専門的な支援が受けられます。さらに、AAやアラノンといった自助グループでは仲間とつながることができ、専門医療機関では本格的な治療を受けることが可能です。大切なのは「一人で抱え込まないこと」です。信頼できる支援先を見つけることで、回復への道は必ず開かれていきます。
参考:アルコール科(アルコール依存症治療) | 診療科・部門 | 病院のご案内 | 久里浜医療センター
参考:アルコール依存症 相談先一覧
アルコール依存症とSDGsの関係
アルコール依存症とSDGsの関係を見ていきましょう。
目標3「すべての人に健康と福祉を」
アルコール依存症の回復は、SDGsの目標3にある「すべての人に健康と福祉を」に貢献しています。
目標3「すべての人に健康と福祉を」の中に、ターゲット3.5「麻薬を含む薬物やアルコールなどの乱用を予防・治療する」があります。そのためアルコール依存症の人が回復するということは、SDGsの目標達成に直結しています。
アルコール依存症に関するよくある質問
アルコール依存症やその治療をめぐっては、本人だけでなく家族も多くの疑問や不安を抱えます。この章では、治療の進め方や社会復帰の可能性、家族や子どもへの影響など、よくある質問に分かりやすく答えていきます。
Q1. 本人が治療を拒否している場合、どうすればいいですか?
アルコール依存症の多くは、自分が病気だと認めにくい特徴があります。そのため、無理に説得するよりも、家族が適切な相談窓口に繋がることが大切です。保健所や精神保健福祉センターなどの公的機関に相談すると、専門家が対応方法を一緒に考えてくれます。家族が孤立せずサポートを得ることが、治療への第一歩につながります。
Q2. 治療にはどれくらいの期間がかかりますか?完全に治るのでしょうか?
アルコール依存症の治療は、短期間で終わるものではありません。解毒や入院などの初期治療は数週間で行われますが、その後は長期的な通院や生活改善が必要です。また、依存症は「完治」よりも「回復を続ける病気」といわれています。完全に元通りになるわけではなく、飲酒をやめ続ける生活を習慣にすることが大切です。
Q3. アルコール依存症でも社会復帰は可能ですか?
適切な治療と支援を受ければ、社会復帰は十分に可能です。実際に依存症から立ち直り、就職や復職を果たした事例もあります。重要なのは、無理に一人で頑張ろうとせず、専門医や就労支援サービスを活用することです。働き方を調整したり、周囲の理解を得たりすることで、再発を防ぎながら社会での役割を取り戻すことができます。
Q4. 飲酒量を減らして普通の「酒飲み」に戻れますか?
アルコール依存症になると、飲酒のコントロール力を失ってしまいます。そのため「少しだけ飲む」という方法は現実的ではなく、再び依存が悪化してしまう危険があります。専門医も「節度ある飲酒」に戻ることは難しいと説明しています。根本的な回復には、断酒を継続することが唯一の方法とされています。
Q5. 家族がアルコール依存症だと子どもへの影響はありますか?
依存症のある家庭で育つ子どもは、心理的な影響を受けやすいとされています。たとえば、親の飲酒に振り回されて不安定な生活を送ったり、家庭内の緊張感から強いストレスを抱える場合があります。また、将来的に人間関係や自尊心に課題を持つケースも報告されています。子どもを守るためにも、家族が早めに相談機関とつながることが大切です。
アルコール依存症には「本人が治療を拒む」「治療期間が長い」「社会復帰できるのか」など、多くの疑問がつきまといます。しかし、正しい情報を得ることで不安は軽減されます。断酒の継続や回復の過程は簡単ではありませんが、専門医療や自助グループ、家族への支援を組み合わせれば、再び安心して生活できる未来を築くことは可能です。大切なのは一人で悩まず、信頼できる支援先を活用することです。
まとめ
アルコール依存症は、完治が難しく一生向き合っていく必要がある重大な病気です。本記事では、その定義や原因、身体と心への症状、家族や社会に及ぶ影響、そして対策や支援体制まで幅広く解説しました。
依存症は本人だけでなく、周囲の人々にも深刻な影響を与える一方で、正しい理解と治療、サポートを受けることで回復へと進むことができます。大切なのは、一人で抱え込まず、相談先を活用することです。支援を受けながら歩めば、少しずつ前向きな未来を取り戻すことができます。
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS