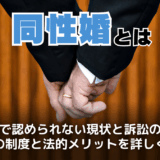母子保健は、すべての母親と子どもが健康で幸せに暮らせる社会を実現するための重要な制度です。本記事では、母子保健の基本から日本の現状、課題、そして行政や地域の最新支援策までをわかりやすく解説します。
あなたとお子さんの毎日を守るために、妊娠・出産・育児について「今」知っておくべき制度とサポートを紹介します。母子保健の制度について理解を深め、「もしものとき、どうすればいい?」という不安に備えましょう。
母子保健とは?
母子保健とは、妊娠中から子どもの健やかな成長を社会全体で支える仕組みです。まずはその基本を押さえて、安心して子育てできるための全体像を知りましょう。
母子保健の定義
母子保健とは、母子保健法に基づき、妊娠中から出産、そして乳幼児期にかけて母親と子どもの健康を守り、健全な発育を支援するために行われる公衆衛生活動の総称です。主な目的は、妊産婦と乳幼児が心身ともに健康に成長できるよう、医療・保健・福祉の側面から総合的に支援することにあります。具体的な活動には、妊婦健康診査、乳幼児健康診査、予防接種、保健指導、栄養指導などが含まれます。
また、母子保健の対象は母親と子どもだけではなく、出産や育児に関わる家族全体にも広がっています。妊産婦(妊娠中から産後1年未満の女性)と乳幼児(満1歳未満の乳児および1歳から小学校入学前までの幼児)が中心であり、各自治体はそれぞれの成長段階に合わせた支援体制を整備しています。こうした支援を通じて、母子保健は母子の身体的・精神的な健康の維持増進を図り、社会全体で次世代の健やかな成長を支える重要な役割を担っています。
日本における母子保健の歴史と法制度
日本の母子保健の歩みは、戦後直後の高い乳児死亡率や妊産婦死亡率の深刻な社会課題を背景に始まりました。昭和23年には児童福祉法が施行され、子どもの福祉向上が法的に位置づけられるようになりました。
その後、昭和40年には母子保健法が制定され、法律面・制度面で大きな進展が図られました。特にこの法整備によって、全国で母子健康手帳の交付が義務化され、妊婦健診や乳幼児健診の受診が普及。これらは妊娠期から乳幼児期まで一貫した健康管理を推進する上で重要な役割を果たしています。
母子保健法の目的は「母子並びに乳幼児の健康の保持増進を図ること」にあり、母子健康手帳の交付、妊婦健診の推奨、乳幼児健診の実施、家庭訪問指導や低体重児届出制度の整備など、現代の母子保健サービスの基盤となる仕組みが、この法律を礎に整備されてきました。
参考:東京の母子保健
参考:子どもの福祉|全国社会福祉協議会
参考:母子保健法の施行について(◆昭和41年03月07日発児第22号)
参考:母子保健の現状と課題
日本の母子保健の現状
少子化や出産年齢の上昇など、社会環境が大きく変化する中で、日本の母子保健は新たな課題と向き合っています。この章では、出生率や乳幼児の健康状態、地域支援の現状を通じて、最新の母子保健の実情を見ていきましょう。
日本における出生数・出生率の現状
厚生労働省が公表した「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」によると、2023年の出生数は72万7,277人で、統計史上最少を記録しました。前年から約5万人減少し、戦後初めて年70万人台にまで落ち込んでいます。また、合計特殊出生率(女性1人あたりの平均出生数)は1.20と前年の1.26からさらに低下し、少子化の深刻さが一層明らかになりました。
さらに、第1子出生時の母親の平均年齢は31.0歳と上昇しており、晩産化が進行しています。これらのデータは単なる統計ではなく、地域社会の担い手不足や労働人口減少、社会保障制度の維持など、日本社会全体への影響を示す重要な課題です。母子保健の充実は、この状況に歯止めをかけるために欠かせない取り組みであり、誰もが安心して妊娠・出産・子育てできる支援体制の構築が急務となっています。
乳幼児の健康・発育状況
こども家庭庁の「令和5年乳幼児身体発育調査」によると、全国の乳幼児の身長・体重の平均値は過去と比較して大きな変化は見られないものの、出生時の体重がやや減少傾向にあることが報告されています。
乳児死亡率は引き続き過去最低水準を維持しており、医療技術の進歩による影響が大きい一方で、低出生体重児(出生時体重2,500g未満)の割合は緩やかに増加傾向にあります。これは、晩産化や妊婦の生活習慣の変化、社会的ストレスなど複数の要因が関与していると考えられています。
また、厚生労働省の乳幼児栄養調査では、母乳・混合・人工栄養の割合や離乳食開始時期の多様化など、育児方法の個別化が進んでいることも示されています。こうした結果は、母子保健の現場が従来よりも幅広い視点で健康支援や保健指導を行う必要性を示唆しています。
母子保健事業や電子母子手帳の普及状況
日本では、自治体を中心に妊娠・出産・育児を一貫して支援する母子保健事業が展開されています。主な取り組みには、妊婦健康診査費用の助成、乳幼児健康診査(1歳半・3歳児健診)、母子健康手帳の交付、予防接種管理、地域保健師による家庭訪問や育児相談などがあります。これらの事業は「地域の子育て支援の根幹」として位置付けられており、全国の母子保健センターや自治体の保健センターで運営されています。
近年では、母子保健サービスのデジタル化が急速に進んでいます。公益財団法人母子衛生研究会の調査によると、電子母子手帳やオンライン相談機能を備えたアプリなど、子ども・子育て領域に特化したICTツールを導入している自治体は全国で37.2%に達しています。このような電子母子手帳アプリでは、健診結果や予防接種日程の確認、母子保健情報の共有がスマートフォンで簡単にできるようになり、子育て世代の利便性が大幅に向上しています。
参考:令和5年(2023) 人口動態統計月報年計(概数)の概況
参考:厚生労働省 令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の要約
参考:令和5年「乳幼児身体発育調査」調査結果の公表について | こども家庭庁
参考:乳幼児栄養調査|厚生労働省
参考:我が国の電子的な母子保健ツールと活用に関する実態調査
参考:母子保健関連施策の体系
参考:千葉市:母子保健事業一覧
参考:赤ちゃん&子育てインフォ
母子保健の3つの目的
母子保健の目的は、母親と子どもの健康を守り、誰もが安心して妊娠・出産・育児を行える社会を実現することです。ここでは、母子保健が果たす3つの重要な役割と、その具体的な取り組みについてわかりやすく解説します。
健康面で母子を守る
母子保健の最も根本的な目的は、母親と子どもの生命と健康を守ることです。各自治体では、妊婦健診により妊娠中の異常を早期に発見・対応し、出産に向けた健康管理を支援しています。また、乳幼児健診では、発育や発達の状態を確認し、先天的な疾患や発達の遅れを早期に把握することで、必要な医療・療育支援へとつなげています。こうした体制により、病気の早期発見と治療、そして事故や重症化の予防が実現しています。
加えて、産後うつや育児ストレスなどのメンタルヘルス対策にも力が入れられており、こども家庭センターを中心に心理士や保健師による早期相談が行われています。低出生体重児や医療的ケア児など、特別な支援を必要とする母子に対しても、NICUとの連携や訪問型支援によって継続的なケアが行われ、すべての母子が健やかに過ごせる社会の実現に寄与しています。
子育て環境を整える
母子保健のもう一つの重要な目的は、「安心して子どもを産み育てられる環境を整えること」です。国や自治体では、出産育児一時金や出産・子育て応援ギフトなどの経済的支援を通じて、妊娠・出産・育児にかかる費用負担の軽減を図っています。育児教室や地域子育て支援拠点、親子交流サロンなども整備され、親同士が交流できる「孤立しない子育て環境」づくりが推進されています。
さらに、子育て世代包括支援センターを中心に、保健師や助産師などの専門職が連携して母子の健康と生活を支援。NPO法人や地域団体とのネットワークづくりを通じて、社会全体で子育てを支える仕組みが広がっています。
少子化対策と子どもの健やかな成長を支える基盤
母子保健は、単に母親と子どもの健康維持にとどまらず、少子化対策の中核としても重要な役割を担っています。安心して子どもを産み、育てられる環境を整えることは、子どもを持つことへの不安を軽減し、結果として出生率の維持・回復に寄与します。
また、こども家庭庁が推進する「こどもまんなか実行計画2025」では、健康支援・教育・経済支援を一体化した総合的な母子保健政策が進行中です。これにより、母子保健は子どもを社会全体で育てる仕組みづくりの基盤として位置づけられ、持続可能な社会形成へと繋がっています。妊娠期からの切れ目のない支援によって、次世代が健やかに成長できる社会を実現する取り組みが今後も強化される見通しです。
参考:母子保健の現状
参考:令和7年度研究事業実施方針(案)【AMED研究】
参考:地域で支える母子と家族のメンタルヘルス
参考:こども家庭庁
参考:出産育児一時金等について|厚生労働省
参考:三井住友銀行
参考:第10回「健康寿命をのばそう!アワード」事例集
参考:APOPLUS保健師
参考:母子保健情報誌
母子保健が直面する主な課題
少子化の進行や家庭環境の多様化により、母子保健は今、大きな転換点を迎えています。この章では、地域格差、健康リスク、デジタル化の遅れなど、日本の母子支援が直面する主要な課題を掘り下げていきます。
地域や家庭による支援格差
母子保健の分野では、経済的・社会的背景の違いによる「支援格差」が依然として課題となっています。特に、経済的に困窮する世帯やひとり親家庭、多子世帯などでは、行政サービスや支援事業の情報が十分に届かず、支援を受けにくい状況が生じやすい傾向にあります。これらの家庭では、情報不足に加えて「行政機関への相談に抵抗がある」「他人に頼ることへの心理的ハードルが高い」などの理由から、母子保健サービスの利用が遅れやすいことが問題視されています。
また、自治体ごとに支援制度やサービス内容に格差があり、居住地域によって母子保健支援の受けやすさが異なる現実もあります。こども家庭庁や厚生労働省は、子育て世代包括支援センターの全国展開や母子保健DX(デジタル化)を通じ、支援情報の公平な提供を目指しています。
妊産婦や乳幼児の健康リスク
現代の母子保健において、妊産婦のメンタルヘルス問題は深刻な課題となっています。特に、出産後のホルモン変化や育児ストレスによって発症する「産後うつ」は、母親のおよそ10人に1人に見られるとされ、そのまま放置すると児童虐待のリスク上昇や子どもの発達に影響を及ぼす可能性があります。また、育児孤立による精神的負担の増加は、母子双方の健康維持に大きな影響を与える要因となっています。
さらに、厚生労働省の統計によると、出生時体重2,500g未満の「低出生体重児」の割合は2019年時点で9.4%に達しており、増加傾向にあります。これらの低体重児は、将来的に発達障がいや生活習慣病を発症するリスクが高いことが指摘されており、出生直後からの適切な医療的支援と長期的なフォローアップ体制の整備が求められています。
ICT(デジタルツール)活用の遅れ
母子保健の分野では、電子母子手帳やオンライン相談など、ICT(デジタルツール)を活用した支援の導入が進んでいる一方で、自治体間での普及率や利用状況に格差が見られます。
特に一部の自治体では、アプリの導入は完了しているものの、利用者数が伸び悩んでおり、実用面での課題が残されています。また、スマートフォンやインターネットの利用に不慣れな高齢者層や情報弱者にとっては、こうしたデジタルサービスの恩恵を十分に受けられないという「デジタルデバイド(情報格差)」の問題も懸念されています。
さらに、自治体間や医療機関との間で母子保健データを共有する体制が未整備であること、システム導入や運用に必要な予算・人材の不足が指摘されています。その結果、母子一人ひとりの健康状態や家庭環境に合わせた「パーソナライズ支援」の実現が難しい状況が続いています。
参考:日本看護科学会誌
参考:地域の母子保健現場からの展開
参考:第一生命経済研究所
参考:地域特性からみた医療アクセスの格差に関する研究
参考:妊産婦メンタルヘルスケアマニュアル
参考:低出生体重児 保健指導マニュアル
参考:活力ある持続可能な社会の実現を目指す観点から、優先して取り組むべき栄養課題について
参考:「母子保健情報のデジタル化について」の概要
参考:令和3年度 子ども・子育て支援推進調査研究事業
母子保健の課題解決策
妊娠・出産・育児をとりまく課題に対応するためには、母子保健の仕組みをより包括的で実践的なものに変えていく必要があります。国や自治体による支援策やICTを活用した事例を具体的に紹介します。
妊娠から子育てまで切れ目のない支援
母子保健では、妊娠届出時の面談から出産・育児期を通じて「切れ目のない支援」を提供する体制が整備されています。妊娠が判明した段階で行われる母子健康手帳の交付時面談では、保健師や助産師が妊婦の健康状態や生活環境を把握し、必要に応じて支援プランを作成します。出産後は、産後ケア事業による助産師の訪問指導や産後ヘルパー派遣、宿泊型・デイケア型施設の利用支援などが行われ、母親の心身の回復を後押ししています。
その後、乳幼児期には1歳6か月健診、3歳児健診など定期的な健康診査や予防接種、育児相談を通じて成長を継続的に見守る仕組みが導入されています。特に、広島県府中町の「ネウボラかるて」などの先進自治体では、妊娠届から健診記録、相談履歴までを一元管理する電子カルテシステムを導入し、切れ目のない支援を実現しています。このように、母子保健は出産期を中心とする支援にとどまらず、子どもが学校に入るまでの包括的な支えとなることを目指しています。
電子母子健康手帳やアプリの導入
電子母子健康手帳アプリの普及により、従来の紙媒体では実現できなかった多様な機能が利用可能となっています。予防接種のスケジュールを自動管理し、接種漏れを防ぐリマインド機能や、健診結果や成長記録をグラフで視覚的に確認できる仕組みが導入され、保護者の負担を大幅に軽減しています。また、地域のイベントや子育て支援情報をプッシュ通知で受け取れるなど、行政と家庭をつなぐ情報発信ツールとしても重要な役割を果たしています。
さらに、電子母子手帳を活用することで、医療機関や自治体との情報共有がスムーズになり、乳幼児健診結果や健康相談履歴をもとに個別最適化されたアドバイスが得やすくなりました。保護者はスマートフォンひとつで子どもの健康情報を一元管理でき、引っ越しや転院時にもデータを簡単に共有できる利点もあります。
母子保健分野における国のデータ活用
国では、科学的根拠に基づいた母子保健政策を推進するため、厚生労働省や国立成育医療研究センターを中心に、全国の母子保健データを統合・分析する体制が整備されています。これには、妊娠・出産・乳幼児健診情報を連携させた「母子保健データベース」構築が含まれ、地域格差の把握や支援の必要性が高い母子世帯の早期発見につながっています。また、電子母子健康手帳との連携により、個々の健康データをもとにしたパーソナライズ支援が可能になりつつあります。
これらのデータは、予防接種の有効性やスケジュール見直し、低出生体重児の発達支援、産後うつの予防策の立案など、実際の政策形成や医療現場での取り組みに活用されています。特に、国立成育医療研究センターの研究成果は、妊産婦のメンタルヘルス対策や新生児医療の標準化にも結びついており、母子保健を支える医療・行政の連携強化を後押ししています。
参考:厚生労働省 2.(3)妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援について
参考:出産・子育て応援事業(ゆりかご・とうきょう事業)について
参考:世田谷版ネウボラ(妊娠期から就学前までの切れ目のない支援)
参考:デジタル田園都市国家構想
参考:ままのて
参考:ベビースマイル 赤ちゃんの健康情報
参考:「母子保健・医療情報データベース」の運営および利用状況報告
参考:ライフコースデータによる予防医療と医療リアルワールドデータの現場への還元
母子保健に関する支援やサービス
母子保健の現場では、妊娠・出産・育児を支えるための支援やサービスが幅広く整備されています。この章では、全国で利用できる相談窓口や経済的支援、産前産後のサポート事業など、暮らしに寄り添う制度をわかりやすく解説します。
全国共通の相談窓口・ホットライン
母子保健では、妊娠・出産・子育て期にわたるあらゆる悩みに対応できる相談窓口が全国に整備されています。中心となるのが「子育て世代包括支援センター」で、市区町村の保健センターや役所内に設置されており、妊婦や子育て中の家庭が気軽に相談できる場として機能しています。
ここには保健師・助産師・ソーシャルワーカー・社会福祉士などの専門職が常駐し、健康相談、育児ストレス、経済的課題など幅広いテーマに応じた専門的アドバイスを提供しています。また、「子ども家庭支援センター」でも家庭環境に悩みを抱える保護者や子どもを対象に、継続的なフォロー支援が行われています。
さらに、夜間や休日など緊急性の高い場合には「24時間子どもSOSダイヤル(0120-0-78310)」や「児童相談所虐待対応ダイヤル(189)」が全国共通で利用可能です。どちらも匿名で相談でき、虐待・いじめ・家庭不和などの事案にも迅速に対応しており、地域の児童相談所や関係機関へ速やかに繋ぐ仕組みが整っています。
母子保健を守る経済的支援
母子保健の分野では、妊娠・出産・育児にかかる経済的負担を軽減するための支援制度が多く整備されています。妊娠期には自治体が実施する「妊婦健康診査費用助成」があり、交付される受診票を医療機関で提示することで、定期健診の費用が助成されます。出産時には、健康保険組合などから「出産育児一時金」が原則50万円(産科医療補償制度加入分)支給され、入院・分娩費用に充てることができます。
さらに、こども家庭庁が推進する「出産・子育て応援ギフト」では、妊娠届出時と出生届出後にそれぞれ5万円相当の経済的支援が給付され、自治体を通じて申請・受給が可能です。また、子どもの成長に応じて支給される「児童手当」も母子保健を支える代表的な制度で、0歳から中学校卒業までの子どもを対象に、3歳未満は月額15,000円、3歳以上から中学生までは月額10,000円(所得制限により一部変動)支給されます。
産前産後ヘルパー、産後ケア事業などのサポート
母子保健では、出産後の母親や家庭を支えるために、産前産後ヘルパーや産後ケア事業といったサポートが全国で整備されています。これらのサービスはワンオペ育児や家族の支援を受けにくい家庭にとって大きな助けとなっており、安心して出産後の生活を送るための重要な支えとなっています。
産前産後ヘルパー派遣事業では、育児や家事をサポートする専門員が自宅を訪問し、母親の体調回復や育児への負担軽減を支援します。また、産後ケア事業では、助産師や看護師が宿泊型・デイケア型施設、または訪問型のケアを通じ、授乳指導・体調管理・メンタルサポートなどを提供します。これらの利用には自治体への申請が必要で、利用者の所得に応じて費用の一部が助成される場合があります。
参考:こども家庭庁|子育て世代包括支援センターの実施状況
参考:ベネッセ教育情報サイト
参考:こども家庭センターについて
参考:「24時間子供SOSダイヤル」について:文部科学省
参考:妊婦健康診査について | 世田谷区公式ホームページ
参考:出産育児一時金等について|厚生労働省
参考:三井住友銀行
参考:児童手当制度のご案内|こども家庭庁
参考:こども家庭庁|児童相談所虐待対応ダイヤル「189」について
参考:産前・産後支援ヘルパー|杉並区公式ホームページ
参考:産褥期の心強い味方!「産後ヘルパー」とは │ 子育てタウン
参考:産後ケア事業について|こども家庭庁成育局母子保健課
母子保健のよくある質問
母子保健制度や支援サービスについて、多くのママたちがよく抱く質問を取り上げ、妊娠や出産、子育てに役立つ情報を解説します。
Q1. 母子健康手帳はどこで、どうやってもらえますか?
母子健康手帳は、妊娠が確認された段階で住民票のある市区町村の窓口で交付されます。医療機関で妊娠が確定すると発行される「妊娠届出書」を持参し、自治体窓口で申請手続きを行います。この際には、妊婦本人のマイナンバーカードや身分証明書、印鑑などが必要です。交付時には、保健師や助産師による面談が行われる場合もあり、妊娠中の健康管理や母子保健制度に関する説明を受けられます。
Q2. 妊娠・出産・育児の各段階で必要な手続きは?
妊娠が分かったら、まず市区町村の保健センターなどで「妊娠届出書」を提出し、母子健康手帳を受け取ります。この際に妊婦健診費用の助成券も交付されます。出産後は、14日以内に役所で「出生届」を提出し、同時に健康保険への加入と乳幼児医療費助成の申請を行います。また、児童手当の申請も市区町村窓口で行う必要があります。育児期には、定期的な乳幼児健診や予防接種を受け、必要に応じて保健センターで育児相談を利用しましょう。
Q3. 産後うつや育児ストレスの相談先は?
出産後のホルモン変化や育児生活の急な変化によって、不安や孤独感を抱く母親は少なくありません。こうした「産後うつ」や育児ストレスを感じたときは、一人で抱え込まず、早めの相談が大切です。まずは、市区町村の保健センターに設置されている「子育て世代包括支援センター」や「子ども家庭支援センター」で、保健師や助産師、心理士などの専門職による面談・カウンセリングが受けられます。
Q4. ひとり親家庭や特別な事情がある場合、どこに相談すればいいですか?
ひとり親家庭や特別な支援を必要とする家庭は、まず自治体の「子育て世代包括支援センター」または「家庭児童相談室」で相談できます。これらの窓口では、保健師・社会福祉士・心理士などの専門職が在籍し、経済的な不安、養育環境、就業支援、生活費や住宅など幅広い課題に対応しています。
Q5. 母子保健アプリやICTサービスの利用方法は?
自治体から案内されるアプリをスマートフォンにダウンロードし、マイナンバーカードや母子健康手帳番号を登録して初期設定を行うだけで利用開始できる場合がほとんどです。登録後は、健診結果や医療機関での記録が自動連携され、必要に応じて医師や保健師との情報共有も可能になります。
まとめ
母子保健は、妊娠期から乳幼児期まで母子を一貫して支援するための社会システムであり、すべての家庭が安心して子どもを産み育てられる環境づくりの要となっています。健診や予防接種の実施、母子健康手帳制度、産後ケアや相談体制など、行政・医療・地域が連携しながら母子の健康を守る仕組みが整備されています。
一方で、地域や家庭の状況による支援格差、情報格差、メンタルケアの課題も残されています。これらを解消するために、こども家庭庁を中心としてデジタル技術の導入が進み、電子母子手帳アプリやオンライン相談サービスなどが拡大しています。今後は、行政、医療機関、地域社会がさらに連携し、誰一人取り残さない母子保健体制を築くことが求められます。未来を担う子どもたちとその家族を社会全体で支える取り組みが、次世代を育む持続可能な社会の基盤となっていくでしょう。
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS