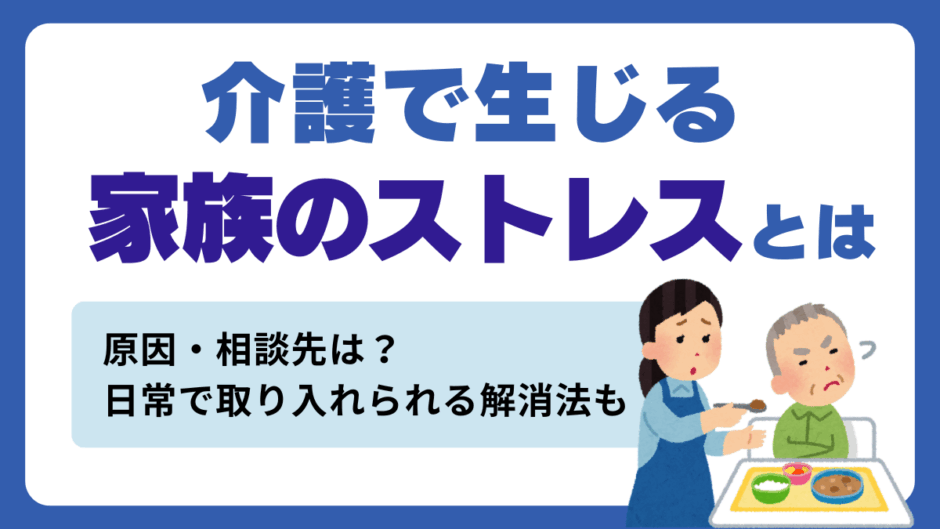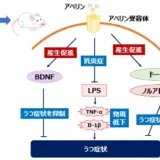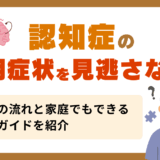介護は大切な家族を支える尊い行為ですが、その一方で大きな負担を伴います。長時間の介護や夜間の対応、仕事や家庭との両立によって、身体的な疲労だけでなく精神的なストレスも蓄積しやすくなります。さらに、経済的な負担や家族間での役割の偏りなども重なり、深刻な問題へと発展することも少なくありません。
本記事では、介護による家族のストレスの実態や原因を整理し、相談先や利用できる支援制度、日常で取り入れられる解消法を徹底的に解説します。
介護による家族ストレスとは?
介護は愛情から始まりますが、日常の負担が積み重なると家族に大きなストレスをもたらします。その実態を見てみましょう。
「家族の介護ストレス」とは、家族が要介護者を支える過程で心身や経済に生じる負担のことを指します。厚生労働省の調査では、主な介護者の約6割が「心身のストレスあり」と回答しており、介護は多くの家庭にとって避けられない課題となっています。ストレスは疲労や睡眠不足だけでなく、不安や孤独感、不公平感など精神面にも大きく影響します。
背景には社会構造の変化があります。高齢化の進行に伴い、夫婦のどちらかが高齢者を介護する「老老介護」が増加しており、体力面の負担が深刻です。また、未成年や若い世代が家族の介護を担う「ヤングケアラー」問題も注目され、学業や就労の機会を制限されるケースが報告されています。さらに、介護と仕事の両立が困難になり退職を余儀なくされる「介護離職」も年間数万人規模で発生しており、社会全体の生産性や家計に影響を及ぼしています。
このように、家族の介護ストレスは個人の問題にとどまらず、社会全体の課題でもあります。相談の場を活用しながら、制度やサービスを通じて少しでも負担を軽減することが求められています。
老老介護問題
老々介護とは、65歳以上の人が別の65歳以上の人の介護を行うことをいいます。2022年に行われた厚生労働省の調査によると、老々介護の割合は63.5%にも上ります。
核家族化や長寿化が進んでいるため、夫婦での介護になってしまったり65歳以上の人が、80代や90代の高齢者の介護をしているのも、超高齢化社会の日本では当たり前にある光景となってしまっています。
介護している側の高齢者は、入浴介助であったり、排泄介助といった介護を行うことは、身体的に負担が大きく、いつまで続くのかわからない日々に精神的にも追い詰められてしまって、共倒れしてしまう可能性も高まってしまうのが老々介護です。
65歳以上の介護者が自分自身の心身を削ってまで、介護をすることによって、追い詰められて犯罪に繋がってしまうことも、老々介護の問題点でもあります。
ヤングケアラー問題
ヤングケアラー問題は、学生などの10代や20代の若者が介護者となり介護を主体となって行うことです。
介護に注力するばかり学業がおろそかになったり、遅刻や欠席などが増えたりしてしまう点が大きな問題です。学業に集中できず、周りの子どもたちから遅れをとってしまうこともヤングケアラーの問題点として挙げられます。
その結果、受験の際に出席日数が足りなかったり、成績が足りなかったりと問題が起き、進学が危ぶまれてしまう場合も多々あります。
他にも介護に時間を取られてしまうため、友人と遊んだりする時間が確保できず、孤立してしまったりなど学校での人間関係がうまくいかなくなってしまうこともあります。
介護を主体となってやっていると、睡眠時間も削られてしまい、成長期に十分な睡眠がとれない点も大きな問題点です。慢性的な睡眠不足になっているヤングケアラーは、どうしても他の健康問題も引き起こしやすい点も問題点として、挙げられます。
介護離職問題
介護離職問題とは、家族の介護が必要になった時に、仕事との両立ができず、現役世代が仕事を辞めざるを得なくなる社会的な課題のことです。家族の介護のために、実家に戻ったりという人もいるため、大きな課題となっています。
介護離職問題の背景にあるのは、要介護認定者の数が増えている点が挙げられます。介護離職しなければならないほどの場合は、要介護の度合いも大きいと言えます。
フルタイムで働きながら介護をするのは、職場の理解などがない限り難しいとされています。介護のために時短勤務や在宅勤務に切り替えができたとしても、会社の理解がなく白い目で見られてしまったりといったことから退職を選択する人もいます。
仕事をセーブして、介護に集中できる環境になったとしても、次に起こるのが経済的な不安です。働けない分手取りが減って、どうしても生活が困窮しがちな点も介護離職問題の大きな課題です。
介護ストレスの背景にある社会構造
家族の介護ストレスは、個人の努力や忍耐だけでは解決できない背景を持っています。その大きな要因の一つが日本特有の同居率の高さです。親と子が同じ世帯で暮らすケースでは、介護の中心を担う人の生活全般に介護が組み込まれるため、休息や自分の時間が奪われやすくなります。
また、介護制度にも限界があります。介護保険や公的支援は存在しますが、サービスの利用枠や時間数には制約があり、現場のニーズに十分応えられない場合が多くあります。サポートが不十分なために、介護者の孤立感や不公平感はさらに増してしまいます。
さらに、社会の核家族化も見逃せない要因です。かつてのように親族や地域で介護を分担する仕組みは弱まり、一人や夫婦だけで高齢者の介護を担う家庭が増えています。こうした環境では、介護の責任が特定の家族に集中しやすく、心身両面での限界を迎えやすくなります。つまり、家族の介護ストレスは社会構造の変化とも密接に関わっており、個人の努力に任せるだけでなく、制度や地域社会全体での支え合いが不可欠なのです。
参考:厚生労働省
参考:東京都健康長寿医療センター研究所
家族が感じる介護ストレスの種類と症状
家族が抱える介護ストレスは一様ではなく、身体・精神・経済面など多岐にわたります。ここではその具体例を整理します。
身体・精神・経済的ストレス
家族の介護ストレスは、多面的に現れるのが特徴です。まず身体的なストレスとしては、夜間の介助による慢性的な睡眠不足や、入浴や移動を手伝う際の腰痛・肩こりなどが挙げられます。特に長期にわたる介護は肉体的な疲労が積み重なり、日常生活にも支障を及ぼします。
精神的なストレスも深刻です。介護が長引くと孤独感や不公平感を抱きやすく、気分の落ち込みや無力感につながります。「自分だけが介護を担っている」という感覚は、家族関係の不和や精神的な限界を招きかねません。また、感情を押し殺して介護を続けることで、うつ状態や不眠症などの症状が出るケースもあります。
さらに、経済的な負担も大きな課題です。介護にかかる費用は介護保険制度で一部軽減されるものの、自己負担や医療費、交通費などが積み重なります。加えて、仕事をセーブしたり離職を余儀なくされたりする「介護離職」が収入減少を招き、世帯全体の生活を圧迫する要因となります。
このように、家族が感じる介護ストレスは単なる心身の疲労ではなく、生活全般に及ぶ複雑な負担です。状況を放置すると健康被害や経済的困窮を引き起こすため、早い段階で相談できる場を持ち、支援制度や地域の資源を組み合わせることが重要です。
ストレスが限界を超えるときに現れる兆候
ストレスが限界を超えるときに現れる兆候を見ていきましょう。
うつ傾向
家族の介護ストレスが長期間蓄積すると、心身に深刻な影響を及ぼす場合があります。特に注意すべき兆候の一つが「うつ傾向」です。
気分の落ち込みや意欲の低下が続き、何事にも無関心になるといった症状が見られます。これを放置すると、生活の質が大きく低下し、介護を続ける力そのものが奪われてしまいます。
その結果として介護虐待やネグレクトといったことが起こってしまうので、介護者以外の人間が早い段階で介入する必要があります。
介護虐待
強いストレスの結果として「介護虐待」が生じるリスクもあります。介護者が心身ともに限界に達すると、暴言や無視などの心理的虐待や、必要なケアを怠るネグレクトに発展することがあります。
これは介護者本人が望んでいない場合でも、過剰な負担が引き金となってしまう点に注意が必要です。
強いストレスにさらされていると、どうしても要介護者本人に矛先が向きやすい傾向にあるため、できるだけデイサービスや訪問介護などを利用して、介護者と要介護者二人きりの時間を無くしていくことが重要です。
家族崩壊
もっとも深刻なのは「家庭崩壊」に至るケースです。介護を巡る不公平感や経済的な負担が原因で家族間の対立が激化し、夫婦関係や兄弟姉妹の絆が壊れてしまうこともあります。こうした事態は介護者だけでなく、介護を受ける本人にとっても不幸な結果を招きます。
注意すべき行動パターンとしては、感情のコントロールが難しくなり、些細なことで怒りや苛立ちを感じやすくなる、周囲との交流を避けて孤立する、食欲や睡眠の乱れが続くといったサインが挙げられます。
介護ストレスの現状と課題
介護ストレスの現状と課題をご紹介します。
介護ストレスの現状
まずは日本の介護ストレスですが、自宅にて同居しながら介護を行っている人のうち約7割の人が日常生活において、ストレスや悩みを抱えてしまっているのが、現状です。
自宅内という限られた場所で、当事者同士しかいない中で介護を行っていくのは、想像以上に追い詰められてしまうため、介護疲れから、介護うつを発症してしまう人も少なくありません。
経済的・肉体的・精神的どれか一つではなく、介護の場合はすべての負担が大きい点も介護ストレスにつながる要因となりえます。
仕事に行けないことから経済的なストレスがあったり、排せつ物の介護など肉体的・精神的に負担がかかる点も、介護ストレスの原因です。
介護ストレスの課題
上記でも挙げた経済的・肉体的・精神的という複雑な要素が絡み合って、介護ストレスは増幅していきます。
介護者自身の心身ともに健康的な生活ができなくなり、仕事にも行けなくなってしまうと経済的な不安が付きまとい、社会的な孤立も明確になってしまいます。
また介護ストレスの大きな課題としては、やはり終わりが見えないという点が大きいです。子育てであれば、できることが増えていって自立していくのが一般的ですが、介護の場合はできないことが増えていって介護者の負担は大きくなるばかりです。
「何年後には施設に入れる」「あと数か月でデイサービスが利用できる」といった目標地点が明確にあれば、介護者もそこまでなんとかできれば、と思えますが介護の場合はそう上手くいかない点も、介護ストレスが溜まってしまう大きな原因です。
身体・精神・経済的ストレスの具体例
身体・精神・経済的ストレスの具体例を見ていきましょう。
身体的ストレス
まず身体的ストレスですが、成人を抱えて移動させて入浴させたり、排泄のたびにトイレまで連れて行ったりといったシーンで身体的なストレスが溜まってしまいます。
他にも介護は24時間休みなく続くものなので、夜間の対応が必要になる場合があります。夜中のトイレに付き添ったり、目覚めてしまえば一緒に起きて、対応する必要があります。
排せつや入浴ではかがむ姿勢が多く、腰痛を発症してしまったりと介護は体力勝負な部分が多々あるため、身体的なストレスが貯まりやすい環境です。
精神的ストレス
要介護者の中には認知機能が低下している場合があります。コミュニケーションがとりにくくなってしまっているので、意思の疎通が難しくなってしまう点も、介護者の精神的なストレスに繋がります。
また終わりの見えない介護がいつまで続くのかを考えただけで、気分がふさぎ込んでしまう介護者も大勢います。自分自身だけで過ごす時間や、趣味にかけられる時間が減ってしまう点も精神的なストレスとなり、介護うつなどを発症してしまう場合があります。
他にも周囲から辛さを理解してもらえず、孤独感を感じている介護者も多いのが現状です。
経済的ストレス
経済的なストレスは、もっとも苦しいと感じる人が多い問題でもあります。介護のために離職したり、時短勤務にした場合に給料が減ってしまい、今後の生活を不安に感じる人も多いでしょう。
また介護には想像以上にお金がかかるもの。デイサービスの費用であったり介護用品の購入など、実費でかかるものも多々あります。収入は減ってしまったのに、購入しなければならないものが多いという点は、大きなストレスに繋がります。
家族の介護ストレスを軽減する公的・民間サービス活用術
介護の負担を少しでも軽くするためには、制度やサービスを知り、上手に活用することが欠かせません。ここから具体例を紹介します。
介護保険・行政支援の活用
家族の介護ストレスを和らげるためには、まず公的制度である介護保険と行政の支援を正しく理解し、積極的に利用することが重要です。介護保険は40歳以上が加入対象となり、要介護認定を受けることで訪問介護やデイサービス、ショートステイなど多様なサービスを一部負担で利用できます。これにより介護者の心身の負担が軽減され、介護を受ける本人にとっても安心できる生活環境が整います。
また、地域包括支援センターは最初の相談窓口として活用できる存在です。介護の悩みや制度利用に関する質問に専門職が対応し、ケアマネジャーとの連携を通じて適切な支援を提案してくれます。さらに、各自治体では高齢者向けの福祉サービスや家族介護者向けの相談窓口を設けており、介護休業制度や在宅介護手当など、状況に応じた支援を受けることが可能です。
公的支援を利用する際の注意点としては、「どのサービスをどの程度利用できるか」を早めに確認しておくことです。介護度や地域によって利用できる内容が異なるため、情報収集を怠ると必要なときに十分なサービスが受けられないこともあります。
家族の介護ストレスとは、制度を知らずに一人で抱え込むことで深刻化するケースが多いため、まずは行政のサポートを積極的に取り入れることが大切です。早い段階で相談し、制度を上手に活用することが、長期的に介護を続けるための安心と余裕につながります。
民間サービス・地域資源の有効活用
公的支援だけではカバーしきれない部分を補うのが、民間サービスや地域資源の活用です。これらを上手に取り入れることで、家族の介護ストレスを軽減できるケースは多くあります。例えば、近年普及している見守りサービスは、センサーやカメラを設置して離れた場所から高齢者の生活状況を確認できる仕組みです。転倒や異変をいち早く察知できるため、介護者の不安を和らげ、外出や仕事中でも安心感を得られるのが大きなメリットです。
また、買い物代行サービスも注目されています。日用品や食料品を自宅まで届けてもらえるため、重い荷物を運ぶ負担を減らし、介護者が外出に時間を割かなくても済みます。特に介護と仕事を両立している世帯では、このような生活支援型のサービスがストレス軽減に直結します。
さらに、地域のボランティア活動も有効な支援源です。高齢者サロンや傾聴ボランティア、外出付き添いサービスなどは、介護者が一時的に負担を手放す機会を提供します。こうした地域資源は費用負担が軽い場合も多く、継続的に利用しやすい点も魅力です。
家族が抱える介護ストレスは、日々の小さな積み重ねによって悪化するものです。多様なサービスを柔軟に組み合わせることで、介護する側とされる側の双方がより安心して暮らせる環境が実現できます。
介護ストレスによる心のセルフケアと感情整理のポイント
介護を続ける中で心身の負担を減らすには、自分の感情と向き合い、適切に整理するセルフケアが大切です。その方法を解説します。
自分だけで抱えない
家族の介護ストレスは、一人で抱え込むほど深刻化しやすい問題です。介護は長期戦になることが多く、体力的な負担だけでなく、精神的な疲労も積み重なっていきます。だからこそ「弱音を吐くこと」や「誰かに相談すること」がセルフケアの第一歩になります。弱音を言うことは決して甘えではなく、自分の限界を見極め、ストレスを緩和するために必要な行動です。
例えば、身近な家族や友人に今の思いを伝えるだけでも気持ちが整理され、孤独感が和らぎます。また、公的機関や地域包括支援センターなどの専門機関に 相談をすることで、制度や支援サービスの具体的な利用方法が見えてきます。相談を通じて新たな選択肢や情報が得られれば、介護負担を軽減するきっかけとなるでしょう。さらに、同じ立場の人が集まる家族会やサポートグループに参加することも有効です。経験を共有することで「自分だけではない」と感じられ、共感や励ましを得られます。
大切なのは、無理に一人で頑張ろうとせず、周囲の人や制度に頼る勇気を持つことです。相談することは介護を続けるためのエネルギーを回復する手段であり、介護者自身と介護を受ける人の双方にとってプラスの効果をもたらします。
感情を整理する具体的な方法
家族の介護ストレスを軽減するためには、感情をそのまま溜め込まず、うまく整理する方法を持つことが大切です。特に介護は予期せぬ出来事が多く、瞬間的に怒りや不安を感じることも少なくありません。そうした場面で役立つすぐに実践できる小さな行動を紹介します。
例えば「イライラしたら6秒数える」という方法はシンプルですが効果的です。人の怒りは6秒がピークと言われており、この間を深呼吸しながらやり過ごすことで、冷静さを取り戻せます。また「終わりを思い描く」という習慣も有効です。介護は永遠に続くものではなく、限りある時間だからこそ、その瞬間をどう過ごしたいかを考えることで心の持ち方が変わります。
さらに、日記やメモに感情を書き出すのもおすすめです。紙に書くことで客観的に自分の気持ちを捉えやすくなり、「なぜこんなに疲れているのか」「本当はどうしたいのか」といった気づきを得るきっかけになります。
また、趣味や軽い運動など自分のリズムを取り戻せる行動も、感情の整理に役立ちます。短時間であっても音楽を聴いたり、散歩に出かけたりすることで気分がリセットされ、介護ストレスに対する耐性が高まります。
相談できる機関や支援を活用するのと同時に、このような小さなセルフケアを実践することが、ストレスを悪化させず前向きに介護を続ける鍵となります。
参考:ライフル介護
参考:東京都健康長寿医療センター研究所
SDGsから考える「介護と家族ストレス」の課題と解決策
介護に伴う家族のストレスは、個人の問題にとどまらず社会課題でもあります。ここではSDGsの観点から解決の方向性を考えます。
SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」
SDGs目標3は「すべての人に健康と福祉を」と掲げていますが、ここでいう「すべての人」には要介護者だけでなく、その介護を担う家族も含まれます。家族の介護ストレスとは、本人の努力や気合いで解決できるものではなく、社会全体で支えていくべき課題です。介護を受ける側が健康で安心して暮らせることはもちろん大切ですが、介護する側の心身の健康が守られてこそ持続可能な介護環境が実現します。
例えば、介護者が長時間の介助で疲弊したり、睡眠不足やうつ傾向を抱えたりすれば、結果的に要介護者の生活の質にも影響を与えかねません。そのため、介護者の健康支援も福祉の重要な一環と位置づける必要があります。定期的な休養を得られるショートステイやレスパイトケアの提供、相談窓口によるメンタルケア支援などは、まさに家族の介護で生じるストレスを解消するための具体的な取り組みです。
さらに、地域や職場が一体となって介護者を支える仕組みを強化することも、目標3の実現につながります。介護休業制度や柔軟な働き方を普及させることで、介護と仕事の両立を可能にし、介護離職を防ぐことができます。
このように、家族の介護ストレスとは社会的な健康課題でもあり、介護者を含めた「すべての人」に目を向けることがSDGsの理念と重なります。介護者支援を福祉の柱として位置づけることが、持続可能な介護体制を築くための解決策となるのです。
介護とジェンダーの偏在性
介護における家族の介護ストレスとは、単なる個人の問題ではなく、社会的な構造に深く根ざした課題でもあります。そのなかでも特に注目すべきなのが、介護負担が女性に偏っている現状です。厚生労働省の調査でも、主たる介護者の6割以上が女性であることが明らかになっており、妻・娘・嫁といった立場の人が日常的に介護の中心を担うケースが多いのが実態です。家事や育児と並行して介護を行うことも多く、心身の疲労や孤立感が重なりやすい点が大きな問題となっています。
この偏在は、女性の就労機会やキャリア形成にも影響を及ぼし、「介護離職」や収入減少といった深刻な経済的課題を生み出します。また、男性が介護に十分に関われないまま、女性だけに負担が集中することで、不公平感や社会的な不均衡が助長されているのです。こうした状況は、家族全体の生活の質を下げるだけでなく、介護そのものの持続可能性を脅かしかねません。
解決のためには、まず「介護は女性の役割」という固定観念を社会全体で見直すことが必要です。男性の介護参加を促す啓発活動や、企業による介護休暇・時短勤務制度の普及が不可欠です。さらに、地域や行政による支援サービスを性別問わず利用しやすい形で整備することも、ジェンダー格差の是正につながります。
参考:国連
参考:東京健康長寿医療センター研究所
介護による家族ストレスに関するよくある質問
ここでは介護を続ける中で多くの人が抱える悩みとその回答をまとめます。
介護による家族のストレスとは具体的にどのようなものですか?
介護による家族のストレスとは、身体的な疲労や精神的な不安、経済的な負担などが複合的に重なる状態を指します。例えば夜間の介助による睡眠不足や、仕事との両立で時間的余裕がなくなることは大きな要因です。
また、兄弟姉妹間で負担が偏ると不公平感が生じ、孤独感や葛藤を深めます。厚生労働省の調査でも、主な介護者の約6割が「心身のストレスあり」と回答しており、これは個人の問題ではなく社会全体の課題です。相談できる場や支援制度の活用が重要になります。
介護ストレスが限界に達したとき、どのようなサインが出るのでしょうか?
介護ストレスが限界に達すると、心身にさまざまなサインが現れます。代表的なのは、慢性的な疲労感や不眠、食欲不振などの身体的症状です。また、イライラが強まり感情をコントロールできなくなる、涙もろくなるといった精神的な変化も起こります。
さらに「自分が介護をやめたい」「家族と距離を置きたい」といった思考に至ることもあります。厚労省の調査でも多くの介護者が心身の不調を訴えており、放置すると介護うつや家庭不和につながる危険性があります。こうしたサインを見逃さず、早めに相談の場を活用することが大切です。
家族内で介護の負担が偏ってしまうとき、どう解決すればよいですか?
介護の負担が一人に集中すると、心身の疲労や不満が募り介護のストレスが深刻化します。解決には、まず家族間で率直に話し合い、役割分担を見直すことが大切です。遠方に住む家族にも定期的な訪問や経済的支援をお願いするなど、関わり方を工夫できます。
また、地域包括支援センターなどに相談を行い、外部の専門機関に調整を依頼するのも有効です。訪問介護やデイサービスを利用することで、介護者が一人で抱え込まずに済む環境を整えることが可能になります。
介護によるストレスを軽減するために利用できる相談先や支援制度はありますか?
介護によるストレスを和らげるには、公的な相談窓口や支援制度を活用することが効果的です。地域包括支援センターは最も身近な相談先で、介護保険の申請やケアプランの作成をサポートしてくれます。また、市区町村の福祉課や保健センターでも相談を受け付けています。
さらに、介護者支援団体や電話相談、オンライン相談サービスなどもあり、匿名で気軽に悩みを打ち明けることが可能です。こうした制度を活用することで、介護者自身の心身の健康を守り、家族の介護ストレスを少しずつ軽減していくことができます。
介護を続けながら自分自身の心身の健康を守るためのセルフケア方法は?
介護を続ける中で心身の健康を保つには、意識的なセルフケアが欠かせません。まず睡眠や食事など生活の基本を整えることが重要です。短時間でも休息を確保し、好きな音楽を聴く、深呼吸をするなど簡単にできるリラックス法を取り入れると効果的です。また 相談を通じて気持ちを共有し、孤立を避けることもセルフケアの一環です。
さらに、地域の介護者支援グループやカウンセリングを利用することで、精神的な負担を軽減できます。自分の健康を守ることは、結果的に家族の介護ストレスを減らすことにもつながります。
まとめ
介護に伴う家族のストレスは、身体的・精神的・経済的な負担が複雑に絡み合って生じます。放置すると心身の不調や家庭内の不和につながるため、早めに気づき、対策を取ることが大切です。
本記事で紹介したように、介護保険や行政の支援制度、地域資源、民間サービスなどを積極的に活用することで、負担は確実に軽減できます。また、セルフケアや感情整理の方法を取り入れることは、介護者自身の健康を守る第一歩です。SDGsの観点からも、介護者の健康を福祉の一部と捉え、社会全体で支える必要があります。
最も大切なのは「一人で抱え込まないこと」です。介護の大変さを共有し、信頼できる人や専門家に相談するだけでも気持ちは軽くなります。あなたは一人ではありません。ストレスと向き合い、支援を得ながら、無理せずに介護を続けていきましょう。
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS