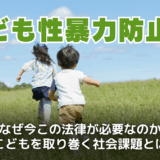自己肯定感は、自分自身を認め、価値ある存在だと感じる心の土台です。自己肯定感が高い人は、困難な状況でも自分を信じて前向きに行動できます。対人関係でも無理に他人と比べず、自分の軸で生きられるのがメリットです。
反対に、自己肯定感が低いと、ちょっとした否定的な言葉に敏感になり、自分を責めて落ち込んでしまうなど、ストレスを抱えやすくなります。また、子どもの頃の環境や関わり方が、自己肯定感の形成に大きく影響することも。
本記事では、自己肯定感が低くなる原因や高い人の特徴、チェック方法から上げ方まで、子どもから大人まで実践できる具体的な方法を、わかりやすく解説します。
自己肯定感とは

自己肯定感とは、自分自身の存在を価値あるものと認め、あるがままの自分を受け入れる感覚を指します。この感覚が育まれている人は、他者と比べることなく、自分の長所も短所も含めて肯定的にとらえる傾向があります。一方で、自己肯定感が低いと、自分の存在に意味を見出せず、自信を失いやすくなるという課題を抱えることになります。
この概念は近年、教育やビジネスの現場でも注目を集めており、個人のウェルビーイング(幸福)や持続的な成長に深く関係しています。国連が提唱するSDGsの中でも、パートナーシップ(目標17)や教育(目標4)などの取り組みは、個々人の尊厳や価値を尊重し合う社会の実現を目指すものであり、自己肯定感の醸成とも強く結びます。
例えば、子どものころから「あなたはそのままでいい」という肯定的な声かけや、失敗を否定しない教育方針が、健全な自己肯定感の土台となります。反対に、過度な競争や比較、否定的な評価が続くと、自己否定が習慣化してしまうことがあります。
このように、自己肯定感は私たちの心の基盤であり、対人関係や仕事のパフォーマンスにも大きな影響を与えます。だからこそ、自己肯定感の理解を深め、適切に育てていくことが、個人と社会双方の未来を明るくする大切な一歩となります。
自己肯定感が低い人と高い人は何が違う?
自己肯定感が低い人と高い人には、考え方や行動、物事のとらえ方に明確な違いがあります。高い人は自分の価値を内面から感じており、他者との違いをポジティブにとらえる一方、低い人は自分の価値を外部の評価に委ねがちで、失敗や拒否に対して極端に敏感です。
| 比較項目 | 自己肯定感が高い人 | 自己肯定感が低い人 |
|---|---|---|
| 自己評価 | 自分の価値を内面で認識できる | 他人の評価に左右されやすい |
| 失敗への反応 | 失敗を経験として受け止め、前向きに捉える | 自分を否定されたように感じ、深く落ち込む |
| 対人関係 | 他者との違いを尊重し、比較に執着しない | 他人と比較して劣等感を抱きやすい |
| 感情の安定 | 状況に左右されにくく、感情が安定している | 周囲の反応や出来事に感情が大きく影響されやすい |
| 挑戦意欲 | 新しいことに前向きに取り組むことができる | 失敗を恐れて行動が消極的になることが多い |
だからこそ、自己肯定感の状態を理解し、自分がどのような傾向にあるかを客観的に見つめ直すことが、自己成長の大きな第一歩となります。そして、適切なアプローチによって「低さ」は必ず変えることができます。
自己肯定感が低い原因
自己肯定感が低くなる背景には、成育環境や人間関係、社会的な価値観など複数の要因が複雑に絡み合っています。特に、幼少期の経験はその後の自己評価の基盤を大きく左右します。
否定的な育てられ方や親子関係
子ども時代に「なんでこんなこともできないの?」などの否定的な言葉を多く受けた人は、自己評価を下げやすくなります。褒められたり認められたりする経験が乏しいと、自分に価値があるという感覚が育ちにくくなります。愛情を条件付きで与えられる環境では、「何かができた自分」にしか価値を感じられなくなり、常に他人の評価を気にしてしまう傾向が強まります。
過度な比較や競争の文化
成績や実績などを軸にした比較が常態化している社会では、劣等感を抱く機会が多くなります。「あの人より劣っている」と感じるたびに、自信を失っていきます。特にSNSの普及により、他人の成功や幸福が可視化されやすくなった現代では、自分の価値を他者基準で測ってしまう傾向が強まっています。
継続的な失敗体験と自責思考
繰り返しの失敗や、目標達成の難しい経験が続くと、「自分はどうせできない」という思い込みが形成されます。ここに自責傾向が加わると、物事がうまくいかないたびに「全部自分が悪い」と結論づける習慣が根づいてしまいます。これは、自分の存在自体を否定する心理につながり、危険なループです。
周囲からの過小評価や批判
職場や家庭など、所属する集団の中で「役に立たない」「期待していない」などの態度を取られると、自分に価値を感じづらくなります。承認されない日々が続くと、「いてもいなくても同じ」などの感覚を持つようになり、自己肯定感は著しく損なわれていきます。
自己肯定感が低い人の特徴
自己肯定感が低い人には、思考や行動に共通するパターンが見られます。それは単なる気分の浮き沈みではなく、日常の感じ方や反応に根づいている習慣的な傾向です。
自分を過小評価しがち
「どうせ自分には無理」「自分は大したことがない」という内なる声に支配されており、実力や経験があっても自信を持てません。成功しても「たまたまだった」「他人のおかげ」と捉え、自分を正当に評価できないのが特徴です。
他人の評価を過度に気にする
人にどう思われるかが常に気になり、自分の意思よりも周囲の期待を優先する傾向があります。その結果、自分らしさを押し殺してしまい、行動や発言にブレが生じます。失敗や否定に対して極端に敏感で、萎縮するような言動が目立つこともあります。
挑戦や変化を避ける傾向がある
新しいことにチャレンジする際、「失敗したらどうしよう」などの不安が先に立ち、一歩踏み出せない傾向があります。これは、自分を信じる力が弱いため、リスクを取ること自体に大きな恐怖を感じている状態です。その結果、行動範囲が狭まり、さらに自己評価を下げる悪循環に陥ります。
他人と自分を比較し落ち込む
周囲の成果やライフスタイルを見ては「自分はダメだ」と感じやすく、必要以上に自己否定を繰り返します。SNSでの他人の投稿などが引き金となるケースも多く、他者の成功を素直に喜べず、自分との落差ばかりに意識が向いてしまいます。
自己肯定感が高い原因
自己肯定感が高い人には、それを育んできた背景や経験があります。生まれつきの性格というよりも、成長過程での人間関係や環境、成功体験などが積み重なって形作られているのが特徴です。
幼少期からの無条件の愛情や肯定的な言葉
自己肯定感が高い人は、幼少期に「あなたはあなたのままでいい」と伝えられるような、無条件の愛情をしっかりと受け取って育っている傾向があります。結果や成績に関係なく、存在自体を認められてきた経験は、自分に対する揺るぎない信頼を育てます。
たとえば、失敗しても「大丈夫、あなたならきっとできるよ」などの前向きな声かけを受けてきた人は、物事に挑戦することに対して恐れを感じにくくなります。親や教師がその人自身を肯定し続けてきたかどうかは、自己肯定感の土台を大きく左右します。
小さな成功体験の積み重ね
成功体験は、達成感と自信を与える大切な要素です。それがどんなに小さなものであっても、「できた」「頑張った」「認められた」という実感が自己肯定感を育てます。例えば、家庭内でのお手伝いや、学校でのちょっとした成果を褒められた経験があると、自分には価値があると自然に思えるようになります。
また、評価軸が「他人との比較」ではなく「自分なりの達成」に置かれていることもポイントです。本人の努力やプロセスを尊重するフィードバックを受けてきた人は、自らを内発的に認める力が身につきます。
安心して失敗できる環境
自己肯定感が高い人の多くは、失敗を「成長のチャンス」としてとらえる柔軟な思考を持っています。これは、過去に失敗を否定されずに受け入れられてきた経験があるからこそです。
「間違えても大丈夫」「完璧でなくても愛される」などの環境で育つと、人は挑戦することに前向きになれます。心理的安全性が確保された家庭や職場で過ごすことで、失敗に対する耐性が強まり、結果として自己肯定感が高まります。
自己肯定感が高い人の特徴
自己肯定感が高い人は、物事のとらえ方や行動、他人との接し方で、ポジティブな傾向を示します。彼らは自分を信じながらも、他者と調和しながら生きる柔軟さを持っています。
自分の価値を外部評価に委ねない
自己肯定感が高い人は、自分の価値を他人の評価や社会的な成功に依存しません。他人からのフィードバックを参考にすることはあっても、それによって自分の存在価値が左右されることは少ないです。自分の内面から「これでいい」と思える感覚があるため、外的な要因にブレない安定したメンタルを保っています。
たとえば、仕事でミスをしても「これは自分にとって必要な学びだった」と前向きにとらえることができます。このような自己受容の感覚は、精神的な回復力やレジリエンスとも深く関わっています。
他者との違いを受け入れる余裕がある
自己肯定感が高い人は、他人と自分を比べることに執着しません。他者の成功を素直に認め、自分は自分という視点を持つことで、健全な人間関係を築くことができます。自分自身の価値をすでに理解しているからこそ、他人の個性や長所にも寛容になれます。
このような姿勢は、職場や学校などの集団生活でも強みになります。他人の意見を尊重しながらも、自分の意見をしっかり持つことができ、対話や協力を通じて信頼関係を築いていけます。
自分の感情や行動を俯瞰できる
感情のコントロールや自己理解にも長けているのが、自己肯定感の高い人の特徴です。何かトラブルが起こっても、自分の感情に飲み込まれず、「なぜこう感じたのか」「どうすればいいか」を冷静に考えることができます。内面を正しく理解し、必要であれば軌道修正できる柔軟性と客観性を兼ね備えています。
その結果として、ストレスに強く、プレッシャーの中でも自分らしさを保てる安定感があります。周囲に安心感を与える存在として信頼されることも多く、自然とリーダー的な役割を担うケースも見られます。
自己肯定感の自己診断チェックリスト
自己肯定感は目に見えるものではないため、自分が今どの程度自分を認められているのかを把握するには、簡単な自己診断が役立ちます。定期的に自己状態を振り返ることで、無意識の思考パターンに気づき、より健全な自己評価へと導くことが可能になります。
まずは、以下の質問に「はい」「いいえ」で答えてみてください。該当する数が多いほど、自己肯定感が高い傾向があります。
<自己肯定感チェック項目(全10項目)>
- うまくいかなくても「次がある」と前向きに考えられる
- 他人と自分を比べず、自分のペースで頑張れる
- ミスをしても自分を責めすぎない
- 自分の意見や感情を正直に表現できる
- 周囲の目よりも自分の納得感を大切にしている
- 他人の成功を素直に祝福できる
- 褒め言葉を素直に受け入れられる
- 自分の長所と短所を自覚し、どちらも受け入れている
- 何かに挑戦する際に「やってみよう」と思える
- 自分の存在には意味があると感じている
「はい」が8〜10個 → 自己肯定感は高め
「はい」が4〜7個 → 自己肯定感はやや不安定
「はい」が0〜3個 → 自己肯定感は低い傾向
このようなチェックリストは、自分の内面を客観視するための第一歩です。「いいえ」が多かった場合でも、落ち込む必要はありません。自己肯定感は訓練によって徐々に高めることが可能だからです。次章では、自己肯定感を上げるための具体的な方法を紹介していきます。
自己肯定感が高いことで得られるメリット
自分を認める気持ちが強いと、毎日の小さなことに幸せを感じやすくなります。仕事や人間関係で落ち込む場面があっても、立ち直りが早く、前向きに行動できるのが大きな特徴です。
さらに、人との関わりが心地よいものになり、自然と良い出会いやチャンスも増えていきます。つまり、自己肯定感の高さは人生を豊かにする土台といえるのです。
ここではそんな自己肯定感が高いことで得られるメリットを紹介しましょう。
メリット① 前向きに挑戦できる
自己肯定感が高い人は失敗しても大丈夫と自然に思えるため、新しいことにチャレンジしやすくなります。
たとえば仕事で大きなプロジェクトを任されたときも、「今は不安だけど、やりながら学べばいい」と前向きに動けるのです。結果だけでなく、挑戦する自分を認めているからこそ、一歩を踏み出す勇気が持てます。この積み重ねが成長を加速させ、自信にもつながっていきます。
さらに挑戦を重ねることで、周囲からも頼れる存在と評価され、より大きなチャンスが巡ってくる好循環が生まれるのです。
メリット② 人間関係がスムーズになる
自己肯定感が高い人は、自分を大切にできる分、相手の意見も素直に受け止めやすいです。職場や友人関係でも相手を否定せず、まず受け入れるという姿勢が取れるので、周りとの関係がスムーズに進みます。
結果として信頼されやすくなり、人から相談されたり、頼りにされることも増えます。お互いを尊重し合える関係性は、長く心地よい人間関係を築く基盤となります。また、意見が対立したときでも感情的にならず、冷静に解決できるため、無用なトラブルを避けられるのも大きな強みです。
メリット③ 心の回復力が高まる
どんな人でも失敗や挫折は経験します。ただ、自己肯定感が高い人は落ち込むのは自然なことと受け止めるのが上手です。ネガティブな気持ちにとらわれすぎず、次はこうすればいいと切り替えができるため、立ち直りが早いのです。
心の回復力があると、ストレスを抱え込みにくくなり、結果的に心身の健康も守られます。さらに毎日を安心して過ごせる大きな支えとなります。
加えて回復の早さは、挑戦を恐れない強さにもつながり、人生全体の充実度を押し上げる原動力となるのです。
自己肯定感が低いことのデメリット
自己肯定感が低いと、自分に自信が持てないだけでなく、人間関係や仕事に悪影響を及ぼすことがあります。人の目を気にしすぎたり、自分の意見を言えなかったりと、行動にブレーキがかかってしまうのです。
その結果、成長のチャンスを逃したり、余計なストレスを抱えて心身に不調をきたすリスクもあります。
ここでは、自己肯定感が低い人が直面しやすい代表的なデメリットを解説します。
①人の目を気にして行動できない
自己肯定感が低い人は、自分に自信がなく、どう見られるかを過剰に意識する傾向があります。
例えば友人と食事に行く際、本当は行きたいお店があっても反対されたらどうしようと考えてしまい、結局相手に任せてしまうことも少なくありません。
このように主体性を欠いた行動が続くと、自分の望みを表現する機会が減り、成長のチャンスを逃すことになります。さらに自分の意見を言ってはいけないという思い込みが強まると、人間関係でも受け身が増えてしまい、ストレスが溜まりやすくなるのです。
やがて自分は周囲に合わせるしかないという感覚が習慣化し、人生の選択肢を自ら狭めてしまうリスクも高まります。
②否定的に物事を捉えてしまう
自己肯定感が低い人は、自分はダメだと感じやすく、その延長で何事にも否定的な視点を持ちやすくなります。挑戦の前から「どうせ無理」と決めつけてしまい、チャンスを掴めないのです。
このような思考は仕事や人間関係、プライベート全てに影響します。さらに否定的な考えが癖になると、自分だけでなく周囲の出来事や他人に対しても批判的になりやすくなります。結果的に人間関係がギクシャクしたり、孤立を招く恐れもあるのです。ポジティブに考える練習を怠ると、悪循環に陥る危険性が高まります。
最初は小さな不安や自己否定でも、積み重なることで何をやっても上手くいかないという思い込みを強化し、前に進む力を奪ってしまうのです。
③人と比べて落ち込みやすい
他人と比べて自分は劣っていると感じやすいのも自己肯定感が低い人の特徴です。周囲の成功を素直に喜べず、逆に自分を卑下して落ち込んでしまうことがあります。
さらに、自分より優れている人に嫉妬し攻撃的になるケースや、自分より劣っている人を探して安心感を得ようとする行動も見られます。人の欠点を探すこのような行為は自分には価値がないという思いを、比較によって補おうとする心理です。
しかしこの考え方では本当の自信につながらず、心が常に不安定になります。結果として心の疲れが増し、人間関係もぎこちなくなってしまうのです。SNSなどで他人の華やかな生活を目にすると自己否定が強まりやすく、現代では一層注意が必要だといえるでしょう。
④頼み事を断れない
自己肯定感が低い人は、嫌われたくないという思いが強く、頼まれ事を断れない傾向があります。気が進まない飲み会や不本意な仕事を引き受けてしまい、心身ともに疲弊することも多いでしょう。
自分では優しく振る舞っていると思っていても、周囲からは自己主張がない人、都合よく使える人と見られてしまう可能性があります。
この状態が続くと、さらに自己肯定感を下げる悪循環に陥ってしまいます。本当に大切なことに集中するためには、時に勇気を持ってNOと言うことが欠かせないのです。断ることはわがままではなく、自分を守るために必要な行為です。
適切な線引きをすることで、かえって人間関係が良好になる場合も少なくありません。
自己肯定感のあげ方
自己肯定感は、後天的に育てることができる「心の筋力」です。どれだけ今低いと感じていても、日々の行動や考え方を少しずつ変えていくことで、確実に高めていくことが可能です。ここでは、今日から実践できる「自己肯定感を育てる3つの具体的な方法」を紹介します。
小さな成功体験を積み重ねる
自己肯定感を育てるうえで、最も効果的なのが「小さな成功体験の積み重ね」です。大きな目標を達成する必要はなく、日常の中にある些細な“できた”を意識するだけで、自分への信頼感は強まっていきます。
「5分だけ早起きできた」「コンビニで甘いものを買わずに我慢できた」「ありがとうを伝えられた」などの誰にでもできるレベルの成功で構いません。ポイントは、「できなかったこと」ではなく、「できたこと」に焦点を当てることです。
このような実感を積み重ねていくと、「自分にはできる力がある」という感覚が自然に身につきます。自信は一夜にして生まれるものではありませんが、小さな達成を繰り返すことで、着実に心の土台を整えることができます。
比較ではなく自己基準で評価する
多くの人が自己肯定感を失う原因は、「他人との比較」にあります。SNSや職場、家庭の中で「自分より優れている人」とばかり自分を比べてしまうと、自分の努力や良さが見えなくなってしまいます。
この悪循環から抜け出すには、評価の基準を「他人」ではなく「過去の自分」に切り替えることが大切です。「昨日より5分早く寝られた」「先月よりもスムーズに話せた」など、自分の成長を自分で認めてあげる視点が自己肯定感を押し上げます。
比較の視点を変えるだけで、自己否定から自己受容に切り替わり、無理なく前向きな行動が取れるようになります。人生は他人とのレースではなく、自分のペースで進む旅路です。
自分を否定しない言葉を使う
私たちの脳は、日々浴びる言葉の影響を大きく受けています。特に、自分自身に対して使う言葉は、自己肯定感の形成に深く関係しています。否定的な言葉を習慣的に使っていると、「自分には価値がない」という信念が根づいてしまいます。
「どうせ私なんてダメだ」「やっぱりできない」などの言葉が口癖になっている人は要注意です。そういったときには、「うまくいかなかったけど、次に活かせる」「まだできていないだけ」と、ポジティブな言い換えを意識しましょう。
最初は違和感があっても、続けていくうちに脳はその言葉に適応していきます。「私は私のままで大丈夫」と思えるようになることは、自己肯定感の本質です。言葉を変えることは、心の状態を変えるもっとも身近で確実な一歩です。
子ども・大人の自己肯定感を上げるための家族や周囲の人の接し方
自己肯定感は、その人の性格や経験だけで決まるものではありません。特に家族や親しい人との関わりが、心の安定や自分を信じる気持ちに大きな影響を与えます。
子どもであっても大人であっても、身近な人からどう接されるかによって、自分に対する見方や感じ方が大きく変わっていきます。
ここでは、子どもと大人それぞれに対して、周囲の人がどのように関われば自己肯定感を育むことができるかをご紹介します。
子どもの自己肯定感を育てるための関わり方
子どもにとって最も身近な存在である親や先生は、心の土台を育てる上で欠かせない存在です。
幼いころから、「あなたがいてくれてうれしい」「頑張ったことをちゃんと見ていたよ」といった言葉をかけることで、子どもは「自分は価値ある存在だ」と実感できます。
特に、失敗した際に頭ごなしに叱るのではなく、「挑戦できたことが素晴らしい」と努力の過程を認める姿勢が大切です。結果だけに注目せず、頑張った気持ちを受けとめることが、自信の芽を育てます。
また、大人が自己否定的な態度を取っていると、それがそのまま子どもに映ります。
日常の中で、親自身が「今日はうまくいかなかったけれど、自分を責めずに次を考えよう」といった前向きな姿勢を見せることが、子どもにもよい影響を与えるのです。
さらに、自分で選ぶ経験を積ませることも自己肯定感を高める要因になります。小さな決断でも「自分で選んでよい」と感じることで、自信を持つ機会につながります。
こうした積み重ねが、やがて「自分にはできる」「自分には価値がある」という確かな実感へと育っていきます。
大人の自己肯定感を支える周囲の接し方
大人になっても、自分の価値を見いだすうえで、周囲の反応や環境からの影響は小さくありません。
家庭や職場で「自分の行動が認められている」「自分は必要とされている」と感じられる瞬間があると、安心感とともに自信が深まっていきます。
特に、感謝や評価を具体的な言葉で伝えることは、心に残りやすく、自己認識を前向きに変える力があります。たとえば「あなたがいてくれて助かったよ」「この部分は本当に丁寧だったね」と伝えるだけで、相手の中にある価値を引き出すことができます。
反対に、失敗を必要以上に責めたり、否定的な言葉を繰り返すと、自分を信じる力は少しずつ失われてしまいます。
「誰にでもうまくいかない日がある」「できないときがあっても大丈夫」といった柔らかな姿勢で接することが、安心して挑戦できる空気を生み出します。
また、心理的に安全な環境をつくることも、自分を認める力を支えるためには欠かせません。
誰かに気持ちを話せる場があるだけで、人は自分の考えや感情に正直でいられるようになります。
大切なのは、相手を変えようとするのではなく、そのままを受けとめること。
「あなたはあなたのままでよい」と態度で伝えることが、どんな励ましの言葉よりも強く、心に残る支えとなるのです。
自己肯定感に関するよくある質問
自己肯定感に関しては、年齢や性格を問わず多くの人が疑問を抱えています。ここでは特に相談が多い5つの質問を取り上げ、実例や根拠を踏まえて解説します。
Q1. 自己肯定感と自信はどう違うの?
自己肯定感は「ありのままの自分を受け入れる力」であり、自信は「できる・成功するという見込み」です。つまり、自己肯定感は“存在”に関する感覚であり、自信は“能力”に対する評価です。たとえ自信がなくても、自己肯定感が高ければ失敗を恐れず行動できるという点が大きな違いです。
Q2. 自己肯定感は遺伝や性格に左右されますか?
性格の影響は多少あるものの、自己肯定感の多くは育った環境や経験によって形成されます。たとえば、同じ兄弟でも親からの接し方が異なると、自己肯定感に差が出ることも。大人になってからでも、肯定的な体験や言葉かけの積み重ねで高めることが可能です。
Q3. 自己肯定感が低いと、どんなデメリットがありますか?
自己肯定感が低いと、他人の目を気にして自分らしく振る舞えなかったり、失敗を極端に恐れて挑戦を避けたりする傾向があります。また、他人との比較が常態化し、常に不安や劣等感を抱きやすくなることも。結果として、ストレス耐性や人間関係に悪影響を及ぼすケースがあります。
Q4. 子どもの自己肯定感はどう育てればいいですか?
子どもの行動や成果ではなく、“存在そのもの”を認める声かけが大切です。たとえば「いてくれてうれしい」「頑張っているね」などの言葉が、自分の価値を実感させます。また、失敗しても責めずに「どうしたら次うまくいくかな?」と寄り添うことで、安心して挑戦できる環境が整います。
Q5. 自己肯定感が高すぎると問題になりますか?
一見すると高すぎる自己肯定感は問題ないように思えますが、「自己中心的」や「他者を見下す」などの態度に偏る場合、それは“自己肯定感”ではなく“自己過信”に近い状態です。本来の自己肯定感は、自分と同じように他人の価値も尊重できるバランスのとれた感覚です。
まとめ
自己肯定感は、他人と比べず、ありのままの自分を受け入れる土台です。高ければ前向きな挑戦や安定した人間関係を築け、低いと自分を否定して行動に制限が生まれやすくなります。しかしこれは訓練によって必ず育てることができます。
まずは日々の小さな成功を認め、自分を責める言葉を手放すことから始めてみましょう。自己肯定感を育むことは、人生全体をしなやかに、そして豊かに変える力を持っています。
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS