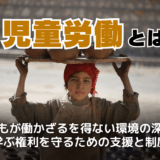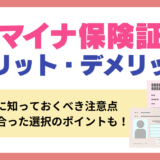家庭内DVは、親密な関係にある人から振るわれる暴力や支配行為を指し、殴る・蹴るなどの身体的暴力だけでなく、精神的圧力や経済的制限、性的強要なども含まれます。被害に気付きにくく、第三者の介入が難しい点が特徴です。
メリットとしては、相談窓口や法的制度を活用することで、保護命令や一時避難などの支援を受けられる点があります。一方で、加害者からの報復や、証拠が不十分な場合に適切な支援を得にくいというデメリットも存在します。
まずは、正確な情報を得て、安心できる支援体制につながることが大切です。行動する勇気が、自分自身と大切な人の未来を守る力になります。
家庭内DVとは?

家庭内DVとは、家庭という閉鎖的な空間で起きる暴力行為のことです。一般的に「DV」と聞くと殴る、蹴るなどの身体的暴力を思い浮かべるかもしれませんが、実際には精神的・経済的・性的な暴力など、さまざまな形態が存在します。また、DVの対象は法的に「配偶者」とされていますが、ここには婚姻関係の有無を問わず、事実婚や離婚後の関係も含まれます。さらに、交際中の相手や同居しているパートナーとの関係でも該当する場合があります。
一見すると単なる口論や意見の対立に見えるケースでも、継続的に相手を支配しようとする意図がある場合、それはDVと認識されるべきです。しかし、加害者は暴力を「しつけ」や「愛情の一環」として正当化することも多く、被害者側もそれを受け入れてしまい、自分が被害者であることに気付けない状況が続くことがあります。
法律上の定義と対象範囲
日本の法制度で、配偶者からの暴力は「ドメスティック・バイオレンス」として明確に定義されています。ここでの「配偶者」には、婚姻届を提出していない事実婚の相手や、すでに離婚している相手も含まれます。また、身体的暴力だけでなく、無視や怒鳴りつけるなどの精神的な攻撃、経済的に生活を制限する行為、さらには性的な強要まで、すべてがDVとされる対象です。
この定義により、DVの被害に対しては保護命令の申立てが可能となり、加害者に対する接近禁止や退去命令が法的に認められる制度が整備されています。ただし、それには証拠や継続的な被害が求められる場合もあるため、早めの相談が大切です。
「家庭内暴力」と「DV」の違い
家庭内暴力という言葉は、DVよりも広い範囲を指します。
| 家庭内暴力 | DV(ドメスティック・バイオレンス) | |
|---|---|---|
| 定義 | 家族の間で起こる暴力全般を指す広い概念 | 配偶者や恋人など親密な関係での暴力 |
| 対象関係 | 親子、兄弟姉妹、高齢者と子どもなど家族全般 | 主に夫婦・恋人間 |
| 特徴 | 家庭内での身体的・心理的な暴力 | 相手を支配・コントロールする目的を持つ |
| 具体例 | 子どもが親に暴力、高齢者虐待、兄弟間の暴力 | 殴る、無視する、経済的に拘束するなど |
| 社会的扱い | 家庭問題として扱われることもある | 重大な人権侵害・社会問題として法的対応が進む |
DVが主に配偶者や恋人間の暴力を意味するのに対し、家庭内暴力には親子や兄弟姉妹など、家族全般の人間関係の暴力が含まれます。たとえば、子どもが親に対して暴力をふるう行為や、高齢者への虐待なども、家庭内暴力の一種です。
一方、DVは加害者が被害者に対して支配・抑圧する目的を持ち、相手の行動や感情をコントロールしようとする点に特徴があります。そのため、DVは人権侵害であり、刑事・民事の両面から対応が求められる重大な社会問題とされています。
見落とされがちなDVの初期兆候
DVは突然始まるものではありません。最初は、軽い命令口調や相手の行動を制限するような言動から始まることが多く、被害者自身がその時点で違和感に気付けないこともあります。外出を制限されたり、誰と連絡を取るかを管理されるなどの「見えにくい暴力」は、精神的暴力の一種です。
このような行為がエスカレートしていくと、最終的には身体的暴力に発展する危険性があります。特に加害者が「おまえのためを思っている」などと正当化する場合、被害者はその言葉を信じてしまい、支配の構造から抜け出せなくなります。
DVの兆候を早期に把握することは、自分や周囲の人を守る上で大切です。「何かおかしい」と感じたときには、ためらわずに専門機関への相談を検討することが大切です。
参考:ドメスティック・バイオレンス(DV)とは | 内閣府男女共同参画局
家庭内DVの主な種類と具体例
家庭内DVは、配偶者やパートナーからの暴力として語られることが多いですが、その実態は身体的な暴力にとどまりません。実際には、言葉による攻撃や経済的な制限、性的な支配など、日常生活のさまざまな場面で行われていることがあります。
一見して暴力と認識しにくい行為でも、被害者にとって深刻な苦しみとなっている場合が少なくありません。
| 身体的暴力 | 叩く,殴る,蹴る,刃物で脅す,物を投げつける,突き飛ばす等 |
| 精神的暴力 | 相手の嫌がる言葉を言う,ののしる,暴言を吐く,無視する等 |
| 社会的暴力 | 頻繁な電話・メール,外出や友達付き合いの制限,過剰な嫉妬等 |
| 経済的暴力 | 生活費を渡さない,借りたお金を返さない,借金を負わせる,仕事を辞めさせる等 |
| 性的暴力 | 性的行為を強要する,避妊に協力しない等 |
ここでは、家庭内DVを五つの種類に分類し、それぞれの典型的な例を説明します。
身体的暴力
家庭内DVの中で最も分かりやすく、外見的に確認しやすいのが身体的暴力です。殴る、蹴る、平手打ちするなど、明確に身体を傷つける行為のほか、物を投げつけたり、髪を引っ張ったりする行為も含まれます。
こうした行動は、被害者の命や安全を直接的に脅かすものであり、緊急性が高いケースもあります。加害者が「カッとなって手が出た」と正当化することがありますが、暴力の根底には相手を支配しようとする意図が存在しています。
精神的暴力
精神的暴力は、目に見える傷がないため、周囲が気付きにくい傾向があります。しかし、被害者の心に深い傷を残す深刻な暴力の一つです。
具体的には、怒鳴る、侮辱する、過度に監視する、無視を続けるなどの行為が含まれます。
たとえば「誰もお前のことなんか相手にしない」「外出なんかするな」などの言葉や態度は、相手の人格や尊厳を否定し、精神的に追い詰めていきます。繰り返されることで、被害者は自分の価値を見失い、他者への相談や自立を難しく感じてしまいます。
経済的・社会的・性的暴力の具体例
経済的・社会的・性的暴力は、殴る・蹴るといった身体的な暴力に比べて気づかれにくいものです。
しかし、日常生活の自由や人間関係、将来の選択を大きく制限してしまい、被害者に深刻な影響を及ぼします。
そこで、代表的な3つの暴力の種類と具体例を、次の表に整理しました。
| 種類 | 具体例 | 特徴・影響 |
|---|---|---|
| 経済的暴力 | ・生活費を渡さない・家計を一切握らせない・働くことを禁じる・無断で借金をする | 被害者の経済的自立を奪い、加害者に依存せざるを得ない状況に追い込む |
| 社会的暴力 | ・外出や実家との連絡を制限する・SNSや電話の利用を禁止する・友人関係を断たせる | 被害者を孤立させ、「誰にも頼れない」と思わせることで支配を強化する |
| 性的暴力 | ・同意のない性的行為の強要・避妊の決定権を奪う・不快な性的要求を繰り返す | 夫婦・恋人間であっても同意がなければ暴力であり、心身に深刻な被害を与える |
これら3つの暴力は、認識されにくいにもかかわらず、生活基盤や人間関係、人格そのものに深刻なダメージを与えます。
次の項目ではそれぞれどのような暴力なのかを解説していきましょう。
経済的暴力
経済的DVには、生活費を渡さない、家計を一切握らせない、被害者が働くことを禁じる、無断で借金を重ねるなどの行為が含まれます。被害者は経済的な自立が難しくなり、加害者から離れることができない状態に追い込まれるのが特徴です。
社会的暴力
社会的暴力とは、外出や実家との連絡を制限する、SNSの利用を禁止する、友人との交流を断たせるなど、被害者を外の世界から孤立させる行為です。「誰にも頼れない」と思わせることで、支配を強めます。
性的暴力
性的暴力には、同意のない性的行為の強要だけでなく、避妊に関する決定権を奪う、不快な性的要求を繰り返すなども含まれます。これらは夫婦間であっても、同意がなければ明確な暴力行為です。
家庭内DVが発生する原因と背景
家庭内DVは突然起こるものではありません。そこには加害者の育った環境や心理的傾向、社会的な背景など、複数の要因が複雑に重なっています。被害を受けた人が「なぜ離れられないのか」と問われることもありますが、その背景には、外部からは見えづらい心の仕組みや依存の構造が潜んでいます。
ここでは、加害者の特徴や共依存の関係、そして暴力がエスカレートしていく過程を詳しくみていきます。
加害者の他社をコントロールしたいという欲求
加害者には、自分を過剰に正当化する一方で、他者をコントロールしたいという強い欲求を持つ傾向があります。外では優しく振る舞っていても、家庭の中では怒鳴ったり無視したりと、攻撃的な言動を繰り返すケースも少なくありません。
その背景には、子どものころに家庭内で暴力を受けていた、または親から十分な愛情を得られなかったなどの経験があることが多いです。また、ストレスや不安に対処する力が弱く、社会生活での不満や挫折を家族にぶつけてしまう場合もあります。アルコールや薬物への依存、精神的な疾患を抱えていることが要因となるケースもあります。
共依存関係による正常な判断不足
暴力を受けているにもかかわらず、被害者が関係を断ち切れないのは、心理的な「共依存」の影響が大きいといわれています。共依存とは、加害者と被害者が互いに依存し合い、健全ではない関係を続けてしまう状態のことです。
加害者は暴力のあとで涙ながらに謝ったり、優しい言葉をかけたりすることがあります。そのたびに被害者は「きっと変わってくれる」と信じたくなり、自分を責めてしまう傾向があります。また、子どもへの影響や経済的な不安が足かせとなって、身動きが取れなくなることも多いです。暴力が日常になると、何が正常かを判断できなくなる危険性もあります。
DVのエスカレーション
DVは初めから激しい暴力をともなうとは限りません。最初は言葉の暴力や無視などの行為から始まり、やがて物を壊したり、身体的な暴力に発展したりします。このように、DVは段階的に深刻化していく傾向があり、これを「エスカレーション」と呼びます。
さらに特徴的なのが「DVサイクル」といわれる構造です。これは、暴力が発生する「緊張期」、実際に暴力が行われる「爆発期」、そのあとに加害者が反省や謝罪を見せる「ハネムーン期」の3つの時期を繰り返します。この優しさが、被害者に「また元の関係に戻れるかもしれない」と期待させ、結果的に抜け出せなくなる要因にもなります。
DVの問題は、単なる個人の性格や家庭の問題ではなく、社会全体で向き合うべき課題です。特に、加害者や被害者の背景に目を向けることで、再発を防ぐための一歩が見えてくるはずです。
家庭内DVの影響と被害者の実態
家庭内DVは、加害者からの暴力や精神的な圧力により、被害者の身体だけでなく心にも深刻な影響を与える深刻な社会問題です。暴力の形が目に見えるものであっても、見えにくい精神的な支配であっても、その被害の深さは決して軽視できません。家庭の日常空間で繰り返される暴力により、被害者は長期にわたって心身をすり減らし、孤立を深めていきます。
心身への影響
暴力を受けた際に負うケガや身体的ダメージは一目でわかりますが、より長く続くのが精神面の影響です。被害者は怒鳴られたり無視されたりする日々のなかで、自尊感情を失い、「自分が悪いのではないか」と思い込んでしまいます。このような状態が長引くと、うつ病や不安障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症することもあります。
近年では、男性が被害者となるケースも見過ごせなくなっています。暴力の種類にかかわらず、精神的な支配や経済的な制限によって苦しんでいる人は性別を問わず存在しています。また、被害を受けるのは大人だけではありません。子どもが暴力の場面に居合わせることも大きな問題です。
面前DVと児童虐待の連鎖によって将来的に被害者または加害者になる可能性
家庭内で親の一方がもう一方に対して暴力を振るう場面を、子どもが見聞きすることを「面前DV」と呼びます。このような体験は、子どもにとって直接的な身体的暴力がなくても、心理的には虐待と同等のダメージを与えます。内閣府の資料によれば、面前DVは脳の発達や感情のコントロールに悪影響を与える可能性があるとされています。
さらに、こうした環境で育った子どもは、大人になった際に加害者または被害者になりやすい傾向があることが指摘されています。つまり、DVは家庭内で完結するものではなく、社会全体に連鎖的な問題を引き起こす要因となります。
相談をためらってしまう
DVを受けているにもかかわらず、被害者が誰にも相談できない状況に追い込まれていることは珍しくありません。「自分が間違っているのでは」「子どもに迷惑がかかるのでは」などの罪悪感や恐怖心が、支援機関へアクセスする勇気を奪ってしまいます。
加えて、経済的に自立できていなかったり、周囲に相談できる人がいなかったりする場合は、その不安がさらに強まります。精神的な暴力の多くは外部から見えづらく、第三者が気付きにくいため、被害者自身も「これはDVなのだろうか」と確信を持てないまま苦しみ続けてしまいます。
参考:DV(ドメスティック・バイオレンス)と児童虐待 ―DVは子どもの心も壊すもの―| 内閣府男女共同参画局
家庭内DVを受けた際の相談・支援先一覧
家庭内DVに苦しんでいる方のなかには、「どこに相談すればよいのかわからない」と戸惑ってしまう場合も少なくありません。深刻な被害を受けていながらも、相手からの報復を恐れて声を上げられないこともあります。
ですが、全国には相談を受け付けている公的機関や、支援体制を整えた団体が数多く存在します。ここでは、DVに悩む方が安心して利用できる相談・支援の窓口をお伝えします。
DV相談ナビ #8008とDV相談+
DVに関する悩みを抱えたとき、まず活用したいのが「DV相談ナビ(はれれば)」です。全国共通の番号「#8008」に電話をかけると、自動的に最寄りの配偶者暴力相談支援センターなどに接続され、支援内容の案内や相談を受けられます。24時間365日体制で対応しており、匿名でも利用できます。
また、「DV相談+」というサービスでは、電話に加えてチャットやメールによる相談にも対応しています。自宅など加害者の目がある場所でも、声を出さずに助けを求めることができるため、より安全な選択肢として認知が広がっています。日本語以外にも、英語や中国語など多言語での対応も可能です。
警察・配偶者暴力相談支援センターの役割
配偶者暴力相談支援センターは、都道府県や市区町村などの自治体が設置している公的な相談機関です。相談内容に応じて、一時的な避難場所の確保や、生活に必要な支援、医療・法律分野の専門機関への紹介など、多面的な支援を行います。
暴力の危険が差し迫っていると感じたときには、迷わず警察への通報を検討する必要があります。警察相談専用ダイヤル「#9110」は、DVに関する問い合わせや緊急の対応を受け付けています。被害者の身の安全を確保するため、警察から加害者への警告や、保護命令の執行などがなされる場合もあります。
弁護士・民間団体による支援
DV被害を受けている方のなかには、離婚や慰謝料の請求を考えている方も多いかもしれません。こうした手続きは精神的にも負担がかかるため、弁護士などの専門家のサポートを受けることが大切です。証拠の収集や、調停・裁判の手続き、保護命令の申請など、被害者が安心して行動できるようサポートが受けられます。
また、全国各地で活動するNPOや支援団体でも、DV被害者向けのサポートが提供されています。一時避難先の提供、カウンセリング、同行支援などを行う団体もあり、行政の支援と連携することで包括的な保護体制が構築されています。女性だけでなく、男性やLGBTQ+の被害者に対応している団体もあります。
参考:DV(配偶者や交際相手からの暴力)に悩んでいませんか。一人で悩まず、お近くの相談窓口に相談を! | 政府広報オンライン
DV加害者への対応と法的措置
家庭内DVの被害に直面したとき、被害者自身が取るべき行動と、それに対する加害者への法的措置について正しい知識を持つことは、安全を守るうえで不可欠です。近年は、DVへの社会的関心の高まりとともに、警察や行政、司法による保護制度や罰則が強化されています。ここでは、通報や相談の窓口、裁判所による保護命令、さらに加害者への刑事責任までの一連の対応を解説します。
警察への通報と「#9110」相談窓口
暴力が差し迫っているときは、迷わず110番へ通報することが最優先です。身の危険がなくても相談したい場合には、全国共通の警察相談専用電話「#9110」へ連絡することができます。
DVに関する悩みや不安を抱えたままにせず、状況に応じて専門機関とつながることが、自分を守る第一歩になります。警察は相談内容を確認し、必要に応じて現場に出向いたり、被害届の受付や関係者への事情聴取を行ったりする体制を整えています。
保護命令・接近禁止命令の手続き
被害者が加害者との接触に恐怖を感じているときは、裁判所に申し立てを行うことで保護命令を得ることが可能です。保護命令には、自宅や勤務先などへの接近を禁じる接近禁止命令や、同居している住宅からの退去を命じる退去命令などがあります。
これらの命令に違反した場合、加害者には刑事罰が科される可能性があります。申立ての際には、DVの被害を証明するための証拠が求められることがあるため、暴力の記録や診断書、相談記録などを日頃から保管しておくことが大切です。
加害者への刑事責任と再犯防止措置
DV行為は、暴行罪や傷害罪、脅迫罪などの刑法に抵触する犯罪行為に該当します。警察や検察の判断により、加害者は逮捕されたり、起訴されたりする可能性があります。刑罰としては、懲役刑や罰金刑が科される場合があります。
また、自治体によっては加害者に対して再発防止を目的とした教育プログラムの受講を促す取り組みも実施されています。これは、被害者の保護だけでなく、加害者の行動を根本から見直させることで、家庭内の安全を取り戻すことにもつながります。
参考:DV(ドメスティック・バイオレンス)について | 舞鶴市 公式ホームページ
離婚・慰謝料請求時の注意点
家庭内DVの被害を受けた方が離婚を考える際、慰謝料の請求は大きな焦点になります。しかし、DVの事実を裏付ける証拠が不十分なままでは、精神的・身体的な被害があっても、裁判で十分に認定されないおそれがあります。
離婚や慰謝料の手続きを検討するときは、法律の知識や証拠の整備、そして適切な支援を受けることが欠かせません。
DV慰謝料の相場と請求の流れ
家庭内DVが原因で離婚する場合、慰謝料の請求は法律上認められています。請求できる金額はケースごとに異なりますが、一般的には50万円から300万円の範囲が多いとされています。暴力の内容や継続期間、被害者の心身への影響、婚姻年数などが金額の判断基準になります。
慰謝料を求めるには、示談交渉から始めることが一般的です。ただし、DV加害者と直接やり取りすることは危険を伴うため、弁護士に代理を依頼するのが安心です。示談が成立しない場合は、調停や訴訟に移行することも視野に入れましょう。
調停では、裁判所を介して中立的な立場で話し合いが進められます。調停が不成立となったときには、離婚訴訟で慰謝料の有無が最終的に判断されます。
証拠の種類と確保方法
慰謝料を請求するためには、DVが実際に行われたことを裏付ける証拠が必要です。客観的な証拠があるかないかで、請求の可否や金額に大きな差が出ることがあります。
証拠として効果的なものには、受傷部位を撮影した写真、医療機関での診断書、怒鳴り声や脅迫を録音した音声、暴言や暴力の記録を記した日記やメモなどがあります。また、LINEやメールに残る加害者の発言、DV相談窓口への相談記録、警察に通報した履歴なども大切です。これらは一つよりも複数あったほうが、事実関係を立証しやすくなります。
証拠を集める際は、加害者に知られないよう十分注意を払ってください。物的証拠だけでなく、被害者自身の心の状態を記録することも大切な備えになります。
法的支援を受けるための準備
離婚や慰謝料請求を進めるにあたり、法律の専門家から支援を受けることは被害者の心強い味方になります。弁護士に相談することで、加害者との接触を避けながら手続きを安全に進めることができます。
収入や資産に制限がある場合でも、法テラスの支援制度を利用すれば、無料相談や弁護士費用の立替が受けられます。また、配偶者暴力相談支援センターや市区町村の女性相談窓口など、公的機関に相談することで、保護命令や一時避難などの制度の案内を受けられます。
こうした支援を受ける際は、状況を説明できる記録や証拠を整理しておくと、よりスムーズに対応してもらえる可能性が高くなります。一人で抱え込まず、信頼できる機関や専門家と連携しながら、離婚後の生活再建を見据えた準備を進めましょう。
SDGsと家庭内DVの関連性
家庭内DVは、個人の尊厳と安全を脅かす重大な人権侵害であり、社会全体にとっても深刻な課題です。近年ではこの問題が、国際的な取り組みであるSDGs(持続可能な開発目標)と密接に関係していることが広く認識されるようになっています。特に注目すべきは、「目標5 ジェンダー平等の実現」と「目標16 平和と公正をすべての人に」という2つの項目です。これらは、DVを単なる家庭内の出来事ではなく、社会構造のひずみによって引き起こされる人権問題としてとらえ、包括的な解決を目指しています。
目標5「ジェンダー平等を実現しよう」とDVの関係
SDGsの目標5では、あらゆる場所の女性と女児に対する暴力の根絶が掲げられています。家庭内DVはその最たる例であり、多くの被害者が、配偶者や交際相手からの暴力に苦しんでいます。暴力の形はさまざまで、殴る・蹴るなどの身体的暴力だけでなく、無視や怒鳴る行為、経済的支配や性行為の強要なども含まれます。
これらの行為は、女性の自立を妨げ、教育や労働などの社会参加を困難にする要因となります。また、暴力の根底には「男は支配する側、女は従う側」という根深い性別役割意識が存在し、それ自体がジェンダー不平等を助長しています。つまり、DVの解消なくして、真のジェンダー平等の実現はあり得ません。
目標16「暴力のない平和な社会づくり」とDV対策
SDGsの目標16は、「暴力と搾取、虐待をなくす」ことを中心に据えた取り組みです。DVは多くの場合、家庭という閉ざされた環境で起こるため、外部から把握されにくい特徴があります。しかしながら、見過ごされた暴力は被害者の心身に深刻な影響を与えるだけでなく、子どもにも悪影響を及ぼします。
たとえば、子どもの前でDVが行われる「面前DV」は、心理的虐待として児童虐待に該当する場合があり、次世代への悪循環を生み出します。そうした負の連鎖を断ち切るためには、被害者の保護だけでなく、加害者への法的対応や再発防止の取り組みも求められます。
参考:ドメスティック・バイオレンス(DV)とは | 内閣府男女共同参画局
家庭内DVに関するよくある質問
家庭内DVに関しては、「どのような行為が該当するのか」「相談してもすぐに通報されるのではないか」など、多くの人が不安や誤解を抱えたまま声を上げられずにいます。ここでは、被害に気付いたときや、身近な人から相談を受けたときに役立つ代表的な疑問を分かりやすく解説します。
どこからが家庭内DVになるのでしょうか?
家庭内DVは、殴る・蹴るなどの暴力行為だけではありません。怒鳴ったり無視したり、相手の交友関係を制限する、生活費を渡さないなどの行為も含まれます。加害者が「しつけ」や「教育」と主張しても、相手が精神的・経済的に追い詰められるような言動であれば、DVとして扱われます。
証拠がないと相談できないのでしょうか?
相談にあたり、必ずしも証拠が必要というわけではありません。「あれはDVでは?」と感じた時点で相談することが大切です。支援機関では、証拠の集め方や記録の残し方などを丁寧に案内しています。たとえ不安が漠然としていても、声を上げることで状況が変わる可能性があります。
男性も家庭内DVの被害者になりますか?
男性も被害者となるケースは少なくありません。内閣府が行った調査によれば、配偶者からの暴力を受けたとする男性の割合も一定数確認されています。DVは性別に関係なく、相手の尊厳を奪う重大な問題です。支援窓口では、男性被害者に対する相談体制も整備されています。
一度相談すると警察に通報されますか?
相談しただけで、いきなり警察に通報されることはありません。多くの支援機関では、相談者本人の意思を尊重して対応します。どう動くべきか迷っている段階であっても問題なく相談できます。命の危険がある場合を除き、無理に介入される心配はありません。
夫婦げんかとDVはどう違うのでしょうか?
夫婦間での言い争いは、意見の衝突によるものが多く、基本的には対等な関係の中で発生します。一方、DVは力関係の差を利用し、相手をコントロールする意図があるのが特徴です。被害者が恐怖を感じ、自由に行動できない状況に置かれている場合、それはDVとみなされます。
まとめ
家庭内DVは、身体的な暴力だけでなく、言葉や金銭の管理、性的な支配など、さまざまなかたちで現れます。自分が被害にあっていると気付かないまま、深刻な事態へと進行してしまう場合もあります。
誰にも相談できず、一人で苦しんでいる方もいるかもしれません。しかし、DVは決して個人の問題ではなく、社会全体で取り組むべき課題です。早い段階での相談が、心身の安全を守る第一歩につながります。
不安を抱えているなら、どうか迷わず支援機関や窓口に相談してください。あなたの声は、守られるべきです。ひとりで抱え込まず、勇気を出して行動に移すことが、未来を変える力になります。
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS