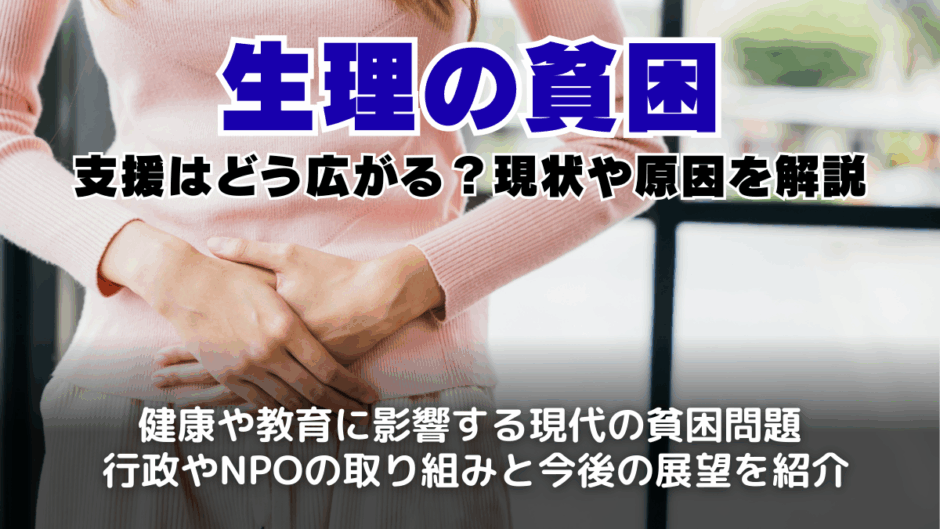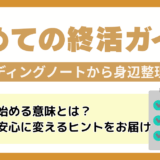生理の貧困とは、生理用品を十分に入手できない状態を指し、日本でも深刻な社会課題として注目されています。経済的な理由だけでなく、「生理は恥ずかしい」という空気や情報不足も背景にあり、健康や学業、社会参加にまで影響を及ぼしています。
近年、自治体やNPO、企業が無償配布や啓発活動を進めるなど支援は広がりを見せていますが、まだ十分ではありません。
本記事では現状や原因、データ、そしてSDGsとの関連まで徹底解説します。
生理の貧困とは?現代が抱える新しい「貧困」

生理の貧困は単なる経済問題にとどまらず、教育や健康、社会参加に影響を与える新しい貧困の形として注目されています。
国が定める生理の貧困の定義
厚生労働省などの公的機関が定める生理の貧困の定義は、「経済的理由で生理用品を購入できない状態」を指します。毎月必要となる生理用品が手に入らず、使い回しや代用品でしのぐなど、健康面や衛生面に問題が生じるケースが増えているのです。日本ではこの定義が認知され、行政や自治体の支援策、無償配布の施策にも直結しています。
生理の貧困は、単なる生活困窮だけでなく、“衣食住に加えた基本的な人権”のひとつと捉えられるようになりつつあります。SDGsの観点でも、生理用品の入手困難はジェンダー平等や健康と福祉の課題として連携され、具体的支援の基準・根拠となっています。
政策や施策では、この公式定義に基づいて支援対象の選定と社会資源の分配が行われており、当事者の声を反映した新たな対応策の重要性も高まっています。結果として、生理の貧困問題は社会的意義が非常に大きく、日本独自の現状と、世界的なSDGsの潮流を踏まえた取り組みの広がりが今後ますます注目されています。
社会的・心理的な壁も含めた国際的な定義
「生理の貧困」という言葉は、世界的に様々な文脈で語られています。日本では主に「経済的な理由で生理用品を買えない」状態と定義されますが、アメリカや欧州などではさらに広い意味を持ちます。具体的には、「生理用品やトイレなどの衛生施設、廃棄物管理、そして生理に関する教育や信頼できる情報へのアクセスが十分でない状態」も生理の貧困に含まれます。たとえば学校や職場で生理について気軽に話せない、必要な支援が受けられないといった心理的・社会的な障壁も、経済的困難と同じく重要な原因です。こうした壁が、当事者が相談できない空気や「恥ずかしい」「話しにくい」といった感情を生み、問題を複雑化させています。
そのため、現状やSDGsの目標達成には、経済的支援のみならず、教育や社会の意識改革、無償配布などサブキーワードに関連した複数のアプローチが求められているのです。
生理の貧困の認知度
生理の貧困についての社会的認知度は、福山平成大学にて学生を対象に行った調査によると、「生理の貧困」を聞いたことがない人が50.0%、「聞いたことはあるが意味を知らない」が40.6%、「意味を知っている」はわずか9.4%に留まっています。このデータからも、生理の貧困が依然として十分周知されていない現状が分かります。
SDGsや支援活動が進むにつれて、現状把握や原因、データによる啓発が求められており、情報発信の拡充が不可欠です。
日本・世界の生理の貧困の現状
生理の貧困を理解するには、具体的なデータや統計をもとに現状を把握し、国内外でどのような差があるのかを知ることが重要です。
生理の貧困を抱える日本の現状
日本における「生理の貧困」は、経済的な理由で生理用品を十分に確保できないという状態が一般的な定義とされています。しかし、海外では生理に関する教育や衛生施設へのアクセス・廃棄物管理の不十分さも含めて広く定義されています。日本の「#みんなの生理」調査(2021年)や厚生労働省の調査によると、若年層の約5人に1人が「生理用品の購入に困った経験がある」と回答しています。特にコロナ禍では収入減少や外出制限によって問題が深刻化し、入手困難になるケースが増加しました。またSDGs(持続可能な開発目標)の観点からも、データや現状を踏まえた支援・無償配布の動きが広がっています。
現状の日本では、経済的な負担だけでなく情報不足や社会的支援の限界が問題の複雑化を招いており、根本解決のためには多角的な取り組みが求められています。
世界も抱える生理の貧困
生理の貧困はグローバルに深刻な問題です。国際団体のMenstrual Hygiene Dayの2023年レポートによると、世界で約5億人もの女性や少女が生理用品にアクセスできず、特にグローバルサウス(アフリカ、南アジアなど)では深刻さが際立っています。たとえばケニアでは、約90%が不衛生な代用品による感染症など健康リスクを経験しています。また、アメリカでも2024年のワシントンD.C.での調査により、10代の3人に1人(約32.9%)が「生理用品の入手に困難を感じ、布やティッシュを使わざるを得なかった」と回答しています。
これらの状況は、教育への出席率の低下や社会活動・健康面への負担・精神的ストレスなど、女性や少女の日常生活全般に大きな影響を与えています。生理の貧困問題はSDGsのジェンダー平等・健康福祉の課題として世界的な社会問題となっています。
参考:【生理の貧困】10代の3人に1人「生理用品の入手に困難」米研究、日本の現状は?|ELLE ACTIVE! for SDGs
世界の取り組みと日本のギャップ
世界では生理の貧困解消のため、イギリスやスコットランドなどが学校・公共施設で生理用品を無償配布する制度を整えています。
生理に関する教育・啓発活動や衛生施設整備も進み、SDGs(持続可能な開発目標)を背景に、多くの国が経済的・社会的「壁」を取り払う施策を導入しています。対して日本は、自治体による無償配布や学校での取り組みが徐々に増加するものの、生理用品には10%の消費税が加算されており、負担が続いているのが現状です。また、無料配布の普及率も世界の標準的な制度と比べ遅れがあると指摘されています。
今後はジェンダー平等や健康福祉の観点を踏まえ、国際水準の支援体制や情報発信がさらに求められます。
なぜ生理の貧困は起きるのか?原因は?
生理の貧困は経済的事情だけでなく、社会的な偏見や教育不足など複数の要因が絡み合って生じている現象です。
非正規雇用や経済格差
生理の貧困が起きる大きな要因として、女性の非正規雇用と収入格差があります。日本では非正規労働者のうち、女性が約53.6%を占めており、非正規雇用の女性は正規雇用の6~7割程度の賃金水準となっています。男女間の賃金格差も大きく、厚生労働省統計によると2024年の正社員の賃金指数は男性100に対し女性75.8で、非正規を含む全体ではさらに低くなります。
さらに、ひとり親家庭(母子家庭)の平均年間収入は約272万円、父子家庭は約518万円と大きな差があり、母子家庭の多くが収入200万円未満で暮らしています。
こうした格差により生理用品の購入が困難となり、経済的困難や情報格差が生理の貧困の原因となっています。SDGsが目指す「誰ひとり取り残さない社会」の実現には、女性やひとり親家庭への支援強化と収入格差の解消が不可欠です。
参考:ひとり親家庭等の支援について
参考:全国ひとり親世帯等調査(旧:全国母子世帯等調査)|厚生労働省
「生理は恥ずかしい」という空気
日本では「生理は恥ずかしい」「人前で話してはいけない」という空気が根強く残っています。学校や職場で生理の話題がタブー視され、悩みを抱えていても誰にも相談できない状況になりがちです。この心理的な壁が、正しい知識の共有や支援へのアクセスを妨げ、生理の貧困問題を複雑にしています。さらに、SNSやメディアでも「生理=隠すもの」という意識が強調されがちで、無償配布や支援制度を知る機会が限られてしまいます。
こうした社会的なプレッシャーが原因となり、困難を抱えた人が孤立しやすくなっています。今こそSDGsや現状を踏まえ、教育や啓発活動を通じて「生理を隠す空気」を変え、適切な支援を誰もが自然に受けられる社会づくりが求められています。
日本と世界が直面する情報や教育の不足
生理の貧困問題の背景には、情報や教育の不足が深刻な原因となっています。
日本でも生理に関する教育は「家庭科」や「保健体育」で簡単に触れられる程度で、実際に必要な知識やケア方法まで深く学ぶ機会が限られています。これにより、誤った知識や偏見が根強く残り、支援情報にもアクセスしづらい状況が続いています。
世界では、発展途上国を中心に生理に関する教育がほとんど行われていない地域も多く、少女たちが初潮を迎えるまで生理の存在を知らないケースもあります。十分な教育がないまま誤解や迷信が広まり、生理期間中に学校へ通えなくなる、体の不調を誰にも相談できないなどの問題につながっています。また、地域によっては生理用品の使い方や衛生管理に関する情報が欠如し、感染症や社会的孤立などさらなるリスクが増加しています。
SDGsの「教育の質の向上」や「ジェンダー平等」の達成には、現状・原因を正しく伝え、情報格差を解消する取り組みが不可欠です。
生理の貧困がもたらす影響と課題
生理の貧困は生活の不便さにとどまらず、健康や学業、社会参加、さらには心の在り方にまで深刻な影響を及ぼします。
健康へのリスク
生理の貧困がもたらす健康へのダメージは深刻です。十分な生理用品を確保できないと、発展途上国や経済的困窮世帯では不衛生な布や紙を何度も使い回すことで細菌感染症にかかるリスクが高まります。教育不足や誤った知識が原因で、本来は交換すべき生理用品を長時間使い続けるケースも多く、その結果としてトキシックショック症候群(TSS)など重篤な健康障害を引き起こす恐れが指摘されています。また、出血量の多い日は生理用品不足で下着や衣服が汚れ、肌トラブルの原因となることもしばしばあります。さらに、生理用品の選択肢や使い方、衛生管理方法を知らないまま初潮を迎える少女が発展途上国や教育制度が十分でない地域で多数存在し、感染症や貧血、不安障害を抱えながら日常生活を送っています。
生理の貧困は単なる経済的困難に留まらず、健康や命にも直結する社会問題であり、現状・原因を明らかにしたうえで情報発信や支援体制の充実が不可欠です。
学業・仕事・社会参加の機会損失
生理の貧困は、単に生理用品を購入できない経済的な問題にとどまりません。必要な生理用品を十分に確保できない状況では、学校や職場に行けず欠席や遅刻が増え、学業の成績やキャリア形成に大きな影響を与えます。日本においても「生理が理由で学校を休んだことがある」という声は少なくなく、特に若年層で顕著です。また、社会活動やボランティア、友人関係など日常的な社会参加の機会も制限されやすく、孤立や格差を深める原因となります。
こうした状況は、SDGsが掲げる「教育機会の平等」「ジェンダー平等」の目標にも直結しており、国際的にも解決が求められる課題です。生理の貧困は目に見えにくい形で人生の選択肢を狭め、社会全体の発展を阻む要因となっています。
精神的ストレスと自己肯定感の低下
生理の貧困は、身体的な問題だけでなく精神的なストレスを強く引き起こします。必要な生理用品を確保できない状況では「常に不安がつきまとう」「清潔に保てないことへの罪悪感」に苦しみやすくなります。その結果、抑うつ気分や不安感、集中力の低下、さらには睡眠障害へとつながり、学業や仕事のパフォーマンスに悪影響を及ぼします。さらに「自分は価値がない」「自分だけが苦しんでいる」といったネガティブな自己認識が形成されやすく、これが自己肯定感の低下を加速させます。
生理そのものに嫌悪感を抱くこともあり、人間関係に消極的になったり、社会参加を避けるようになることも少なくありません。こうした精神的ダメージは見えにくいですが、長期的には人生の選択肢や社会とのつながりを奪う深刻な問題です。
生理の貧困に対する広がる支援と新しい取り組み
生理の貧困を解決するために、自治体や企業、NPOが多様な支援や新しい取り組みを広げ、社会全体で解決策を模索しています。
企業の生理の貧困に対する支援事例
生理用品が買えなかったり、お金がなくて困ったりする「生理の貧困」は、女性が勉強や仕事をする機会を奪ってしまう問題です。
ただ、最近は、この問題を解決しようと動き出す会社が増えてきました。 生理用品を無料で配ったり、生理について学べるイベントを開いたり、災害が起きたときのために生理用品を備蓄したりと、多くの方法があります。ここでは、特に活躍している5つの会社を例として紹介します。
オイテル株式会社(OiTr)
オイテル株式会社は、「OiTr(オイテル)」という個室トイレに生理用ナプキンを無料で置けるディスペンサーを販売してます。
トイレットペーパーのように生理用品が当たり前に置いてある社会を目指して、お店や大学、会社など多くの場所に導入され、すでに全国30都道府県に3,500台以上も設置しています。
また、生理に関する正しい知識を広める活動も行なっています。
今後はさらに設置場所を増やしつつ、教育・啓発活動により生理用品を使いやすく、そして多くの人の理解を得られる社会を目指しています。
参考:オイテル
株式会社G-Place
株式会社G-Placeは、「フェムテックジャパン」というブランドで、自治体や学校、会社などに生理用品を無料で提供したり、若い人や経済的に苦しい家庭の女性が安心して生理期間を過ごせるように寄付を集めるプロジェクトや生理について理解を深めるための活動を行っています。
ただ生理用品を配るだけでなく、教育や意識改革も含めて幅広く応援することで女性が安心して生活し働けるる社会を作ることに貢献しています。
参考:フェムテックジャパン
ユニ・チャーム株式会社
ユニ・チャームは、世界中の女性が安心して自分らしくいられるように、生理の問題やジェンダーの課題に取り組んでいます。特にアジア圏で、生理について正しく学べる初潮教育や生理用品を配る活動をしています。
例えば中国では、女子生徒にナプキン入りの「成長ボックス」を配ったり、台湾では政府に生理用品を100万枚寄付しています。他にもインドでは「Project Jagriti」という活動を通して農村部の女性が仕事を見つけ、経済的に自立できるよう支援しています。さらに、「Charm Girls Talk」というオンラインサイトで、コロナ禍でも勉強できる場を提供しました。
これらの活動は、SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」や目標5「ジェンダー平等をしよう」に繋がっています。教育、普及、経済的な支援を組み合わせた手厚いサポートが特徴です。
参考:ユニ・チャーム
大王製紙株式会社
大王製紙は、2022年から「奨学ナプキン」という企画を始め、お金がなくて生理用品を買うのが大変な学生向けに1年間ナプキンを無料で提供しています。
さらに大王製紙では、紙で包装した環境に優しいナプキンも発売しています。
このように生活者の健康と生活を守りながら、環境への負担を減らすことにも力を入れているのです。これからも若い人たちへの支援や啓発活動を行うことにより、社会全体で生理の貧困による問題を理解してもらえるよう活動しています。
参考:大王製紙
コメットテクノロジーズ・ジャパン株式会社
コメットテクノロジーズ・ジャパン株式会社は、横浜市男女共同参画推進協会という団体とともに、生活が苦しい女性を応援する活動に参加しており、コロナで経済的に大変な女性のために生理用品や吸水ショーツを配る活動に対して売り上げに応じて寄付を行なっています
2022年には横浜市内の男女共同参画センターや関係団体を通じて約21万円分の生理用品を配りました。これは、社内SDGs活動の一環で、女性の仕事や生活に大きく関わる「生理の貧困」という問題を少しでも解決したいという思いから生まれた取り組みです。コメットテクノロジーズは、女性が安心して働き学べる社会を作るために、地域に寄り添った支援を続けていきたいと考えています。
参考:ヨコ寄付
自治体・NPOによる無償配布の最前線
生理の貧困に対する支援は、日本各地で広がりを見せています。たとえば東京都豊島区では、公共施設のトイレに生理用品を設置し、誰でも自由に利用できる仕組みを導入しました。これにより、人目を気にせず必要なときにすぐ入手でき、利用者の心理的ハードルを下げています。また福島県相馬市では、専用の引換カードを使ってコンビニで生理用品を受け取れる制度を開始しました。日常的に利用する場所で配布されることで、アクセスのしやすさが大幅に向上しています。
さらに、NPO法人でもフードバンクや地域団体と連携し、生理用品を無償配布する活動が広がっています。これらの取り組みは、生理の貧困を抱える人々が安心して支援にアクセスできる環境づくりに直結しており、SDGsの「誰一人取り残さない」という理念を体現する動きといえます。
参考:新生活応援!生理用品の配布窓口を増やしています|すずらんスマイルプロジェクト
参考:「生理の貧困」について考えてみませんか?/相馬市公式ホームページ
企業の生理の貧困に対する支援事例
近年、生理の貧困への関心が高まる中で、企業も積極的に支援に乗り出しています。たとえばユニ・チャームは全国の自治体や教育機関と連携し、生理用品の無償配布や教育プログラムを提供しています。またP&Gジャパンも「生理の貧困」解消に向けたキャンペーンを展開し、若年層への啓発活動や物資支援を実施しています。
さらに、コンビニ各社では地域の自治体と協力し、レジで受け取れる仕組みを整える動きも広がっています。こうした企業の取り組みは単なるCSR活動にとどまらず、社会課題を自社の事業領域と結びつけ、持続的な支援体制をつくる点に大きな特徴があります。
生理の貧困は個人だけでは解決が難しい問題であり、企業が社会資源として役割を担うことは、SDGsの推進やジェンダー平等の実現に直結しています。
参考:世界中の女性が自分らしく過ごせる社会に向けた支援活動|2022年
参考:無料で生理用品を利用・寄付できる、「つながるナプキンBOX」をファミマ店舗内に試験設置国際女性デーに先がけ3月4日(金)より開始~生理用品の2%引きも3月8日(火)より実施
生理の貧困に立ち向かう国際的な取り組み
世界では、生理の貧困を解消するために多様な支援が広がっています。たとえばスコットランドは世界で初めて生理用品の完全無償化を法律で定め、学校や公共施設で自由に入手できる体制を整えました。ニュージーランドでも全国の学校で生理用品を無償配布しており、教育機会の確保と健康維持を同時に目指しています。また、アフリカの一部地域では、NPOや国際機関が布ナプキンや月経カップの提供、衛生教育の普及を進めることで、生理の貧困と教育格差の是正を両立させています。
これらの取り組みはSDGsの「目標1:貧困をなくそう」「目標3:すべての人に健康と福祉を」「目標5:ジェンダー平等を実現しよう」「目標6:安全な水とトイレを世界中に」と深く結びついており、生理の貧困が単なる個人の問題ではなく、社会全体の持続可能性に直結する課題であることを示しています。
各国の先進的な事例は、日本における支援拡充の参考にもなる重要なモデルです。
生理の貧困のよくある質問
生理の貧困に関する疑問や不安は多く寄せられています。ここではよくある質問を取り上げ、具体的な支援や実態を解説します。
Q1. 生理用品が買えないとき、どこで支援を受けられますか?
生理用品が買えないときは、自治体の福祉課や教育委員会、または地域のNPOが行う無償配布支援を利用できます。
東京都豊島区や大阪市などでは公共施設や学校での配布が進んでいます。基本的に必要な持ち物はなく、その場で受け取れる場合が多いですが、持ち帰りやすくするためにエコバッグを用意すると安心です。利用にあたっては「一人あたりの数量制限」などのルールがある場合もあり、多くの人が安心して受け取れる仕組みづくりが進められています。
Q2. 支援を受けるのが恥ずかしい・周囲に知られたくない場合は?
多くの自治体やNPOでは、名前を書かずに受け取れる仕組みや、トイレ・保健室など人目につきにくい場所での配布を実施しています。
コンビニや学校の窓口で引換カードを使う制度もあり、周囲に知られずに利用可能です。支援は「特別なこと」ではなく、生理の貧困という社会課題を解決するための正当な制度です。恥ずかしさを感じる必要はなく、安心して利用できる環境が整えられています。
Q3. 生理にかかるお金はどのくらい?負担の実態は?
生理用品の平均費用は1回の生理で1,000円前後、年間では約12,000円から15,000円程度といわれています。さらに鎮痛薬や下着の買い替えなどを含めると負担は大きくなり、日本でも経済的に困難な人にとって深刻な問題です。
この費用は固定的に発生するため、生活が逼迫している世帯にとっては生理の貧困を加速させる要因になっています。
Q4. 生理用品以外で受けられる支援は?
生理の貧困に対する支援は、生理用品の無償配布だけにとどまりません。自治体やNPOでは、医療相談やカウンセリング、生活費や食料支援といった包括的なサポートを行う場合もあります。例えばフードバンクで日用品とともに提供されるケースや、学校の保健室で健康相談が受けられる制度もあります。
こうした取り組みは、経済的な負担の軽減だけでなく、安心して生活を続けるための環境づくりにもつながっています。
Q5. 支援で受け取る生理用品は清潔な新品ですか?また、広告や宣伝は含まれていますか?
支援で配布される生理用品は、必ず清潔な新品が用意されています。中古品や衛生的に不安のあるものが渡されることはありません。また、受け取った際に広告チラシや宣伝が同封される場合もありますが、自治体やNPOは利用者の尊厳を守ることを重視しており、生理の貧困への支援は「安全で信頼できる形」で提供されています。
まとめ
生理の貧困は、日本でも深刻な社会課題として認識されつつあり、経済的な原因や教育の不足、偏見などが複雑に絡み合っています。健康被害や学業・就労への影響、精神的なダメージまで広がるため、解決は急務です。自治体やNPOによる無償配布、企業や国際的な支援活動など取り組みは拡大しており、SDGsの実現にも直結しています。
支援の輪を広げ、誰もが安心して生理期間を過ごせる社会を築くことが求められています。
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS