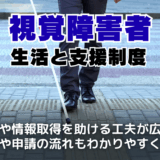「ADHDってどういう症状?」「自分や家族がADHDかもしれないけど、どうすればいいの?」と悩んでいる方もいると思います。
ADHDの診断と治療には専門医が必要ですが、その前に、ADHDに関する知識を身につけておくことが大切です。
この記事では、そもそもADHDとは何か、その定義や症状による分類はどのような基準でされるのか、主な症状やその特徴を解説します。また、ADHDの診断方法や治療法、ASDとの違いや障害者手帳についてや、年齢によって変化するADHDの特徴、大人のADHDの対処法なども紹介します。
ADHDとは?
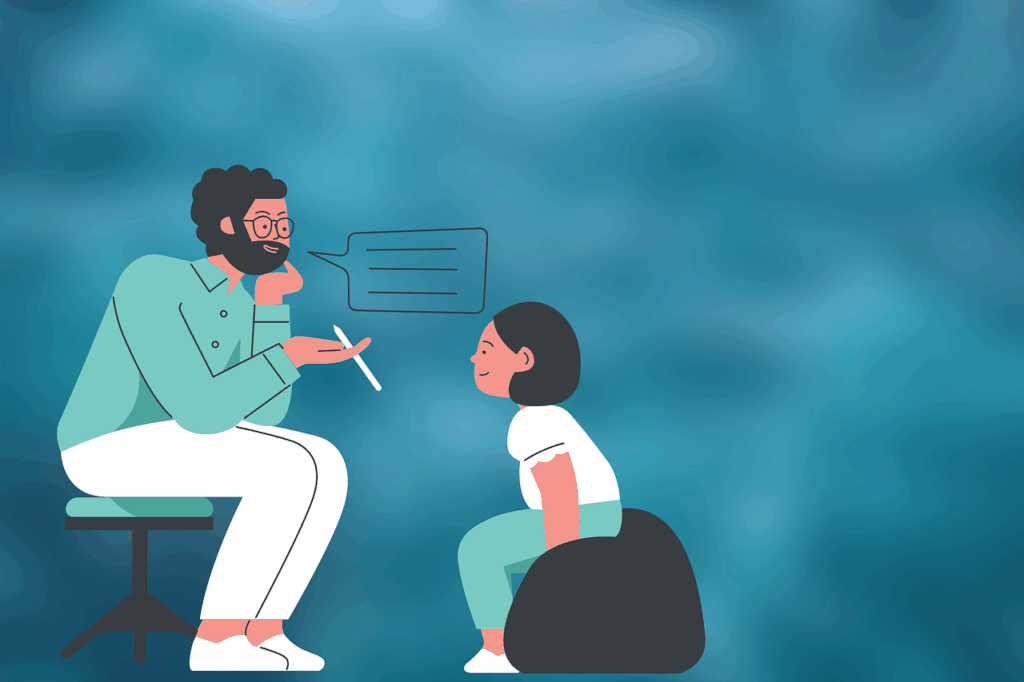
ADHDとは、注意欠如、多動症のことを指します。英語表記ではAttention Deficit Hyperactivity Disorderと言います。ADHDという病名は、「注意力の欠如」と「多動、衝動性」を表しているのです。
ADHDの歴史をたどると、1940年代に「微細脳機能障害」という新たな病名がつけられました。当時、この病気は脳の障害が原因だと考えられていました。その後、1960年代には「微細脳機能障害」から「小児脳機能障害」に病名が変わりました。
そして1980年代に入り、「注意欠陥障害(ADD)」という診断名が使われるようになります。この時点では、多動性の有無によって「ADDと多動性を伴うADDの2つのタイプ」に分類されました。
このような変化を経て、1987年にADHDという病名が定められました。振り返ってみると、病名が複数回変わっていることから、1940代からこの症状について議論が繰り返されてきたことが分かります。
ADHDの分類と特性
ADHDは、主に3つの種類に分類されます。
| 分類 | 特徴 | 留意点 |
|---|---|---|
| 不注意優勢タイプ | 集中力を維持するのが困難、物忘れが多い、整理整頓が苦手 | 多動は目立たないため気づかれにくいが、学業や仕事で支障が出やすい |
| 多動・衝動優勢タイプ | 動いていないと落ち着かない、多弁、衝動的に行動してしまう | 周囲の理解とサポートが必要。衝動性による対人関係のトラブルに注意 |
| 混合タイプ | 不注意と多動・衝動性の両方の特徴を併せ持つ | 両面で困難があるため、生活や学習に広範囲の影響が出やすい |
上記で紹介した3つのタイプを詳しくご紹介していきます。一口にADHDといっても人によって異なる症状が出てくるので、どれが一番当てはまるのかチェックしてみましょう。
不注意優勢タイプ
1つ目は「不注意優勢タイプ」です。このタイプの人は、集中力を維持するのが困難であり、物事を忘れやすいという特徴があります。しかし、動いていなければ落ち着かないといったような多動性はあまり目立たず、不注意が優勢となっているためこのように分類されています。
学校や会社でも不注意が目立つため、持ち物を忘れてしまったり大事な資料を置いてきてしまったりという、不注意が目立ってしまうタイプです。コミュニケーションも不注意で失礼な発言があったりすると、継続した人間関係が築けないといった特徴もあります。
多動・衝動優勢タイプ
2つ目は「多動・衝動優勢タイプ」です。動いていないと落ち着かない多動性の特徴があります。常に何かをしていようとするため、授業や業務中はどうしても他の人に迷惑をかけてしまう場合もあります。
また衝動的な行動も多く、思い立ったらその場ですぐに行動してしまうこともあります。突発的に動いてしまうので、周囲の人が振り回されてしまったり、周囲のサポートも重要となります。多動や衝動は薬によって落ち着かせられる場合もあります。
混合タイプ
3つ目は「混合タイプ」です。混合タイプは不注意と多動・衝動性のすべての特徴を持っているのが特徴です。そのため、不注意さと多動、衝動性のどちらに対しても警戒しておかなければなりません。
多動と言っても身体が動いてしまう多動も多いのですが、中には頭の中で考え続けてしまうような多動もADHDの中にはいます。混合タイプの中には、そういった特徴を持っている人も多いので、一概に外見だけではわからない場合も多くあります。
上記で紹介したタイプはあくまでも目安であり、個人差が大きいのもADHDの特徴です。また、年齢によって症状が少し異なったり、変化していくため、、その人に合った対応、手助けを行うことです。周りの人が理解していれば、そういった症状がある人にかかるストレスも軽減されることも期待できます。
参考:ADHD(注意欠如・多動症) | NCNP病院 国立精神・神経医療研究センター
ADHDとASD(自閉スペクトラム症)の違い
ASD(自閉スペクトラム症)は、社会的コミュニケーションの困難さと限定的な興味、反復行動を特徴とする発達障害です。感覚に過敏すぎる、コミュニケーションや対人関係の苦手さ、特定分野への強いこだわりなどが見られます。
ADHDとASDは、ともに発達障害に分類される症状ですが、その特徴や背景にあるメカニズムは異なります。この章では二つの症状の違いについて詳しく見ていきましょう。
行動特性・対人関係の違い
ADHDの人は、集中力が長く続かずすぐに飽きてしまったり、じっとしていられなかったりするため、落ち着きがないと思われがちです。一方、ASDの人は、冗談が通じなかったり、相手の表情から感情を読み取ることが苦手だったりするため、空気が読めないと評価されることがあります。
ただし、空気が読めないというように思える行動であっても、そのメカニズムはADHDとASDで異なります。ADHDの場合は、注意力の欠如や衝動性が原因で、状況に合わない、場違い感のある行動をとってしまうことがあります。ASDの場合は、常識的な行動をとることや他者の感情を理解することが難しいのです。
また、対人関係においても、ADHDとASDでは違いがあります。ADHDの人は、多動性や衝動性のためにコミュニケーションが思うように取れず、友人関係がうまくいかないことがありますが、基本的に他者との関わりを絶つことはなく、求める傾向がありますが、ASDの人は社会性の困難さから、他者との関わりそのものを避ける傾向があります。
| 特徴 | ADHD | ASD |
|---|---|---|
| 行動特性 | 集中力が続かず、すぐに飽きる/衝動的に動く/場にそぐわない行動をしてしまう | 冗談が通じにくい/相手の表情や感情の読み取りが苦手/常識的な行動が取りにくい |
| 行動の背景 | 注意力の欠如や衝動性が原因で、結果的に場違いな行動になる | 社会的理解や他者の感情の把握が難しく、そのために行動がずれる |
| 対人関係 | 他者との関わりを求めるが、衝動性や不注意で友人関係がうまくいかないことが多い | 社会性の困難さから、他者との関わりを避ける傾向がある |
| 周囲の見られ方 | 「落ち着きがない」「場を乱す」などと思われやすい | 「空気が読めない」「距離感がつかめない」と評価されやすい |
併存(合併)するケースもある
ADHDとASDはそれぞれ独立し、異なった症状ですが、二つの症状の特徴を併せ持つ人も実際にいます。ADHDの人の約20〜50%がASDを併存していると言われています。
ADHDとASDが併存する場合、症状が重なり合い、日常生活に支障をきたす場面が増えることが多くなり、複雑な問題を引き起こすことがあります。ADHDによる衝動性とASDによる社会性の困難さが組み合わさることで、対人関係のトラブルが起こる頻度がさらに高くなる可能性があります。
また、ADHDとASDが併存する場合、診断がつきにくくなることがあります。どういうことかというと、例えばADHDの症状が前面に出ていると、ASDの症状が見落とされることもあります。逆に、ASDの症状が強い場合、ADHDの存在が見落とされることもあります。
そのため、ADHDとASDのどちらの症状も疑われる場合は、両方の症状を詳細に理解し、適切な診断を行うことが重要です。
ADHDの主な症状と困りごと
ADHDの特徴のひとつに年齢によって現れる症状が異なるといった点があります。
では具体的にどのような違いが年齢によってあるのか、この章で解説していきます。
不注意・多動・衝動
実際にどのような行動をとってしまうのか、いくつか例を紹介します。
子どもの場合、学校で宿題を忘れてきたり、授業中に席を立ち歩いたりするという行動を起こします。また、他の子とのコミュニケーションがうまくいかず、友達とのトラブルにもつながるケースもあります。
大人になると、子どもと比較して症状は少し変化します。社会人の例を挙げると、書類の締め切りに間に合わない、人の話を最後まで聞けないことが頻繁に起こる、人間関係がうまくいかないことや、衝動的に買い物をしたりします。
しかし、これらはADHDの人がふざけていたり、怠けているわけではありません。このような行動をとってしまう原因には、脳の働きが関係しており、簡単には改善しないのがADHDの特徴です。そのため、このようなADHDの特性を理解し、それぞれの場合において適切なサポートをすることが大切です。例えば子どもの場合は、学校の先生と相談、連携して、学校生活を送る上で可能な限り手助けしてあげることや、授業中の集中力を高める工夫をしたりすることが対策案として挙げられます。
大人の場合は、スケジュール管理やタスク管理を簡単に正確に行うために、便利なツールを活用したり、仕事の環境を整えたりすることが重要です。
年齢によって変化する症状の出方
ADHDの症状は、年齢によって変化します。そのため、子どもの頃と大人になってからでは、症状の現れ方が少し異なります。
子どもの頃は、多動性や衝動性といった、過度に動いてしまう症状が現れやすいです。じっとしていられない、順番を待てない、危険な行動をとってしまうなど、周りに迷惑をかけてしまうようなこともあります。しかし、ADHD発症が思春期と重なってしまうと、精神面にも大きな負担となります。
大人になると、不注意の症状が目立つようになります。子どもに多い多動性のようなじっとしていられないといったことは少なくなりますが、気が抜けていると周りから思われてしまうような機会が増えてしまいます。
ただ、具体的な症状は個人差が大きいので、一概には言えません。そのため子どもの頃から不注意の症状が目立つ人もいれば、大人になっても多動性や衝動性が続く人ももちろんいます。
以下が、子どもと大人のADHDの症状の比較表となります。
| 症状 | 子ども | 大人 |
|---|---|---|
| 不注意 | 宿題を忘れる、物をよく失くす | 仕事や家事が計画通りに進められない、約束を忘れる |
| 多動性 | じっとしていられない、席を立ち歩く | 落ち着きがない、必要以上に喋る |
| 衝動性 | 順番を待てない、危険な行動をとる | 衝動買いをする、人の話を遮る |
年齢によるADHDの症状の変化を理解することは、その人と接するうえでも重要となります。子どもの頃からADHDの特性に気づき、成長に合わせたサポートをすることが大切です。
参考:ADHD(注意欠如・多動症)|さいたま新都心のふせき心療クリニック 心療内科・精神科・児童精神科
ADHDの二次障害
ADHDの人は、行動面、精神面で悩みを抱えている人が多いため、二次障害として様々な問題を抱えやすいという特徴があります。二次被害としてよくあるのが、うつ病や不安障害、低い自己肯定感です。
ADHDの特性によって、普通の人よりも仕事や人間関係がうまくいかないことが多いです。そのような失敗する経験や、うまくいかない経験が重なってしまうと、自分に自信が持てなくなります。
また、ADHDの人は精神面を制御することが難しく、ストレスに弱いことが特徴的です。ストレスがたまると、うつ病や不安障害を発症することにつながります。実際、ADHDの人の多くが、うつ病や不安障害などの精神的な病を抱えています。
これらの二次障害は、生活に大きな影響を与え、仕事や学業がうまくいかなくなったり、人間関係が悪化したり、日常生活に支障をきたすことが予測されます。
そのためADHDの人やADHDの人の家族は、二次障害に対する対策法を知っておくべきです。ストレス管理の方法を身につけたり、自分に合った仕事や働きやすいと思えるような環境を見つけたりすることが重要です。
ADHDの原因
ADHDの原因は実ははっきりとはわかっていません。ただこれが原因なのではとされているものをご紹介します。
脳の機能障害
主な原因として挙げられるのは、脳の機能障害であるということです。ADHDの原因はいまだはっきりと解明されていませんが、最新の研究によると生まれつき脳に機能の障害が生じていることが、原因のひとつと判明してきました。
ADHDの脳内では、神経伝達物質が不足していることが判明しています。
神経伝達物質にはノルアドレナリンやドーパミンなど意欲や興奮に関わるものや、セロトニンなどの抑制性に関わるものもあり、ADHDの方はこの神経伝達物質の量が少ないことが原因で、正常に情報が伝えきれていないのではないかと考えられています。
引用元:万代メンタルクリニック
遺伝
ADHDは脳の疾患なので遺伝が原因ではないかといわれています。ADHDの子どもの親も気づいていないだけでADHDの症状があらわれている場合があります。
ただ遺伝だけで必ずしもADHDになるわけではなく、環境的要因も関係している場合が多いです。親がADHDだからと言って、必ずしも子どももADHDになるわけではありません。
ADHDは親のしつけの問題ではなく、遺伝的可能性はありつつも、基本的には脳の仕組みが異なるため、しつけができていないからといったことが原因ではありません。
子どものADHDの特徴と症状
子どものADHDの特徴と症状を見ていきましょう。
子どものADHDの特徴
子どものADHDの特徴がわかるのは、大体2~3歳になります。集団生活などで周りの子と一緒に座っていられなかったり、動き出してしまったり、落ち着きがない点が特徴として挙げられます。
他にも小学生になると忘れ物が一気に増えたり、列に並んで待っていられなかったりといった特徴が顕著に表れるようになります。
小学生くらいになって初めて子どものADHDの症状に気付いたという場合も多々あります。
子どものADHDの症状
子どものADHDの症状としては、不注意や多動傾向にあること、衝動性が挙げられます。
特に不注意では宿題を忘れてきてしまったり、筆箱など必ず必要なものまでおいてきてしまうことがあります。他にも衝動性から授業中に他のことを始めてしまい、注意されてもやめられないといったことも挙げられます。
他にも細かい部分まで注意が向かないため、テストなどでもケアレスミスが増えてしまう点もADHDの症状です。
大人のADHDの特徴と症状
大人のADHDの特徴と症状もご紹介します。
大人のADHDの特徴
大人のADHDは、注意力散漫になってしまい仕事などにおいてケアレスミスが起きやすい点が特徴です。
他にも待つことが苦手で行列に並べなかったり、仕事に集中できない場合もあるのが大人のADHDの特徴です。
順序だてて物事を進めることが苦手なので、会社でもミスが目立ってしまう点も特徴として挙げられます。
大人のADHDの症状
大人のADHDの具体的な症状をご紹介します。
例えば一人暮らしの部屋の片づけができずに、部屋がゴミ屋敷になってしまっていたり、時間の管理が苦手で遅刻や約束の期日までに仕事が終わらせられないといったことも考えられます。
また社会生活を行うにあたって、衝動的に思っていることを口に出してしまうので、会社での人間関係がうまくいかなくなってしまう可能性もあります。
多動傾向が強い場合は、貧乏ゆすりがでてしまって周りに迷惑をかけてしまうこともあります。
ADHDの診断方法|いつどこに相談すべきか
身近な存在の人がADHDと診断されたらどのような対応をとるべきなのでしょうか。この章では、年代に分けてどこを受診すべきかを解説していきます。
診断の流れと必要な手続き
ADHDの診断は、まず本人や家族からの詳しい話を聞く問診が実施されます。学校や職場での様子、生活習慣など普段の日常生活の内容を聞き取ることで、ADHDの可能性があるかないか、詳しく探ります。
次に、心理検査を行います。心理検査は質問紙やテストを使って、注意力や衝動性、行動に関する出来事などを評価します。これらを総合的に判断し、医師がDSM-5という診断基準に照らし合わせ、ADHDかどうかの診断をします。
受診先の選び方|小児科・精神科・発達外来
DHDの診断を受ける際、どこを受診すべきかよく分からないという方は多いと思います。結論から言うと、年代によってオススメの受診先が異なります。
子どもの場合は、まずはかかりつけの小児科を受診するのをオススメします。小児科医は、子どもの発達事項における専門知識を持っているため、ADHDの可能性について的確なアドバイスをしてくれます。もし小児科医だけでは判断が難しいという場合でも、専門の医療機関を紹介してくれることがあります。
思春期から成人の場合は、精神科や心療内科がオススメです。ADHDは、うつ病や不安障害などの二次障害となる精神疾患を引き起こすことが多いため、精神科医の診断が適しています。ただ、一般の精神科では、ADHDの診断に関して不慣れな部分もあるため、事前に確認が必要です。また、子どもから大人まで年齢関係なく、発達外来も選択肢の一つとして挙げられます。発達外来は、発達障害全般を専門的に診断してくれる医療機関であり、ADHDの診断に力を注いでいるため、もち近くに発達外来がある場合は受診してもよいかもしれません。
ADHDの治療法
ADHDの治療は主に二種類あり、薬物療法と非薬物療法に分けられます。それぞれの治療法にはどのような特徴があり、どのような症状の人向けの治療なのかを解説します。
薬物療法|使用される主な薬と効果
ADHDには薬物療法も治療法として適切な場合もあります。改善を目指し、様々な工夫された対応をしているのにも関わらず、効果がないという状態が続き、日常生活に支障をきたす場合には薬物療法が考慮されます。種類が複数あり、効果の強さや持続時間などが異なっています。その時の状態や精神状況に応じて、主治医と一緒に薬剤の選択を考えていくことになり、薬剤の種類の中には精神刺激薬というのに分類される依存リスクがある薬剤もあります。
そのような薬剤は流通規制が敷かれており、患者さんの登録が必要になっていること、処方できる医師や調剤できる薬局も限定されていることなど、容易に処方することができないようなシステムになっています。
なんでもかんでも薬物療法が最善というわけではないため、あらかじめ相談が必要です。治療には個人差が大きく、効果や副作用の現れ方は人によって異なるのが普通です。また、薬物療法だけでは、ADHDの根本的な問題を解決することはできないため、生活環境の調整や非薬物療法との組み合わせが重要となります。
副作用と注意点
薬物治療による副作用として考えられる要素としては、不眠になり夜に眠れなかったり、食欲が低下してしまうなどがあります。不眠は、薬の摂取により、体が少し興奮状態になってしまうため、就寝時間間際には服用しないなどの工夫が必要です。また、食欲の低下は、薬の影響で空腹であると感じにくくなることが原因で起こります。成長期の子どもの場合、身体の成長が抑制されてしまうため、服用する場合は慎重に行わなければなりません。
その他の副作用として、頭痛、腹痛、倦怠感などが挙げられます。これらの症状は、個人差が大きく、服用量や体質によって現れ方が異なります。副作用が現れた場合は、医師に相談し、服用量の調整や薬の変更を検討する必要があります。
参考:ADHD(注意欠如・多動症) | NCNP病院 国立精神・神経医療研究センター
ADHDと障害者手帳
ADHDを持つ人にとって、障害者手帳の取得は大きな関心事の一つです。障害者手帳は、障害のある人の生活を支援するための制度ですが、ADHDが対象となるかどうかは、少し複雑な問題なのです。この章では、取得条件や支援内容について紹介していきます。
精神障害者保健福祉手帳の対象となるか?
ADHDは、発達障害の一種ですが、それ自体では精神障害者保健福祉手帳の対象とはなりません。しかし、ADHDに加えて、うつ病や不安障害などの精神疾患を併発している場合は、手帳の対象となる可能性があります。
手帳の取得には、医師の診断書が必要です。診断書には、ADHDの症状だけでなく、併存する精神疾患の症状も詳しく記載される必要があります。また、日常生活や社会生活に著しい制限があることを示す必要があります。
手帳の等級は、障害の程度によって1級から3級まであります。等級によって、受けられる支援やサービスが異なるため注意が必要です。
手帳取得のメリットと注意点
障害者手帳を取得することで、様々な支援やサービスを受けることができます。例えば、就労支援や生活支援、福祉サービスの利用などです。また、職場での合理的配慮を求める際にも、手帳は重要な根拠となります。
ただし、手帳の取得には注意点もあります。手帳を取得することで、周囲から障害者として見られることがあります。これは、社会の偏見や差別につながる可能性があります。また、手帳の取得や更新には、定期的な診断書の提出が必要です。これは、経済的な負担になることもあります。
手帳の取得は、ADHDを持つ人にとって、メリットとデメリットがあります。自分の状況や必要性を考えて、慎重に検討することが大切です。手帳の取得を考えている人は、まずは医師や専門家に相談することをオススメします。
また、手帳の取得は、あくまでも支援を受けるための手段の一つです。手帳がなくても、様々な支援やサービスを利用することができます。例えば、地域の発達障害者支援センターや、就労移行支援事業所などです。
参考:障害者手帳について
大人のADHDとその対処法
大人になってからのADHDの症状は、子ども時代に起こる症状と特徴が異なることが多いです。この章では、大人のADHDに多い特徴と困難やライフハックについて紹介していきます。
大人のADHDの特徴と問題点
大人のADHDは、仕事や家事、人との交流、コミュニケーションをとるといった様々な場面で困難に直面します。
仕事では、締め切りを守れなかったり、書類にミスが多いなどの問題が起こりやすいです。家事では片付けが苦手で、部屋が散らかってしまうことが最もよく見られます。対人関係では、会話が噛み合わなかったり、周りに合わすことができず、空気が読めなかったりすることが頻繁に起こってしまうという困難があります。
また、感情のコントロールが難しく、怒りっぽくなったり、気分の浮き沈みが激しくなったりすることもあります。
これらの特徴は、ADHDの症状である不注意、多動性、衝動性が、大人になっても持続しているために起こります。ただ、周囲の理解と医療機関の受診によって改善する場合があります。
大人のADHDに対する周囲の支援
ライフハックを活用してみることで、改善を目指すといったことも考えられます。
具体的な策といえば、スケジュール管理やタスク管理のアプリを駆使し、視覚化したりすることで忘れ物や 間違いを未然に防ぐことができます。また、長時間の集中が難しい場合は、定期的に休憩を取ったりするのも効果的です。
自己や周囲の手助けだけでは対応が難しい場合は支援機関を利用するのもオススメです。例えば、LITALICOでは、大人のADHDを専門に扱うプログラムがあります。個別カウンセリングや、グループワークを通して、自分の特性を理解し、対処スキルを身につけていくことができます。
ハローワークでは、障害者専門の職業相談や、就労支援のプログラムを提供しています。また、職場では業務内容の調整や、勤務時間の配慮などを受けることができます。上司や同僚に自分の特性を伝え、必要な配慮について話し合うことが大切です。
自分の特性を理解し、周囲の支援を受けながら、自分らしい生き方を見つけていくことが大切です。
ADHDとニューロ・ダイバーシティの考え
ADHDとニューロ・ダイバーシティの考えとして、ADHDの人を病気とするのではなく、脳の多様性として受け入れる動きがあります。
脳の多様性として認めたうえで、ADHDの人に向いている職を任せるといった考え方です。普通・障害で区別するのではなく、発達障害も多様性の一つとして進めていくことができれば、さらに社会が発展するのでは、と考えられています。
ADHDの人たちはその衝動性などをうまく活用できれば、躊躇してしまうようなこともスムーズにチャレンジできる場合があります。
ADHDの方に私たちができること
ADHDを持つ人を支えるためには、周囲の理解と支援が欠かせません。私たち一人ひとりができることを考えていくことが、ADHDを持つ人が生きやすい社会を作ることにつながるのです。
ADHDについて正しく理解する
ADHDの方を支援するために、まず大切なのはADHDについて正しく理解することです。ADHDは、単なるわがままや怠惰ではありません。脳の機能の特性によって引き起こされる症状なのです。
ADHDの特性や困難さを知ることで、ADHDの方の行動を正しく理解することができます。例えば、約束を忘れてしまったり、人の話を最後まで聞けなかったりするのは、ADHDの特性によるものだと理解できるようになります。
必要な配慮やサポートを提供する
ADHDを持つ人が、学校や職場、日常生活で困難を感じることがあります。そんな時に、周囲が必要な配慮やサポートを提供することが大切です。
例えば、学校では、授業中の座席の配慮や、課題の量の調整などが必要になることがあります。職場では、業務内容の調整や、勤務時間の配慮などが求められます。日常生活では、スケジュール管理の手助けや、整理整頓の支援などが役立ちます。
ADHDを持つ人の困りごとに耳を傾け、必要な配慮やサポートを提供することが、私たちにできる大切なことです。
ADHDの方の話を聞き、寄り添う
ADHDを持つ人は、周囲の理解を得られず、孤独を感じることがあります。そんな時に、私たちができるのは、ADHDの方の話を聞き、寄り添うことです。
ADHDの方の経験や思いに耳を傾け、共感することで、ADHDの方は自分が一人ではないと感じることができます。また、ADHDの方の苦労を認め、励ますことで、ADHDの方は自分を肯定的に捉えることができるようになります。
ADHDを持つ人に寄り添い、支えていくことが、私たちにできる最も大切なことかもしれません。
ADHDに関するよくある質問
以下に、ADHDに関する質問を5つピックアップしました。読者の方の疑問が少しでも解決しましたら幸いです。
Q1: ADHDは子どもだけの障害ですか?
A: いいえ、ADHDは子どもだけの障害ではありません。ADHDは、多くの場合、子ども時代に発症しますが、成人期まで症状が持続することがあります。実際、成人の2~3%がADHDであるといわれています。成人のADHDは、子ども時代とは異なる症状が現れることがあり、仕事や対人関係、日常生活に影響を与えます。
しかし、適切な治療とサポートを受けることで、ADHDを持つ成人も充実した生活を送ることができます。ADHDは、年齢に関係なく、理解と支援が必要な障害なのです。
Q2: ADHDの原因は何ですか?
A: ADHDの明確な原因はまだ特定されていませんが、遺伝的要因と環境的要因の両方が関与していると考えられています。ADHDの子どもの多くは、親族にもADHDの人がいることが報告されており、遺伝的な影響が示唆されています。また、脳の発達や神経伝達物質の機能にも関連があると考えられています。
一方、環境的要因として、妊娠中のアルコールやタバコの摂取、低出生体重、脳の損傷などが挙げられます。ただし、これらの要因がすべてのADHDの原因というわけではありません。ADHDは、複数の要因が複雑に絡み合って発症すると考えられているのです。
Q3: ADHDの症状は、年齢とともに変化しますか?
A: はい、ADHDの症状は、年齢とともに変化することがあります。子ども時代は、多動性や衝動性が目立つことが多いですが、成長につれて、これらの症状は減少する傾向にあります。一方、注意力の問題は、年齢が上がっても持続することが多いです。
成人のADHDでは、子ども時代とは異なる症状が現れることがあります。例えば、物事を整理整頓することが苦手、時間管理が難しい、気分の浮き沈みが激しいなどです。ただし、これらの変化は個人差が大きく、一概には言えません。ADHDの症状は、年齢とともに変化する可能性があることを理解しておくことが大切です。
Q4: ADHDの治療法はありますか?
A: はい、ADHDの治療法はいくつかあります。大きく分けて、薬物療法と非薬物療法の2つがあります。薬物療法では、中枢神経刺激薬や非中枢神経刺激薬などの薬を使用して、脳内の神経伝達物質のバランスを整えます。これにより、注意力を高め、衝動性を抑える効果が期待できます。
一方、非薬物療法では、認知行動療法や行動療法、環境調整などを行います。ADHDの特性を理解し、対処スキルを身につけることで、日常生活の改善を目指します。また、両者を組み合わせることで、より高い治療効果が期待できます。ADHDの治療は、個人の特性に合わせて、医師と相談しながら進めることが大切です。
Q5: ADHDと診断されたら、学校や職場ではどのようなサポートを受けられますか?
A: ADHDと診断された場合、学校や職場では、様々なサポートを受けることができます。学校では、特別支援教育の枠組みの中で、個別の教育支援計画を作成し、生徒の特性に合わせた指導を行います。例えば、授業中の座席の配慮、課題の量の調整、テストの時間延長などです。
また、職場では、障害者雇用の枠組みの中で、合理的配慮を受けることができます。例えば、業務内容の調整、勤務時間の配慮、ノイズキャンセリングヘッドフォンの使用などです。ただし、これらのサポートを受けるためには、診断書の提出や、学校や職場との話し合いが必要です。ADHDと診断されたら、まずは医師や専門家に相談し、必要なサポートについて情報を集めることが大切です。
まとめ
ADHDは、注意力の欠如、多動性、衝動性を主な特徴とする発達障害です。その症状は年齢によって変化し、二次障害を引き起こすこともあります。ADHDとASDは、ともに発達障害ですが、その特性や対人関係の違いを理解することが大切です。
ADHDの診断には、医師による問診や心理検査が必要です。子どもの場合は小児科や児童精神科、大人の場合は精神科や発達外来を受診するのがよいでしょう。診断後は、薬物療法や非薬物療法を組み合わせた治療が行われます。薬物療法では、中枢神経刺激薬などが使用されますが、副作用にも注意が必要です。
ADHDを持つ大人は、独自の困難さを抱えています。しかし、ライフハックや支援機関、職場の配慮を活用することで、その困難を乗り越えていくことができます。また、障害者手帳の取得も検討する価値があります。
ADHDの方を支えるためには、私たち一人ひとりができることを考えていくことが大切です。ADHDについて正しく理解し、ADHDの方の強みを認め、必要な配慮やサポートを提供すること。そして、ADHDの方の話に耳を傾け、寄り添うこと。これらは、ADHDの方が生きやすい社会を作るために、私たちができる大切なことです。
 NEXT WELLNESS
NEXT WELLNESS